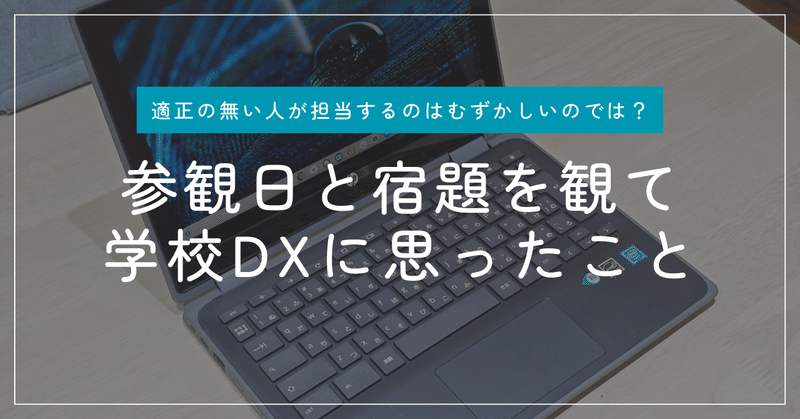
こどもの参観日と宿題を観て思った田舎の小学校DXに思ったこと「適正の無い人が担当するのはむずかしいのでは?」
私の娘は小学校2年生です。つまりこれは田舎の小学校1・2年生に対する学校DXについてのお話です。
昨年から小学校に入りコロナ禍ということもあり、急にChromebookで宿題がでたりしました。
まずこの段階で思ったのは「Chromebookについて家庭に取り扱いの説明とか設定の説明、時間制限やフィルターの説明、フィルターのエラー番号の説明など何もないのかよw」というところです。
小学1年生に説明し、素人かもしれないご家庭にWiFi接続頑張って!と丸投げ。Chromebookで何をするのか、どんな目的があるのか、子供にどんな方針で教えていくのかなどなど、なんの説明もありませんでした。
急ごしらえの学校DXなので仕方ないのでしょうということで、とりあえず言われたことだけを進めた1年生。そして2年生になり状況は悪化しました。
たぶん、1年生の時の担任よりDX適正が低い先生が担任になった
数日前、娘がChromebookを重そうに持ち帰り、宿題をやるというので、いつも通りQRコードでログインするとi-Filterのエラー勃発です。ログインじたいはできているのでWiFi接続などが原因ではなさそう。20時を過ぎていたので、もしかすると時間規制がかかっているのかも?と思いつつ、とりあえず何度か再起動なども交えて試してダメだったのでその日はあきらめました。
翌日、娘が学校に行く少し前に私が再チャレンジするとあっさりと教室に入れました。やっぱり時間規制がありそうだな~と思いつつ、とりあえず先生に昨日ログインできなかったので宿題をできませんでした、対処方法があったら教えてくださいと連絡帳に書いてもらい娘に託すも、、、「学校では正常に繋がりました」と返事が返ってきました。
「終わった。このタイプの先生か。」
残念なことに、担任の先生は問題を解決する気はなく「もめ事に巻き込まれたくないを全開でぶつけてくるタイプ」のようです。今後もこのエラーは頻発するでしょう。
何が問題なのか。
アナログベースの授業であれば、教える内容が主体になるのは当然です。ですがDX化を進めることで、システムの仕組みを教師と生徒の親で把握するのは絶対条件のはずです。今回の現象をアナログ風に言うと「娘を教室まで連れて行ったのですが、鍵がかかっていて入れません。どうすればよいでしょうか?」という質問に「大丈夫です!学校では教室には入れてます!」と言われた感じです。
システムに関しては素で「学校では正常に使えるので何もおかしく無い」と本気で思っていて、そう書いているような気がするので、そこが一番怖いところです。
つまり、システム音痴の先生だと仮定すると
学校ではで問題ない=ご家庭の不具合=ご家庭の問題なら私が説明する必要はない+もめ事にしたくないので、ご家庭の環境では?という言葉は書かないという最善の配慮=私は気を使っている=私えらい!
の流れだと考えられます。
全国各地でこういった現象が起こっているのではないでしょうか。
そして、もう一つ。。。
私の知るDXのプロフェッショナルの方はよくこういっていらっしゃいます。「紙ベースの仕組みをデジタル化するのがDXではありません」「デジタル化に合わせてより使いやすく・よりわかりやすく仕組みから変えていくのがDXです」というものです。
その言葉を胸に、娘のChromebookでの宿題を観てみると。。。。
プリントの問題の解答欄が選択式になっているだけ。
「これは、、、やってんな!」
例えば、問題をひとつ作るにしても、紙媒体では伝え難いイメージを3Dモデリングや数字連動でグラフや図の長さが変わるなど、頭のなかでこういう風にイメージを膨らますことで正解にたどり着けますよ!という事が分かりやすく動きをつけるなどの工夫をして作り込んだ問題を使って欲しいわけです。
これは最初こそ時間がかかりますが、その仕組みが優秀であればあるほど、その後その分野の授業はその問題を使うだけで、サクサク子供たちも理解できるようになるので、お金をかけて開発する意味があります。
ただ、〇か×かを判断してくれるだけの問題システムなんて、それこそ数世代前にでもやっとけ!というレベルです。
また、Chromebookを活用してこのレベルだとしても宿題が出せるのであれば、紙で書かせる宿題は無くして、この形式の宿題にすべてシフトするべきです。
あなたのお子さんは宿題をやっているとき、丁寧な字を心がけて書いていると言い切ることができますか?
字の綺麗なお子さんをお持ちのご家庭では上記の質問はYes!と自信をもってお答えいただけると思いますが、大半のご家庭では「殴り書き選手権になっています」というのが事実だと思います。
文字を書く事は重要ですが、宿題で殴り書きさせるのは得策ではないのでは?
殴り書きは癖になります。変な書き方が癖になると直すことは容易ではありません。ですが、低学年の子供は遊びたいが最優先ですので、宿題の回答に丁寧な文字を書こうとはこれっぽっちも思いません。その積み重ねが矯正不可能な下手な文字につながっていくのだと、私自身が身をもって立証していますw
どうやって綺麗な文字を書けるようにしていくのか?
宿題はタブレット、授業もタブレット、これでは文字を書く機会が少なくてだめです!!話になりません!!とお𠮟りを受けると思いますが、そうではありません。
集中できる時間を作り、文字は丁寧に書くことを学んでいく。
1・2年生は文字を書く時間は難しい事は考えさせず、ただ綺麗に書くことに集中してもらうわけです。文章を書き写したり、新しい漢字などを練習する時間にすべてを注ぎます。3・4年生で少し手書きの宿題を増やし、筆記の速度を上げる練習を開始します。5・6年生で今までどおりのスケジュールに合流します。低い学年の子供たちほど「問題を解く」という事と「綺麗な文字で書く」を同時に行うというプレッシャーがあり、どちらかに自信がないとなかなか前に進めないというお子さんも多いと思います。※マルチタスクがまだできない年頃なので。
なので、問題だけを解いていく宿題と綺麗に書くことに専念する宿題に分けるだけです。この流れでしっかり自信をもって文字を書ける状態になるまで続けることが重要だと考えています。
素人が勝手なこと書いているだけなので、見当違いでしたら申し訳ありませんw
道徳参観日というのに参加した結果
道徳の授業を見ることができる日ということで行ってきました!
教科書の絵を大きくプリントし、モニターカメラで写真を写して大画面に表示。そのプリントを黒板に貼って児童の意見を聞いて書き込む。
機材を活用していますね!!という感じの授業でした。
いや、プリントをカメラで撮る必要ないでしょ!
タブレット接続して大画面拡大表示したい場所を表示すればもっと簡単で毎回ピントも合わせる必要がありません。
というか、先生、子供たちに意見を聞いてるはずなのに「え?これって仲間外れにしてるのかなぁ?そうかなぁ。」とか言わないでください。それに、私から見ても仲間外れにされています。そう表現したくない事情があるのかもしれませんが、3匹の動物が1匹の動物に向かって「君は泳げないからダメ!」って言って連れて行ってもらえなかったら仲間外れ以外の表現って浮かびません。
それはさておき、道徳の授業で子供たちからの意見収集に時間がかかり、45分授業で完結できず、まとめも微妙な感じで終わってしまいました。
みんなで仲良くするためには、譲り合いの心が必要です!というのを伝えたかったのか、友達が暗い顔をしているとみんな楽しめないから察してあげましょうといいたかったのか、はたまた、単純に友達を傷つけるような言い方はやめましょうということだったのか、大人でも分からない授業でした。
いや、45分で道徳の授業って無理でしょ。あと、どんな内容で収束させるべきなのかとかは、親には教えておいてほしい。その授業が失敗に終わっても、家で解説してあげたり、子供の意見によりそいつつ、いろんな考え方があるから、その考え方が正しい時もあるよね!と伝えてまとめたいんです。
授業参観の結果、アンケートもなく、ひどい授業でしたね!と伝えることもできない。DX化で大変だから、巻き込まれた子供たちは残念でしたでは済まされないと思うんです。
道徳だけでなく、他の教科も夏休みの宿題は〇付けまでご家庭でお願いします!と言われますが、算数などはどういう方針でこの問題をこんな回りくどい方法で解いているのかなどが分からないので、娘に勝手な解説もできません。先生方にはきっとカリキュラムで方向性などは開示されていると思うので、そういった資料も家庭に公開してほしいものです。もちろんChromebookでかまいませんw
また、小学校低学年にChromebookは重過ぎると思います。正直キーボードを使わない学年になんでクラムシェルタイプあてがってるのかが分かりません。体力もあり、キーボードで文字入力をする学年になったらクラムシェル、それまではタブレットで良くないですか?
それに、ただ宿題をタップするだけなら、URLとログインQRコードだけで家にChromeが使える環境があるひとなら、家の端末で良くないですか?
DX化を昭和の頭で行っているというイメージしか湧きません。
DXを推し進めるのであれば、エンジニアは必要です。ちゃんとしたエンジニアの管理のもとでシステムトラブルは先生ではなくエンジニアが対応し、先生が授業に集中できる環境も必要なのではないでしょうか。
ちなみに、娘のクラスの担任の先生はGarminのスマートウォッチを付けていました。これは、少なくともガジェット素人が選ぶ端末ではありません。
なぜなら、私も妻に同じものを買って使ってもらっているからですw
Lily Classic | スマートウォッチ | Garmin 日本
これ凄く素敵ですよ!性能としては3世代くらい前なので、最新鋭の技術でリニューアルしてくれることを願っています。
つまり、先生はガジェットも使いこなす玄人なのかもしれません。ただ、先生から見た我が家はWiFiもろくに使えないご家庭wという扱いなのは間違いないでしょう。
結局のところ、システムなどは使えたところで適正がなければ「どういう部分をあらかじめ解説しておかないとトラブルになるだろうという見極め」や「この部分はタブレット、この部分は黒板が向いているなど使い分け」、「アナログの黒板も毎回写真に残し、子供たちがChromebookで振り返れるように残すなどの工夫」もできません。
先ほども書きましたが、私はこう思っています。「DX化に向け、学校には定席のエンジニアが必要です。」と。※私はエンジニアではありませんw
先生とエンジニアがタックを組んで本気で学べる授業や宿題を作ったら凄く面白い世界になると思うのですが、DXに取り組む先生方は先生方だけで解決するのがDXだと本気で思っているのでしょうか。
できないのにできると思っている人ほど、怖いものはありません。
こういう事ってどこに言えばいいんでしょうね。
念のため書いておきます
DX化はまだ始まったばかりで、適正の有り無しで先生方は採用されていません。また、先生が悪いとか学校が悪いとかではありません。その人のそれまで置かれてきた環境ではそのやり方がベストだったという事も事実でしょう。
ただ、DX化ってデジタルでできることが幅広く想像できる人でなと実現できないものだと思います。なので既存の先生で適正がある人ってDXについてnoteで書いてるようなレベルの方々くらいだと思います。
あと正直、先生は悪くない!と言ってはあげたいですが、自分の子供が中途半端な授業ばかり受けつづけ、全然内容を理解せずに時間ばかり過ぎていくのは困りものです。
もう一度言います。DX(デジタルトランスフォーメーション)はモニターやタブレットを使うという事ではなく、デジタル技術を活用し、今までの仕組みをより使いやすく作り替えていくという事を意味します。デジタルツールを無理して使う授業や、何でもかんでもデジタル化して学習効率を落とすような使い方を推奨するものではありません。しっかり仕組みから変えて取り組んでもらいたいですね!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
