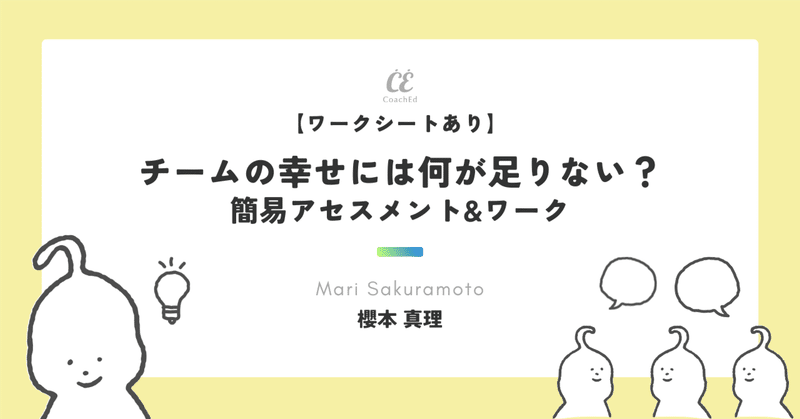
【ワークシートあり】チームの幸せには何が足りない?簡易アセスメント&ワーク
今日は、チームの状態、悪くないんだけど何かが足りない…何かモヤモヤした雰囲気が漂っている…というときに役にたつワークをご紹介します。
チームの幸せとは?
「幸せになりたい」が万人の願いだとして、メンバーに幸せになってもらいたい、というのはチームづくりに関わるほとんどの人の願いなのではないでしょうか。
ただ、ここで問題になるのが、「幸せって何?」という基準が人によって、組織によって異なることです。とにかく大きな目標を達成して自分たちが稼ぐことが幸せだ!というチームもあれば、社会にインパクトを生み出すことが幸せだ!というチームもあれば、自分たち自身がお互いを尊重し合って育て合っていることが幸せだ!という会社もあります。
往々にして「とにかく金」とか「とにかく関係性」みたいに、どれかひとつの軸に偏る組織はうまくいきません。成果は出ても殺伐としてしまったり、仲良しクラブになって成果が上がらなかったりします。
じゃぁ、組織コンサル入れて、MVV定義しよう、課題を発見しよう、となる前に、いつでも誰でも簡単にできるセルフ・アセスメントのためのワークをご紹介します。
その前に、まず「幸せとは何か」を考えておきましょう。
さて、あなたが幸せな瞬間はどんな瞬間ですか?思い浮かべてみてください。
ゆっくりお風呂に入っている時。
友達と楽しくお酒を飲んでいる時。
大きなプロジェクトが良い結果に終わった時。
人それぞれ、挙げる「幸せ」は違うはずです。それも、ひとつではないと思います。
これらを整理する上で、ポジティブ心理学の父、マーティン・セリグマンは、以下の5つの要素を定義しています。

ポジティブ感情:楽しみ・喜びなどの前向きな感情・快楽
フロー状態:集中して取り組んでいる・没頭している状態
人間関係:周囲の人との良好な人間関係
意味:人生における意味・意義
達成感:成長・達成の感覚
これらの頭文字をとって、「PERMA理論」と呼ばれます。
チームの状態、悪くはないんだけど、何か足りないなぁ…というときには、これらのどれからが足りていない可能性が高いです。
完全に切り分けられるわけではありませんが、ドーパミン的な幸福(フロー状態・達成感・ポジティブ感情など)、セロトニン的な幸福(ポジティブ感情・意味など)、オキシトシン的な幸福(人間関係など)がそれぞれ含まれていることがわかると思います。
短期的にはどれかひとつでも成り立つのですが、長い目で見れば、人は、これらの要素のどれが欠けても「幸せ」とは言えない状態になるのです。
多くの幸福に関する議論は、この辺りがごちゃ混ぜかつトレードオフ思考になってしまっているので、うまく噛み合わないことも多いようです。
例えば「人間関係を大切にしたい人」(オキシトシン的)と「刺激を求めたい人」(ドーパミン的)がいたとします。「ビジネスのために集まってるんだから人間関係なんていらないでしょ」などと二元論的な議論になりやすく、短期的には噛み合いません。でも、長期思考+両立思考を取り入れながらフレームワークを眺めると「今は短期的な成長が重要だけれども、長期で見れば関係性に投資していく必要があるよね」と両方を大切にする意思決定ができるようになったりします。
自分で点数をつけてみる
まずは、自分で点数をつけてみるところから始めると、イメージしやすいかと思いますので、少し時間をとって、考えてみてください。ワークシートも用意していますので、もしよろしければご活用ください。
それぞれの項目について、過去1ヶ月の自分の点数は何点ですか?チームに所属している人は、チーム全体としての点数は何点ですか?(10点満点)

どんなことに気がつくでしょうか。
例えば、成果は出ているけどなんだか殺伐としている、というチームは、「ポジティブ感情」「人間関係」のスコアが低いかもしれません。
上から降りてくるタスクをひたすらこなしている、というチームは「意味」のスコアが低いかもしれません。
チームビルディングばかりを頑張っていたチームは、「達成感」「フロー状態」が足りていないかもしれません。
チームの点数は高いのに自分の点数は低い、という人は、自己犠牲的になって、助けを求められていないのかもしれません。
どうでしょうか。自分の「盲点」となる要素があったのではないでしょうか。
これらの点数をつけたら、なぜその点数をつけたのか、どこか変えたい軸はあるのか、あるとしたら何ができそうかを考えていくことになります。
チームでの対話がおすすめ
一人でももちろん内省することはできるのですが、一人ではなかなか思考が深まりづらいのではないかと思います。そこで、チームのメンバー同士でワークシートを入力して、それをもとに対話をするのがおすすめです。特にチームの状態については、お互いに見えているものが違っている可能性がありますし、対話によって相互理解・現状理解が深まります。
こうしたフレームワークに沿って対話をする意味は、
・抽象的な概念(例:幸福)についてより具体的な話をすることができる
・感情やバイアスを除外しやすくなる
・新たな視点を持つことができる
・客観的に自分のチームを捉えることができる
ことです。
例えば「今、チームの状態が悪い」という現実に気づいたとき、組織の専門家は「人間関係のせいだ」と考えがちです。営業リーダーは「目標達成できてないせいだ」と考えがちですし、ビジョナリなリーダーは「もっとMVVの浸透を」などと考えて、それに沿った施策を考えてしまったりしますが、実際の問題はもっと別のところにある、というのもよくあることです。
多くの場合「事実」→「原因」→「アクション」の思考にはバイアスが入り込んでいます。個人の思考には必ず盲点が存在しており、本来重要だが自分が重要視していないポイントを見落としてしまっている可能性が高いのです。
これらの盲点をなくして具体的な施策を考えていく上で、以下のような内容について、チームで対話してみると良いのではないかと思います。
その点数をつけた背景にある具体的なエピソード
全体からどんなことに気がつくか
何が目的に向かう上でのボトルネックになっているか
理想状態はどんな状態か
それぞれの項目のチームにとっての優先順位はどうか、個人にとってはどうか
チームと個人のバランスはどうか
阻害要因は何か
どんなアクションが取れそうか

アクションに落とし込む
ちなみに、それぞれのスコアをあげていきたい時のアクションのイメージは例えば以下のようなものがあります。他にもブレストしあって、自分ができるものに落とし込みましょう。

このような場で設定されたアクションは流れていきがちですので、具体的で実行可能か、必要なリソースに対してインパクトの期待値は十分大きいかをしっかり検討した上で、一人一人がお互いにアクションを宣言して、振り返りをするようにしましょう。
おわりに
チームビルディングのために「雑談の時間」などを取り入れているチームも多いのではと思います。そのときに、全くのフリーアジェンダでおしゃべりをするのも良いですが、このようなフレームに沿って対話をすることで、お互いの価値観の理解やチームの現状理解につながり、より豊かな時間になることも多いかと思います。ぜひご活用ください◎
コーチェットのチームコーチは、チーム内では深まりづらい対話のサポートや、チーム内で対話促進できるリーダーの育成をお手伝いしています🍀

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
