
テレビとマンガ、垣根を超えて強いコンテンツを作っていく〜マンガボックス社長・副社長対談〜
2013年から提供を開始したアプリ「マンガボックス」。
有名作家の人気作から新進気鋭の話題作まで、枠にとらわれない幅広いラインナップを擁し、マンガボックス編集部オリジナル作品の『ホリデイラブ~夫婦間恋愛~』『にぶんのいち夫婦』はTVドラマ化、週刊少年マガジン編集部作品の『恋と嘘』はアニメ・映画化するなど数々のヒットコンテンツを生み出してきました。
今回はマンガボックスの現副社長である十二竜也さんが登場。株式会社マンガボックスの生誕秘話や、TBSとの合弁会社になったことにより、テレビとマンガの世界が出会いどんな化学反応が起きたのか。マンガボックス社長の安江亮太さんとともに、2人だからこそ語ることのできる物語を聞いていきます。

株式会社マンガボックス社長 安江亮太(やすえ・りょうた)
2011年DeNAに新卒入社。DeNAでは韓国やアメリカでマーケティング組織の立ち上げを手がけたのち、『マンガボックス』、『エブリスタ』の二事業を管掌。その後、マンガボックスを会社化させ、現在代表取締役社長に。Twitter: https://twitter.com/raytrb

株式会社マンガボックス副社長 十二竜也(じゅうに・たつや)
1989年にTBSに入社。バラエティのADからキャリアをスタートさせ、テレビ編成部でドラマ企画や映画の買い付けなど多くのジャンルを経験したのち、ドラマ制作部長、映画・アニメ事業部長に。その後マンガボックスと出会い、現在副社長。
「誰かの心に響くような作品を本気で作りたい」マンガボックスが法人化を決めた理由

──このマンガボックスのnoteでは、マンガボックスの考え方をはじめとして、マンガ業界、そしてコンテンツの未来まで、様々なお話をしていただきたいと思っています。記念すべき第一回目は、社長の安江さんと、副社長の十二さんにご登場いただき、お二人の出会いから、会社設立の経緯、そしてマンガボックスの展望などについてお伺いできればと思います。
安江:そうですね、これを話すにはまずマンガボックスが会社化した経緯からお伝えする必要があります。マンガボックスは最初、DeNAの1事業として立ち上がりました。DeNAってプラットフォームを作ることをすごく得意としているところがあって。たとえばMobageとかPococha(ポコチャ)とか、多くの人がそこで楽しめる"場"を作るのが上手なんですよね。横浜DeNAベイスターズの横浜スタジアムなんかも、そういった一例だと思います。
十二:DeNAといえば、数々のサービスを生み出して、大きくしてきたイメージがあります。
安江:そうですね。で、その中でも僕は当時、1事業部としてローンチしていたマンガボックスの責任者をしていました。そこで、数々のマンガや作家さん、編集者、そして同業界の方々と触れ合ううちに、僕の中で、「後世に残るようなコンテンツを自分たちでも作りたい」という気持ちがふつふつと湧いてきたんです。そして、もっとエンタメに事業方針を振り切るには、DeNA内の一事業としてだけでやり続けるのが必ずしもベストではないと感じるようになっていました。

十二:なるほど。でもそれはDeNAの中ではできなかったことなんですか?
安江:ここは難しい話なんですが、当時のDeNAは“場”を先に作るという考え方が強かった印象があります。コンテンツとプラットフォームの議論をするときによく出る話なんですが、鶏卵の議論になりがちです。どちらかというと僕は“コンテンツ イズ キング”、作品ありきなんじゃないかと。だから、もっと多くのオリジナルのコンテンツを作りたいという思いがありました。"場"を作れば良いだけじゃなくて、誰かの心に響くような"作品"を本気で作りたくて。その辺りの考え方でよく当時の社長と喧嘩をしてました。まぁ自分の論理が稚拙で喧嘩にもなってなかったとも思いますが(笑)。
十二:コンテンツに特化した事業を立ち上げて成長させるのって、お金もかかりますからね。でも、その考え方だとなかなかうまくいかないことが多かったんじゃないですか?
安江:そうですね。かなり苦しい時期でした。「マンガボックスはまだ成長余地があるんです!」っていう主張はしていたんですけど、他にも社内にイケてる事業がたくさんある中、DeNA規模の会社のお金や人材を回してもらうのは一定の限度があって。まあ僕がDeNAの社長の立場でも同じ判断をすると思います。でも、このままじゃマンガボックスは僕が思い描いているように成長できないと感じたので、DeNAからスピンオフし、会社化することを決意しました。そこで、出資主となりうるパートナーを探しに行ったんです。
マンガとテレビ、お互いの欲しいところが、上手く組み合わさった瞬間

十二:それでのちに出資会社となるTBSと出会うわけですね。話が繋がってきました(笑)。
安江:そうですね(笑)。マンガボックスを法人化するためにいろんな形を模索する中で、TBSと協業すれば新しいコンテンツの形が生まれるんじゃないかと思ったんですよね。会社設立が決まった後、当時の社外取締役の一人として関わってくれたのが十二さんとの出会いでした。
十二:そうですね。僕は新卒でTBSに入社して、バラエティのADからPD、テレビドラマの編成、海外映画の買い付け、ドラマ制作部の部長、直近は映画・アニメ事業部の部長をしていました。安江さんとお会いしたのは、映画・アニメ事業部のときでしたね。
──十二さんから見て、そのときマンガボックスはどのような印象だったのでしょうか?
十二:そうですね、同じようなものを必要としているというか。まさにTBS側も新しいプロセスでコンテンツを生み出す力をちょうど必要としているときだったんです。例えば、テレビドラマって、ヒットすると、ステーションブランドを上げることになりますが、直接的にコンテンツから得られる収益は映画やアニメのように半永続的に続くものではないんです。小説やコミックが原作の場合、テレビ局は大元の版権を持っていませんから。なので、ものづくりのもっと上流、つまり原作から立ち上げられる仕組みを欲していました。そんなときにちょうどマンガボックスの話をいただいて、渡りに船だと。

安江:お互いが課題としているところがうまく組み合わさったんですよね。マンガボックスはコンテンツを生み出すとこまではチームとして組成し始めていたんですが、拡散する力が足りなかったので。TBSというパートナーを見つけることによって、IP創出におけるバリューチェーンに必要な登場人物が揃ったなと。
十二:はい。お互いがWin-Winでしたので、TBSとして出資させていただいて合弁会社化することを決めました。その後、僕もマンガボックスにジョインすることになりました。
組織を透明にしていく、今の時代に合わせた垣根のないものづくり

──TBSの資本が入り、DeNAとの合弁会社となったマンガボックスですが、マンガの領域と、テレビの領域とで、コンテンツの作り方や組織のあり方等で、やはり最初はぶつかる部分が多かったのではないでしょうか?
安江:それが意外と大きなトラブルもなく、上手く行き始めているなという印象でした。
十二:テレビとマンガって、作品を制作するっていう意味で世界観が近いんだと思います。文化が近いというか。制作の全体の大きな流れとかがお互いなんとなく掴めていたので、チーム同士のやりとりやスケジュール感もスムーズに共有できましたね。
安江:それにテレビとマンガって事業シナジーが分かりやすいんですよね。マンガが原作でドラマ化になることもたくさんあるし。実際にマンガボックスの『ホリデイラブ〜夫婦間恋愛〜』というマンガ作品はテレビ朝日でドラマ化してヒットしました。マンガはドラマやアニメの原作になっていくことができるので、テレビ関連事業への展開がしやすいんですよね。

十二:そうですね。その逆もしかりで、先々、ドラマ化するためにマンガを作ることも可能です。これはマンガボックスとTBSが一緒にやってみたからこそわかったことなんですが、ドラマを作ろうと発想したアイデアって、マンガの構造に当てはめると分かりやすくなることが多いんです。そういう意味でもシナジー効果が起きていて、プロデューサーやディレクターの発想の自由度がぐっと広がったように感じます。
安江:例えば、TBSの『リコカツ』というテレビドラマがあるんですけど、それはドラマが放映される同時期に、マンガ版の配信が開始されました。正確に言うとドラマ開始よりも少し前ですね。また、テレビ東京の『にぶんのいち夫婦』というテレビドラマは、マンガボックスでのマンガが電子書店を中心に売れ、その作品をベースにドラマを制作いただきました。いま水面下では、マンガの編集者とテレビドラマのプロデューサーが一緒になってコンテンツを制作し始めています。業界だとなかなかない例だと思いますが、マンガとドラマ、どちらかが先行するケースもありえますし、一緒に作るという意欲的な取り組みも始まっていてワクワクしています。
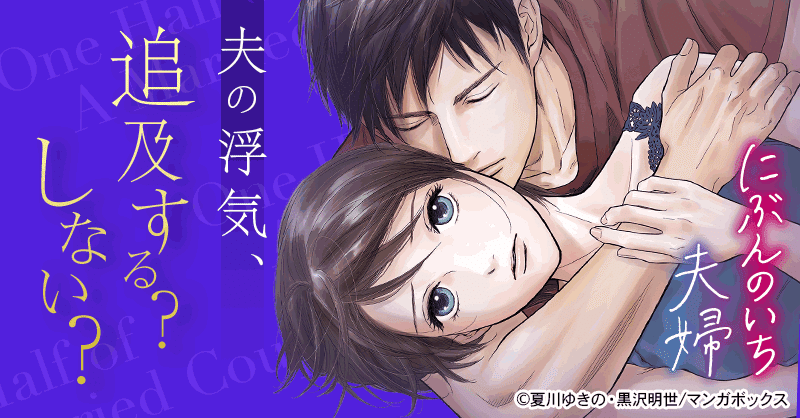
https://www.mangabox.me/reader/94179/episodes/36725/
十二:いい化学反応が起きていますよね。アウトプットの手法は異なっても、物語のコアの部分ってマンガとテレビドラマどちらにも共通して言えることがあると思うので、マンガ編集者とドラマプロデューサーの垣根はあまり作らず制作できていると思います。最終的に仕立てる段階で、それぞれのプロが担当するような、柔軟な組織になっていますね。
安江:これはTBSとDeNAの合弁会社であるマンガボックスだからこそできることだと思っていて、各々の世界で身につけてきたノウハウを共有して、一緒にいい作品を作っていくためにどうしたらいいのかを考えていきたいです。オープンに共有して、組織を透明にしていく動きは今の時代っぽいなあと思います。
「僕たちの世代の人間は何も言わずに若手に任せた方が、いいものができるんですよ」

安江:とはいえ、TBSの方と仕事をしていく中で、DeNAにはなかった文化もありました。それは1つのプロジェクトに関わっている人数がすごく多いこと。DeNAはセクションに合わせて独立していて、事業責任者との意識摺り合わせが行われたら組織がダイナミックに動いていくという感じです。関係者が多いこともあり、TBSの方がチーム全体を動かしていく難易度は高いかもしれません。でもそれはDeNAではあまりなかった別のチャレンジなので、面白いなとも感じています。
十二:そうですね、母体が大きいですし、歴史のある会社なので、その面では大変かもしれません。とはいえ、僕が約30年間TBSにいた中で、ここ最近の変わりようはすごいです。今のTBSには「なんかおもしろそうじゃん! やってみようぜ」という風潮があります。今回のマンガボックスとの協業もそうですが、TBSは今まで“テレビ”にこだわっていたので、異業種の外部の会社と何かを一緒にやることがあまりなかったんです。
安江:その風潮ができたのはなぜなんでしょうか?
十二: そうですね、TBSがここ数年で柔軟性がでてきたのは、テレビが昔ほど格段に強いメディアでなくなったからというものあるかもしれませんね。僕らが30代のときと今働いている30代の社員とでは考え方が全く違い、いい意味で変なこだわりがなくなったというか。僕らの世代は「死んでも制作がやりたくてここに来ました!」っていう感じの人間ばかりだったんです。

安江:なるほど(笑)。
十二:けど、最近は、考え方やスタンスが柔軟なんです。必ずしも、番組を作るためだけにテレビ局に入ったんじゃない、と。だから、今は年次関係なく、様々なクリエイティブの現場にどんどん新しい若い社員が投入されています。そして、その人たちにどんどん任せて行こうという会社の空気を感じますね。
安江:マンガボックスの組織づくりもそのあたり近いかもしれません。僕ももうクリエイティブの現場にはほとんど入らず、現場のメンバーに一任しています。
十二:そうですね、上の人間はあまり口を挟まない方がいいのかもしれませんね。
安江:変に社長が首を突っ込むと、忖度が起こって、結局コンテンツがつまらなくなってしまうんじゃないかなって(笑)。マンガボックスには強い人材が集まっているので、僕は会社の戦略を練ったり、メンバーが事業に集中できる環境を作ったり、そういうことに終始していこうと思っています。
十二:マネジメントに専念するということですね。
安江:そうですね。一番売れた作品を作った人が編集長になるべき、って考えもあると思うのですが、その考えもわかる一方で、「ものづくりの現場で価値を最大限出せるプレイヤー」と「人や組織を組み立てていくマネージャー・編集長」って求められるスキルが違うと思うんですよね。
十二:たしかにプレイヤーとしては優秀な人でも、マネージャーとしては必ずしもそうであるとは限らないですからね。その2つを全く別のものだと考え、人を配置しているマンガボックスは、他の出版社とは違う組織づくりができているのかもしれませんね。
いつか興行収入100億を超える作品を生み出したい

──お二人にお話を聞いてきた中で、マンガボックスは成り立ちから組織づくりまでユニークな企業だなという印象を感じました。
十二:独特な個性をもっている組織だと思います。それに本当にメンバーが優秀な人ばかりで、ひたすら感心してますね。個人差はもちろんあるけど、判断力もあるし、人に説明して納得させる能力もあるし、会話してても、皆さん面白いんですよね。
安江:ロジック整理ができるというDeNA的な良さを持っている人ももちろんですが、いろんな人の感情に寄り添える社員が多いですよね。性格がいい人が多いなと思います。
──最後に今後のマンガボックスの目標を教えてください。
十二:いつかこのみんなで、多くの人が認知するような作品を生み出したいですね。マンガから映画化して興行収入100億くらいいっちゃうような。
安江:間違いないです。強い作品を作りたいですね。
十二:天体望遠鏡で見ているような話だけど、あながち無理ではないんじゃないかなあと僕は思いますよ。でもそれには多様な人の力が必要になるので、みんなが場数を踏めるようにチャンスを引っ張ってくるのが僕の仕事だと思っています。そして、そんな経験を継続していくことで、いい意味での変貌を遂げられるのではないでしょうか。だからこそ、これからはいろんな能力・個性を持った人がきてほしいなと思います。
安江:いろんな人が集まって多様性があるのが僕たちのいるマンガボックスの良さなので、それを知ってくれたらいいですね。振り返ればここまで長かったけど、まだまだ僕たちは道の途中にいるので、一緒に歩いてくれる仲間たちを見つけながらこれからも頑張っていきましょう!
マンガボックスでは現在積極採用中です。ご応募お待ちしています!https://mangabox.super.site/#d41b571efd714f77a1dc31ed238c381d
(文・写真/高山諒)
