
40年の歳月を一瞬で忘れるほど鮮烈なストーリーテリング。BBC『Miners’ Strike: A Frontline Story(炭鉱労働者のストライキ: フロントライン・ストーリー)』
「私のマスコミとの歴史、特にBBCは、我々の言うことを捻じ曲げ、重要な部分を編集する傾向がある。私が何を伝えたいかではなく、彼らが何を望んでいるかがすべてなんだ」。元炭鉱労働者のデイヴ・ローパーは、冒頭のアウトテイクで、そう語った。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
BBC『Miners’ Strike: A Frontline Story(炭鉱労働者のストライキ: フロントライン・ストーリー)』は、1984年の炭鉱ストライキに参加した労働者たちが、何が起こったのかを彼らの視点から曲解なしに語る。炭鉱ストライキといえば、英国の現代史を語るのには欠かせないので、出来事として認識している人は多いかと思う。私自身も史実としてのストライキは知っていたし、それにまつわる映画やドラマもいくつか見てきた。しかし、この作品は、ストライキに参加した炭鉱夫たち、そしてその家族たちが、自らの経験として語る貴重なインタビューに、実際の映像を交えたスポークン・ドキュメンタリーであり、ここでは、より人間の感情、生活、人生に関わる話が聞ける。英国を一変させたこの大規模ストライキから40年。実は観る前は、レビューを書こうと思っていたのだが、観終わった後、彼らの語る一言一言がとても重要に思えてきて、結局は文字化することにした。映像無しに理解するのは、難しいと思うし、文字だけで実際どれくらい伝わるかは分からないが、放送に沿ってできるだけ彼らの言葉が届くよう努めた。いくつか聞きなれない言葉が出てくると思うので、先に説明しておく。
マイナー:炭鉱労働者、鉱山労働者
ピット:炭鉱、坑道
ピケット:ストライキの間、職場やその他の場所の外に立って抗議したり、他の人が仕事にいかないように説得しようとしたりする人またはグループ。
ピケットライン:職場の外や入り口付近に集まる人々を指す。ストライキを行う労働者、雇用主から締め出された労働者、労働組合の代表者などが含まれる。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
40年前、17万人のマイナー(炭鉱夫たち)がストライキを行った。1年間、マイナーとその家族たちは、政府に対抗し...お互いに謀反しあった。これは、当時、この紛争の最前線にいた15人の男女の物語である。
デヴィッド・ニクソン(南ヨークシャー炭鉱夫):炭鉱での仕事は、とても過酷で危険でだった。でもそこには笑いがあり、ユーモアがあり、仲間意識があった。皆お互い助け合い、作業後のシャワーでは、背中を洗おうか?と訊いて、誰かが同僚の背中を洗い出すと、それを見ていた別の人がその人の背中を洗い、最終的に4人くらいがお互いの背中を洗い流すということもあった。そこには意識せずとも、深い友情が生まれていた。

デイヴ・ローパー(南ヨークシャー炭鉱夫):1984年当時、私は29歳。結婚して子供が一人、妻は二人目を妊娠中だった。自宅近くのシルバーウッド炭鉱で働いていた。仕事は好きだったが、危険で事故が多かった。一度、目の前でワゴンが制御不可能になり、そこにいた作業員にぶつかってしまったことがあった。即死だった。

リサ・マッケンジー(炭鉱夫の娘):曾祖父、祖父、父、皆炭鉱夫だった。祖父は以前、自分たちがいかに重要な仕事を担っているかを語っていた。人々の家に明かりが灯るのは自分たちが働いているからだと。炭鉱コミュニティーでは、ピットは人生であり、仕事以上のものだった。お金はなかったが、仕事には忠実だった。私自身このコミュニティーで育ち、常に安心と安全を感じていた。それが1984年にすべて失われてしまった。

保守党圧勝により、マーガレット・サッチャーは、すでに高い失業率であるにもかかわらず、さらに厳しい経済政策を打ち出す。サッチャーの計画には、国有産業の民営化と労働組合の権力抑制が含まれていた。そしてそれは最もパワフルな組合を持つ、石炭産業にまで及んだ。

ニュース「全国石炭委員会は、石炭の生産を減らすことを明らかにしました。これにより向こう12か月中に12のピットを閉鎖、2万人が職を失うことになります」。
閉鎖に名前の挙がった最初の炭鉱の一つが、南ヨークシャーのコートンウッド炭鉱だった。
ドン・キーティング(南ヨークシャー炭鉱夫):私は、コートンウッド炭鉱で働いていた。ある日ミーティングに呼ばれて、「石炭委員会がコートンウッド炭鉱を2週間のうちに閉鎖する」と聞かされた。何の相談も話し合いもなかった。
ジャッキー・キーティング(ドンの妻):ショックだった。4月から全く収入が無くなる。私たちの知っている家族はみな同じだ。ハードワーキングな人々にこのようなことをするなんて、正しいと言える?
ニュース「石炭委員会は、コートンウッド炭鉱は生産性がなく、経済性もないと主張していますが、組合側は、ピットは生存可能で上質の石炭を生産していると反論しています」。
デイヴ:誰もストライキなんかしたくなかったんだよ。それはいつだって最後の手段だろ?
1984年3月6日:ストライキ1日目
ヨークシャーのすべての炭鉱が、閉鎖を阻止するためストに突入。全国炭鉱労働組合(National Union of Mineworkers、NUM)指導部は、すべてのマイナーにストに参加するように呼び掛ける。

アーサー・スカーギル(NUM会長)「我々マイナーが勝利すると確信しています!それには、メンバーの固い決心と結束が必要です」。
デヴィッド・ニクソン:皆、ストは長くは続かないと思っていた。すぐに仕事に戻って再び稼げるだろうと。以前石炭委員会と争ったことがあったが、勝利していたので、我々には自信があった。ストライキの目的は電力をカットすることだった。我々の産出する石炭のほとんどが発電所に供給されていたから。石炭の供給を止めれば、電力が無くなるんだ。
【ノッティンガムシャー】
レス・セイント(ノッティンガムシャー炭鉱夫):私は、ストライキには行かずに働き続けた。実は、ストライキが発生する2年前、アーサー・スカーギルがオラトンに来たので、私は同僚と見に行った。スピーチは力強く素晴らしいものだったが、聞けば聞くほど、こう感じたからだ。彼は、我々鉱山労働者たちに興味があるのではなく、政府を転覆させることを目的としているのだと。だから私はストライキには参加しなかった。北ノッティンガム地帯の炭田は肥沃だった。だから炭鉱夫達の中には「自分たちの炭鉱は大丈夫だ」と思っている者もいた。

アンディー・ビアード(ノッティンガムシャー炭鉱夫):1984年当時、私は22歳だった。ノッティンガムシャーでは、ストライキをするかどうかという意見は半々に分かれていた。中には、命令されるのは御免だ、という人もいたが、私もその一人だった。しかし、私の兄は違った。

スティーヴ・ビアード(ノッティンガムシャー炭鉱夫、アンディ―の兄):ストライキに行かないという選択肢はなかった。コートンウッド炭鉱閉鎖の話はすでに進んでいたし、他の炭鉱も閉鎖になると聞いた。そうなれば我々の産業は死んでしまうし、いま戦わなければいけないと思った。

アーサー・スカーギル(NUM会長)「(TVインタビューで)私のノッティンガムシャー・マイナーたちへのアドバイスは、皆がストライキに参加することです」。
デヴィッド・ニクソン(南ヨークシャー炭鉱夫):ヨークシャーは100%揺るぎない態度だった。そこで、我々は別の炭鉱へ行った。ストライキに参加するように呼び掛けるために。これがピケティングだ。
ブルース・ウィルソン(南ヨークシャー炭鉱夫):南ヨークシャーとノッティンガムシャーは隣同士。さらに全国マイナー組合は一つの団体なので、ノッティンガムシャーはその一部だ。だから、彼らは全員ストライキに参加しなければならない。

デヴィッド:ヨークシャーからのピケット達は、別の炭鉱へ行って、ストライキをサポートする、もしくは参加するように勧める(=ピケティング)。
ブルース:自分の炭鉱でピケティングするのは、ただのピケットで、別の炭鉱でピケットをすることを、フライング・ピケットと呼ぶ。恐らく2~300人の南ヨークシャーからのピケットが来ていたと思うが、私たちは炭鉱入り口に立って、仕事に来る人達を説得した。彼らが(仕事に行くのをあきらめて)帰っていけば、拍手を送り、もしピケット・ラインを越えて仕事に行くようであれば、ブーイングをした。仕事に行く人たちを「Scab(スキャブ、スト破り)」と呼んでいた。確かに罵り言葉を浴びせたりもしたけど、ピケティングは楽しいゲームのようなものだった。

3月14日:ストライキ9日目
デヴィッド・ニクソン(南ヨークシャー炭鉱夫):我々は、ノッティンガムシャーのオラトンに行くように指示された。
レス・セイント(ノッティンガムシャー炭鉱夫):ノッティンガムシャーと南ヨークシャーの間には、いつも何らかの敵対心があった。オラトンの人々は単にヨークシャー人が嫌いだったというのもある。ヨークシャーの人々がオラトンを(ピケティングの)ターゲットにしたのは、ここを制覇すれば、あとはドミノ式だと考えたからだ。でもそれは間違いだった。
トレイシー・ウィリス(ノッティンガムシャー警察):オラトンの人は、言ってみれば頑固者だ。独断的とも言える。何かをやるように強要しようなんて思いもしないだろう。

デヴィッド・ニクソン(南ヨークシャー炭鉱夫):我々が、ノッティンガムシャー、オラトンのピケットラインに到着すると、警察が我々を入り口の両側に配置した。
スティーヴ・ビアード(ノッティンガムシャー炭鉱夫):あの日、ヨークシャーからピケット達が到着していた。私は、ストライキ中だったのでピケット・ラインを超えることはなかったが、ノッティンガムシャーのオラトンでは、炭鉱夫たちにストライキをさせるのは非常に困難だった。
トレイシー・ウィリス:私はその日非番だったが、自分のいる場所から、警察車両や労働者を運ぶバンが入って行くのが見えた。私は地元民だから、よそ者が大勢いるのが分かった。NUMのバッジを付けた者や(サポートする)フットボールチームのマフラーから見分けがつく。地元民たちは、南ヨークシャーから来た人たちを見て、なんでお前らはここにいるんだ、何やってるんだと思っていた。警察は炭鉱に仕事に行く人たちを守っていた。
デヴィッド:スト破りたちがピケットラインを越えて、仕事場に入って行くまで、警察との押し合いがあった。夜シフトの作業者たちが入って行った後、何人かのピケット達は帰宅した。しかし、どこからか、叫び声が聞こえた。奴らが車をダメにしやがったと。家に帰れない。そこで我々は追いかけた。
レス:私たちはその時パブにいたのだが、誰かが、喧嘩が始まった!と駆け込んできた。行ってみると、二組の炭鉱夫たちがレンガや道路の石などを投げ合っていた。
デヴィッド:走っている途中、誰かが倒れた。レンガが当たったようだと私の友人が言った。周りにいた人たちが、彼を道路脇の芝の上に横たわらせ、後に救急車で運ばれた。2時間くらいたった後、その人が亡くなったと聞いた。
スティーヴ・ビアード:最悪だった。オラトンの作業員たちでさえも、自分自身の安全をどのように確保しているかを理解していなかったのだ。私は弟(アンディ)のことが心配だった。彼がピットにいることを知っていたから。
アンディ:仕事中に、できるだけ早くピットから出るようと言われた。理由は分からないが、ピケット・ラインで死亡者が出たと。オラトンの炭鉱夫が殺されたのだと思って、怒り心頭だった。地上にあがると、ヨークシャーからのピケットが殺されたと聞いた。我々は自力で自宅へ帰らなくてはならなかった。ヨークシャーからのピケット達がまだ残っているというのに。警察のエスコートも管理会社からのヘルプもなかった。自分で自分の身を守るしか方法はなかった。恐怖を感じた。
デヴィッド(南ヨークシャー炭鉱夫):とにかく誰かを攻撃しろ、復讐だ!という感情が沸いていた。
スティーヴ:何か対策をたてるほど、十分な警察はいなかった。すると(アーサー・)スカーギルがどこからともなく現れた。
デヴィッド:アーサーは、踏み台の上に立ち「まずは1分間の黙祷を捧げよう」と言った。その黙祷が、そこにいた皆に何が起こったのかを振り返るきっかけとなった。我々はそのまま帰宅した。
ニュース「亡くなったのは、ヨークシャー、南カークビーからのピケット炭鉱夫、デヴィッド・ジョーンズさん、24歳。死因は、鉄柱、もしくは車両との衝突と伝えられています」。
アンディ:あの死亡事故以来、もうこんな経験はしたくないという同僚もいた。そのために、ピケット達は活動していたのだ。炭鉱に戻らず、ストライキに参加することを奨励することを目的としていたのだから。その時点で私も(仕事に行くのはやめて)ストライキに参加することにした。
何人かのノッティンガム・マイナーはストライキに参加することを決意したが、大多数は、引き続き炭鉱で働いていた。
3月19日:ストライキ14日目
ニュース「炭鉱夫間の亀裂は、過去最大となりました。ヨークシャーからのピケット達を追い返すため、3000人の警察官が出動しています」。
「英国全土から警察や車両がノッティンガムシャーに集められ、オペレーションを敷き、働きたい炭鉱夫達が、引き続き作業ができるように誘導しました」。
トレヴァー・コックス(テムズ・ヴァレー警察):自宅から離れて勤務するということで、就寝場所も確保されていた。いろいろな意味でショックだったが、給料は2倍に跳ね上がった。電子レンジを買う者、冷蔵庫を買う者、中には車を買う者もいた。「これはスカーギルの洗濯機だ。ありがとうスカーギルさん」などと言っていた。
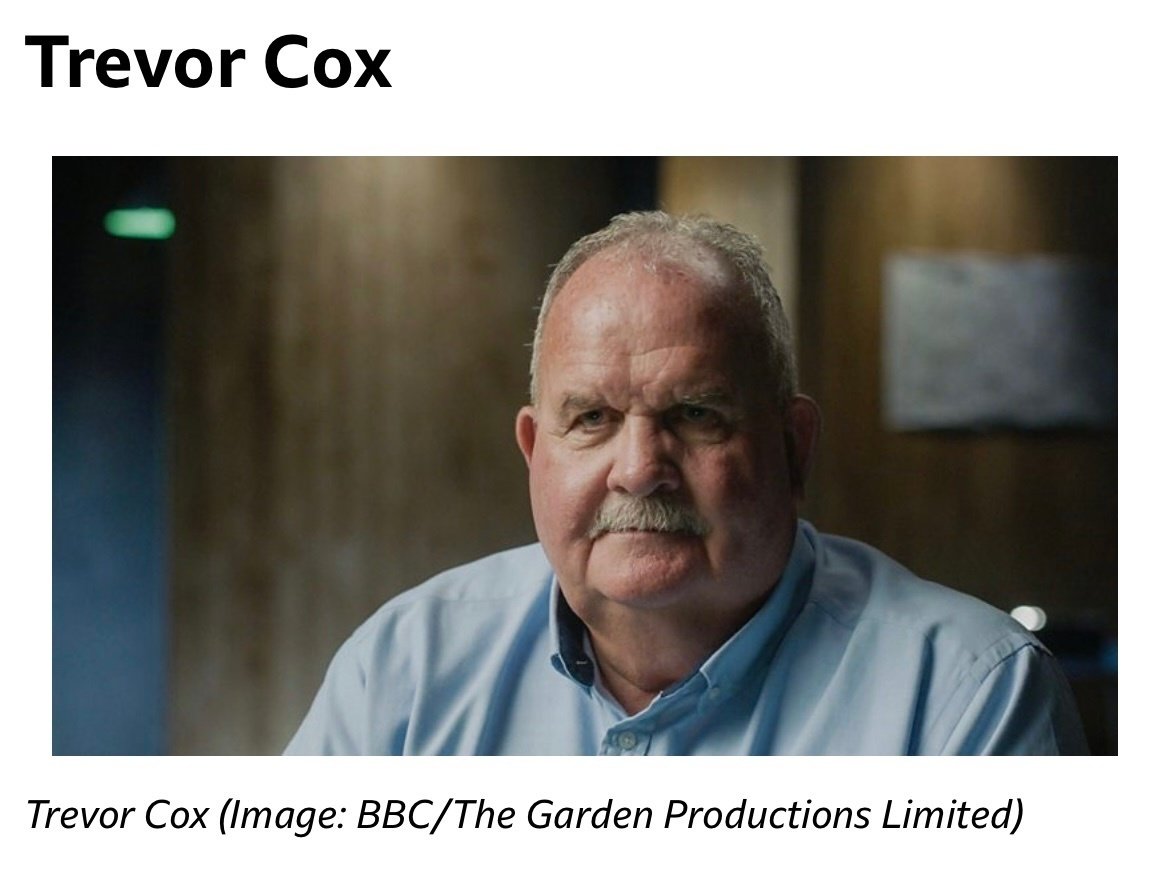

トレイシー・ウィリス(ノッティンガムシャー警察):ピケット達が入ってくるのを防げば、問題は発生しない。じゃあ、やりたくてやっているのか、と訊かれれば、それは違う。(警察は)政治的に利用されているのか、もちろんそうだ。それを気付かないのは馬鹿だ。
ニュース「空からの撮影で、閉鎖されている道路のパターンが見えてきます。そこでは、主要道路をすべて封鎖、検問し、炭鉱夫たちが乗っている車両かどうかを捜査しています」。

警察官「引き返すか、そうでなければ逮捕になります」。
運転手(炭鉱夫)「それだったら、私を連行するしかないな。答えはノーだ」。
マーガレット・サッチャー「TVを観ている私たちのほとんどは、警察に賞賛を贈るでしょう。彼らのおかげでマイナーたちは炭鉱を開けることができるのです。警察は本当に素晴らしい仕事をしてくれています」。
ブルース・ウィルソン(南ヨークシャー):ピケティングに行くのに前も後ろも警察に挟まれたことがあった。止められて、「どこから来たんだ?どこに行くんだ?」と訊くから、ノッティンガムシャーにピケティングに行くと言ったら、「ここで引き返してヨークシャーに戻れ」と言われた。この時、自分のご先祖さんたちが、自由と民主主義のために二つの大戦で戦ったのを思い出した。こいつらに、自分の国で、私が何ができて、何が出来ないのか指図される筋合いはないと思った。「ノッティンガムに行くと決めたら行くんだ、馬鹿野郎!」って言ってやったよ。横道にそれて、そこから行ったんだ。その後も、何とか突破する方法を考えていた。決心は硬かった。仲間を車のトランクに入れたり、アクセントを変えたりして突破していた。
リサ・マッケンジー:父はピケット・マネジャーを務めていた。ただの炭鉱夫だったから戦略などの知識はなかったが、すべてをコード化して、エクセルのようにスプレッド・シートを作り、どこに行くのか、警察に知られないようにしていた。
トレイシー・ウィリス(ノッティンガムシャー警察):このストライキは長引く、と感じていた。そして、今よりももっと状況は悪くなる、と知っていた。強い意思のぶつかり合いになると。
4月19日:ストライキ45日目
英国全土の炭鉱夫の80%がストライキに参加していた。しかし、レスターシャー、ダービーシャー、ノッティンガムシャーでは意見が割れていた。
レス・セインツ(ノッティンガムシャー炭鉱夫):私は、ストライキをするべきかどうか、国民投票を実施するべきだと思っていた。
デイヴ・ローパー(南ヨークシャー炭鉱夫):80%がストライキに参加しているんだ。なぜ国民投票の必要がある?
NUM代表団は、全国ストライキの国民投票を開催するか、地方スト継続かの是非を決定するため会合を開いた。
ニュース「本日ちょうど1:15過ぎ、NUM代表のアーサー・スカーギルがサポーターたちに揉まれながら登場しました」。
アーサー・スカーギル「今回の会議で、すべての地域で既にストライキを行っている80%の炭鉱夫達と共にストライキを続行することをすべての炭鉱夫達に呼びかけることに同意いたしました!」
ニュース「全国ストについての国民投票に関する言及はなく、ストライキ続行となりました」。

アンディ:「アーサー、何をやっているんだ?間違っている。ちゃんと国民投票をし、大多数を得た上で、皆にストライキを呼びかけるべきだろう?」と思った。この時初めて疑念が湧き出てきた。このままストライキを続行するべきだろうか?それが正しいことなのか?
レス:もし国民投票をしていたら、(自分はストライキには行かないが)ストライキを続行するほうに投票していただろう。ピケットラインではなく、投票箱を通すべきだった。この時から、このストライキが、この論争がおかしくなり始めた。
ブレンダ・ボイル(南ヨークシャー炭鉱夫の母):5人の息子の内4人がシルバーウッド炭鉱で働いていた。誰もストライキがこんなに長く続くとは思っていなかった。

5月4日:ストライキ60日目。
ストライキに参加した炭鉱夫たちはすでに二ヶ月間、給料なしの生活を送っていた。
ニュース「ストライキで給料が支払われない間、炭鉱夫の妻たちで結成されるサポート・グループはスープ・キッチンを設立しました」。
ブレンダ:なけなしの材料から何かを作り出すことを学ばなければならなかった。できるだけ満腹になるようにミートとポテトのパイをよく作った。おねだりチームは、店をまわっては材料をねだって、何の動物なのかも分からない肉を貰ってきていた。

スティーヴ:芋やニンジン、ネギなどを農夫から貰ったり、時に野生のウサギやキジなどの動物を捕獲することもあれば、すぐにスープ・キッチンに持って行った。これで美味しいシチューができると思って。
ブレンダ:「シチューの中から何か変なものが出てくるかもしれないけど、飲み込まないで。多分動物の歯だから。もし自分が歯もげだったら、その歯を入れとけば?文句言わないの。ディナーであることに間違いはないんだから」と言っていた。
デイヴ:スープキッチンは、とにかく一日一食のちゃんとした食事ができるところだった。あの時は本当に厳しかった。貯金もなかった。子供が一人いて、もう一人がちょうど生まれたところだった。病院にいた妻が「よく分からないが、スペシャル・ケアに連れていかれた」と言う。いろいろと疾患があったようだ。そして生まれて1週間後、病院から連絡があった。「残念ですが、アダムは亡くなりました」と。最悪の出来事だった。葬儀の補助金を申請したが、ストライキ中だから権利がないと言われた。葬式にいくらかかるのかも分からなかった。葬儀屋に、「亡くなった乳児がいるが葬式金がない。ストライキ中で金がないんだ」ということを伝えたら、それなら、最近亡くなった人の葬儀をするが、乳児なので、一緒に棺に入れてもらえるかどうか、親戚に訊いてみると言われた。結局、亡くなった人の棺に一緒に赤ちゃんの死体を入れてもらい、無料で息子の葬式を出すことができた。葬儀屋が、火葬場を教えてくれたが、葬式には行かなかった。他人の葬式に参列して、あれは誰だ、となるのも嫌だったし、その人たちからすると、あれが葬式代も出せない親だ、と思われるのも嫌だった。少しのプライドが邪魔した。とりあえず、ありがとうと伝えてくれとだけ言った。クソ保守党のせいで、ローンを組むことさえ出来なかった。
5月27日:ストライキ83日目
アンディ:ストライキ中はとりあえず物を売ったりして何とか生計を立てていた。持っている物はなんでも売った。スープ・キッチンに行くと、皆、もううんざりしていた。やるやると言っていた国民投票は一度も行われず、何かが変わるべきだと感じていた。このままではダメだと思った。そこで、仕事に戻ることにした。頭を低くして、誰とも話さず、スープ・キッチンに行くのもやめた。とにかくストライキ中の人との接触を避けた。仕事に戻るかについて、(兄の)スティーヴと話したかどうかは憶えてないけど、彼はこのことを知ると、私に背を向けた。
スティーヴ:感情的にはなったが、仕事に戻るのは自身の決断だ。誰もストライキを強制したりはしない。弟を恋しく思うか?イエスだ。
トレイシー・ウィリス(ノッティンガムシャー警察):覚えておいて欲しいのは警察も生身の人間だということだ。唾を吐きかけられ、物を投げられ、暴言を吐かれる。ピケット達に暴力を振るわれる同僚もいた。でも警察が絶対に正しかった、とは言わない。
ブルース・ウィルソン(南ヨークシャー):警察はピケット達を逮捕するだけでなく、地面に押し付け警棒で殴りまくった。病院送りになるまで。
ドン・キーティング(南ヨークシャー炭鉱夫):私はかつて、Grenadier Guards(イングランドの近衛歩兵連隊)で北アイルランドに駐屯していた。だから、警察を尊敬するのが当たり前だった。ストライキが始まった当初からピケティングに参加しなかったのは、パートタイムで消防士の仕事をしていたからだ。しかし、ピケティングから帰ってきた炭鉱夫達が「警察がああした、こうした」と言うので、信じるには自分の目で確かめるしかないと思った。

ブルース:あの日があんなに大事になるとは思っていなかった。日曜の夕方7時に、シルバーウッド炭鉱の事務所バギンズに行くと、「明日のお前のターゲットはオーグリーヴだ」と言われた。
初夏には、南ヨークシャーのオーグリーブ・コーキング工場は、炭鉱夫達と警察の衝突の場となる。ピケット達はコークス(石油・石炭精製物)が工場から出ていくのを阻止しようとしたが、失敗する。
ニュース「炭鉱夫たちは、ここでのピケットをいつまでも続けるつもりだと言っています。彼らは、ブリティッシュ・スチールのスカントープ工場へ向けて、ここを出発するコーク輸送車を阻止しようとしているのです」。
6月18日:ストライキ105日目
NUM(全国炭鉱労働組合)がオーグリーブの大規模ピケットを呼びかけ、英国全土から8000人のマイナー達が集まった。

ラッセル・ブルームヘッド(南ヨークシャー炭鉱夫):何か様子がおかしいと思った。普段だったら途中で止められて、引き返させるのに。それどころか、警察はどこへ行けば駐車できるのかさえ教えてくれた。

そこで、炭鉱夫たちは暴徒鎮圧用装備の警察犬や馬などを装備した6000人の警察官と対面する。
ブルース:雲一つない、晴天の朝だった。
ドン:特になにも期待していなかったし、何が起こるとも思っていなかった。
デイヴ:皆、Tシャツと短パンのような格好で、冗談を言い合ったりしていた。ただ、あんなに沢山の警察を見たのは人生で初めてだった。
ポール・ブラウン(南ヨークシャー騎馬官):たくさんのピケット達が来ていた。我々は、コーク輸送車が到着するのを待ち、ピケット達が、輸送車が入ってくるのを阻止するためにピケットラインを超えないよう、見張っていた。しかし、段々とエスカレートしていった。

ドン:輸送車がコークスを運搬するために入ってくると、段々と騒ぎが大きくなり、押し合いが起こり始めた。誰かが私の頭を後ろから掴み、首が固まってしまった。腕を取られ、足をつかまれて引っ張られ、地面に叩きつけられた。首をつかまれた時は、ーー認めたくないがーー本当に怖かった。その後、私はバスに連行され、そこで座席に手錠をかけられた。

ポール:ピケット達は段々激しくなってきた。ラインの圧力を緩め、我々が前進するために、騎馬隊が出動することになった。
ラッセル:これまで馬が出てきたことはなかったので、これは予想外だった。後方にいたピケット達は投石を繰り返していたが、警察隊には届かず、結局仲間たちに当たるので、後ろを振り向いて、投石を止めるように言った。
デイヴ:警察隊の長が「これ以上投石を続けるようであれば、騎馬隊を出動させるぞ」と言った。その後、警察官たちを二つに分け、その間から騎馬隊が現れた。警察官たちはピケット達を追い回し、追いつくと警棒で叩き始めた。抵抗なんて出来なかった。もしそうすれば殺されていただろう。
ポール(南ヨークシャー騎馬官):我々は統制されたユニットであるという信念があった。だから、どんな警官であろうと、他の人間を傷つけたり、深刻なダメージを与えることがあるということが、信じられなかった。しかし、アドレナリンが上昇し、急激に怒りが込み上げたのだろう。
ラッセル:私は赤のセーターに白のシャツを着て、ブルーのショーツを履いていた。警官に捕まって、警棒で殴られ始めた。どれくらい酷かったか。事実、警棒が二つに折れていた。警官たちは完全におかしくなっていた。

ニュース「暴動にも関わらず、コークを乗せた輸送トラックはスカントープ工場へ向けて、出発しました。騎馬警官はマイナー達を追い続け、逮捕者を拘束するため、その後に警官たちが続きました」。

ブルース:追いかけられながら、なんて数の馬なんだ、と思った。追いかけられている途中に右を観たら、テラスハウスの間の小路を見つけた。小さなトンネルで、抜ければ裏庭にアクセスできる。だから騎馬隊が行ってしまうまでそこに隠れることにしたんだ。若いマイナーも私についてきた。だが一人の騎兵警察がかがんで、「何もしないから出てこい、とりあえず、通りに出るんだ」という。私は一緒にいた若いマイナーに、奴らを信用するな、出たらダメだといった。だが、奴は分かったと言い、出て行った。するとその警官はすぐにそいつの頭を警棒で殴りつけた。そいつは倒れてあたりは血の海となった。次の瞬間、機動隊が盾を片手に走ってくるのが聞こえた。



ラッセル:警察官たちは、あの日に起きたことの責任を問われる心配はまったくなかった。デスクまで連れていかれると、別の警察官が「その傷はどうした?」と訊くので、あいつだ、あの警官が警棒で殴ったんだ。警棒は折れて、奴のポケットに入っているはずだ、と言った。奴はポケットをカバーしてそれを隠した。それで終了だった。私は、頭から血が流れて肩まで来ていた。背中には青あざがあった。病院で診てもらい、レントゲン検査をし、その後、シェフィールド警察に行った。いったい自分に何が起こっているんだ?と思った。信じられない気持ちで一杯だった。なぜなら私は何ら悪いことはしていない。ただ、そこに立っていただけだ。
ニュース「警察、マイナー、双方から多数のけが人が出ています。警察はコーク工場からピケット達を押し出しました」。
ブルース:そこはまるで焼野原、まるで戦場と化していた。


オーグリーヴの事件では95人の炭鉱夫が逮捕された。
ドン:シェフィールドで収監された。「せめて妻に電話をかけさせてくれ。子供の学校の迎えに行けないことを伝えないと」と言った。
ジャッキー(ドンの妻):子供たちに父親が逮捕されたことを伝えなければならなかった。息子は「お父さんは何も悪いことはしていない」と言い、娘は、ただ泣いていた。

ドンとラッセルは、最高刑無期懲役となる「暴動」の容疑で検挙された55人のマイナーの内の2人だった。
デヴィッド・ニクソン(南ヨークシャー):あの抗争はセッティングされたものだと今でも思っている。警察は、我々が何をしに来たのかを分かっていながら、オーグリーヴへの入場を止めなかった。これは、この混乱を招くためにセッティングされたものだったんだ。しかもTVの報道なんて、信じられないものだった。常に、我々マイナーたちが悪者であると描かれていた。
ニュース①「警察官たちは、投石などの集中砲火に対して戦い続けています。午前中には、ピケッティングは暴動になりました」。
ニュース②「サッチャー首相は、”暴徒支配の試み”と非難しました」。
ニュース③「警察官たちに対する暴力は恐怖の極みです」。
デイヴ:ストライキ中、いつだって報道は偏っていた。人々は、我々をフーリガンだと決めつけて「なんであいつらは仕事に行かないんだ」と言っていた。我々がストライキを起こすのがなぜなのかを理解しようとしていなかった。
ラッセル:TVでの報道を観るたびに、私はだんだんパラノイアになっていった。警察が私の後をつけているんじゃないか、電話を使用できないようにするんじゃないかとか。私は髭をのばして、外見を変え、人に気付かれないようにした。
マイナーたちに対する訴追裁判は、警察が虚偽の証拠を提出したことにより失敗に終わった。南ヨークシャー警察は、暴行、不当逮捕、不当訴追のかどで、マイナーたちに£425,000の支払い命令を言い渡された。しかし、この件に関して、警察側から懲戒されたもの、訴追されたものは出ていない。
ラッセル:大変怒りを感じた。他の人間に対してあんなことが出来るなんて信じられなかった。
6月20日:ストライキ137日目
ニュース「ウェストミンスターの定例委員会でサッチャー氏は、”フォークランド紛争では対外の敵と戦ったが、今回は、自由を脅かす国内の敵と戦っている”と述べました」。
ドン:一国のリーダーともあろう者が、炭鉱夫として国のために尽くした我々を”国内の敵”と呼ぶなんて、信じられないし、非常に卑劣だ。サッチャーは事態を理解していない人々の心にそのような印象を植え付け、それを楽しんでいた。
ジャッキー:私は猛烈に怒りを感じ、マスコミの報道に当惑した。そして、炭鉱夫たちの報道されない側面が見られるべきだと思った。ドンは、マスコミを嫌っていた。でも、前に出ていかない限りは理解してもらうことはできない。ほかに選択肢はないと思った。そこで私が前に出ていくことにした。
ジャッキー「今朝来た請求書は何?」
ドン「水道代、£59.11」
ジャッキー「オー」。
ジャッキー:「(TVに向かって)私は他の炭鉱夫の妻よりも、恵まれていたと思います。皿洗いの仕事で£17は稼げます。

ジャッキー:ちょうどTVの撮影が来ていた時、私たちは牛乳を買いに出かけるところだった。一番サイズの小さいものだった。しかし実は、普段は粉末ミルクを使用していた。液体の牛乳より安かったから。それが私の小さなプライドだった。とても良い映像が撮れたと思った。しかし、実際に放送されたのは、誰かがTVカメラに向かって唾を吐いた、その映像だけだった。その時思ったのだ。もうこれ以上はやらない、と。結局マスコミは”奴らは最低な人間たちだ”ということを知らせたいのだな、と思った。
デヴィッド:その夏に、パワーステーションの脇を運転していて、石炭の備蓄があるのを見たんだ。山ほどの石炭がそこにはあった。そのころ、ラドリー計画のことを知った。その時に気付いた。保守党政権はすべて準備周到だったのだと。
保守党は政権を掌握する前、イギリスにおける国有産業の私有化を掲げていたが、漏洩した報告書には、マイナー・ストライキの制圧に関する記載があった。石炭を備蓄しておくために、非組合員のトラック運転手を雇っていた。さらに、大規模な移動警察隊を訓練していた。
ニュース「バビントンは、4000人のフライング・ピケット達に包囲されました。抗争は新しい局面に突入しました」。
デヴィッド:後は消耗戦だった。私たちは、どれだけ時間がかかろうとも政府よりも長く闘えると思っていた。
5か月間に渡るストライキでこれまで最大の16万人のマイナーたちがストライキに参加していた。
ブレンダ:強くいなければいけなかった。でも借金はかさみ、子供は欲しいものも与えれれなかった。皆がそこまで強くなれるわけではなかった。
ニュース「ストライキが始まって24週目の今日、これまで完全に機能停止していたエリアで、ストライキが中断する最初の兆しが見え始めました。伝統的に仲間に忠誠を誓うイギリス北東部でさえも、ストライキが崩れ始めました」。
ジェフ(南ヨークシャー炭鉱夫):「Ode To A Scab(クズへの頌歌)、Scab(クズ)とは、コルクスクリューのような魂と、水浸けの脳と、ゼリーと接着剤でできたコンビネーションの背骨を持つ二本足の動物である。他の者が心臓を持つのに対して、彼は腐った主義主張の腫瘍を携えている(Jack London)」。これ、私のことだ(笑)。あの時も、そして今でも、ストライキは本当に時間の無駄だったと思う。自分は仕事には行かなかった。というのも南ヨークシャーの産業地帯でストライキ中に仕事に行くなんて自殺行為と同じだったからだ。

ブルース:8月、石炭委員会議長のイアン・マクレガーが南ヨークシャーで"仕事に戻ろうキャンペーン"を推進することを耳にした。すべての炭鉱のすべてのストライキ中の炭鉱夫たちに、差出人のない茶封筒が届き、中には仕事に戻ることを強要する、もしくは奨励金を渡すという内容の手紙があった。
ジェフ:手紙には切り取り線があったので、私は申請書を埋めて送り返した。私はストライキ中、母の遺族年金で暮らしていたが、出費は嵩むばかりだった。炭鉱マネージャーは、私にまだ何も行動を起こさないようにと言った。「計画がある。まだ実現はしていないが、機が熟せば、君にも連絡がいく」と。南ヨークシャーでは、スト破りたちは、誰かが行動を起こすのを待っていた。
8月21日、ストライキ169日目:南ヨークシャーで一人の炭鉱夫が最初のスト破りを行った。
ニュース「48歳の電気工マイナーが警察の警護のもと、夜明け前に炭鉱に入りました。シルバーウッド炭鉱に復職した男性は、午前中に仕事を終え、罵声を浴びせられる中、職場を後にしました」。
デヴィッド:マスコミは、仕事に戻る人たちの数を連日報道し始めた。そしてその数は増える一方だった。
ニュース「仕事に戻った7人のマイナーは、ストライキ中のマイナー達から、”7人のscabs(クズ、軽蔑の意味で、ストライキ中に働く、または労働者を提供する人)”と呼ばれていますが、彼ら自身は自らを、”壮大な7人”と呼んでいます。仕事に戻った理由は、ストライキはもうたくさんだ、と感じたからであり、そもそも最初からストライキには参加したくなかった、とも語っています」。

サッチャー首相「日に日に、責任感のある人たちはこのストライキから距離を置くようになっています。マイナーたちは、自分たちの職場に行く権利を主張しています。マイナーとその家族の勇気と忠誠は、決して忘れ去られることはないでしょう」。
インタビュアー:原則については理解していていても、非常に難しい決断を迫られるかもしれない人の人生に何が起こっているのか、あなたが知ることはできないと思うのですが。
デヴィッド:ちょっと待て。私は、結婚した直後で、家のローンに首を絞められ、息子が生まれて、家にはガスも通らず、食べるものもなかった。私は底辺にいたんだ。その私がストを続行していたんだ。彼らには簡単にできたはずだ。
ニュース「最初のストライキが発生した、南ヨークシャーのコートンウッド炭鉱では、マイナーたちの間に憤りが沸騰、レンガやボトルなどが投げられています」。
ジェフ:コートンウッドのマイナーが仕事に戻ったのは、仕事復帰が可能であることを証明したといえる。
11月23日:ストライキ202日目
ジェフ(スト破り):マネージャーが連絡してきて、プランがあると言った。「ロザラム警察署に集合だ」と。集まった人々は、皆身元がばれないように、バラクラバやスキー帽、フルフェイスのヘルメットなどを被っていた。私は青いパーカーを着て、フードを目深に被り、顔を隠していた。乗り込んだバンには、石や石炭、犬のものかもしれないが、排泄物などが当たる音がした。本当に怖かった。仕事が終わると、我々は警護のもと、ロザラム警察署へ戻った。そこでバンを降ろされるが、そこから自宅までは自己責任だ。数日のうちに、隣人たちは、私がスト破りだと知ることになった。そこからは私は自分で車を運転して仕事に行くことにした。助手席に手斧を携帯して。
ブレンダ:仕事に戻ると決めて、「今週は賃金が入る」と言う人がいれば憎んだ。それまで、ここはいつもフレンドリーな地域だったから。近所の人が仕事に戻ったけど、それを咎める者はいなかったし、暴力を振るうものもいなかった。ただ彼を「scab(スト破りのクズ)!」と呼ぶことはあった。するとどこからか大勢の警察官たちが現れ、パトカーがやってきて、7人が逮捕された。そのうちの4人は私の息子たちだった。ただ、庭に出て平和にピケティングしていただけなのに。
インタビュアー:誰かに向かって、scabと叫ぶのは平和的だと思いますか?
ブレンダ:ええ、私はそう思うわ。息子たちが刑務所送りになるのかも分からない。息子たちの育て方を間違ったのか、何か間違ったことをしたのか?と考える。でもその時に正しいと思ったことをしただけだ。ただ彼らは自分たちの仕事を守るために闘ったのだ。
クリスマスまでに約5万人のマイナーが仕事に戻り、12万人がストライキを続けた。
ニュース「炭鉱ストライキは284日目を迎えました。ストライキ中のマイナーとその家族にとって、クリスマスは当然厳しいものとなります」。
スティーヴ:暖炉をつけるのは、遅い夕食から就寝までの間で、あとは布団を被って寒さをしのいでいた。暖を取るために薪を拾って、燃やせるものはすべて燃やしていた。
インタビュアー:アンディのところへ、助けを求めることはしなかったのですか?
スティーヴ:いや弟のところへは一度も行かなかった。ストライキ中のマイナーが、働いているマイナーのところへ金を借りに行くのは原則に反しているからだ。
ニュース「本日、南ヨークシャーのドンカスターで、暖炉にくべる石炭のために線路の土手穴に入り、事故死した10代の男子2人の葬儀が執り行われました」。
ニュース「ストライキ発生後、ヨークシャーでは、石炭の採取による事故により、これまで5人の命が奪われています」。

ニュース「ロザハム近郊のシルバーウッド炭鉱近くで、マイナーたちが、大量の石炭混合物の山で石炭を探し回っている最中に、デイヴ・ローパーは頭からつま先まで前進、瓦礫に埋もれてしまいました」。
デイヴ:息ができなかった。このまま死ぬのだと思い、目をつむった。1分だったのか10分だったのか知る由もないが、誰かが「ここにいるぞ!」と叫んだ。私は目を開けると、彼らが私を掘り起こしてくれた。
リサ:クリスマスが終わると、すべてのムードが変わった。私は終わったと確信した。泣いている父を見て、心が引き裂かれそうだった。
1985年5月3日:ストライキ363日目
ニュース「マイナー・ストライキが終了しました。NUMは、すべてのマイナーに火曜日には仕事に戻るようアナウンスしています」。
デイヴ:大多数のマイナーたちにとっては、正しい決断だったと思う。12か月やって、どこにも行きつかないのだから、もう勝つ見込みはなかったということだ。石炭委員会だけでなく、国を相手にした。国家を打ち負かすことはできない。
ブルース:仕事に戻るマーチ(祝賀行進)が起こった時、私はその行列の最後尾にいた。仕方がないので行ったが、とても失望していた。このような形で仕事に戻りたくなかった。ストライキ中、失望したのはこの時だけだった。
スティーヴ:ストライキ開始日から一度も戻らなかった。恐らくオラトンでは100人ちょっとが戻らなかった。確かに終わったが、撤収し、引き下がったわけではない。それでいいんだ。
デヴィッド:胸が張り裂けそうだった。12か月に渡る、心の痛み、経済的困難、消耗は...何のためだったのか...。
ドン:騙され、何もかも盗まれたと感じた。最悪だった。負けたんだ。これで終わりだった。友人が...ストライキは人々に与えたのは...、彼は首を吊った。ストライキが始まってすぐだった。このストライキには結末があるんだ。悲しい結末が。
次の総選挙でマーガレット・サッチャーは圧倒的勝利を収めた。

インタビュアー:(トライトン・ノール=風力発電機を見上げながら)世界は今全く違う場所にいますね。
ブルース:ああ。トライトン・ノールは、クリーンな電力を生産する。もしもっと段階を経て、時間をかけて変わっていったのなら、こんなに痛みを伴うことはなかったんだ。コミュニティーを破壊することもなかっただろう。

ニュース「ダービーシャー最後のシャイアーブルック炭鉱が閉鎖しました...。北ノッティンガムシャーのビーバーコーツ炭鉱ではかつて、1400人が働いていました...レスターシャーでは、炭鉱閉鎖後、400人が仕事を失いました...」。
ストライキから10年でイギリスの石炭プラントの90%が閉鎖された。

ブルース:あのことを思い出すと、今でも胸が一杯になる。政府がマイナー達、その家族、そのコミュニティーにしたこと...。あんなことをする必要はなかったんだ。
デヴィッド:マイナーはコミュニティーを守るためにプロテストを実行した。これらのエリアは打ちのめされ、荒廃した。40年を経て、いまだにそこから立ち直ろうとしているものもいる。
アンディ:起こったことに関しては未だに組合を非難する。もう昔のようには戻れない。しかし、どちらにしてもこの産業は環境問題の面から、続かなかったと思う。皆もう踏ん切りをつけたんだ。
(ドキュメンタリー終わり)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
40年の歳月を一瞬で忘れるほど鮮烈なストーリーテリングだった。炭鉱ストライキといえば、”政府VSマイナー”という図式が一般化されているかと思うが、実際はそれほど単純なことではなく、政府と組合、組合と炭鉱夫たち、そしてその炭鉱夫たち同士が敵対した。彼らが対峙したのは、政府や警察だけではなかった。スティーヴとアンディのビアード兄弟のように、ストライキに参加するか否かが兄弟で意見が分かれるという悲しい現実は、スティーヴが弟を今でも恋しいと思うかに、イエスと即答したことからもうかがえる。また、デイブ・ローパーが、ストライキ中のため、補助金が下りず、死亡した次男の葬式が出せなかったため、他人の棺に入れてもらったという話には怒りが込み上げた。
そして、1984年6月18日のオーグリーヴの戦いに関する衝撃的な検証には言葉がなかった。異例なほど厳戒態勢を敷いた警察は、ストライキに参加した労働者たちに牙をむき、馬で突撃し、極端な暴力を振るった。警棒を振り回す警官に襲われる若者の姿が映像に収められているが、ラッセル・ブルームヘッドは「ただそこにいた」だけで警棒が二つに折れるほど叩かれ、警察に連行され、訴追された。そのことを語る彼の語り口は、今でもそのトラウマ苛まれていることがひしと伝わってくる。鉱山労働者たちが警察に石を投げつけて紛争を誘発したかどうかという問題については、そのような挑発は最小限であったことが示される。国家による残忍な弾圧の姿は、鮮明である。
「炭鉱ストライキ」と言っても、鉱山労働者たちが、それぞれ違う意思で、それぞれ違う立場をとって過ごした一年間であった。政府を責める者、警察を責める者、組合を責める者、そして仲間を責める者、今でもその思いは万別のようにも見えた。時間が解決することもあれば、苦い経験と共に生きることを受け入れぜるを得ないことも分かっている。40年という節目に今一度この出来事を振り返ることのできる素晴らしいドキュメンタリーだった。
Don't miss this one-off feature length documentary film Miners' Strike: A Frontline Story available from 18th February on BBC and BBC iPlayer #minersstrike #strike #thegarden #thegardenproductions #miners
Posted by The Garden Productions on Friday, February 16, 2024
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
リサ・マッケンジー(炭鉱夫の娘):私はこれまでも何度かプロテストに参加して逮捕されたこともあります。
スティーヴ・ビアード(ノッティンガムシャー炭鉱夫):自分の信念のために、立ち上がらなければならない。
デイヴ・ローパー(南ヨークシャー炭鉱夫):誰も我々の権利を奪うことはできない。
デヴィッド・ニクソン(南ヨークシャー炭鉱夫):もし、同じようなことが再び起こったら、またストライキを起こすか?答えはイエスだ。じゃあ、もっと違った方法でやるか?多分そうするだろう。誰から家に侵入してきて何かを盗もうとしたとする。この家を守るために防御する価値はあるのか?もちろんある。だから、自分たちのやったことに後悔はない。全くない。
(終わり)
