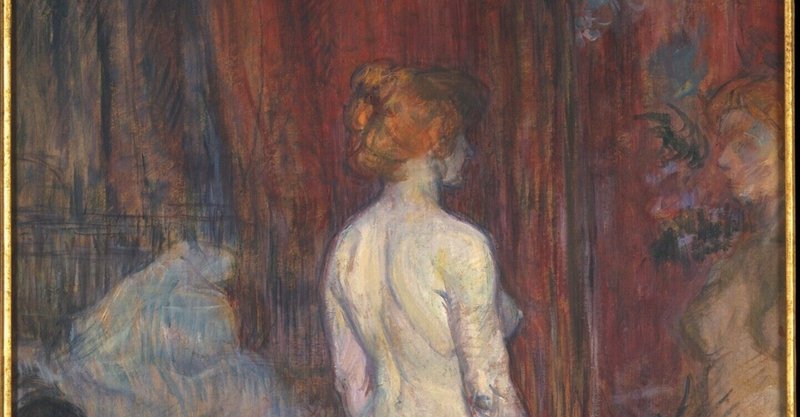
日記7月11日(日)。 #日記 一本の弦。
老人に残されているのは、ただ一本の弦を奏でることだと言われる。それはおそらく、調子の外れた弦。聖ステファヌスが「ウルフトーン」と呼んだもの。だが、この調子外れの弦だけが、無傷の若さの楽器よりもずっと深くて幅のある音色を奏でるのだ。
ジョルジョ・アガンペン 書斎の自画像 P.21 月曜社 岡田温司訳
年をとって初めてわかるのが、年を取る辛さだという。
年のわりには若く見られてきた義母が、この前しみじみ言ったという。年を取って悲しいのは、人に侮られることだ、と。
特になにもしていなくとも、わかっていない人、まごまごしている人、という前提で声掛けがある。その声色の、その言い方の「侮り」が、それこそが、一番傷つくのだ、と。魂が、傷つくのかもしれない。
人は、年をとり、小さくなり、眼が見えず、まっすぐ歩けず、倒れそうになる。だがいやでも、買い物に、病院に、行かねばならない。
そこで、そう、扱われる。それを聞いて、自身にも問いかける。そういう目で、自身も見ているのではないか、と。
そう、実際になにかを言わなくても、そういう気持ちになっていることがある。
秘してはいても、思っていれば同じこと。
どうして、そう思ってしまうのだろうか。
冒頭の引用。自身がなんのために、生まれたのか、と問うても、特に意味などはないのである。ないのであるが、それではくやしいから、となにか、自身の魂に最もあったなにかを、一生で探し続けて、その結果、いまにも切れそうな、「一本の弦」が、ぼんやりと見えれば、それは嬉しいことだろう。
全ての人が、弦を、1本の弦でさえも、見つけられるわけではないだろう。
だが、そうであっても、いまは無弦の楽器であっても、なんとか1本を見つけるように、いつも意識しておく必要があるような気がする。
そして、それがほそぼそとでも張ることができたのであれば、へろへろでも、かすかな音でも、なんとか引き続けるようにしたいものだ。
そこからでも、いやそこからでしか、「世界の秘密」は覗けないような、気がする。
(「ウルフトーン」。味わい深い、言葉ですね)
お志本当に嬉しく思います。インプットに努めよきアウトプットが出来るように努力致します。
