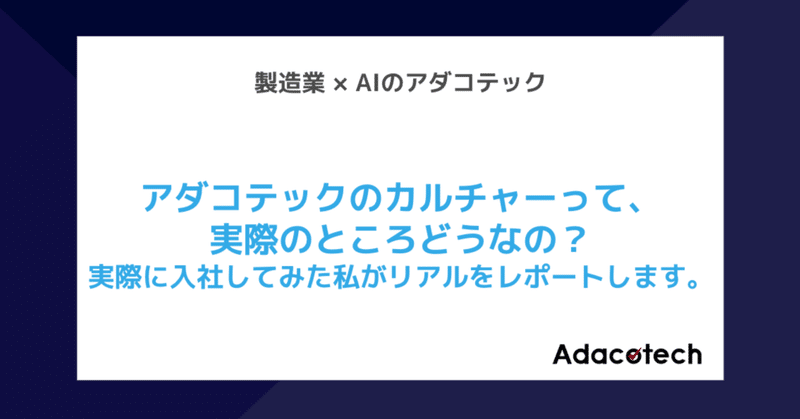
アダコテックのカルチャーって、実際のところどうなの?実際に入社してみた私がリアルをレポートします。
製造業×AIのアダコテックで事業開発をしている阿部です。
今年の4月にアダコテックに参画して2ヶ月が経ったので、アダコテックのカルチャーについて偉そうにも書いてみようと思います。
というのも、多くの企業がホームページで”企業理念”や”Value”を掲げていますが、「実態を表していない」なんてことよくあると思うんです。
このNoteを通して、実際にアダコテックで働いた私が「実際のところどうなの?」を少しでもお伝えできれば幸いです!
私とアダコテックの出会い
新卒で機械系メーカーの商品企画部に5年間在籍。
その会社の上司から ”レンタル移籍(*)”という社内制度を紹介され、その制度を使って現在アダコテックでお世話になっています。
(*22年4月〜22年9月末の期限付移籍。留学制度の会社版、というイメージ。)
なぜアダコテックだったのか?
元々、自分が製造業に身を置いていたこともあり、この業界のアナログさには課題感を持っていました。
そんな中で「製造業×AIのアダコテック」というワードを見つけてしまったら、それは興味を持つほかありません。(笑)
ただ最終的に「アダコテックに移籍してみたい!」と思ったのは、代表・河邑さんとの面談で、製造業変革に対する熱意がビシビシ伝わってきたこと、「製造業のリアルな課題って何ですか?」とペーペーの自分の意見に傾聴してくれたこと、「是非、移籍中に色々失敗して財産にして下さい」と許容力を感じたこと、などなど。
思い返すと、この時からアダコテックのカルチャーを感じ取っていたのかもしれません。
アダコテックが大切にしていること

そんなアダコテックが「大切にしていること」は…上記4つのように表現されています。
これらが本当に業務の中で実践されていれば、これからジョインしようとする人も認識の齟齬なく入社できますよね。
それでは本題の、アダコテックのカルチャーって実際のところどうなの?をこの4つの「大切にしていること」にフォーカスを当ててレポートしていこうと思います。
1. ユーザーのリアルに向き合い続ける
ベンチャー企業って何となく自己成長が目的の人や、事業開発そのものを経験したくて入社してくる人も多い印象を持っていました。
しかしアダコテックの面々は、お客様の課題解決大好き集団です。
とにかく一次情報を取りに、営業は泥臭く日本中のお客様の元に飛び回っています。(まだまだ営業メンバーも少ないので、完全に身体が足りていません。)
そしてエンジニアも、営業と一体となって飛び回ります。
世のエンジニアの中には「要件定義だけください」という人もいるんだと思いますが、アダコテックのエンジニアは躊躇なく自分の足で客先に向かいます。
これが日常の風景です。
頭の良いはずのメンバーが「論理だけ組み立てて頭でっかちになるくらいなら、お客様に聞きに行こう!」というフットワークの軽さを持ってます。重装戦士がすばしっこいって卑怯です。
そんな、会社が一体となってお客様起点でコトに向き合い続けている集団、それがアダコテックだと思います。
(逆に、気合いと根性で案件取ってきます!という人はカルチャーに合わないかもな、という印象を持っています。)
2. フィードバックを歓迎する
これはお客様に対しても、仲間に対しても実践されています。
・お客様に対して
お客様から受けたフィードバックがすぐに全体共有されるのは当然のこと、当日〜翌日にはそれをみんなが話し合っていて、
「〇〇は方向修正した方がいいよね」
「〇〇に対してもっと自分達ができることは?」
「まだ解像度が低いから次は□□をヒアリングしないと」
と具体的アクションが洗い出されていきます。
そして皆、「これは自分がやっておきます!」と自発的にアクションに移し、プロダクトに反映していく。
お客様の声を大切にしている組織だからこそ、お褒めの言葉も厳しい言葉も皆が当然のように受け入れて糧にできるんでしょうね。
”絶対に聞き逃せないフィードバックが、そこにはある” 状態です。
・仲間に対して
メンバー同士のコミュニケーションでも、お互いの社歴や立場に関わらず毎日フィードバックし合っています。それは代表と一社員との間でも、です。
そもそも現在のアダコテックのメンバーは、各人が専門性を持ったビジネス戦闘力たかたかのプロフェッショナル集団、つよつよ歴戦の民なので、お互いを尊重し背中を任せている感があります。「この分野は自分より○○さんの方が詳しいのでご意見下さい!」と言い合えて、役職はあっても非常にフラットな関係性が出来上がっているのも素敵だと思います。
まさに無知の知って感じの意識が各人にあって、他人から学ぶ貪欲さ、吸収力が尋常じゃないです。
3. むずかしい、を面白がれる
そもそも製造業界を変える、ってとても難しいことです。何もかもが細かいし、全てに世界最高水準を求められるし、重厚長大なプロジェクトが多く辛抱強さが求められる。そして、アナログな構造がたくさん残っている。そこに切り込んで行くだけでも相当高難度なミッションです。茨の道に自ら好き好んで参入しようとしている人たちなので、むずかしいを面白がれるマゾヒストしかいないと思います。(笑)
冗談はさておき…
いざ難しいことに向き合おうとした時、仮に失敗しても許容してもらえると思える安心感や仲間の存在が必要だと思います。
そしてアダコテックにはその土壌があります。
だって私、代表から直々に「私にブチギレられるくらいの失敗をしてみて下さい。そのくらいのポジションを取って良いんですよ」と言われましたもん。
千手観音がゴールキーパーをやってくれる時くらいの心強さがあります。
その他にも、「いいですねぇ」が口癖の人がいて、その口癖が周りに伝播していく、みたいなことが起こっています。
モチベーターが多く心理的安全性があるのは、アダコテックの特徴の一つだと思います。
むずかしいコトって、抽象度が高くて具体的なマイルストーンすらよく分からない、そんな状態でオーダーされますよね(いや皆、オーダーされる前にむしろ自分から取りに行っている)。
でもそれは丸投げではなく、「この人に自由に任せておけば、自分が言わなくてもやってくれる」という信頼の表れから来ていると思います。
そして実際に、その期待に応えようとするかのように皆自分のコントロールで回している。
そこらの会社であれば、かなり役職の高い人が任せられるようなオーダーを自然と受け渡ししているし、全くそれを厭わないスタンスで会社が動いています。
4. 遊ぶように学ぶ
例えば、放課後友だちとかくれんぼをしていたあの当時を思い出してみて下さい。
あなたが鬼に見つかったとします。でも見つかったことをミスだと捉えて悩む人なんていませんよね。
「次はどこに隠れようかな?」と思案したり、「ここは意外と見つかりやすかったから気をつけて」と仲間に情報共有したり、遊びの中では自然と未来志向になっていると思います。
アダコテックのメンバーもそんな感じです。
前向きな人が多く、できないことを悔やむ人はあまりいません。
もちろんみんな完全無欠ではないので「ああしていた方が良かったな」という話も出てきますが、それはクヨクヨしているのではなく、ミスをミスとして捉えてないというか、最終的には「じゃあ次どうしようか?」という議論になる。
普通の会社だったらミス認定されるよなー、というようなことに対しても、それをいちいち咎めてくる人もいません。
だからこそ、トライアンドエラーが自然とできているのだと思います。
また、各人のジブンゴト化力・共感力が高いのも、皆が自然と色々なことを学べている要因なのかな、と思います。
アダコテックでは、仕事のことも、時事ネタも、(時にはプライベートなことも、)情報発信・オープンなコミュニケーションを大切にしています。
自分が面白いと思ったことは情報共有するし、皆アンテナを張り巡らせている好奇心バリバリの人たちなので、それらの情報に対して反応してくれるんですよね。
そしてそこに、常に自分のやるべきことのヒントがないかを探している。
他人の考えに思いを巡らせ、自分の事として仕事を取りに行ける、「また新しいこと学べる!」とハイな状態になっている方々です(ので、守備範囲広すぎ!とツッコみたくなる時があります)。
プロ意識を求め合おう。共に創ろう、期待を超え続けよう。

ここまで長文にお付き合いいただきありがとうございます。やっとまとめに入ります。
ここまで紹介してきた4つの「私たちが大切にしていること」、これを我々の価値観=VALUEに置き代えると、
「プロ意識を求め合おう。共に創ろう、期待を超え続けよう。」
になるのだと思います。
私たちが日々大切にし、実践していることが、この言葉に集約されてます。
結論、
「アダコテックのカルチャーって、実際のところどうなの?」という問いに対しては、アダコテックが表明している通りのカルチャーがここには存在していました!
世に言う大人ベンチャーな雰囲気で、会社としての勢い、仕事としての自由度がありつつも、現実的なアプローチでPDCAを回し、前に進んでいく。
能ある鷹が爪を隠しきれていない集団。簡潔にアダコテックの人たちを表すと、このようになると個人的には思っています。
代表の河邑さんの熱意に惹かれて働き始めましたが、カルチャーを形成している中の人たちはとても魅力的な人ばかりでした。
最後に
自分が入社してからも、どんどん人が増えており、組織は急拡大中です。
募集中のポジションはこちら、採用ピッチもぜひご覧下さい!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
