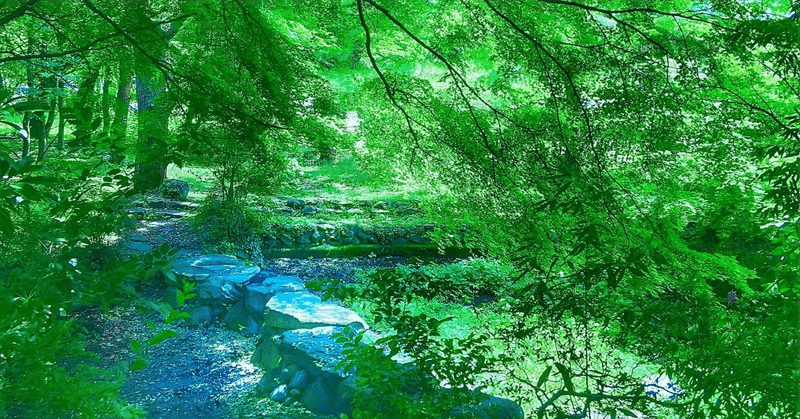
「おしゃべり」のこと
鎌倉のまちを歩くと、小さなお店に立ち寄り、店員さんとおしゃべりをすることが多い。
それにしてもいつの間に自分はそんなに「おしゃべり」が好きな人になったのだろうと、ふと考えた。そして「おしゃべり」のシーンを振り返るうち、気づいたことがあった。「おしゃべり」という行為の中で私が主にしているのは「尋ねかける」ことであり「話す」ことではないのだ。
「聞いて」ではなく「聞かせて」という感覚にいることが、自分にとってはとても居心地がよい。「これが好きなんです」と言うより「こういうものが好きなのですか?」と尋ねる方が。特に、こういった(ちょっとした出会い)を通じた交流の中においては。
それにしても「何も話さなくても場は成立する」のに、あえて言葉を交わそうとするのは何故なのだろう?
その理由は、割とはっきりしている。お互いの存在を感じながら、まるで役割の中でしか交流できないような感覚(形ばかりの挨拶や機能的な会話など)は、何かがもったいないような気がするのだ。交流してはいるけれど出会ってはいないような、接してはいるけれど触れてはいないような。そんな感覚がもどかしいのだ。
作法としてではなく、本当に、目の前にいるお互いを感じあったところから生まれてくる言葉に、私は出会いたいのだと思う。
それは「私を知って欲しい」ではなく、「あなたとほんの少しでも出会わせてほしい」みたいな感覚だ。あっているのに出会ってないのって、なんだかもにゃっとすることだもの。
今日はずっと昔から知っている友達ふたりとあって、お互いが実は思っていたことなどについて(思わず)言葉にしたりなどして、なんだかとても愉快な気持ちになった。お互いの中に、お互いが生まれ出す瞬間を、目撃しあっているような。時に暗闇をつくり、そこに花火を一緒に仕掛けて、打ち上げ、その光に目を細めているような。
ゴールデンウィークがまもなく終わろうとしている。夏休みの子どもみたいに、一日がとっても長くてたっぷりなあの時間の感覚が戻ってきたらいいのに。時の感じ方が変わったのは「長く生きたから」というより、クロスする「時間」のなかで時空がどこか歪んでしまっているからじゃないかな。そこ、点検してみる価値がありそうな気がするけれど。
例えばそんなことをしゃべりながら、潮風に肌をさらし、ばかげた思い出話で盛り上がりたいね。
…と、すぐさま過去になる記憶に「追伸」を打つ。
