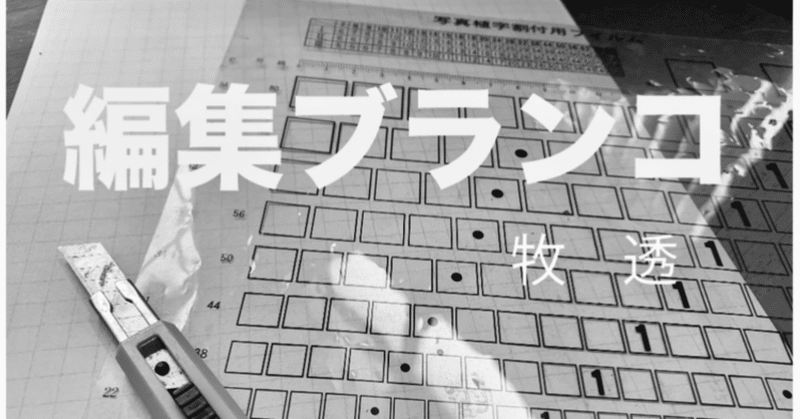
編集ブランコ4-”書き屋” という病気
かの出版社の社長室。呼ばれて入ると、いきなり「君は今日から社長室長だ。給料は変わらない、いいか」と、社長が山積みの本のデスクの向こうからゴルフ焼けした赤黒い首だけをのぞかせて、いつもの命令口調で言った。
僕は、ほんの二、三日前に大きな誤植を指摘されてひどく怒られたばかりだった。もちろん、そのゲラは目の前で破られ、僕は再び印刷所に清刷を頼まなければならなかった。だからまた誤植があったのかと思い、緊張して社長室を訪ねたのだった。
「社長室長って、何をすればいいんですか」、堅い口調で訊いた。すると社長は本の山の陰から「この部屋にある本の目録を作れ、全部だ。備考欄を設けて、そこへ必ず400字程度の要約を書き込んでおくこと」と、論文の試験官のようなことを言った。
ただの一覧表を作ればよい話ではなかった。要約文を書くとなるとひと通り読まなければならない。しかも部屋中の本の山、全部である。机の上や書棚はもちろん、その周囲には床の上から1mの高さに積み上げられた本の山もある。空間が残っているのは社長の机の前と、そこから出入口のドアまでのわずかなスペースだけだ。あとは皆、本の山、山、山であった。
会社は出版社を名乗ってはいるものの版元になった本は一冊もなかった。主に重工業系の業界紙や他社が発行する本の編集を請け負っていた。いわば今で言う編集プロダクションのような会社だった。社長は大新聞社を抜け出した一匹狼で、社長の肩書きよりフリーライターなどと孤立無援を気取った名刺を持っていた。
しかし、社長へは毎日のように本が送られてきていた。それが社長室のおびただしい数の本の山というわけである。社長は社員の給料日以外はほとんど社長室にこもって本を読んでいるか、書き物をしているかしていた。
会社は東京タワーを見上げる街の小さなノッポの雑居ビルにあった。最上階の6階の一部屋が社長室。そして他の部屋と、どういうわけか5階がよその会社で、社員23名がその下の4階の全フロアにひしめき合っていた。
総務と営業、それに制作部という3つの部があり、編集部というのはなかった。本を出版しているわけでなかったから、今思えばなるほどと思える。
社長の本のリスト作りは、思いなしか僕の才能を開花させてくれた。才能といっても、ただ要領の良さ、悪く言えば一寸ずるい手管を身に付けただけである。ワンパターンの連続が意外な能力を植え付けたというのが正直なところだ。
というのも、いつ終わるか知れない本の要約は、僕を“書き屋”の病気にしたと思う。少し大袈裟な言い方をすれば、鉛筆を持つと閃きの神様がその筆先からひとりでにおしゃべりをし始めるように筆が走った。5冊ずつまとめて読んでから書き進んだ。読み方は社長が“編集者の読み方”とかいうのを教えてくれた。
それは、まさしくスーパー読書法であった。まず奥付を読め、次にしっかり目次を読め、そして「あとがき」と「まえがき」を読んだら、あとは理解しようとしないで印象で読め、というものだった。付け足しには「帯や宣伝文は絶対に読むな」という“極意”であった。
“印象で読め”というのが、僕の仕事を大いに助けた。つまり黙読をしないで、見開きの文章を景色として眺め霊感を働かせる。と言ってもまじないをかけるわけではないので、イメージを確実に結んでいくという集中力を維持してさえいけばゴールは速かった。技術的には、段落の始めと終わり、特に語尾に注意した。「と思う」「しなければならない」「必要である」「重要である」などだ。ひらがなが多くなったり、逆に漢字ばかりになったりしている景色は飛ばした。そういう所は大体が抽象的か、要約するには難解すぎた。要はスケッチするように読む。いいかげんのようだが、数をこなすにはこの手しかなかったし、途中で読み方を変えるにはもう元に戻れなかった。
“書き屋”というのは、社長が付けた呼び名であった。会社へはよく社長の同僚や先輩の人達が現れた。彼らは社長室の階へ上がり、半日ほどで数ページの原稿を書き上げる。そのための資料を僕が届けていた。“書き屋”達はその資料と電話取材だけで、いかにも現場に行ってきたかのような“名文”をしたためるのだった。
彼らの中に、細身の作家然とした風貌のナカノさんという“書き屋”さんがいた。社長と一緒に新聞社を抜け出した人らしく、仕事を終えるときまって社長とタクシーでどこかへ繰り出して行くのだった。タクシーを捕まえてくるのも、見送るのも、やっぱり僕の役目だった。
そんな会社の制作部で、僕は社長のリストづくりを2年ほどかかって終えると、退社して次の世界に飛び込んだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
