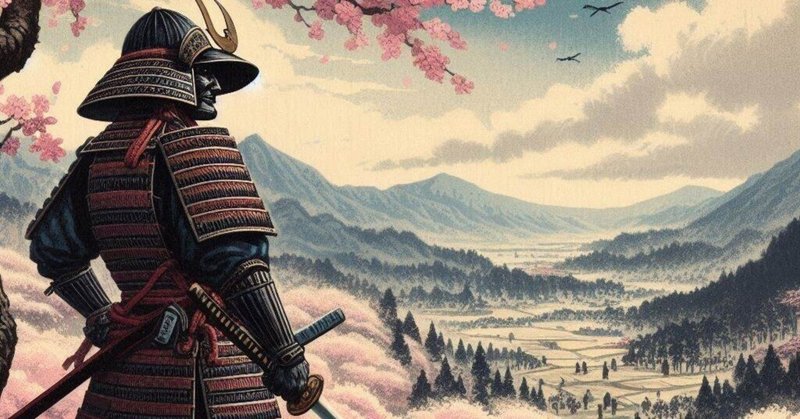
ザ・日本人 鎌倉殿と13人そして承久の乱~
上記の画像はAIで「鎌倉時代の武士の姿」と質問した結果の画像となります。
それでは、現代社会に向けて進みます。
1199年1月13日 源頼家(18歳)、朝廷の臨時除目で近衛中将に任じられ父・源頼朝の後を継ぐ。(後に第2代・征夷大将軍。)
1199年4月12日 源頼家の"親裁"が止められ北条時政以下13人の合議制となる。北条時政・北条義時・大江広元・三善康信・中原親能・三浦義澄・八田知家・和田義盛・比企能員・安達盛長・足立遠元・梶原景時・二階堂行政の13人。比企氏の勢力が強大となる事を恐れた北条氏は、源頼家の母政子と結んで北条時政・大江広元・梶原景時・和田義盛ら13人の有力御家人の合議制によって政治を進める事にし源頼家の独裁を抑え様とした。
1199年10月25日 結城朝光が源頼朝を追慕し『忠心は二君に仕えずと云うが頼朝様の御遺言に従って出家しなかった。今となっては後悔している』と御家人達に語った。
1199年10月27日 北条政子の妹が結城朝光に『梶原景時があなたの発言を謀叛の表れと頼家様に讒言しあなたを討とうとしています』と告げた。
1199年10月28日 結城朝光が三浦義村に相談、三浦義村は他の御家人に呼掛け連盟で梶原景時の弾劾状を大江広元に提出。
1199年11月13日 源頼家、梶原景時に弾劾状の弁明を求めたが梶原景時一言も抗弁する事無く一族郎党を率いて本拠地相模国一宮(神奈川県高座郡寒川町)に退去。
1199年12月9日 梶原景時、一旦、鎌倉に帰還。
1199年12月18日 和田義盛・三浦義村を中心に評議が重ねられ結果、梶原景時を鎌倉から追放する処分が決定。
1200年1月20日 梶原景時、前日夜に子息らを連れて相模国一宮を密かに離れた。この行動が謀反を起こす為に上洛したものとみなされ駿河国清見関で討たれる。
1201年7月27日 藤原定家、百首歌を企画してから後鳥羽上皇に見出され和歌所が置かれると寄人に選ばれる。更に「新古今和歌集」の編纂を藤原有家・源通具・藤原家隆・雅経・寂蓮らと共に命じられる。また鎌倉の源実朝からは和歌の指導を求められて「近代秀歌」を贈る等して声望は上がった。後に百人一首を編纂。
1202年7月 源頼家、従二位に叙され征夷大将軍に宣下される。第2代・征夷大将軍。
1203年5月 源頼家、軍勢を派遣して阿野全成を謀反人として捉え常陸国に配流、翌月、下野国で八田知家に誅殺。阿野全成は北条時政と源頼家の後継者を源頼家の弟を担ぎ出し、一方、源頼家・比企家は源頼家の嫡子を後継者に考えていた。北条政子は、嫡子が後継者となれば北条家の権威低下を危惧。
1203年8月 源頼家、病で危篤。北条氏と比企氏の対立は避けられない状態。
1203年8月31日 源頼家、症状が重くなった為出家して嫡男一幡への家督継承の準備を始める。
1203年9月2日 比企氏の乱:北条時政、一幡の外祖父である比企能員の権勢が高まる事を恐れ自宅に呼び出し比企能員を謀殺し、次いで比企一族を滅ぼす。源頼家の嫡男一幡(6歳)は一旦逃げ延びたが捉えられ北条義時の手勢に刺し殺される。
1203年9月5日 源頼家、多少病状が回復、息子と舅の死を知り激怒、北条時政征伐を和田義盛等に命じたが和田義盛らは北条方に付いた為失敗。
1203年9月7日 源頼家、北条政子の命により出家。
源実朝(12歳)、第3代・征夷大将軍となる。「実朝」の名付けは後鳥羽上皇。幕政は北条政子が親権を行使する形で将軍権力を代行し、実質的に北条時政(66歳)が執る。北条時政、初代執権に就く。
1203年9月29日 源頼家、伊豆国修善寺に幽閉。
1203年10月 東大寺南大門の金剛力士像、阿形像が運慶・快慶、吽形像が湛慶・定覚により造立。
1204年7月18日 源頼家(23歳)、修善寺で殺される。
1204年11月4日 京都の平賀朝雅の屋敷で酒宴があり畠山重安と平賀朝雅が口論。
1204年 源実朝、後鳥羽上皇の近臣・坊門信清の娘が御台所として鎌倉に入る。
1205年3月26日 後鳥羽上皇(26歳)・藤原定家等により「新古今和歌集」完成。
1205年6月21日 平賀朝雅(24歳)、北条時政の妻・牧の方を通じて『畠山重忠に謀叛の意思あり』と北条時政に讒訴。
1205年6月22日 畠山重忠の乱:北条時政(68歳)の陰謀で、畠山重安、由比ヶ浜で北条時政の指示を受けた三浦義村の軍勢に討たれ、且つ、武蔵国二俣川(横浜市)で源頼朝以来の重臣、畠山重忠(42歳)を討つ。畠山重信『逃げれば本当に謀叛を企てたと疑われる』と134騎で大軍に立ち向かう。
1205年6月23日 北条義時、父北条時政の下に畠山重忠の首を持ち帰り『戦場に従ってきたのは僅か1百騎ばかり、畠山重忠に謀叛の意思がない事は明らか』と責め立てる。
1205年7月19日 北条時政、北条政子に無断で源実朝(14歳)を自邸に招く。北条義時・北条政子はこれを拉致・監禁と判断し北条時政を謀叛と認定。源実朝を北条時政邸から連れ出し北条義時邸に入れる。北条時政、北条政子の命令で出家。
1205年7月20日 牧氏陰謀事件:北条時政・妻の牧氏、平賀朝雅を将軍に立て様と謀り失敗、初代執権・北条時政は伊豆国に退く。北条義時、第2代執権に就く。
1205年7月26日 在京御家人が後鳥羽院の御所に集結、平賀朝雅を追討、平賀朝雅は一旦闘争したが追撃され討ち取られる。後鳥羽上皇は幕府内紛で近臣を討ち取られた事に衝撃。
1205年 源頼家の子・公暁(6歳)、北条政子の計らいで仏門に入る。
1206年 チンギス・ハン、モンゴル帝国を樹立。
1207年 親鸞、法然の承元法難に連座し越後に流される。その後、常陸・信濃・下野等を教化し浄土真宗を開き、阿弥陀様による万人救済を説いた。
1209年4月 源実朝、従三位に叙されこの機に政所開設し親裁権を行使。当初、北条義時・大江広元ら幕府首脳部は、若い源実朝侮るような行動に出る。
1209年5月12日 和田義盛、源実朝に上総介任官の推薦を願い出る。北条政子は『侍が受領になる事は頼朝様の時代に禁じられている』として反対。
1209年11月27日 源実朝、和田義盛の上総介任官について対応を約束し暫く待つ様命じる。
1210年6月 後鳥羽上皇に仕える北面の武士・藤原秀康が上総介に任命。
1210年11月 第83代・土御門天皇譲位、第84代・順徳天皇即位。
1210年12月 和田義盛、上総介任官の希望を撤回。北条義時、和田義盛を警戒。
1213年2月16日 泉親衡(ちかひら)の乱:信濃国の御家人である泉親衡が源頼家の遺児千手丸(13歳)を擁して北条義時を倒す計画が発覚。逮捕者の中に和田義盛の子・義直・義重と甥・和田胤長がいた。
1213年3月8日 和田義盛、我が子の赦免を源実朝に直訴。源実朝は衆議に掛ける事なく勲功に免じて和田義盛の子である足立義直・義重を赦免。
1213年3月9日 和田義盛、甥の和田胤長の赦免も訴えたが、大江広元が申し継ぎ、源実朝はこれを拒否。そこへ甥の和田胤長が後ろ手に縛られたまま一族の前を歩かされ流罪となる。北条義時の挑発であった。和田義盛、深い怒りを覚え出仕せず。
1213年3月25日 和田義盛、甥の和田胤長屋敷地の拝領を願い出る。源実朝は直ぐに許可。
1213年4月2日 北条義時、和田義盛の願い出た和田胤長の跡地は自分が拝領したとして和田義盛から取上げ。
1213年4月27日 源実朝、不穏な情勢を鎮め様と和田義盛を慰撫する使者を送る。和田義盛『反逆の意思はないが義時の傍若無人に怒っており止める事ができない』と返答。
1213年5月2日 和田合戦:執権・北条義時は幕府創業以来の御家人で侍所別当の職にあった和田義盛を挑発、和田一族に反乱の軍を挙げさせた。和田氏は頼みとした三浦義村が北条氏に味方した為、鎌倉で戦って全滅。以後侍所別当は執権・北条氏の兼任となり執権政治が確立していった。幕府創立以来の御家人多数が討ち取られ新しい執権政治体制が整う事となる。
1213年5月3日 由比ヶ浜・若宮大路で激戦が繰り広げられ和田義盛・朝盛・義直らが戦死、和田氏滅亡。源頼朝死後、最大の内戦。源実朝から北条義時に和田義盛追討令が出され御家人は北条義時軍に加勢、戦いが決定的となった。
1213年5月5日 北条義時、政所別当・侍所別当を兼ね、これによって執権職が確立したと云われる。
1215年1月6日 北条時政(78歳)没。初代執権。
1216年7月24日 鴨長明(61歳)没。賀茂御祖(みおや)神社の禰宜長継の次男。従五位下に叙せられ南大夫または菊大夫と呼ばれた。琵琶を中原有安に、和歌を俊恵 (しゅんえ) に学ぶ。後鳥羽上皇の和歌所設置に伴い、寄人(よりうど) に選ばれ、多くの歌会・歌合に参加。上皇の恩顧により河合(ただす)神社の禰宜に任じられ様としたが、同族鴨祐兼(すけかね)の反対により実現せず、これを機に50歳で出家、法名を蓮胤(れんいん)と号し日野の外山に隠棲した。著「方丈記」。
1216年11月24日 源実朝、巨大な唐船を建造するよう命じる。北条義時・大江広元は思い留めるよう諫めたが聞き入れず。
1217年4月17日 巨大な唐船の進水式、5百人の人夫が5時間かけて引いたにも拘らず船は油井浦に浮かばず。その後、巨大な船は朽ち果てる。
1217年6月 源頼家の遺児・公暁(くぎょう)が鎌倉に下り鶴岡八幡宮の別当となる。源実朝呪詛の祈祷をしていた可能性が高い。且つ、親王将軍が推戴されるとなれば自分が将軍となる道が閉ざされる。
1218年2月4日 北条政子・北条時房、上洛。六条宮雅成親王・冷泉宮頼仁親王のどちらかを源実朝の後継将軍として鎌倉に下して貰う約束を取付ける。
1219年1月27日 源実朝(28歳)、鶴岡八幡宮で源頼家の子・公暁に殺される。鶴岡八幡宮で右大臣就任拝賀の式典が終り大石段を下ると公暁が『親の仇はかく討つぞ』と叫んで首を落す。更に先導する太刀持ちの源仲章(なかあきら)も惨殺。公暁、一人で三浦義村の屋敷に向かうも三浦義村に殺される。
1219年2月11日 源実朝の叔父・阿野全成の子・時元が軍勢を率いて駿河国阿野郡の山中に城郭を構え宣旨を賜って東国の支配を企てる。北条政子の命令により同月22日に自害させる。
1219年2月13日 北条政子、朝廷に雅成親王・頼仁親王どちらかの鎌倉下向を申請する使者を上洛させる。後鳥羽上皇の回答は『親王二人の内一人は必ず下向させよう。但し、今すぐにと云う訳にはいかない』。
1219年3月9日 後鳥羽上皇は藤原忠綱を弔問使の名目で鎌倉に送る。弔意を伝えた後、北条義時に長江荘・倉橋荘の地頭改補を要求する院宣を伝える。
1219年3月15日 北条政子・義時・時房・泰時・大江広元が審議を重ね、結論は北条時房が北条政子の使者として千騎の軍勢を率いて上洛し地頭改補を拒否した上で親王の早期下向を後鳥羽上皇に要請すると云う強攻策であった。
1219年3月27日 源実朝の叔父・阿野全成の子・僧侶となっていた道暁を死に追いやる。
1219年6月3日 九条道家の子・三寅(後の頼経)、北条時房・泰時・三浦義村らと共に六波羅を出発し鎌倉に下向する。
1219年7月13日 大内(皇居)の守護を努める源頼茂『我将軍にならん』と望んでいたが絶たれ謀叛。後鳥羽上皇、在京武士に命じ源頼茂の討滅を命じる。源頼茂、内裏に火をかけ自害。内裏の大部分が焼失。
1219年7月19日 九条三寅(3歳)、鎌倉に着き北条義時の「大倉亭」に入る。北条政子が「理非を簾中で聴断」する事となり尼将軍の誕生。
1219年8月4日 後鳥羽上皇、藤原秀康に北陸道・山陽道・諸国の国務を担当させ大内裏の再建に当たらせる。
1219年10月 後鳥羽上皇、この8月から諸国の国務の人事を進め、院宣を下し自ら内裏再建を命じる。しかし、大多数の地の国司・領家・地頭の別なく造内裏役を拒否する抵抗の嵐が吹き荒れる。
1220年3月22日 後鳥羽上皇、内裏造営の「事始」を行なう。後鳥羽上皇、元々、大内裏焼失は幕府内紛が原因で幕府が地頭を指揮し積極的に再建に協力すべきと考える。にも係わらず、地頭の抵抗を幕府に訴えても幕府は無視。幕府の中に元凶がいると考える。それは誰?。
1220年3月26日 京の清水寺本堂等焼失、この4月には祇園社・大内裏陽明門等が相次いで焼失。
1220年4月15日 三浦義村の弟・三浦胤義が源頼家の遺児禅暁を公暁に加担した嫌疑により京都で誅殺。幕府は、数人の将軍候補の粛清が終わる。
1220年7月 後鳥羽上皇、この頃から北条義時討伐に傾く。
1220年10月18日 大内裏再建の殿舎・門・廊下等の「立柱上棟」を行なう。
1220年12月8日 大内裏再建の「檜皮葺始(ひわだぶきはじめ)」を行なう。しかし、幕府の協力もなし、国司・領家・地頭を問わず全国的な抵抗の嵐で造営をいったん中止。
1220年12月 後鳥羽上皇、造内裏行事所解散。
1221年1月27日 後鳥羽上皇、城南寺で笠懸を行ない兵の招集を行う。
1221年2月4日 後鳥羽上皇、29回目の熊野詣でに出る。北条義時追討の祈願をしたのではないか。これが最後の熊野詣でとなる。
1221年4月2日 後鳥羽上皇、伊勢・石清水・加茂三社に奉弊。
1221年4月20日 第84代・順徳天皇、譲位し第85代・仲恭天皇(4歳)即位。九条道家が摂政となる。
1221年4月28日 1千余騎が後鳥羽上皇・土御門上皇・順徳上皇らが集まる院御所高陽院殿に集結。鎮護国家・仏敵降伏の祈祷に乗じて北条義時を調伏したと思われる。
1221年5月14日 後鳥羽上皇、幕府に近い西園寺公経・実氏父子を幽閉。
後鳥羽上皇、流鏑馬大会を表向きの理由に諸国の兵を召集、畿内・近国・在京の武士1,700余騎が集まる。
1221年5月15日 三浦胤義の兄・三浦義村を誘引する書状を携えた使者、伊賀光季が緊迫した情勢を知らせる為討伐を受ける前に発信した使者、西園寺公経の家司である三善長衡が官宣旨が五畿七道に下された事を伝える使者、それぞれの使者が京を発ち鎌倉に向かう。
後鳥羽上皇、北条義時追討の院宣を下す。
承久の乱:後鳥羽上皇、三浦胤義ら8百余騎の官軍に京都守護伊賀光季(みつすえ)の宿所を攻め討ち、北条義時追討の院宣を下す。後鳥羽上皇が鎌倉幕府執権の北条義時に対して討伐の兵を挙げて敗れた兵乱。 日本史上初の朝廷と武家政権の間で起きた武力による争いであり朝廷側の敗北となる。以後、鎌倉幕府では北条氏による執権政治が100年以上続いた。北条義時は朝廷を武力で倒した唯一の武将。
1221年5月16日 北条義時追討の院宣、院の下部の押松(おしまつ)に託され午前4時頃、押松、京を発つ。
1221年5月19日 5月15日に発した使者、相次いで鎌倉に入る。三浦義村の進言により押松を捕え各地に配る宣旨等の書状を押収。
評議を行ない、足柄・箱根で迎撃するかに決まりかけたが、大江広元が『追討軍が京を発つ前に逆に攻勢を掛けるのが最善策』と進言し結論に達する。
尼将軍名演説:北条時房・泰時・大江広元・足利義氏・安達景盛・武田信光・小笠原長清・小山朝政・宇都宮朝綱・長沼宗政・足利義氏が北条政子の邸宅に集まる。『皆、心を一つにして奉(うけたまわ)るべし。これ最後の詞也。故右大将軍頼朝が朝敵を征伐して関東を草創して以降、御家人達は官位も俸禄も手に入れた。その恩は既に山岳よりも高く、溟渤(めいぼつ:海)よりも深し。報謝の志は浅い筈がない。今、謀叛を企む悪臣の讒言によって後鳥羽が道理に背く勅命をお下しになった。名を惜しむの族(やから)は、秀康・胤義等を討ち、三代に渡る将軍が残した遺産を守る様に。但し、院中に参らんと欲する者、ただ今申し切るべし』皆、涙に暮れて充分な返答も出来ずひたすら命を捨てて恩に報いようと思う。一気に主戦論に傾く。
1221年5月21日 一条頼氏が鎌倉に下向し西園寺公経が拘束され伊賀光季が自害した等の緊迫する京情勢を伝える。御家人達の不安・動揺が表面化する。
1221年5月22日 06時頃、小雨が降る中、北条泰時(38歳)・時房ら18騎の決死の出撃。最終的に19万の軍勢となる。
1221年5月25日 幕府軍は3軍に分れて進撃、東海道軍、北条泰時・北条時房、東山道軍、武田信光、北陸道軍、北条義時の息子の北条朝時(ともとき)。
1221年5月26日 後鳥羽上皇、関東軍が上洛しようとしている第一報が届き『まさか自分に刃向かうとは……』慌てて西国から兵を徴兵。19万の敵を2万で迎え撃つ圧倒的に不利な状況となる。
1221年6月1日 18時頃 幕府が院宣の返事を持たせて返した押松が院御所の大庭に帰り着き北条義時に言われた通り報告。
1221年6月3日 幕府軍が遠江国府に着いたとの報を受け公卿僉議(せんぎ)が開かれ、藤原秀康を追討使とする軍勢の派遣が決められる。その数19,000騎。
1221年6月5日 幕府軍、尾張国一宮に到着、軍議を開き攻撃の分担を決める。
美濃の合戦:幕府軍、大井戸・河合で木曽川を渡った武田・小笠原に対し朝廷軍奮戦も退却。
1221年6月8日 朝廷軍の藤原秀康らが傷を負いながら帰洛、状況報告に院中は騒然となる。
後鳥羽上皇、比叡山延暦寺の増兵に期待し比叡山に御幸。西坂本の梶井御所に泊まる。
1221年6月9日 幕府北陸道軍、砺波山で幕府軍が朝廷軍に勝利。
1221年6月10日 後鳥羽上皇、延暦寺から届いた返答は『衆徒の微力では東士の強威を防ぎ難い』と云うもの、高陽院殿に還御。
1221年6月12日 後鳥羽上皇、朝廷軍勢を諸処に派遣の指図を行なう。
1221年6月13日 北条時房は瀬田、北条泰時は宇治、毛利季光・三浦義村は淀・芋洗に向けて出陣。
1221年6月14日 宇治川の戦い:宇治・瀬田の合戦で京方敗北。夜、幕府軍、瀬田の渡河に成功、朝廷軍は敗走。
夜半 三浦胤義らが院御所の門前で奏上するが、後鳥羽上皇、それらを追い払う。
1221年6月15日 幕府軍入京。08時頃、院宣を捧げ持った勅使の小槻国宗ら20人、樋口河原で北条泰時と対面。院宣の内容は『今回の大乱は後鳥羽のご意志によって起きたのではなく、謀反を企む「謀臣」が起こしたものである。今となっては泰時らの申請通りに宣下するつもりである』。
1221年6月19日 後鳥羽上皇を四辻殿に移し、土御門上皇らを本来の御所に戻す。
1221年6月23日 02時頃、北条泰時からの戦勝報告が鎌倉に届く。公私の喜びは例えようがなかったと云う。
1221年6月24日 04時頃、大江広元、平家滅亡時の先例に基づいて関係者処罰に関する指示を文書に纏め京へ送る。
1221年7月6日 後鳥羽上皇の身柄を四辻殿から鳥羽殿に移される。
1221年7月8日 後鳥羽上皇、似絵(にせえ)の名手・藤原信実に御影(みえい)を描かせる。現在、水無瀬神宮に所蔵される肖像画。警護の武士に懇願して対面を許された母の七条院殖子は悲涙を抑えて帰る。
1221年7月9日 鎌倉幕府の指示により第85代・仲恭天皇(後鳥羽上皇の孫)廃位となり茂仁親王へ譲位。第86代・後堀河天皇(10歳)即位。守貞親王が後高倉上皇となって院政を開始。後高倉上皇は天皇を経験せず治天の君になる等前代未聞。幕府の前に王家・摂関家・公卿達の合議は全く機能せず人事権を幕府に握られる。
1221年7月10日 北条泰時の子・武蔵太郎時氏が鳥羽殿に参上し、弓の片端で御廉をかき揚げ『君は流罪におなりました。早くお出下さいませ!』と責め立てられ、後鳥羽上皇は返事すら出来なかった。しかし、再び責められると昔から寵愛していた『伊王左衛門能茂に今一度会いたい』と答える。武蔵時氏が北条泰時にその旨を書状で伝えると北条泰時は藤原能茂を出家させた上で後鳥羽殿に行かせる。後鳥羽上皇は『出家したのだな。自分も今は姿を変えよう』と仁和寺御室を戒師に出家し、切った髻(もとどり)を七条院に送った。これを見た母は声も惜しまず涙を流し悲しんだと云う。
1221年7月13日 後鳥羽上皇、鳥羽殿から隠岐島に移送される旅路につく。伊藤祐時(すけとき)が身柄を受取り「四方の逆輿」に乗せたと云う。供奉(ぐぶ)したのは藤原能茂と坊門信清の娘で頼仁の母「西の御方」ら女房2~3人、旅先での急死に備えて用意された聖(ひじり)一人であった。
1221年7月20日 順徳上皇、佐渡国に配流。
1221年7月21日 後鳥羽上皇、出雲国大浜湊に着。武士達の多くはここで帰京。後鳥羽上皇、ここで暫く風待ちで留まる。
1221年7月 幕府、後鳥羽上皇を隠岐へ、順徳上皇を佐渡へ配流等3人の上皇が配流、前代未聞の事であった。幕府の支配が日本全体に広がり武士の世が確立。
1221年8月5日 後鳥羽上皇、舟に乗り隠岐島に渡って行く。後鳥羽上皇は、幕府監視下の生活で地元豪族の村上氏が生活の面倒を見る。『われこそは 新島守よ おきの海(み)の あらきなみ風 心して吹け』(私はこの隠岐の島の新しい番人である。隠岐の海の激しい風よ、気をつけて吹け)。
1221年8月7日 幕府、京方の在京御家人の守護職を没収し有力な東国御家人に与え、京方の貴族や武士の所領三千余カ所を没収し鎌倉方の御家人達に恩賞として配分。新恩を給与された東国御家人は西国の没収地に新補地頭として次々と移住。鎌倉幕府の全国支配が成し遂げられる。
1221年10月10日 土御門上皇、土佐へ配流。後、阿波国に移る。三人の院が流罪となる三上皇配流という前代未聞の結末を迎える。
1221年 幕府は京に六波羅探題を設置。役割は、①朝廷の監視・交渉、②京の治安維持、③西国関係の裁判。
1224年6月13日 北条義時(62歳)没。
1224年6月28日 北条泰時、京都から戻り北条政子の御所に招かれる。北条政子、北条泰時を執権に任命、大江広元も賛同。しかし、北条義時の後妻である伊賀の方が北条泰時による家督継承に反対。伊賀の方は自分の子である北条政村を執権職に就け娘婿の一条実雅を将軍に擁立しようと企てる。
1224年6月 伊賀氏の変:鎌倉幕府の実権争奪を巡って起きた執権北条氏の内紛。執権・北条義時の死後、北条義時の後妻・伊賀局(伊賀守・藤原朝光女)は兄弟の政所執事・伊賀光宗と謀り自分の子の北条政村を執権にし女婿の藤原(一条)実雅(一条能保の子)を将軍に立てて幕府の実権を握ろうとし、北条義時の長子・北条泰時を執権にしようとする北条政子と対立。伊賀氏らは幕府最大の豪族・三浦義村を味方にして野心を実現しようとしたが、6月末機先を制して北条政子は北条泰時を執権に指名すると共に翌月、三浦義村を説得してしまった為、伊賀氏らの野望はついえた。伊賀局は政子により流罪。
北条泰時、第3代・執権に就く。幕府を大倉から鎌倉中心部の宇都宮辻子に移転したのを機に、評定衆を定め合議制を制度化し鎌倉大番の制を整えた。幕政大いに刷新し、ここに執権政治が確立したと云える。
1224年7月17日 深夜、北条政子、三浦義村を訪ね謀叛の詰問。北条泰時側に付く様迫る。三浦義村は北条政子に謀叛の気持ちはないと弁明。
1224年8月29日 伊賀の方、伊豆国北条に幽閉、伊賀光宗は信濃国に流罪、一条実雅は越前に流され伊賀一族は九州に流された。この事件は北条政子が伊賀氏を追い落とす為の陰謀。
1225年6月 大江広元(78歳)没。
1225年7月11日 北条政子(69歳)没。
1226年1月27日 摂政・九条道家の子の三寅、元服し藤原頼経(9歳)と名乗り第4代・征夷大将軍となる。
1227年 大内裏焼失。同じ場所に再建されず。
1228年12月 九条道家、関白を務め朝廷政治を主導。
1230年 寛喜の飢饉:1230年6月雪が降り7月霜が降りる天候不順による大凶作が全国を襲った。この状況は翌年8月頃まで続き、餓死者の死骸が所々に放置されていたという。
1230年代から40年代初めに掛けて「承久記」原型の成立とほぼ時を同じくして保元の乱、平治の乱、治承・寿永の乱を活写した「保元物語」「平治物語」「平家物語」の原型が作られた。平家物語の作者は信濃前司行長と云われている。これらの軍記は敗れ去り死んでいった人々への追慕・鎮魂と云う精神的な基盤の上に成立。
1231年10月 土御門上皇(37歳)、配流先阿波国で没。
1232年8月10日 北条泰時、裁判制度の指針となる御成敗式目51ヵ条を制定し即日施行。飢饉による訴訟等が多く徳政の到達点がこの法であった。
1235年5月14日 1235年3月、朝廷政治を主導する九条道家が幕府に対して後鳥羽上皇の還京を本格的に働きかけるも北条泰時が明確に否定、還京の望みが絶たれる。
1239年2月22日 後鳥羽上皇(60歳)隠岐島で没。後鳥羽上皇、晩年、「永五百首和歌」「遠島五百」の和歌集作成。隠岐島と京の母七条院・寵妃修明門院・歌人藤原家隆らと書状・歌書等の遣り取りを行なって作成。遺骨は藤原能茂が首に掛け京に持ち帰る。
1242年6月20日 北条泰時(60歳)、数日間高熱に苦しみ「辛苦悩乱」して絶命。後鳥羽上皇の呪いと云われる人々は恐怖。北条経時(19歳)、第4代執権に就く。将軍頼経(25歳)、将軍・執権の年齢が逆転し幕政の主導権を巡る緊張関係が生じる。
1242年7月8日 後鳥羽上皇の本来の諡号は「顕徳院」。呪いを恐れ「後鳥羽院」に改められる。前例のない措置であり、後鳥羽の名はこの時から始まる。
1242年9月12日 順徳上皇(46歳)没。配流先佐渡で還京の望みも絶たれ自ら飲食を断つ。
1243年6月 鎌倉大仏:初代の阿弥陀如来像を安置した大仏殿の落慶供養。鎌倉仏像造立。初代は木造であった模様。
1244年4月28日 幕府は、藤原頼経(25歳)の子・藤原頼嗣を第5代・征夷大将軍とする。藤原頼経は、御家人と親密となり執権勢力に対抗する様になると、これを恐れた執権・北条経時は藤原頼経に迫って将軍職を子の藤原頼嗣に譲らせた。藤原頼経は翌年出家。
1246年3月 執権・北条経時没。北条時頼が第5代・執権に就く。
1246年6月 執権・北条時頼、藤原頼経派の粛清を敢行。
1246年7月 宮騒動:執権・北条時頼、藤原頼経を京都へ送還。北条得宗家が専制権力を振るう。北条一族の名越光時が執権の地位を奪おうとした事件に関係して藤原頼経は京都に追われた。この事件によって藤原頼経の父・九条道家も失脚し、三浦光村が藤原頼経の寵臣であった事から翌年の宝治合戦へと続く。
1247年6月5日 宝治合戦:鎌倉で行われた北条時頼と三浦泰村との合戦。三浦氏の乱とも云う。北条氏と三浦氏は協調的関係を続け幕政に重きをなしてきた。三浦泰村も北条泰時の女婿として勢力をふるったが北条時頼の外祖父・安達景盛父子と対立し北条氏とも疎遠になった。北条時頼・景盛の陰謀により一族は反抗したが敗亡。これ以後、北条氏の独裁体制が確立した。
1249年 三十三間堂に仏師運慶の長男湛慶が仏像を造立。
1252年 鎌倉大仏二代目の鎌倉仏像造立。現在に至る。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
