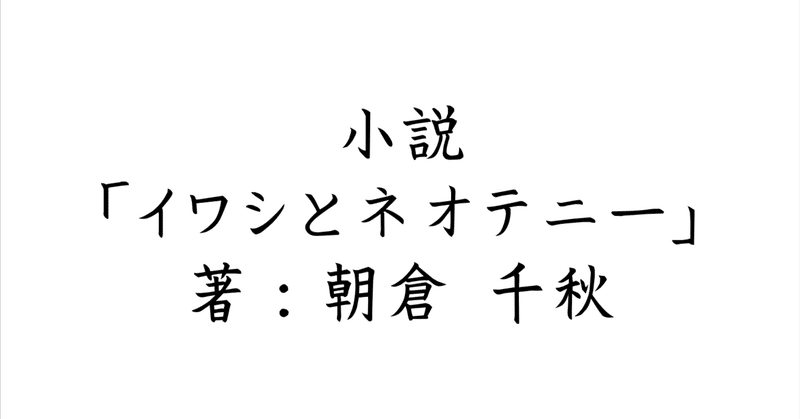
イワシとネオテニー 著:朝倉 千秋
2022年の神奈川文芸賞に応募した作品です。
残念ながら落選となりましたので、文字数の関係で削っていた部分などを多少加筆し、こちらへ投稿します。
イワシとネオテニー
著:朝倉千秋
美しい、と思うと同時に、淡い恐怖も湧き上がった。その二つは深い部分で切り離すことができないのだろうと、幸典は思った。新江ノ島水族館の中でも目玉となる巨大な相模湾大水槽、エイやサメなど大型の魚類が悠然と泳ぐ中、鈍く光る塊は異様なまでの存在感を放ってそこに在った。
全体でひとつの個体のように捻じれ、脈動しながら形状を連続的に変化させるその表面には、個々の〝構成員〟の向きに沿ってうねるような流れが刻まれる。流れはときに先端から枝分かれし、あとに続く個体〝たち〟がその枝葉を太く変えていく。気づけばそれもまた塊に飲み込まれるように循環し、巨大な全体を形作る。塊は形を変える度、水面から降る光を受けて鈍く輝いた。
解説によれば、八〇〇〇ものカタクチイワシがその塊を構成しているという。八〇〇〇……。直感的に把握するには多過ぎるその数量が、実体を持って目の前にあった。幸典は目を凝らし、一匹のイワシを目で追ってみることを試みた。しかし目をつけた次の瞬間にはもう、それは再び〝構成員〟のひとつへと戻ってしまっているのであった。
「こんなところにいたのかよ」
声の方を振り返ると、やや呆れたような表情を浮かべながら歩み寄る浩平の姿が目に入った。短く刈り込んだ短髪には汗が滲み、今まで冷房の効いた館内にはいなかったことが見て取れる。浩平は幸典の隣へと歩み寄り、巨大な水槽を並んで見上げた。
「へぇ、すげぇな、あの群れ」
「カタクチイワシだよ」
「イワシか。弱そうには見えないな」
「はぁ?」
「魚偏に弱いって書くじゃん、イワシって」
「まぁ、小さいしね」
「でも強そうだよな、あれ」
こいつには自分と同じものが見えているのだろうか、と軽く疑問に思いつつ、その能天気さにあてられて、幸典は自分がいつの間にか、深海から地上へと戻って来ていたことに気がついた。
「小学校の教科書でさ」浩平が言った。「スイミーってあったじゃん?」
「魚の群れが大きな魚を追い返すやつね。一匹だけ色の違うスイミーが目になって」
「アレがさ、小さい頃は納得いかなかったんだよな。そんなに上手くいくのかよって」
寓話だから、と言いかけて幸典はその言葉を飲み込んだ。そういう話がしたいのではないのだ。一緒に江の島を訪れたゼミの同期の中でも、入学当初から知り合いだった浩平とはそれなりに付き合いも長い。
浩平は水槽を指さして続けた。
「でも今、納得した。これには勝てないわ」
思わず小さな笑い声を漏らすと、浩平は「なんだよ」と不服そうに言った。
「ごめん、まるで今から自分が戦うみたいな言い方だったから」
「大きな魚の視点で考えてだよ」
調子狂うな、と浩平は頭を掻いた。
「でもさ、スイミーはこれとは違うと思う」
「何で?」
「これじゃあ大きな魚には見えないし、スイミーが目になる必要もない」
そもそも一匹だけ違う色の魚が混じっていても、この奔流の中では……、どこにいるのかも見定めることはできないだろう。
浩平は眉間にしわを寄せ、たしかに、と呟いた。
幸典以外のメンバーは売店の近くにたむろし、冷たい飲み物やアイスを片手に涼んでいた。みんな今まで外でイルカショーを観ていたのだ。幸典もショーが始まること自体はアナウンスで認識していたが、うだるような暑さの屋外でショーを見るより、そっちに人が流れた隙に館内を満喫する方が性に合っていると思い、敢えて館内に残っていた。
イルカショーは青年たちに鮮烈な印象を残したらしく、その場はショーの感想でもちきりだった。実物を観たのはみな久々で、童心に返ったように夢中になったらしかった。
同期のちひろと香苗は、イルカの大きなぬいぐるみが一等のくじ引き機の前で、くじを引くべきかどうか真剣に相談していた。透明なドーム状のくじ引き機の中では、大量の紙片が風に舞い踊り、桜吹雪のように勢いよく渦を巻いていた。結局行動力のあるちひろの方が思い切ってくじを引き、小さなアザラシのマスコットを手に入れるに至った。
帰りのレンタカーの車内、幸典はイルカショーの間に何をしていたのかと問われ、シラスを見ていた、と答えると皆一様に彼を笑った。お前らしいな、と運転席から浩平が言った。俺らしいのか、と幸典は思った。
しかし実際、シラスの展示はなかなか見事なものだった。新江ノ島水族館は世界で初めて、人工でのシラスの孵化と展示を成功させている。展示は三種類の水槽に、それぞれ別の生育段階のシラスたちが展示されており、水槽を追うごとにシラスが成長していく過程を見ることができるようになっている。ほんの小さな、水中に揺らめく埃にも見える稚魚たちが、少しずつ大きさを増し、見慣れたシラスの姿となり、ぐるぐると水槽の中で巨大な渦を形作るようになっていく。その過程を辿った後に、大水槽で渦巻く八〇〇〇匹のカタクチイワシと相対したときの感動は、時間をかけて鑑賞せずには得られないものであったろうと、幸典は確信していた。
スマホの振動で目を覚ました。昼休憩終了五分前にかけたアラームだ。握りしめていたスマホのアラームを止め、トイレの洗面台で顔を洗い、自販機でエナジードリンクを購入して自席に戻る。数分席を離れている間に、隣の席の田代さんもランチから戻ってきていた。彼女は幸典がデスクに置いた缶を見て、「身体に悪いよ」と茶化すように言った。
「飲まない方がダメな気がして、最近」
「中毒じゃん、ヤバいって」
「忙しくない時期は飲まないよ」
「ほぼないってことじゃん」
はは、と示し合わせたように笑う。労働環境が悪いのを茶化して笑い合うのは、彼らにとってささやかな息抜きのひとつだった。
常駐先に派遣されて開発を行うSESというエンジニアは、上から降りてくるシステムの設計に基づいて黙々とプログラムを書いていく。IT土方と呼ばれたりもするが、その呼称を幸典はあまり好まなかった。
実際の現場は上流の遅延による皺寄せを食っているのが常で、正確な設計が降りてくることなどまずない。中途半端な設計と降り注ぐ仕様変更を元に、何とかシステムが動くよう四苦八苦しながらコードの海を泳ぎ回るのが幸典たちの仕事だった。巨大なシステムの末端を黙々と作り上げ、個々の成果物が本流のシステムに統合されてやがてシステム全体を形作る。傭兵のようだ、と幸典は思っていた。彼らには作戦に口を出す権限はなく、いかに戦況が苦しかろうと、上層部の指令が理不尽だろうと、ただ淡々と従うのみだ。
過多で理不尽なタスクや、度重なる仕様変更による「今堀った穴をまた埋めさせられる徒労感」の連続に耐えかね、姿を見せなくなる人間も多い。これでも前より労働環境は良くなったと聞くが、それにしても過酷なことには変わりはない。
人の入れ替わりが激しい環境の中、幸典と田代さんは既に一年以上共に業務にあたっていた。SESの幸典と正社員の田代さんで雇用形態こそ違ったものの、年齢も近く、デスクも隣で、同期のように親しくしていた。仕事の愚痴を言い合い、くだらない会話で息抜きができる戦友がいなければとっくに辞めていたかもしれないと、幸典は時折考えた。
定時が近づき、幸典はそそくさとその日の作業を畳みにかかった。
「今日は早いね」
「ちょっと飲みにね」
「さてはデート?」
「ないって。男友達」
なぁんだ、と残念そうに田代さんは仕事に戻った。がっかりすることでもないのに、と幸典はモニターの電源を落とした。
消灯したタッチパネルに指先で触れると、慌てて目を覚ましたかのようにパッと画面が点灯する。ビールをタップして注文確定を押そうとしたところで、浩平が「俺もビール」と空のジョッキを掲げた。ビールの表示を再度タップし、数量を増やしてから確定ボタンを押す。ほどなくして生ビールが二つ届き、店員は慌ただしく去って行った。横浜駅からほど近い居酒屋は平日夜も混雑しており、狭い通路を縫うように店員がテーブルからテーブルへ飛び回っていた。
浩平は届いたジョッキに待ってましたとばかりに口をつけ、やっぱビールだよな、と最近蓄え始めた口髭に泡をつけて笑った。口髭以外、学生時代そのままだった。
ゼミの同期で、未だに時々飲みに行くのは浩平くらいのものになっていた。社会人になってすぐは全員で集まることも多かったが、関東を離れたり、結婚をして家庭を持ったりする人が増え、結局一番親しかった二人だけで飲むようになってしまった。最後に全員で集まったのはいつだったか……。
「どうかしたか?」
「ああ、前の同期飲み、いつだっけ?」
「ちょうど一年くらい前じゃないか? ほら、ちひろがこっちに来たとき」
「あーそうか。あれも夏だったね」
ちひろは大学卒業後二年ほど経った頃、転職で地元の広島へと帰っていた。
「一年か。あっという間だな。仕事始めてからは飛ぶように時間が過ぎるよ」
「おっ、どうした感傷的じゃん」
いやいや、とそれを笑い、幸典もビールを飲んだ。
「四年のときにさ、みんなで江の島行ったの覚えてる?」
「あったなぁ。アレもこの時期だった」
「あの頃の夢を見た気がしてさ」
「やめてくれよ、老人かよ!」
笑うことないのに、と幸典は気恥ずかしくなり、餃子をひとつ口へと放り込んだ。
「でもあのときは楽しかったな。みんなで子どもみたいにイルカショーで喜んで」
「俺は観てないんだって」
「そうだそうだ、お前はシラスに夢中で」
「素晴らしいシラスだった」
「いつもどっかズレてんだよなぁ」
浩平は笑って、でもまぁ、と続けた。
「俺は今もあの頃と同じくらい楽しいよ」
「会社、上手く行ってるんだ」
「まぁね。今度オフィスを移転する。社員も増えてきたし、ちょっと前に内見して場所も決めてきた」
おめでとう、と幸典は実感のないまま言った。浩平は大学を卒業後、友人と数人でベンチャーを立ち上げていた。最初の頃は時折ライフラインが止まるなどして周囲から心配されていたが、最近は軌道に乗ったらしく、横文字の肩書きを持った経営陣として溌剌と働いている。蓄え始めた口ひげも威厳を出すためのものだそうだ。部下に威厳を示すのも仕事のひとつだ、と浩平はよく言っていた。
「羨ましいよ、仕事が楽しそうで」
「楽しくなくちゃ人生じゃないよ」
意識がスッと少しだけ後ろへと遊離する。店内の喧騒が急に強く、幸典の鼓膜をたたき始めた。ビールを飲み干した浩平は、やや乱暴にジョッキを置いた。
「お前さ、うち来ない?」
少しだけ低いトーン。幸典が笑ってかわしても、浩平は笑わなかった。
「採用って骨が折れるんだ。面接なんか一生懸命やってもさ、短時間じゃ何も分からん。入れてみりゃ期待外れがほとんどだ」
「俺だって、期待に沿えるとは限らないよ。スキルだってほぼない」
「スキルなんてこっからどうにでもなるさ。大事なのは信用に足るかどうかだ」
「そんな大層な人間じゃないよ」
「いいや、その点は確実だ。何年もかけて面接してるみたいなもんじゃんか」
その言いぐさに幸典はムッとした。浩平は慌てて「すまん」と謝った。
「信頼してるって言いたかったんだ。言い方が悪かった」
何か飲むか? まだあるよ。そうか。
浩平はビールを頼み、店員が空のジョッキと新たなビールを取り替えた。
「でも実際さ」ジョッキに手をつけず、浩平は言った。「お前さ、どうすんの、今後」
「どうすんのって」
「ビジョンだよ、ビジョン。今の仕事続けてって、どうなりたいとか」
「特にはないよ。楽な仕事ではないけど、それなりに続けていけてる」
「もっと年収上げたいとか」
「今くらいで十分だよ。多くはないけど食うには困らない」
「今はそうかもしれないけどさ、俺らもそろそろ二十代終わるんだぜ? 結婚とか考えたらさ」
「そんな相手もいないし、別に結婚願望もないから」
「後になって後悔してからじゃ遅いぜ? ゼミの同期でも俺らくらいだ、まだ独り身なのはさ。子どもが居るヤツだっている」
「それはお前が焦ってるだけだろ?」
口が滑ったか、と幸典は思った。しかし浩平は小さく肩を落とし、「これだもんな」と残念そうに呟いて、手をつけていなかったジョッキを勢いよく傾けた。
それ以上、今後の話はしなかった。流行の漫画の話や、日常のくだらない話をして、明日も仕事だからと早めに切り上げた。さっきのは気にしてないという態度をお互いに貫いていたが、わだかまりから目をそらすのに双方の意識が注がれているのは明らかだった。東横線に向かうエスカレーター前で別れ、一人で京急の改札を目指しながら、色んなものが終わっていくな、と幸典は思った。
翌日の昼、幸典は田代さんとオフィス近くの定食屋で昼食を摂っていた。幸典は唐揚げ定食を頼み、田代さんは焼き魚定食を見事な箸捌きで綺麗に食べていた。
「よく揚げ物いけるね? 昨日飲んで、もたれてないの?」
「そんなに飲まなかったしね……」
ふうん、と彼女は鯖の小骨を淀みなく取り除いていく。気になりませんという態度ではあったが、幸典自身が思いがけない沈んだ声に自分自身でたじろいでいたから、田代さんがそのことに気づいていないはずもなかった。沈黙に耐えかねて、幸典は自分から昨日のやり取りを簡単に説明した。
「良いんじゃない? 友達の会社でしょ?」
「あ、そんな感じなんだ?」
「うん。大体この会社、みんなそれなりのところで次に行こうって思ってるでしょ」
それは間違いなかった。彼らの会社には若手と四十代後半以降のベテランはいても、三十代の中堅がごっそりと抜けているようなアンバランスさがあった。ある程度のところで〝卒業〟する人が、それだけ多い。
「でもさ、ベンチャーだよ?」
「大変そうなイメージだけどね。うちみたいな下請けよりやりがいありそう。学生時代の友達とって、何か夢あるし」
「楽天的だなぁ」
あはは、と田代さんは笑った。
「田代さんは、この先何か考えてるの?」
「私? まぁ、年収は上げたいよねぇ。でもここで偉くなってもやりがいはなさそう。そもそも上にあげてもらえるのかどうかすら怪しいよね、うち」
「転職はするつもりってこと?」
「一応資格とか取って準備してる。どっかで転職活動始めるかな、みたいな」
田代さんは簡単そうに言った。それが当然なのだ。いつもどっかズレてんだよなぁ、と浩平の言葉が頭を過ぎる。
「まぁでも」彼女は続けた。「タイミングが難しくて……。結婚とか、色々あって」
「え、結婚すんの?」
「今ちょっと考えてて。プロポーズはまだされてないけど、そういう空気っていうか」
「へぇ、おめでとう」
唐突に告げられた事実に、幸典の脳は上手く追いつけていなかった。彼の記憶が正しければ、出会った当時、彼女は「長年付き合っていた彼氏と破局した」と愚痴をこぼしていたはずだった。田代さんのことを異性として意識していた訳でもなく、プライベートな話を全て知っているつもりもなかったが、毎日顔を合わせていた背後で、彼女の人生が急速に動いていた事実に、目眩がした。
幸典の動揺に気づくことなく、田代さんは転職と結婚にまつわる悩みについて語った。語り終える頃には焼き魚も綺麗に骨だけの姿になっていた。もちろん、幸典は何一つとして有益な発言はできなかった。
週末の夜、その週のうちに済ませておきたかった仕事が思ったように片付かず、いつもより帰宅が遅くなった。近所のスーパーに立ち寄ると刺身が安くなっていて、幸典はそれを買い物かごに放り込んだ。刺身に合わせて少し奮発し、飲みきりサイズの日本酒も買った。残業はしたものの、悪くない晩酌ができそうだ、と軽い達成感を感じつつシャワーを浴び、刺身やいくつかの総菜を食卓に並べているときに、窓の方からカリカリと音がするのに気がついた。
窓の外には黒猫のクロが来ていた。幸典が窓を開けると、手が届かないギリギリの距離までさっと飛び退く。一階の幸典の部屋のベランダほとんど外と地続きのため、時折クロは柵をくぐって入り込んでくるのだった。
クロ、というのは幸典が勝手につけた名前であったが、一度も声に出して呼んだことはなかった。黒猫はその警戒心の強さから野良猫であろうと思われたが、もしかすると飼い猫かもしれず、何となく勝手につけた名前で呼ぶことは遠慮していた。その名前は、幸典の頭の中での便宜的なラベルみたいなものだった。
クロとの出会いは半年前、冬の寒い夜だった。雨が降り出す音で洗濯物を取り込んでいないことに気づき、慌てて取り込み始めた幸典の耳に、キーキーと軋むような奇妙な音が聞こえてきた。音源を探って室外機の奥を覗き込むと、黒い毛玉がそこにあった。聞き慣れないその音が猫の鳴き声だと気づくのにはいくらか時間を要した。それはあまり普通の鳴き声ではなかったのだ。
幸典の悩む間、洗濯物に雨が染みた。怪我でもしているのだろうか。寒さで風邪を引いたのだろうか。お腹を空かせているのだろうか。小さく黒い毛玉のような命に対して、何かをしてやりたい気持ちはあった。しかしペットを飼える物件ではない。猫についての知識もない。適切な対処法も分からない。
気づけば猫は幸典の方を怯えたように見つめていた。助けて欲しいとか、甘えているとか、そういう目ではなかった。その瞳は言うなれば、「貴方は私に危害を加える者か?」と幸典に問いかけていた。幸典は心の中で「いいえ」と答えた。それからなるべく猫を脅かさないように、重みを増した洗濯物を静かに部屋へと取り込んだ。軒先を貸すくらいしかできないよな、と心の中で誰にともなく言い訳をしながら、窓を閉めた。
部屋に戻ってしばらく経っても、幸典の頭からは黒い毛玉が離れなかった。何度か窓に歩み寄っては引き返すことを繰り返し、とうとうゆっくりと窓を開けて室外機の奥を再び覗くと、相変わらず小さな毛玉がそこにあった。先ほどよりもキーキーという鳴き声は小さくなっているような気がした。雨音が強まっただけかもしれなかったが、その変化は幸典の心をざわつかせた。もしも明日、ここでこいつが死んでいたら……。そう考えて耐えきれなくなり、部屋からツナ缶とタオルに包んだカイロを持ってきてやった。
幸典が近づくと、黒猫は後ずさりするように、室外機と壁の隙間に身体を押し込もうとした。なるべく怯えさせないよう、カイロとツナ缶を雨に濡れない、猫から少し離れた場所に置き、静かに部屋の中へと戻った。
気休めにしかならないかもしれないし、餌づけが良くないことだというのも、幸典には分かっていた。ただ彼は、そこで震える小さな命を無視することができなかった。
翌朝、雨が上がって綺麗な青空が広がっていた。室外機の奥に黒い毛玉の姿はなく、空のツナ缶と冷えたカイロが残されていた。後日、ベランダにスズメの死骸が届けられたのを見て、幸典は苦笑した。
それ以来、猫はたびたびベランダに現れるようになった。一度あげてるし今更だ、と言い訳をしつつ、幸典は猫にかつおぶしや煮干しを与えた。猫は決して一定以上に近づいてこなかったし、幸典も触ろうとしたり、親しげに話しかけたりはしなかった。猫が現れ、幸典が食べ物を与え、猫が食べ、静かに立ち去る、それだけだった。
その夜もクロは、やはり幸典と一定の距離を保っていた。マグロの刺身を持ってきて、小さくちぎってすのこに置いた。素早くマグロを平らげた黒猫は、丁寧に顔を洗ってその場を立ち去った。一度も触れたこともない、名前を呼んだことも声をかけたこともないその猫が、幸典は好きだった。
部屋に戻って晩酌をしていると、スマートフォンに着信があった。浩平からだった。浩平は既に酔っているようで、やや大きすぎる声で「この前は悪かった」と言った。
「こちらこそ、感じ悪かったと思う」
幸典は自分が悪いとはあまり思っていなかったが、一旦素直に謝り、安心したような浩平の声を聞くと、腹を立てていたことも馬鹿らしいような気がするのだった。
「お前の楽しそうな顔が見たいんだ、俺は」
浩平はしみじみと言った。愛じゃん、とからかうと、茶化すなよ、と浩平は笑った。
「学生時代のお前は、結構楽しそうだった」
「そりゃ楽しかったよ、学生だし」
「社会人だって、楽しんで良いと思う」
「毎日変わり映えしないしさ」
「人と会おうぜ。色んな人と。新しい人と」
「人とねぇ」
「結局、人間それなんだよ。決まった人としか会ってないと、どんどん小さくなってくんだ。別に転職はしなくて良いよ。プライベートでさ、新しく人と会おう」
新しい知り合いと新しいコミュニケーションを行う、そういうのも悪くないのかもな、と思ったのは、少しくらい気持ちよく酔っていたからかもしれなかった。
スピーカーで話しながらその場でマッチングアプリを入れさせられた。幸典も最初は渋ったが、今は誰でもやってる、いつでも辞められる、と上手いこと丸め込まれ、クスリみたいだな、と笑っているうちに登録が完了した。浩平と飲みながら何かをするのが久々で楽しかっただけかもしれない。プロフィールは浩平が考えた。それは割と見事な文章で、浩平の器用さに素直に感心させられた。
電話を切った後、幸典はマッチングアプリに表示された、たくさんの異性の写真と名前、それから簡単なプロフィールを見るともなしに眺めてみた。今は誰でもやっている、と言われていたように、実際にそこには誰でも存在しているように思われた。夥しい数の女性たちが、それぞれのアイコンと同一の形式に刻まれたプロフィールを携えて、ずらりとそこに並んでいた。適当な条件で絞込やソートをかけることができた。あなたにおすすめの女性、とわざわざシステムが提案してくれていた。店頭に陳列された商品のようだと思った。そして女性の側から見れば、幸典もまたそういう商品のうちのひとつとして、男性利用者の陳列棚に収まっているのだろうと思った。やりたくないなと思っていた理由が、何となくわかった気がした。
しかし、物事は思いがけずとんとん拍子に進んでいった。せっかく入れたからと時折触っていたマッチングアプリで、気の合いそうな女性と出会い、デートの約束が成立した。落ち着いて感じのよさそうな女性で、趣味も近く、メッセージも気さくで話が弾んだ。画面越しだけのやりとりで最初は実感もなかったが、やりとりを重ねるうちに、幸典の中にも自然と「会ってみたい」という感情が芽生えた。
相手の女性、真紀さんは幸典よりひとつ年上で、大手メーカーに勤めていた。おそらく自分より収入も多いであろう相手に軽く物怖じしたが、真紀さんはそのことをほとんど気にしていなかった。学生時代の話になり、江の島いいよねと盛り上がって、その週末に一緒に出かけることになった。
幸典には女性経験がないという訳ではなかったが、就職以来はからきしだったから、当日はそれなりに緊張していた。最初は会話もぎこちなかったが、真紀さんの気さくさがすぐに空気を和らげた。レンタカーの車内、カーステレオに繋いだスマホから真紀さんが音楽をかけた。幸典のリアクションを見て、彼女は幸典が好むであろう音楽を選出して流してみせた。それは見事な選曲だった。すごい、と幸典が驚くと、彼女は勝ち誇ったように笑った。
水族館に着く頃にはもう、二人はすっかり意気投合していた。あの日観なかったイルカショーも、二人で一緒に楽しんだ。夏の暑さに汗は滲んだが、それも気にならない程度には刺激的なショーだった。
しかし何より、幸典が楽しみにしていたのはシラスだった。シラスが一番楽しみなんです、と幸典が言うと、真紀さんは不思議な人だと言って笑った。シラスの展示がいかに貴重なものか熱弁すればするほど笑い声は大きくなったが、実物を前にすると彼女も静かにその水槽に引き込まれた。
「ここのシラスは、もう何代もこの場所で繁殖をして、脈々と受け継がれてるんです」
「それって、大変なことなんだ?」
「多分、結構大変なんじゃないですかね」
「幸典くんが昔見たシラスたちの、子孫ってことだよね」
そう言われて初めて、子孫……、と幸典は思った。考えたことがなかった。あの頃眺めたシラスたちが成長し、卵を産み、それが孵化し、その稚魚が成魚になって、また卵を産み……、というサイクルが、幸典の頭の中で高速で回転していた。
「うん、多分、何代も後の子孫ですよ」
「それって凄いね。私たち、ぺろっと食べちゃうけど。申し訳なくなってきた」
「ありがたくいただかないと」
真紀さんは水槽に向けて手を合わせ、二人は笑った。帰りに立ち寄った海鮮丼屋で、二人揃ってしらす丼を食べた。帰りの車内でも真紀さんが音楽を流した。行きより幸典の好みの音楽が多くなっていた。
東名から首都高渋谷線を経由して都心環状線へ、それぞれの今日を抱え込んだテールランプたちが次々と流れ込む。目の前に広がる夥しい数の光を見ながら、幸典は少しの寂しさを感じた。デートが終わる寂しさとは、少しだけ違っていた。でも、何かが終わる感触があった。それが良いことなのか悪いことなのか、幸典にはまだ判断はつかなかった。
ひと月が経った。その土日には台風が迫っていた。幸典は食料を買い込み、万が一に備えて湯船に水を張った。お気をつけて、と真紀さんにチャットを送った。そっちもね、と返ってきた。あれからまだ大きな進展はしていなかった。そろそろ交際を申し込みたい、と幸典は思っていた。しかしまだ、行動には移せていない。気づけば最近、そのことばかりを考えていた。少し前の幸典からは考えられないことだった。
幸典はベランダの片づけを始めた。すのこを入れるゴミ袋を片手にベランダで作業をしていると、近くから猫の鳴き声がした。ベランダの外からクロが見ていた。彼が鳴くのは珍しい。そういえば最近、クロの姿を見てもいなかったと、幸典は気がついた。台風がやってきたら、クロはどこでやり過ごすのだろう。どこかの軒下に入り込むのか。そのような場所を、きっとクロは持っている。気をつけてな、と心の中で声をかけ、幸典は部屋に戻った。それから思い直して、窓の隙間を猫一匹分開けておいた。台風の過ぎる一晩くらいなら、誰も咎めやしないだろう。しかし、クロは来なかった。そんなもんだよな、と諦めて、幸典は窓を閉めた。
夜が更ける頃になると雨風も強くなり、ガタガタと不穏な音で窓枠が揺れた。幸典は夕食を終え、昔観た映画を流していたが、いまひとつ集中できなかった。十二時を回り、観るのを止めようかと考えている頃に、唐突に電気が止まった。ちょうどいい頃合いだったのかもしれない。起きる頃には復旧してると良いな、と幸典はベッドに入った。
しかしその日はなかなか寝付くことができなかった。ガタガタと鳴る窓と激しい雨風の音が幸典の意識を揺さぶっていた。それでもようやくうとうとし始めた頃、幸典は夢を見た。出会ったあの日と同じように、クロは室外機の奥でキーキーと鳴いていた。激しい雨風が黒い毛並みに不気味な文様を刻んだ。幸典は手を伸ばす。クロは身をよじって後ずさる。あと少しで手が届く。そのとき、飛ばされてきた植木鉢が勢いよくクロの身体を押し潰し、幸典は跳ね起きた。Tシャツがじっとりと濡れていた。
窓を開けると、雨風が勢いよく部屋へと吹き込む。それでも構わずベランダに出て、室外機の奥を覗いた。クロはいなかった。幸典は一度部屋に戻り、濡れた床もそのままにサンダルをつっかけ、家を飛び出した。
あてなどなかった。見当もつかなかった。クロ、と口から漏れていた。幸典自身、そのことに驚きながら、クロ、クロ、と確かめるように名前を呼んだ。一度も呼んだことのない名前を、一度も聞かせたことのない声で振りまいたって、何の役にも立ちはしない。それでも今、呼ばずにはいられなかった。
何度もクロの名前を呼んだ。そのたびに、一度も呼ばなかった後悔が幸典の心に澱のように降り積もった。クロ、クロ、とあえぐ声を、渦巻く大きな雨粒たちは乱暴にかき消し、幸典ごと巻き取って消し去ろうとするようだった。届くはずのない声を絞り出しながら、幸典は嵐の中を歩き続ける。クロ、クロ、と唇の先で消える名前を、祈るように叫び続ける。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
