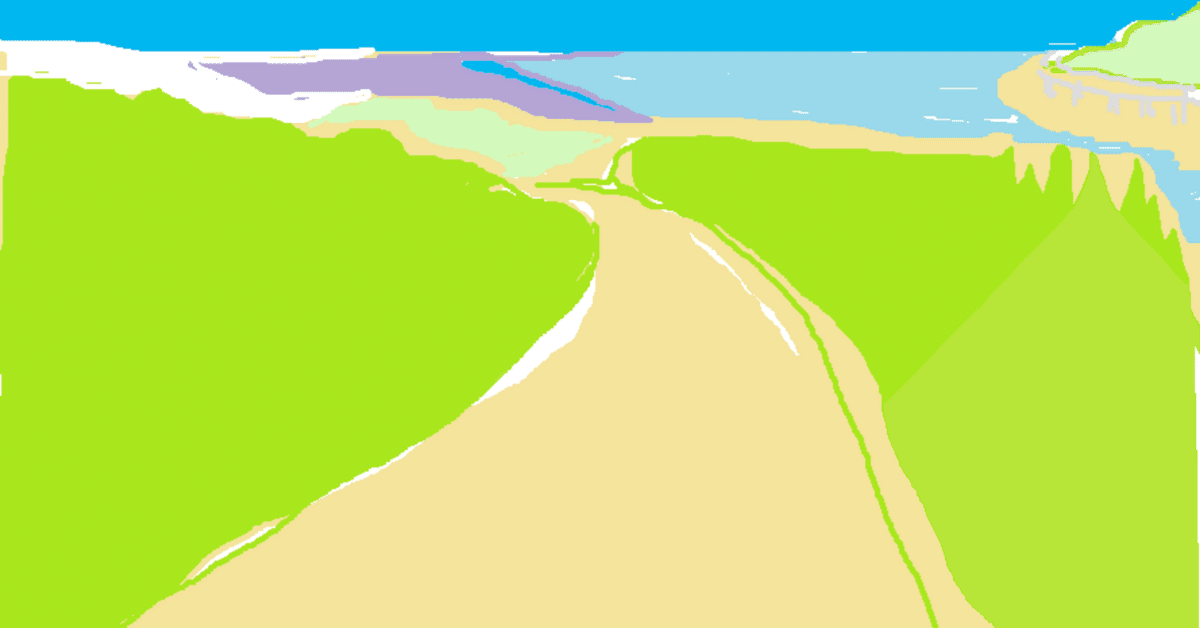
【少年小説】「ぼうくうごうから」②
ゆきおが好きなものに〈隠れ家〉のようなものは少なくなかった。
夏の時季の蚊帳はゆきおを夢中にさせた。近所の子どもたちとの遊びでも、川や山などで年上の子どもたちと基地をつくる遊びが好きであった。
コックピットのような場所をつくるとわくわくした。
テレビ番組で宇宙船の操縦席を見ることがあった。
ゆきおは操縦席が大好きで、簡単な操縦席を木の枝や石などを使ってつくって遊ぶことがあった。
砂地に枝を深く入れてレバーにしていた。
茶摘みの季節がやってきた。
ゆきおの家にも茶畑があった。
そこまで広くはないにせよ、子どもにはかなり広い場所で、この時季は家族や親戚や手伝いの人たち総出で茶摘みをする。
体も大きくなり、ゆきおは茶摘みの手伝いを始めた。
午前中の数時間、祖母に教えられながら茶を摘む。
いちばん小さい籠でもなかなか一杯にはならない。
さすがに飽きてくる。
ある程度〈働いたということが認められるレベル〉で、お役御免となる。
父親とともにお昼ご飯に飲むためのお茶を沸かす作業を手伝う。
小屋の隣の枯れ枝を集めて積み上げてある場所から枯れ枝を持ってくるように言われる。
かまどのように斜面をくりぬいた場所で湯を沸かす。
枯れ枝を積み上げて新聞紙を押し込んでマッチで火をつける。
茶畑の周りから、枯れ枝を集めるように言われて辺りを歩きながら集めてきた。
それを父に渡すと、使えそうな枝をとって、火のなかに押し込んでいく。
ゆきおがもってきた枯れ枝は細いものばかりで、父は時折枝をさらに短く折りながら火に投げ込む。
数十分たつ頃に湯が沸く。
そのなかに父は我が家でいちばん古いお茶っぱをかなりの量をヤカンに入れた。
父が湯が沸いたことを祖母に告げると、茶摘みの作業が中断され、小屋に向かってみんなが集まってくる。
父は木にかけていたヤカンを下ろすと、小屋のなかに持っていった。
祖母を中心に小屋のなかは食事の準備が行われる。むしろを敷いて、皆が持参した弁当が広げられる。
父は焼き魚をアルミホイルにくるんだものを、灰の中に埋めるようにして入れた。
しばらくすると、それは極上のあつあつの焼き魚に仕上がっていた。
家族6人に近所の人たちの総勢10人が、狭い小屋のむしろの上で食事をとるのだ、全員が小屋の中には入れないので、近所の人たちから食事が始まる。
ゆきおは普段とは違う食事の時間に興奮を覚えていた。
自宅から持参した客用の大きめの湯飲みに熱いお茶がつがれる。
自分が沸かしたお茶でもあったせいだろうか、
どんなお茶なのか興味がわいたせいか、すぐに手を出していた。
のどが渇いていたせいか、すぐにお茶に口をつけた。
飲めないくらいの熱いお茶は、緑茶だったはずが、濃い茶色になっていた。
ふーふーと言いながら、さましながら…ゆっくり少しずつ飲むと、
意外に「うまい」と感じた。
小屋の中で…たくさんの弁当箱が開く。
どきどきが止まらなかった。
