
そもそも品質工学f 制御因子と誤差因子(11)
感覚量である持ちやすさ。
それをどうやって評価するのか?
どうやって実験をするのか?










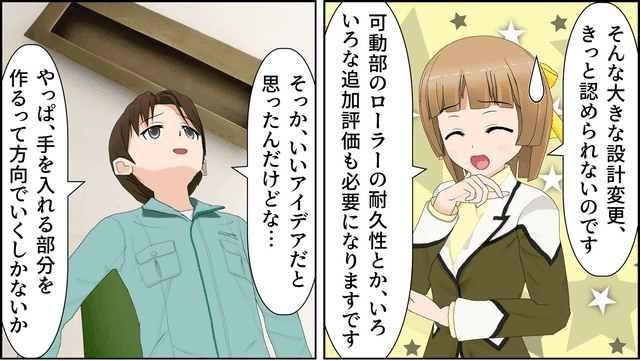



















人の感覚値ってのは、やりたくないんですよね。
とってもばらつくから。
だいたい、同じ人間はこの世に2人といないし、使用者自体もばらついている。それに合わせるとするなら、一品一様にしないといけない。
それを実現したのが、一蘭。
そう、あの豚骨ラーメンの一蘭です。
ある日、常連のお客様がラーメンを注文し「美味しい」と言って帰っていきました。翌日同じお客様がご来店し、大将不在で吉冨が一人で切り盛りしている事に気づかれました。ラーメンを注文され、食べ終わると「君の味はまだまだだな」とおっしゃいました。また翌日、同じお客様がご来店。ラーメンを注文したので「大将がつくりました」と偽りお出しすると、「やっぱ大将のラーメンは美味しいね。」とおっしゃいました。3日間すべてのラーメンは吉冨が作ったものですが、お客様の美味しさの感じ方は異なっていました。その時「人は誰が作ったかによって味の感じ方が変わる」という事に吉冨は気づきました。
(中略)
<オーダー用紙>
7項目それぞれから好みをお選びいただくことで、お客様こだわりの一杯をご提供いたします。食通のお客様の微妙な味覚の違いにお応えできるシステムです。
実際に食べたことがありますが、正直初めてだったので、標準条件でのオーダーをしましたw
7項目(因子)あるから、直交表L18の実験ですね。
18杯食べて、確認実験をしないと何が自分に最適なのかはわかりませんね。
そもそも、食べる日が違うので、そこは大きな誤差因子…
あ、18杯じゃない!誤差因子入れたら36杯!!
そこ、「信号因子は?」って突っ込まない。
108杯は勘弁してください(^^;
作る側がお客様のオーダーに合わせてチューニングできる。
これは技術開発の鏡ですね。
基礎技術だけ開発しておけばいいってことですから。
ラーメンのトッピングもある意味制御因子かな?
いや、それは追加機能になるのか?
話を戻します…w
ばらつくなら、強制的にばらつきを作ってしまえばいい。
それが誤差因子なんですよね。
偶然にばらつくのを待つのではなく、ばらつきを作る。
これも効率的に実験をするためのアイディアなのかもしれませんね。
続きが気になる人はこちら!
…おや?サムネイルは桂先生、なんか嫌な予感が!?
↓ ↓
いただいたサポートは、有益な情報を提供し続けるための活動にあてていきたいと思います!
