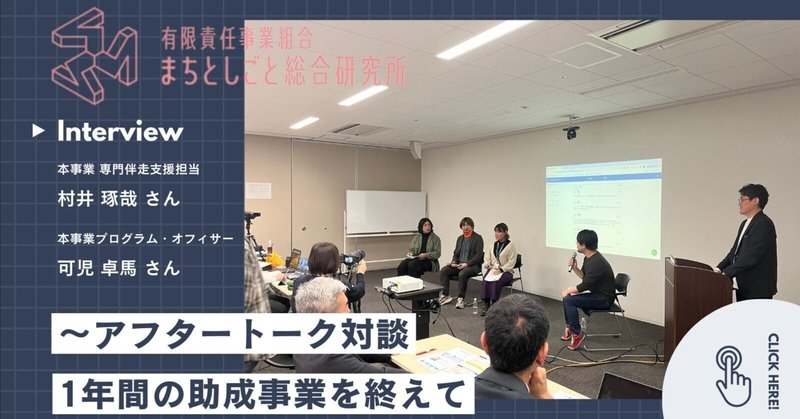
【アフタートーク】1年間の助成事業を終えて_物件・居住からはじまる vol.03
まちとしごと総合研究所(以下当研究所)は2023年度、休眠預金を活用し、「京都の若者へ寄り添うアプローチによる生きる基盤支援事業」を実施し、事業資金の助成ならびに団体への伴走支援を実施しました。
2月末で各団体の事業が完了を迎え、今回の助成事業において、事業担当の三木に伴走してくださった村井さん、可児さんとアフタートーク的に対談をさせていただきました。
■村井 琢哉(むらい たくや:NPO法人山科醍醐こどものひろば前理事長)
関西学院大学人間福祉研究科修了、社会福祉士。子ども時代より「山科醍醐こどものひろば(当時は「山科醍醐親と子の劇場」)に参加。たくさんの“人間浴”をしながら育つ。学生時代には、キャンプリーダーや運営スタッフを経験し、常任理事へ。その後、副理事長、事務局長、理事長を歴任。京都府子どもの貧困対策計画検討委員。
■可児 卓馬(かに たくま:公益財団法人京都地域創造基金 専務理事・事務局長)
基金の専務理事・事務局長として、多種多様な社会問題・課題解決に取組む市民活動を活性化するために、地域を支える新しい資金循環の仕組み作りに取組む。基金は公益財団法人として、約8億円の寄付を運用。
ーー休眠預金活用事業を京都というスケールでやってみたことも今回の重要なチャレンジだったと思います。採択団体はすべて京都市内であったことなど、今後は市外に情報を届けることも課題です。京都でのチャレンジを増やすためにはどんなことが求められるでしょうか。
村井:そもそもの部分だけど、休眠預金活用事業は、資金の性格から高いガバナンスやコンプライアンスが求められる。それにしっかりと対応できる団体はまだ多くないのではないかと思う。選考会でもその観点は難しかったのでは?
三木:今回の趣旨に非常にマッチした取り組みであっても、例えば役員構成の問題や、資金管理において管理者と決済者を別の方が担っているかなども選考委員のみなさんは考慮にいれてくださっています。ただ、日頃取り組みを行っているNPO等団体のみなさんは「支援対象者に接する上で気にかけること」などを中心に関心があるので、今回求められていることと開きがあったかもしれません。
可児:基盤に対しては、助成資源を今回も提供しているJANPIAからは、新しく活動支援団体という枠組みができたね。「資金支援の担い手(既存の資金分配団体を含む)」、「民間公益活動を実施する担い手(既存の実行団体を含む)」など、「ソーシャルセクターの担い手の一層の育成」という観点がある。
三木:従来、市民活動支援を掲げてきた各種団体の支援と重なる部分も多いですね。わたしたちも伏見と下京のいきいき市民活動センター(以下、いきセン)の運営を行っていることもあります。いきセンはもう少し裾野の部分を担っている活動が多いですが、活動フェーズをあげたい団体さんの相談があったときに、求められていることは頭に入れておく必要がありますね。
ーー休眠預金には通常枠と緊急枠があり、これをどのように考えるのかは難しいと感じています。なにをもって緊急性と捉えるのかということです。
村井:NPO法人happinessのようなシェルター活動は何十人も受け入れることはできないけど、見据えている課題に対してケアを行う活動もあれば、公益財団法人京都市ユースサービス協会のように2000人近いたくさんの方へ対してリーチしていくような活動もあるよね。野球で例えれば、高い打率を目指す活動や、打席にたくさん立とうとする活動という整理もある。
可児:緊急枠の受け入れ幅はかなり広くもとられられると思うよ。捉えている課題に対して、まだどういう手法が有効なのかかわからないようなケースなどに緊急的に行動していくというニュアンスもある。緊急度と重要度のバランスは確かに、要項だけみると深刻な課題に対して行動しなければならないように見えるかもしれない。そこは資金分配団体からの丁寧な説明が必要だよね。
ーー休眠預金活用事業を終えてこれからを考えると、今回の実行団体さんが取り組んでくださったチャレンジを、どう広げていくかも論点になります。
村井:今回の助成事業に付随する件としては、例えば子ども食堂支援の領域では社会福祉協議会は精力的だと思う。立ち上げ支援やネットワークづくり、寄付の分配情報や助成金情報などが流れ、各区に窓口がしっかりある。福祉領域と切れ目のない連携を考えていくことは、ますます重要だと思う。
可児:今回の採択団体の事業が、他の団体にも広がっていくために必要な要素を、どう分解するかだよね。各事業、リーダーのモチベーションや使命感などのリーダーシップで引っ張るのはもちろんあるけれども。
村井:まずは団体としての活動手数を増やすと、出会う人たちが増える。その課題に対応していくうちに自団体の専門性を高めていく、足りない専門性を補助できる連携先を増やすスタイルをみなさんとっているように思う。自分たちで決め付けて解決しようとしない。それらを作るには、子ども食堂や子どもたちとの野外活動などが基盤や土台作りに効いたりするよね。
可児:活動対象者のための意味もそうだけど、団体の基盤としてもそう。関係性づくりもやみくもに出会っていくのではなく、団体としての戦略性を持てるか、管理ができるかが重要。今回は実行団体への伴走支援の一貫として、事業終了後の寄付戦略のためのシステム導入などもやったけど、これらも土台を耕すことが寄付や支援拡大にとって有効になる点では同じ。
三木:先進的な事例やトレンド感などを見て、そのまま導入しようとしてうまくいかないケースは、子ども食堂の流行り始めにもよく聞く話でした。現在の活動やこれまでの取り組みの延長線上に、新しいチャレンジをどう位置づけるかですね。
ーー居住支援など住まいや居場所に着目した支援は徐々に増えているように感じます。対象者にどれだけ届けられたかが指標の全てだとは思いませんが、届いた数に着目すれば先程の野球の話でいえば、東京などの人口が多いエリアでは打率が低くともたくさんの方に届けることはできるかもしれません。京都のようなエリアではどのようなスタイルになっていくのでしょう。
村井:今回の事業でいけばアウトリーチなどをどんどん展開する団体と、支援力のある団体にどんどんつないでいく。
可児:専門機関にどんどんつないでいけるような構造が各行政区に点在している形ができるといいよね。ネットワークの形成という意味では、今回の事業でまちごと総研が言っていた、民間事業者や専門機関などを交えた若者型の居住支援ネットワークがどう形になるかだよね。
村井:ただそういう全市に展開していくような議論が団体からできるようになっていくには時間がかかる。やはり各団体は目の前の困っている子たちに本当に真剣になっているし、各団体がいう「ネットワーク」という言葉は「今見ている子たちがよくなっていくためのネットワーク」。
可児:政策提言やアドボカシーなどの役割を改めて認識しないといけない。私も各種の委員などに参画しているのは、そういう役割をちゃんと果たしていかなければならないという意識もある。
村井:最終報告シンポジウムに参加してくださったみなさんと、ちゃんと一緒に考えて話せる場づくりから、まちごと総研がしっかりやっていきましょう。
ーー特定テーマや課題の中で、それらを政策や組織を超えた事業化につなげられるような、視野を広げることが必要だなと改めて感じます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
