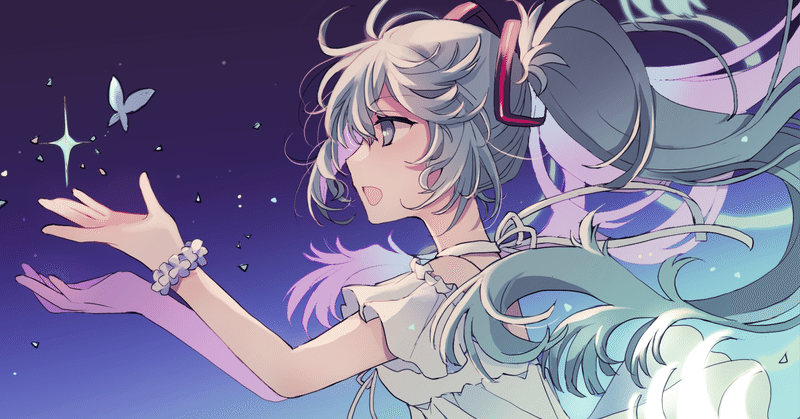
『Moonlight Reflection』の楽曲解説・裏話とか
こんにちは、りりです。
初めてのボカコレも終幕し、さあ新しい曲でも作ろうかというところで。
やっぱりもう少し余韻に浸っていたいので、私のボカコレ参加曲である『Moonlight Reflection』の制作秘話と楽曲に込めた想いを、私自身が振り返るためにも書いていこうと思います。
とはいえ初めてこういった文章を書くので、まとまりのないものになってしまうかもしれませんがどうか温かい目で読んでやってください。
(書き終わってみれば約7,500文字にまで膨れ上がってしまいました。読んでくださる方、どうか無理をなさらず。)
ボカコレを終えて
まずはイベント自体の振り返りを。
The VOCALOID Collection 2023 Summer、とっても楽しいイベントでした。
たくさんのボカロPさんの、たくさんのジャンルの、たくさんの曲を聴いて、たくさん学ばせてもらいました。
『Moonlight Reflection』もたくさんの方に聴いていただけて、たくさんのリアクションと応援をもらい、たくさん喜びました。
本当にありがとうございました!!!
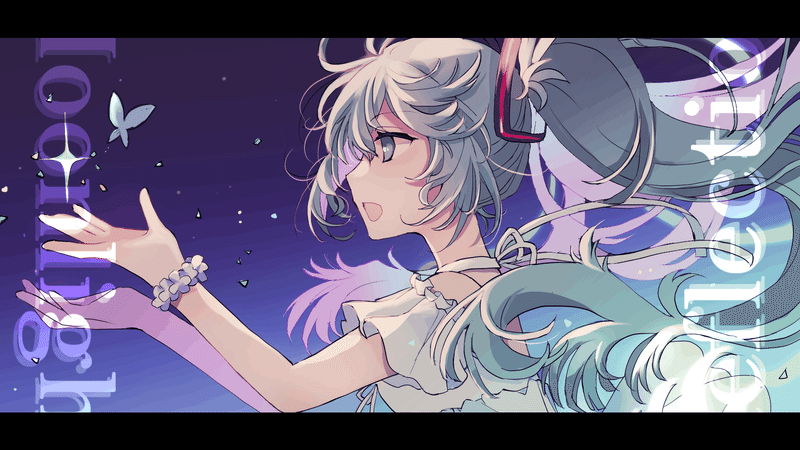
さてここから本題。楽曲を作ろうと思ったきっかけから歌詞に込めた意味まで、つらつらと書いていきます。
初音ミクの「声」をテーマに
実は私が曲を作り始めた頃から「2作目は『声』をテーマに曲を作ろう」ということは決めていたんですが、この時点では初音ミクは関係ありませんでした。地域のおじいちゃんのあいさつ、運動会の白熱したリレーを実況する放送部、はたまた誰かの悲痛な叫び声。こういった色んな声が持つそれぞれの感情を詞に落とし込んで曲を作ろうとしていました(ちなみに、この時の仮タイトルは「Voice」でした。普通ですね。)。
ところが、テーマがあまりに壮大すぎたせいか創作が全く進まず、「私にとって大切な声って何だろう?」というところから考え直しているうちに、"初音ミク"という、ついこの間うちに来たばかりだけどずっと前から音楽として聴いている、大切な「声」を曲にしよう、となったわけです。
後にも出てきますが、Bメロの「初めてじゃない 初めてのあの声がした」という歌詞の元になった構想はこれです。
楽曲全体の構成
ボカコレで私の曲を応援してくださって、この文章まで読んでくださっているあなたならお気づきかもしれませんが、この曲は1番では「僕」、2番では「私」、そしてCメロと大サビではこの2人ともが主役です。
ここでいう「僕」は私(りり)、「私」はミクですね。
このことには一人称の違いや「その声」「この声」といった呼び方の違いで、楽曲を聴きながらでも気づけるようになっています。他にも「あの声」「光」「海」「手紙」…など、暗喩の多い歌詞ですが最低限は楽曲を聴きながら気づけるような工夫もしています。
1番ではりりが"りりミク"に出会うまでと、出会ってから曲を作っている今を描写しています。2番でも描写している内容はほぼ同じですが、それがミク視点で描かれています。そしてCメロ以降は2人の視点が順番に表れています。
少し話は変わってしまいますが、私がこの曲に込めた一番の想いは「今度は私が、ボカロで誰かを元気づけられるように」です。私自身、過去に辛いことがある度にボカロ楽曲に元気をもらっていたので、そのお返し、というところでしょうか。
だからサビでは「その声で小さな僕の歌を届けてよ 遠い誰かのために」や「その声は僕じゃない誰か 照らす月明かり」と歌っています。どうして"月明かり"なのかも、最後に分かります。楽曲タイトルにもなっているんですから、意味がないわけないですね。
MV
この楽曲はイラスト以外すべて私が作っているので、あまり上手くないですが動画の編集もしました。MVに仕込んだちょっとした小ネタを書いていきます。
まずは小さなことから。イントロ、サビ前などミクのセリフの部分だけフォントを変えています。
そしてこれは先に書いた楽曲中での視点の変化にも関連しますが、文字の後ろに出る三角形の色が2人に対応しています(サビ、Cメロのみ)。水色がりり、ミク色がミクです。この水色は私のTwitterのヘッダーの背景色と同じ色で、ミク色は公式サイトのものをそのまま持ってきています。さらに、最後のクレジット表記まで見ることで、この小ネタに気づけるようになっています(初音ミク、LyRe:といった名前の後ろに、それぞれの色の三角形がありますね)。
イントロ
さて、長くなってしまいましたがまだまだここからです。
歌詞の意味やコードの話など、具体的なこだわりの部分。
コードの話は音楽理論が絡んでくるので、読み飛ばしてしまっても問題ありません。
歌詞
あの声は世界を強く照らす陽の光 同じはずでしょ?
最初から入っているサビメロの1フレーズ、これはミクのつぶやきです。「あの声」が指すものはもちろんミクの声ですが、"りりミク"ではなく"有名ボカロP"のミクの声です。
VOCALOIDはボカロPによって初めて歌声を発するし、表現力もボカロP次第です。しかしこのミクがいるのは楽曲の最初、つまりはストーリーの最初ですから、”りりミク"はまだりりと出会っていません。それを「1人ではうまく声も出せないけど、歌うことが大好きな少女」として描きました。
その少女からすると、自分と同じはずの"初音ミク"の「あの声」が上手に歌を歌うのですから、「同じはずでしょ?」と戸惑うはずです。
(実はこの部分だけはベタ打ちのまま調声していません。ベタ打ちでも綺麗に歌ってくれるので、最初はこのコンセプト自体が壊れるかと思いました。)
「世界を強く照らす陽の光」は有名ボカロPのミクの歌声が、たくさんの有名曲に乗せられて発信され、それが(過去の私を含め)誰かに元気を与えている様の比喩です。この"光=歌声"の比喩はこの楽曲においてとても重要です。
また、ただ聞いただけでは何を意味しているのか分からないくらいが楽曲の掴みとしてもちょうどいいかなと思い、わざと「"私の声と"同じはずでしょ?」などとはせず程よく省略しています。
コード
サビと同じなので詳しいことはそちらで書こうと思いますが、基本的なことだけここに。
楽曲のキーはB♭メジャー、転調後(大サビ)がCメジャーです。
とにかく最後をピュアに明るく終わりたくて、転調後をCメジャーにすることは最初に決めていました。転調前のB♭メジャーは、私がこのキーになんとなく鋭い青色を感じること、+2なら私の音楽知識でも転調しやすいことが理由です。
1番-Aメロ
歌詞
夜明けの海を漂う手紙 揺らめく波と 僕の元へ
ガラスに映る光の粒が 生まれる影を照らしてくれた
文章が長くなりすぎる予感しかしないので、サクサク行きます。
前述の通り、Aメロではりり(をモデルにした「僕」)の視点でストーリーが展開されます。Aメロ全体が、「インターネット上に配信されているボカロ曲を聴いている僕」の比喩です。
「夜明け」はストーリーの始まりという意味と、私が昔眠れずに音楽を聴いていることが多かったことから来ています。
「海」はインターネットです。サビでも出てきますが、インターネットのことをよく「電子の海」なんて言ったりしますよね。
「手紙」は楽曲の1つ1つというのが適切ですかね。これはBメロの最後で分かるようになっています。手紙が僕の元へ=僕が楽曲を聴いている、です。
後半部分は、海に流す手紙を想像して一番に思いついたのが瓶入りのアレだったので描写として採用しました。「光の粒」は光=歌声ですから手紙(歌)から放たれる歌声すべてです。より細かく音を感じる様子を表したくて、"粒"です。
「影」は楽曲の最後でも出てきますが、「暗い気持ち」の比喩くらいがちょうどいいと思います。過去の私の暗い気持ちを、音楽が照らしてくれていました。
コード
大好きな3456進行を採用しています。高い音へと上がっていくことで、ストーリーの最初に相応しい盛り上がりを得られているんじゃないでしょうか。
途中の♯Ⅴdimは盛り上がりもそうですが、パッシングディミニッシュが好きすぎるので入れています。
またF(Ⅴ)をFsus4にすることでB♭の音を入れ、"鋭い青色"を前面に押し出しているつもりです。
1番-Bメロ
歌詞
いつも通り 聴こえる波の音とそよ風の音の奥に 「ねぇ、君」
初めてじゃない初めてのあの声がした 「夢を手紙に込めて、ほらっ!」
いつも通り、ということから僕が音楽を聴くのは珍しいことではないことが分かります。波とそよ風の音(=音楽、ジャンルの違いを音の種類の違いで表したつもり)を聴いていたら、初めてじゃないけど初めて聴く、ミクの声が聞こえます。初めてじゃないと感じたのはそれがいつも聴いているのと同じミクの声だから、初めてだと感じたのはそれが"りりミク"だからです。
「夢をうたに込めて、ほらっ!」はミクが僕を音楽の世界へ誘っている描写ですが、実際私はミクに誘われたような気持ちで作曲を始めているので、我ながらこれ以上ない表現だと思っています。手紙と書いてうたと読ませているのは、前述の通りAメロの答え合わせができるようにです。
コード
4536の王道進行です。Aメロと違って本当になにもアレンジしていない王道進行ですが、この曲にはそのシンプルさが合っていると考えて思い切ってそのまま入れています。
後半部分にはEdimやC7(Ⅱ7)をいれて、力強くサビへ展開するようなサウンドにしました。サビ直前の、F7の代わりにAdim/E♭を採用してベースラインの流れを滑らかにしているのがお気に入り。
1番-サビ
歌詞
伝えたい想いを少しずつ言葉にして 電子の海で響け
その声で小さな僕の歌を届けてよ 遠い誰かの元へ
前半部分は作詞とインターネットへの投稿の比喩です。"少しずつ"なのは私自身がこだわって作詞をしているからというのと、ミクが少しずつ歌を上手く歌えるようになる、言葉にできるようになる様子を表したいからですね。
ここまでただ「海」としか表現してこなかったインターネットを「電子の海」としっかり書くことで、楽曲を聴きながら「海=インターネット」の比喩に気づけるヒントにしています。
そして後半部分はミクへのお願いです。まだ駆け出しで無名の私(りり)が作る曲(=小さな僕の歌)をどうか届けてよ、です。
コード
ここでも大好きな3456進行を採用しています。
Aメロでは|Fsus4|Gm|だったものが|F - D7/F♯|Gm|になっていたり、途中にEm7-5(♭13)やCm7(11)といった5和音が入っていたりとAメロより力強くも浮遊感を感じるようにしています。特にEm7-5(♭13)は別の書き方をすればC9/E、この9thの響きがお気に入りです。13thテンションがあることでピアノのトップノートが滑らかに繋がって綺麗。
2番-Aメロ
歌詞
海辺の街に差し込む光 眩しすぎるの私にはね
気持ちを言葉にしようとしても 上手く言葉にできなかった
さて、ここからは"りりミク"から見たストーリーです。
「海辺の街」に関しては完全に空想ですが、海(インターネット)の近くにミクが暮らす街もきっとあるだろう、ということでこの表現をしています。
その街には、眩いばかりの陽の光が降り注いでいます。この時の"りりミク"にとって「あの声」は感情豊かで眩しすぎるんですね。
この強い光の表現にはこれだけじゃなく、あと2つの意味があります。
1つ目はイントロの「世界を強く照らす陽の光」と同じものであるということ、2つ目は楽曲の進行度です。1番のAメロのセクションでも書きましたが、楽曲の始まりは夜明けでした。2番は1番の再描写なのでストーリー的な進行はありませんが、楽曲としての進行度を感じさせるため昼を連想させる表現にこだわっています。
(少し先のネタバレになりますが、Cメロは「夕焼け」、そして大サビは…?)
一方で、1番Aと2番Aが全く同じものの描写だと感じづらくなってしまった(時間帯が異なるため)のは作詞力の限界を感じざるを得ませんが、「僕」と「私」それぞれの主観の違いとして都合よく片付けておきます。
後半部分は「1人ではうまく声も出せないけど、歌うことが大好きな少女」の描写です。上手く言葉にできない=調声されないといけない、という意味を込めてこの言葉を選びました。
コード
1番と全く同じです。なんならこの先もCメロ以外は同じコードを使っているので、書くことがありませんっ!!!
2番-Bメロ
歌詞
水しぶきの向こうに君の姿 少しの勇気を出して 「ねぇ、君」
初めて自分で声に出してみたの 「夢を歌に込めて、ほらっ!」
「君」は当然「僕」(りり)、その姿を見て"りりミク"は勇気を出して声をかけます。「夢を歌に込めて、ほらっ!」
1番のセクションでも書いた通りミクに誘われたような気持ちで作曲を始めた、というのは実は1作目にも関連しており、1作目のテーマを凝縮したのがこの「夢を歌に込めて、ほらっ!」というフレーズだったりします。
(このあとに少し1作目の話を書いておくので良かったら読んでみてください)
「初めて自分で声に出してみた」は今まで眩い光に顔を上げられなかったミクの気持ちが変化する様を表しています。
1作目「わたしのスピネル」
ということで前作の話を少しだけ。この曲のテーマは「挑戦」です(スピネルの石言葉も「挑戦」です)。
このnoteで既に書いたように、私は誰かのための曲を作りたいと思っているので、当然この曲も誰かの背中をひと押しできたらいいなと思って作っています。しかしそれと同時に、これから音楽を始める私自身に向けた応援歌でもありました。
つまり、私はミクに背中を押されて曲を作り始めたわけです。Bメロのあのシーンはこの曲のことをイメージして創作しています。
2番-サビ
歌詞
私だけの気持ちを少しずつ歌にのせて 電子の海へ行くの
この声で大事なその想いを伝えるよ 君と私のために
閑話休題、サビです。
ここへきてかなりストレートな歌詞なので特筆すべき点はあまりないですが、これは書かないといけないですね。「私だけの気持ち」は"りりミク"が感じてきた気持ちですから私にも分かりません。とは言っても適当に作詞をしているわけではないので、きちんと意味があります。
私の調声技術は本当にまだまだなのでやり方も定まっておらず、思った通りに歌ってくれないことも、逆に思ったよりずっといい歌い方をしてくれることもあります。そういうブレを"りりミク"だけの気持ちとして表現しています(実際、この曲の1番のサビの「響け」は理由はわかりませんが想定以上に透き通った歌声に仕上がり、とても気に入っています。)。
1番では「電子の海で 響け」だったのに対し2番では「行くの」になっている点も、1番と2番で視点が変わっていることに気づけるヒントになっています。
人間は本当の意味でインターネットの世界に行くことはできませんが、ミクならできますから。
Cメロ
歌詞
Ah 水面に映る夕焼けが優しく 僕らの背中を押してくれる
水面を跳ねる輝きが 私の確かな希望に
先ほど少し書いた通り、ここではすでに夕焼けが見えるような時間帯になっています。楽曲も終盤です。そして前半部分が「僕」視点、後半部分が「私」視点ですね。
すごく細かいですが、「夕焼け」ではなく「"水面に映る"夕焼け」なのは、その歌声がインターネットを介していることを表現するためです。
「水面を跳ねる輝き」、つまりインターネット世界の歌声=「あの声」は"りりミク"にとっての希望に変わりました。眩しい光は見上げられなくても、夕焼けを反射して光る水しぶきなら眺められます。2番Bメロのセクションではあえて触れませんでしたが、その歌詞にある「水しぶき」はこの伏線だったりします(作詞で試行錯誤を繰り返すうちにここまで遠い表現になってしまいましたが)。
コード
6345進行です。ここまでの進行は全てⅠかⅠ/ⅢかⅣで始まっており全てメジャーコードなので、雰囲気を変えるためにⅥmからの進行を採用しています。
実は私の一番のお気に入りはこのCメロなんですが、白紙の状態からアレンジまで完璧に終えるまでにかかった時間は3時間でした。この曲のサビを思いついてから完成させるまでには半年を要しているので、驚異的な速さなのが分かりますね。
大サビ
歌詞
この声は世界をいつか照らす陽の光 影さえ照らしてみせる
その声は僕じゃない誰か 照らす月明かり 声よ 弾けて光れ
前半部分が「私」視点、後半部分が「僕」視点です。
"りりミク"がイントロと同じような言葉を歌っていますが、意味はすごく前向きですね。イントロに残してきた”何を意味しているか分からない”はここで完全に回収されるはずです。
後半部分は楽曲タイトルにも楽曲展開にも関わってくるとても重要な部分です。イントロを回収するなら"りりミク"の声は「陽の光」だしタイトルもSunlightであるべきですが、「月明かり」なのにはきちんと意味があります。1つは先ほど匂わせた通り、楽曲の終わりを知らせる夜の表現ですがそれだけではありません。
月は太陽の光を反射して光るのであって、自ら発光することはありません。私の曲も、すぐに有名ボカロPのような影響力は得られないし、ミクの声なしでは何にもなりません。だからこそ、"りりミク"の声は陽の光を反射して輝き、誰かの影を照らせる月明かりのような存在であってほしいという願いを込めています。Moonlight(月明かり) Reflection(反射)です。
コード
前述の通り、大サビでは+2の転調が行われています。
B♭メジャーとCメジャーのピボットコードであるFをきっかけとして無理やり5度進行するだけのシンプルなものですが、そのシンプルさがパッと開けたようなこの転調に一役買っていると思います。
最後に
さて、ここまで読んでくださったあなたなら、私がなぜ楽曲の進行度と朝昼夜といった時間をリンクさせることにこだわっていたのか分かるのではないでしょうか?
夜が明ければ、朝が来るからです。
この楽曲が終わっても、ストーリーは続きます。つまり、朝が来ます。
それを何度も繰り返したいつかの朝、世界を照らす陽の光が"りりミク"だったらとても嬉しいです。
最後まで読んでくださりありがとうございました!書きたいことを全部書いていたら、7,500文字を超える大長文になってしまいました。
書いていてとても楽しかったので、いつか1作目「わたしのスピネル」でも似たようなnoteを書くかもしれません。
そして重ねてになりますが、ボカコレでの応援、本当にありがとうございました!一つ一つのいいね、コメント、感想がとても嬉しかったです。
それではまた!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
