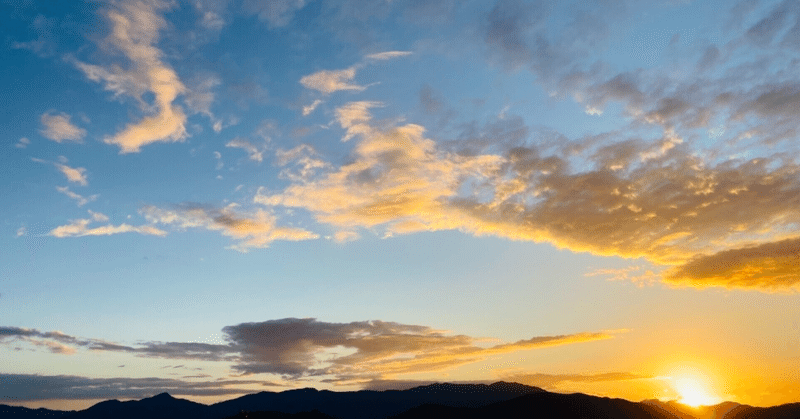
読書メモ『監査役の覚悟』
■手に取ったきっかけ
時折見ている監査役向けのメルマガで、「新任監査役におススメの本」として取り上げられていたので。
■本の概要
2007年ジャスダック上場のIT関連事業を営むトライアイズ社の常勤監査役となった古川孝宏氏の「物言う監査役」としての戦い・裁判の記録。
第1部 実際の案件をモチーフにした監査役の就任から監査妨害・株主総会での解任劇、訴訟から和解までのストーリー
第2部 他の監査役経験者、弁護士、メディアから見たコーポレートガバナンスに対する現状の課題や方向性についての見解
第3部 トライアイズ社案件の当事者であった古川氏へのインタビュー
「監査役としてどうあるべきか」を現行の会社法のたてつけの限界や矛盾を踏まえつつ、「それでもあなたは監査役としてコーポレートガバナンスの一翼を担う覚悟がありますか?」と投げかけている。
■本の感想
恥ずかしながら、トライアイズ社の案件については初耳だった。
取締役会での買収案件事項等に対する経営陣からの説明不足、社内書類や会計監査人へのアクセス妨害、内部統制構築に向けた提言への真っ向からの拒否などといった経営陣(特にオーナー社長)のガバナンス欠如に対して、指摘・提言を続けていた常勤監査役。それが社長にとって煩わしい存在として解任され、それに対する訴訟まで、どんなことが起き、それぞれの関係者がどう行動したかを生々しく語られている。
①なぜそんな会社の監査役になったのか?
本でも述べられているが、「そもそもそんなコンプラ意識の低い会社の監査役就任は避ける(もしくはさっさと辞任する)べき」というのが、自分を守るということであれば「賢い選択」なんだろうと思う。
たとえ、会社の業績が悪くても、組織体制が未整備でも、社長以下会社全体が「社会の役に立つ会社にしよう!」と前向きに一丸となって頑張っている会社で、「そのためにも耳の痛い提言でもどんどん言ってきてほしい」と考えている社長であれば、多少の苦労があっても私が役に立てることがあれば頑張ろう!って思えるけど、社長が「余計なことはしてくれるな・言ってくれるな・黙って監査報告書にサインしとけばよい」というスタンスの会社に自分の大事な人生の一部を捧げたくはないと思うものだ。
古川氏は、監査役就任前に経理部長として入社しており、前任の常勤監査役が社長ともめて辞任している経緯は知ったうえで承諾している。社内からの期待や「自分がやらなければ誰がやる」といった気概から就任を決意されたとあるが、私だったら、それを天命として受け入れるだろうか…
②監査妨害に直面したら
古川氏は、取締役会での買収決議に際して、ろくな資料が添付されなかったり説明も拒否されたり、あげくには取締役会の40分前に開催通知がメールで送られるなど、取締役会での適正な議論・決議がなされない状態に直面する。また、社内資料を見せてもらえない、会計監査人との面談についても「余計なことはするな」と恫喝されるなど、監査役監査としての活動を制限される状態に陥いる。
会社として不正が行われていないか、株主や会社の利益ではなく自己の利益を優先するような意思決定がされていないかを『監督する』立場であるにも関わらず、監督するための材料が入手できないという状況。
社長に直訴しても恫喝されるだけ、質問状という形で出しても体のいい回答しかこないといった状況で、最後の手段は、監査役監査報告書に「不適正意見」または「意見不表明」を提示することだが、これはかなりハードルが高い手段となる。
まず、上場会社でそのような監査役報告がなされた場合には、証券取引所で上場廃止すべき会社かどうかの検討がされることになり、また、「そんなごたごたが生じている会社」として株価の下落を招くことにもなる(実際そんなごたごたが起きてる会社なんだけど)。そうなると、「お前がそんな報告をして会社をつぶす気か、従業員の雇用を守れるのか」と詰められることになる。明確な不正が行われていることが確信できているとかならともかく、「監査妨害のため不正等が行われているかどうかが分からない」ということでそこまでできるかというと現実的にはかなり難しい。
従って、「不適正意見(又は意見不表明)」を出すのは核兵器と同じで、あっても使うことは想定されない武器なのだ。
現実的には、核兵器をちらつかせながら、「そんなことにならないように監査に協力してくれ」と説得を続けるくらいか。また、他の社外取締役や監査役を味方につけて、独りでは無理でも「監査役会として」「取締役会として」の意見であれば、聞かざる負えないという状況に持っていくこともできるかもしれない。
この案件では、当初、古川氏と同じく社長に憤慨していた他の非常勤監査役が、社長の恫喝により会社側に転じ、「適正意見」の監査役報告を提出することになる(監査役会として監査役の多数決で監査報告を出すことになるため)。
③監査役解任議案・費用請求の訴訟、和解
古川氏は、定時株主総会にて、計算書類が取締役会の承認を経ていないこと、監査役報告に(古川氏の)個別付記事項を記載せずに添付したこと、任務懈怠として監査役の解任議案を提出されたことに対して、決議取り消しの訴訟、並びに当該訴訟にかかる費用請求の支払いを裁判所に訴えた。
結果的には、定時株主総会の7か月後の臨時株主総会にて古川氏の解任決議が承認されたことをもって、古川氏が監査役でなくなる=他の決議取り消しを訴える権利が消滅したとして、決議取り消しは否認され、訴訟費用の請求は弁護士の説得もあり和解に終わる。この「監査役でなくなった時点で権利が消滅する」というのは法の盲点であることが分かる。
また、このような訴訟を起こして裁判に持ち込むというのは、弁護士の適切なサポートと本人の膨大な時間的・精神的労力が不可欠となってくる。この案件でも、当初依頼した弁護士事務所とのいざこざも書かれていたりと、大変な苦労があったことがしのばれる。
本では、弁護を依頼する際の選定ポイントについても書かれていたが、そもそも日常の中で弁護士を依頼するというシチュエーションがほとんどない中で、かつ社内の顧問弁護士も経営層サイドのため協力を得られない中、自分だったら途方にくれてしまうだろうなと。
監査役協会の中にも、個別相談窓口として弁護士が対応してくれるとのことだが、訴訟で弁護してくれるわけではないので、どういうつてでどうやって適切な弁護士を探し出せばいいのか。めったに起きないことではあるけど、おきたら瞬時の対応が求められる、そんな有事への対応は、とにかくこういう事例を良く知っておいて、その際に相談できる箇所(知り合いでも公的窓口でも)をいくつか押さえておくことくらいか。
③監査役の覚悟とは
監査役就任にあたり、監査役って何のために何をやるの?という心構えや実務的な対応などは、いくつかの著作やセミナーを受けたりして何となくわかったつもりでいたけど、こういう具体的な事例をバンとつきつけられて、「あなたならどうしますか?ここまでできますか?」と問われると、正直うーん…と思ってしまう自分がいる。
もちろん、問題に目をつぶって監査報告書にサインするような人間ではないと思っているが、簡単に辞任せずに会社(社長)と戦えるかというとそこまでの自信はない。
ここまで極端な事例は、プライム上場クラスの会社では少ないと思うけど、IPO準備会社やグロースなどの上場したての会社であればあるあるだという話は周りからもよく聞く。そういう会社を選ばない(もしくはさっさと辞任する)のが「賢い」やり方だと思うが、それでいいのかという思いもある。
それに、品質不正問題など、何か問題が生じたときに、監査役としてどこまで経営陣に適切な対応を迫れるかといった点では、大なり小なりどんな優良企業でも生じることではある。
「逃げずに問題に向き合う」って言うは易しだけども、具体的にどこまでどうすべきかはとっても難しいこと。今できることは、「そもそも何のために監査役になったのか」「お天道様に顔向けできる行動・言動とは何か」の原点を常に腹の底に持っておくこと、独りで悩まずに信頼して相談できる場所を確保しておくことかなと、改めて感じた本でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
