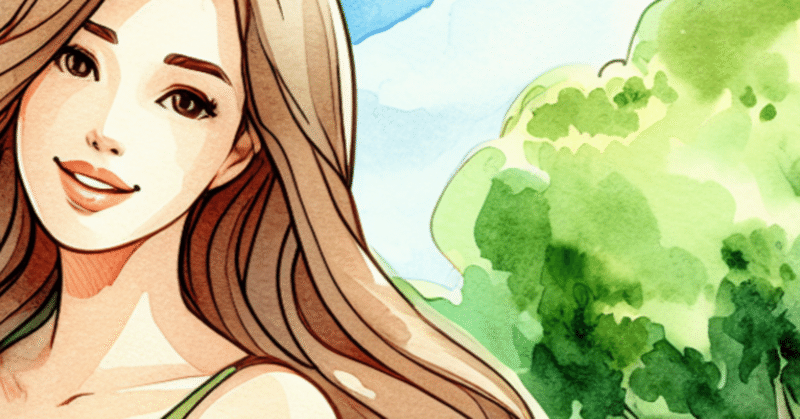
変わらずにいてください
「床屋」は僕の中では、ひらがなの「とこや」である。特定の意味などなく、髪を切る人のお店=とこやだ。
これが「八百屋」だと、漢字の意味からなんとなく類推ができる。
「八百万の神」と言うように、もともと「八百」とはきわめて数が多いことを意味する。 多くの野菜を売っていたことから、「八百屋」の文字があてられたんだろう。
いま調べてみると、江戸時代に八百屋は「青物屋」と呼ばれていた。「青物」とは野菜の総称で、だから青物屋は「野菜や果物を売る店」になる。
これが「青屋」と略されて、いつしか「あおや」が「やおや」と呼ばれるようになったという説があるそうだ。なるほどね。
床屋の起源は、江戸時代といわれる。この当時は「髪結い」と呼ばれていた。
さらにこの「髪結い」の歴史となると、室町後期までさかのぼる。
月代(前頭部から頭頂部にかけて頭髪を剃りあげた部分)が広まり、一銭程度の料金で髪を結い月代を剃った「一銭剃」が起源となる。
江戸の庶民は召使のいる武士などと立場が違い、自分一人では月代を剃ることができない。そこで髪結いという商売が生まれた。
髪結いは町や村単位でのお抱えとなり、床と呼ばれる店で商売を行ったことから、床屋と呼ばれるようになる。
ちなみに女性の髪を手がける女髪結いは、遊廓や顧客の家を個別訪問していたため、自分の店は持たなかったらしい。
板や竹を組んで簡易な床を張っただけの仮設の店、折り畳み式の移動できる屋台 のようなところで、髪結いは生業をたてていた。
商品を売るだけで人の住まない簡単な仮設の店の総称は、「床店」となる。
床店には、かんざしや化粧品などを置く小間物屋や古本屋、薪商売、占方など様々な業種があった。
江戸に限っては床店の髪結いが多かったため、「髪結い床」と呼ばれるようになる。
それに職業を表す「屋」が付いて、床屋となったそうだ。
由来を知ればなるほど、「とこや」は「床屋」としてよく理解できる。ここ数10年に生まれたカタカナの業界などと、歴史の重みがまるで違うことも分かった。
ところが由緒正しいこの「床屋」の呼称を、使わなくする風潮があるというから腹立たしい。
「床屋」に限らず、日々現金収入がある(日銭が入る)職業(主として小売業やサービス業)の多くは、八百屋・魚屋・風呂屋・床屋などのように、接尾語として「屋」が付く。
その多くが、特定の日に金銭の授受が行なわれる商慣習を持つ商いでなかったことから、軽蔑を込めて用いられていたという。
そのため大手メディアでは、放送禁止用語とまでいかないまでも、各局の判断により自主規制の形をとっているらしい。
「床屋」に限れば、「床」という言葉が性的な意味合いを持つとの解釈も、そこに加味されてくるんだとか。
バカらしい。オレは今後も、「とこや」でいくよ。
それはその通りなのだが、こういう問題は後から響いてくる。
実際、僕ら世代がいくら「とこや」を常用し続けても、続く世代で使わなくなれば、その言葉は絶えてしまう。大げさなようだが、それは一つの文化が消えてしまうに等しいことだと思う。
言葉の自主規制と共に、「とこや」の形態もすっかり変容した。むかしなら客との対話がサービスの一環で、床屋さんに行くと世間の様々な情報を入手することができた。
僕の母親など、行きつけの店主を「あの人は口が軽いから」とそれこそ軽口をたたいていたが、来店する客からの情報を他の客に伝えることで、世間の動きを広めてくれた側面は否定できない。
それが今では、会話しないことの方がサービスになっているようだ。
おまいう案件で、安くてカットのみの店にしか行かない僕が言っても説得力はゼロだが、
こんな私のわがまま聞いてくれるなら
とこやは とこやのままで
変わらずにいてください そのままで
あと、「八百屋」も「魚屋」も、「お主も悪よのぉ」の「越後屋」も。
イラスト hanami🛸|ω・)و
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
