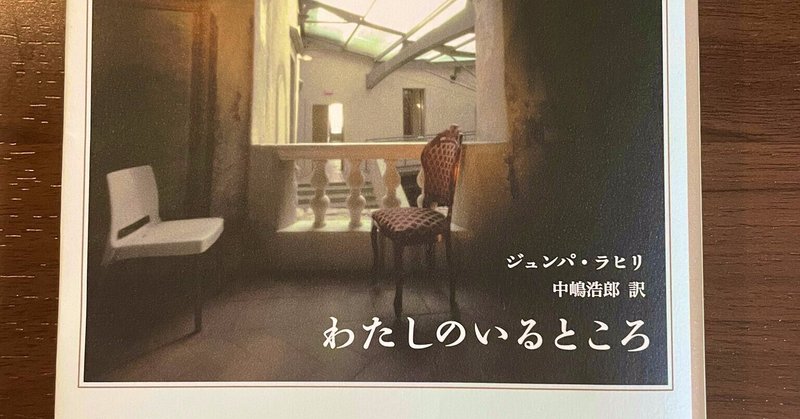
【読了】わたしのいるところ/ジュンパ・ラヒリ 著
確かにわたしは一人暮らしで、友だちも趣味も多くはない。
友だちはたいてい結婚して子育てに忙しい時期だし、そういう間の時間を縫っていろいろ工面して会おうとしていた時期もあったけれど、まあ、そういうのは無理しなくていいか、と今は思う。だから今は誰にも会っていない。
だから嫌いになったとか、どうでもいいとか、そういうことでもなくて。もちろんね。お互いにお互いがその時間、生きていればそれでいいのだと思う。
今は生きている世界軸が違うから、なかなか分かり合えないこともあって、それでももしかしたらまた交わり合うことがあるかもしれないし、ないかもしれない。来月かもしれないし、三十年後かもしれない。
この先のことは分からないけれど、唯一分かっているのは、わたしにとって彼女たちはかつてとても大切だった人だという事実で、現在の関係性が過去をまで歪ませるなんていうことはない。だから、これはこれでいいことなのだと思う。
わたしは、できることならば、なるべく静かに暮らしていたい。
でもそれは「丁寧な生活」と呼べるような立派なものではない。よくSNSで見かけるような、器にこだわるような食生活とか、身体に優しい手作りおやつなどとは程遠い生活を送っている。自分はなんて怠慢なんだろう…と反省する。本当はもっとそんなふうでありたいんだけれど。でもまあ、できないので。
わたしには仕事があって、働くことのできる体や心がある。
行きたいところへ行かれる足があって、問題を解決するための思考力がある。多くはないけれどお金もある。これ以上の幸せなど、どこを探しても見つからない。
それで、だからわたしは、自分の生活や人生をこの上なく豊かで、色彩に満ち満ちたものだと感じる。
十年前も今日も、わたしはほとんど同じ仕事をしている。同じような時間に起き、食事をし、仕事をしたり家事をしたりする。変わらない。
そしてその変わらなさの中にも、必ず色彩はあるのだ。いつだって。
孤独であること、ひとりで暮らすこと。心細いこと、寄る辺のないこと、不安、焦燥、憎しみ。それらすべてをふくめて、それはわたしの人生をかたちづくる大切なものものなのだと感じる。
ひとりで生きるということは、彩りがないことと同じではない。決してそうではない。わたしはわたしの生活の静謐さの中にしかない彩りを誇らしく思う、愛おしく思う。
「わたしのいるところで」/著:ジュンパ・ラヒリ(訳:中嶋浩郎)
本作は「長篇小説」となっているけれど、ひとりの「わたし」という女性の様々な視点から見た「掌篇小説」のようでもあり、だけれどもそのひとつひとつのコマはやはりどれか一つが欠けても成立しない。
「歩道で」「仕事場で」「プールで」「バールで」「母の家で」「自分の中で」「文房具店で」・・・46篇に分かれたそれらの小さくて短くて、どこかそっけなくて、繊細で神経質で意志が強くて、偏屈さすら感じるような、だけど確かに彼女をすべてかたちづくるものであるこれらの場所たちと、そこで彼女が見たもの。
主人公である「わたし」は、それぞれの場所で、それぞれいろいろなことを感じたり、考えたりする。それはほとんど起伏のないように見えるような、ありふれたなだらかな感情でいて、誰の心にも必ず存在するとても普遍的な、小さな小さなささくれや漣のことが素晴らしく内観され、描写されている。
たとえばこんな話がある。
友だち夫婦の娘、十六歳の美しい娘。これからなんだってどんなことだってできるように見える輝かしくて天真爛漫で綺麗で瑞々しくて眩しいような娘を、ほんの少しの嫉妬まじりの憧憬の瞳で見つめる彼女。ただ真面目一辺倒だっただけの地味な青春時代の自分を重ねて、そして年を取った自分を重ねて彼女を見つめる。すると娘は彼女にこう言った。
「お義母さんのことが我慢できないから。あの人には自分というものがないし、自分の声もないの。ママも同じだった。だからパパに捨てられたのよ。そんなタイプはもう時代遅れ。わたしはあなたみたいに強くて独立した女になりたいの。」—— P.23「広場で」
たとえば、演劇のチケットを予約する。少しだけ未来のその日、その時間、どんな服を着て、どんな気持ちでいるだろうかと想像する。
たとえば、ネイルサロンで、結婚をしている前提で話が進んでしまう。結婚はしていないと伝えた時の、ほんの少しだけ悪意の混ざったネイリストの微笑と、相対する彼女のプレーンなピンク色の爪。
たとえば、好きな相手が自分の友だちの夫だとしたら。
わたしたちは罪のないつかのまの情愛を味わう。これでは前へ進めないし、追い風もけっして受けられない。彼は清廉な男性で、わたしの友だちと子どもたちを愛している。—— P.10「道で」
だけどそれは、どうにもならないような燃え上がるような感情ではなくて、静かで誰にもどこにも漏らすことのない、自分の中だけの気持ち。スーパーで買い物をしすぎて荷物を乗せて車で送ってもらうという申し出を断ることのできる分別だってある。
たとえば、動物の死骸をみてしまったとき。死骸はもう死んでいて何かをしてくるはずがないのに、いつまでもそれに引きずられる。それに、自分が処理をしない限りそれはそこからいなくなることは絶対にない。
たとえば、つまらないホームパーティーで受けた些細な苛立ち。変に意地を張ってしまって空気を壊してしまった罪悪感。
たとえば、友だちの夫の感じが悪かったこと。大切な本をぞんざいに扱われたこと。そしてその子どもに汚された大切なソファの傷のこと。そしてそれらすべてに気がついていて、彼らは何も伝えてくれなかったこと。
たとえば、友だち一家の不在中に家の留守を任された日のこと。
いくつかのブラインドを下ろし、ガス栓を閉め、ベッドにカバーをかける。ゴミ袋を閉じる。これこそが二人の人間が愛し合って二人の子どもをつくるという平凡でありながら唯一無二の道筋をたどってきた家族のプライベートな形態なのだ。わたしは家族がいかに巧妙な有機体であり、他人を寄せつけない集合体であるかを一瞬のうちに理解する。——P.130「彼の家で」
目の前を通り過ぎていく当たり前の景色を、どうしても受け流せないことがある。心の中にしこりのように残るもの、心の奥底に澱のように沈んでゆくもの。そういうものを彼女の目は見過ごさない。
彼女の目を通して、わたしは、わたしの中にも確かに存在したそういうものの存在を改めて認識し直す。そしてそれらはいつしか、わたしの中にある「孤独」を肯定し、赦し、前へ進むことを導いてくれるように思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
