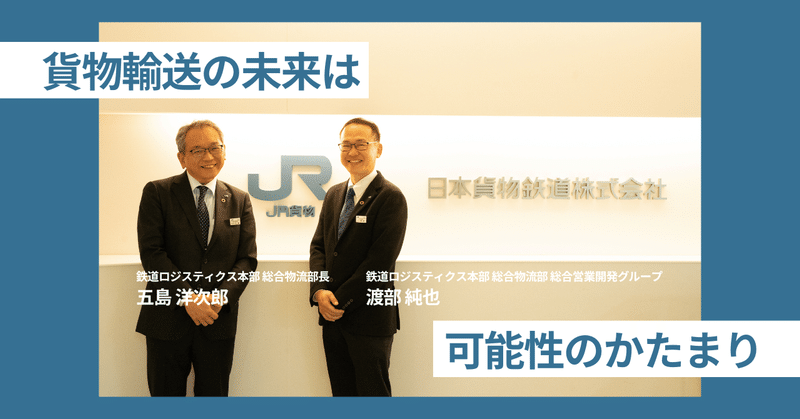
貨物輸送の未来は、可能性のかたまり #03【JR貨物 日本貨物鉄道株式会社】
ロジ人では物流テックと分類される業界の著名人、サービスにフォーカスしていきます。前回に引き続きJR貨物 日本貨物鉄道株式会社で鉄道ロジスティクス本部 総合物流部長を務める五島 洋次郎さんと、総合営業開発グループの渡部 純也さんにインタビューしました。#03では、「いま貨物輸送の舞台で求められる人材」についてお話いただきました。
<プロフィール>

▼ 鉄道ロジスティクス本部 総合物流部長 五島 洋次郎氏
1967年生まれ。1991年に日本貨物鉄道株式会社(JR貨物)入社。1999年に現・公益社団法人全国通運連盟へ出向。2004年にJR貨物本社の営業部グループリーダー、2006年に東北支社次長などを経て、2021年に総合物流部長に就任。

▼ 鉄道ロジスティクス本部 総合物流部 総合営業開発グループ 渡部 純也氏
1979年生まれ。人材サービス会社での勤務を経て2015年に日本貨物鉄道株式会社(JR貨物)入社。2020年に日本フレートライナーへ出向。2023年より総合物流部営業開発グループサブリーダーとして勤務。
物流の明るい未来のためにできること
― 30年以上、JR貨物で貨物輸送に携わってこられた五島さんは、長らく不安視されていた「2024年問題」を迎えて、いま何を思いますか。
五島さん:物流の「2024年問題」について改めて振り返ってみた時、この機会はやはり物流業界に携わる当事者、つまり私たちのような関係者が変革するターニングポイントになるのではないかと考えました。これまでは荷主側の立場が非常に強く、プレイヤーである数多の物流事業者の中で過当競争が起こっていました。「トラック業者なんていくらでもある」という風潮の中で仕事を請け負うため、さらに下へ下へと落ち込んでいった物流事業者との関係が、「2024年問題」をきっかけにこの先は変わっていくことと思います。荷主側も物流事業者側も対等にコミュニケーションをとり、持続的な関係を築いていくような時代にしなくてはならないと考えています。
― 渡部さんは、この先貨物輸送はどう変わっていくとお考えですか。
渡部さん:トラックの自動運転化などの話題も出ている中で、どう変わっていくのかは正直言ってまったく分かりません。ただひとつ言えることは、モノは作っただけでは消費できず、必ず運ばなくていけないということ。これから先は、運ぶための手段に何を使うかをしっかりと考え、選んでいく時代になると思います。従来、トラック、海運、航空といくつもある選択肢の中で「鉄道」は選ばれにくいものでしたが、これからは鉄道輸送も当たり前に使ってもらえるような時代になると思っています。
― これまで鉄道が選ばれにくかった要因は、何だと思われますか。
渡部さん:それは、私たちが貨物輸送の使い方をうまくお伝えできていなかったからだと思います。そのため、これからはもっと分かりやすく、本当に使いやすい輸送手段のひとつとして訴求をすることが必要だと感じています。まだ天候や旅客列車の影響で、遅れや運休が生じるなど、乗り越えなくてはならない壁は数多くありますが、デメリットをカバーして使いやすい輸送手段に変えていかなくてはならないと考えています。それが今後、鉄道を選んでいただく上での大切なポイントになることは間違いないでしょう。

未完成の仕事はオモシロイ
― 貨物輸送という仕事の面白みと、この先 物流業界を志す若者へのメッセージをお願いします。
五島さん:この先特に大切になると言われているのは、物流業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)です。デジタル技術を活用した組織全体の変革は、物流業界でも積極的に推進していかなければならないと思っています。実際JR貨物でも、トラックドライバー用のアプリを全国の貨物駅で展開したり、貨物駅のスマート化を促進したりと、少しずつ取り組みを始めてはいます。とはいえ、正直言ってまだまだ手作業ベースの仕事も多々あります。こうした観点からも、物流業界にはまだまだDXできる余地と、新しい仕事が待っているぞ!と学生の皆様にお伝えしたいです。
― たしかに物流業界のDXはこの先、必須になってくると思います。既に感じているDXのメリットはありますか。
五島さん:営業や計画部門の社員が、幅広い領域の情報に触れられるのと同時に、部署や会社の枠を超えてコミュニケーションを取りやすい環境が作りやすくなったことでしょうか。いつでも誰とでもすぐにつながれる。だからメールも電話も、しょっちゅうです(笑)。それが社内だけでなく、社外の人ともつながりやすくなったという点は非常に大きいと思います。
― 具体的にはどのようなコミュニケーションが生まれていますか。
五島さん:以前は「このキャパシティだとウチではダメだね」という一言で計画がストップしてしまっていたところが、他社に相談することで「その仕事うちでさばくよ」「うちが手配できるよ」という連携が取れるようになりますし、他社同士をつなぐこともできます。DXが発端にはなりますが、人や会社のネットワークがうまく機能してきていると思います。私自身、かつては手作業が多い部署で人間関係にも非常に苦労していましたが、DXの力でいわゆるヒューマンネットワークをすごく作りやすくなりました。今後も、良好なコミュニケーションを生むきっかけとしてDXを推進していきたいですね。
― DXによって便利になる一方で、留意すべき点もあると思います。五島さんはどんな点に気を付けてほしいと考えますか。
五島さん: 最も大切なのは、DXを目的にしないことです。デジタル技術の存在は偉大で、仕事を効率的にこなしていくには必要不可欠だといっても過言ではありません。ただ、DXが進んだとしても変わらず大切なのは、現場、現物、現実、原理、原則です。モノを動かす現場で、どのようにモノを動かしているかということですね。フォークリフトが自動で動く現場もありますが、フォークリフトで貨物を動かすためには、その貨物を動かすことを企図した人間の考えが必要です。物流がデジタルで「見える化」している時代が到来していますが、いろいろな意思があって物流が動いていることを忘れないようにすべきだと思います。
― DXで便利になる反面、考えることを止めてはいけないということですね。
五島さん:そうです。便利な世の中になると、単純作業に従事する機会が格段に減ります。反対にいえば、なぜこの荷物がこう動くのか、「想像力を持つ仕事」「想像力を高める仕事」をするよう心がけ、自ら努力することを忘れないでほしいと思っています。

― 渡部さんは、物流業界へどのような若者に飛び込んできてもらいたいですか。
渡部さん:モーダルコンビネーションの取り組みをはじめ、今あるものから派生できるサービスはまだまだ無限大にあり、この仕事は非常に可能性を秘めています。そのため、そこに面白みを持っていただける方に入社いただけたら嬉しいです。私は、前職とは全く異なる業界に飛び込んできたわけですが、鉄道を走らせてモノを運ぶという軸を中心に様々なコラボレーションを行うことで、無限の可能性が生まれるのを目の当たりにしてきました。物流業界には、社会全体の可能性を広げるおもしろい仕事がたくさんあります。これからの物流業界では、新たなアイデアを生むことや、それを実現することを楽しめる人が活躍すると思いますね。
変わり目こそが、最大のチャンス
― 読者の皆さんにお伝えしたいメッセージをお願いします。
五島さん:以前、とある物流専門紙の方が「物流に携わる人々、この業界全体が古くから下に見られ続けていたから、対等に等身大で評価してもらいたい」とおっしゃっていたのがすごく印象に残っています。ようやくその時代がやってきました。効率的かつ持続的な物流体系を作るため、あらゆる業種の人たち、物流業者の人たちが対等なつながりを持つようになっています。そんな中、JR貨物という会社としても、物流を担うひとつのグループとしても、物流事業の展開を多角的に進めていきたいと思っています。若い人たちには恐れずに、色々な方面からぶつかってきてもらいたいです。変わり目の時代だからこそ、人とのつながりを大切にしつつチャレンジすることを忘れないようにしてほしいですね。
― 渡部さんはいかがでしょうか。
渡部さん:JR貨物という会社は、今まさにターニングポイントを迎えていて、社内外の状況が変わってきていると実感しています。そうした中で私が特に実感しているのは、仕事に対する考え方の変化です。今まで鉄道会社は鉄道を走らせることがメインでしたが、物流会社として“お客様のモノを運ぶ”ことを本質的に考える会社に変わりつつあるのです。その現場のど真ん中に身を置いているので、非常に面白い仕事だと日々感じています。この面白さをぜひ、一緒に感じてもらいたいと思います。
― この先の貨物輸送が、どのように花開いていくのか。とても興味深く、また、ワクワクする未来を想像させられました。五島さん、渡部さん、貴重なお話をありがとうございました。

<取材・編集:ロジ人編集部>
JR貨物 日本貨物鉄道株式会社の採用HPはコチラ ▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
