テストと評価
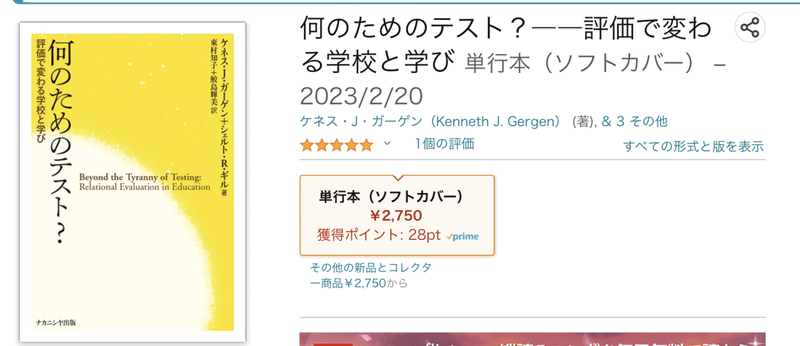
読書会に参加していました。
3章くらいまでは普通に読めるんですが、4章以降の具体例のあたりから、ページをめくっているだけ。という感じになりました。
とりあえず通読してみて、何となく筆者の主張みたいなのが分かった気になった状態で参加しました。
でも、まだまだ解像度は荒く、月1回の読書会で深めていけるといいなあ。と思います。
朝に考えていたことがどんどん薄くなっていく気がしたので、とりあえず書き留めておきます。
まず、テスト=評価 評価=テスト となっている人が多くいるように感じました。
もちろん両者は切っても切れない関係ではあるけれど、重ならない部分も多々あると思います。
「評価」という言葉を使って語る時、相手が教員であっても保護者であっても子供であってもズレを感じることが多いです。
「評価」ってのは、もっと広い意味で、「学びを支える」という側面があって、それがゴールではないイメージです。(と、思えるようになったのも、ここ数年の話ですが)
評価という言葉がいろいろな人に使われ過ぎていて、もう「評価」という言葉以外を使った方が良いような気すらしてきました。
現場で話をするときに、まず形成的評価と総括的評価の違いについて理解しているか確認しなければ、話し合いの土台が違い過ぎてすれ違いまくります。まずはそこを丁寧に。
本書では、総括的評価として、テストによって子供たちの能力(のごく一部の側面)を数値化して序列化して、ヒエラルキーを作ってしまう。心を傷つけてしまう危険性について書かれていました。
テストは、学びを支える手段だったはずなのに、いつの間にか目的になってしまっている。そこを何とかしたい。という話でした。いろいろな具体例が書かれていたのですが、海外の事例なので僕にはピンときません。
・テストは本当に悪いのか?
・テストによって数値化する良さは何なのか?
・「関係のプロセス」を支えることは良いことだらけなのか?
朝よりどんどん解像度が下がっています。何を書いているのかよくわかりません。
ずっと、マイクラをしていたからでしょうか。。
やはりアウトプットは早めに限ります。反省。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
