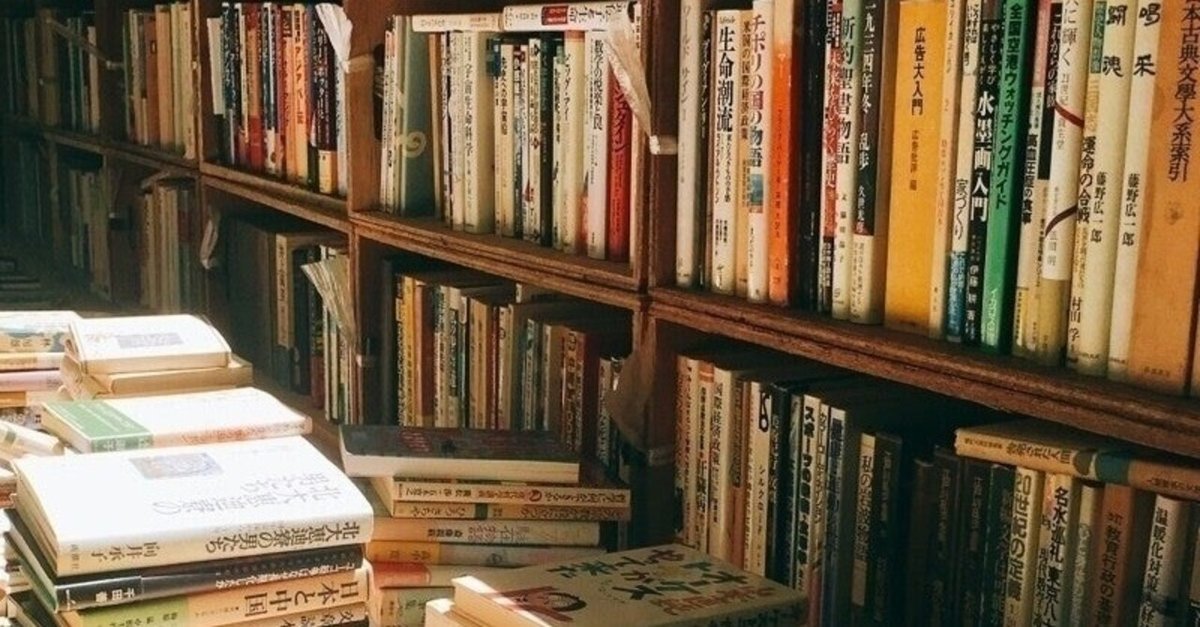
210205 〈読書〉政治的人間と宗教的人間
1.『淮南子』詮言訓より
森三樹三郎(1994)『老子・荘子』(講談社学術文庫)講談社において、紀元前二世紀の漢代に書かれた道家系の書『淮南子』より、以下の一節が紹介されていた。
「私という人間が生まれるまでに、この天地は無限の時間を経過している。私が死んだ後も、また無限の時間が流れてゆくことであろう。してみれば私という人間は、無限の天地と無限の時間の流れに浮かぶ一点にすぎない。
このわずかな数十年の命しかない一個の人間が、広大きわまりない天下の乱れることを憂えるのは、あたかも黄河の水の流れが少なくなったことを悲しみ、その涙で黄河の水を増そうとするのに似てはいないだろうか。三日の命しかない蜉蝣(かげろう)が、三千年の寿命をもつ亀のために長命法を心配してやったとすれば、きっと物笑いになるにちがいない。
してみれば、天下の乱れなどは憂えず、ひたすらに我が身の治まることを楽しみとする者であってこそ、始めて永遠の道を語る資格があるといえよう」(詮言訓)(pp.67-68)
さらに本文は以下のように続く。
この一文の最後のところの原文は「故に天下の乱るることを憂えずして、その身の治まることを楽しむ者は、ともに道を言うべし」となっている。人類や世界の運命がどうなろうとも、それは一瞬の存在でしかない一個の人間の力をはるかに超えた問題であり、そのようなことに心を煩わすことなく、我が一身の安心立命をこそ考えるべきだ、というのである。
もしこの一文を読んで、その個人主義に強い反感をおぼえるというのであれば、その人は政治的人間であることを自ら認めたことになろう。反対に、この利己主義に共感をおぼえるというのであれば、その人は宗教的人間であるということになる。この一文は、そうした人間の類型を判別するリトマス試験紙として役立つはずである。 (p.68)
タイトルが示す通り、本書の目的は老荘思想の内容とその歴史的役割を明らかにすることにある。そのため、上記で引用した『淮南子』の一節は本筋からは外れているものの、一般に老荘、道家として一括にされている老子と荘子の間にある質的な相違を捉える文脈でその導入として紹介されており、非常に興味深くも考えさせられる視点だと感じた。
2.読書の経緯と前置き
本書は昨年、古本市で偶然見かけて何となく手にとって購入した。いざ読んでみると、老荘思想が成立した時代背景や主たる内容、それらが後世の文学・宗教などに与えた影響について、幅広い視点から非常にわかりやすくまとめられていて、とても読み応えのある一冊だった。それもそのはず、本書は1978年刊行の『人類の知的遺産〈5〉老子・荘子』が文庫化されたものであったらしい。ここではそのごく一部にしか言及できないけれど、思わぬ形で老荘思想の入門として優れた良書に巡り会えたなと思う。こうした出会いがあるのも、古本を手に取ることの魅力の一つだ。
「政治」「宗教」といった語句だけを見ると何だか危うい話題を扱っている気がしてきたので、念の為ここで断りを入れておく。私は「政治的信念は何か(右か左か)」とか「神様を信じるか否か」といった話をしたいわけでは、全然ない。ここでは話を単純化するために、冒頭の引用における各語句の意味を以下のように理解するものと仮定して、文章を進めることにする。
ここでの「政治的人間」とは、「世の中にある諸問題は解決可能であるとともに世界はより良く変化していくものだと信じており、自分の行動や仕事等を通じて、自らもその変化に貢献できると考えている人」を指すこととする。また「宗教的人間」とは、「世の中の様々な問題は自分一人の力でどうこうできるものではないので、そうした問題は横においておき、何はともあれ自分自身の人生と生活の安寧を第一に考えようとする人」を指すものとする。
(※以下、文中の引用はすべてpp.68-70より)
3.老子と荘子の違い―政治的人間と宗教的人間
筆者によると、「もし自分という一個の人間の救いだけを求めることを利己主義とよぶならば、あらゆる宗教は利己主義」であり、宗教は「利己的で非社会的な一面をそなえて」いるといえる。だから宗教的人間は、「往々にして現実の問題に冷淡になる」のだ。他方で、国家や民族などの集団の次元で解決できるのは、せいぜい「福祉」や経済生活の向上といった問題に過ぎない。いわゆる『魂の救い』は個人の深奥に根ざした問題であり、「人間が死の運命を背負わされているという事実は、集団の力ではどうすることもできない」ため、すべての宗教はその本質において個人を場としてあらわれることになる。
筆者は「一人の人間のエネルギーには、おのずからなる制限」があり、「政治と宗教、この異なった二つの方向に、同等の関心をもつことはむずかしい」という。そのうえで、老子は「文明の中毒に犯された社会に、自然の健康を取り戻させようとする政治的な関心から出発」しており、「政治的であると同時に、哲学的であり、宗教的であるという、めずらしい人間の型」であるが、しかしそれゆえに「半ば政治的な人間である老子自身の性格が、宗教的世界への深入りを妨げた」のではないか、と指摘する。これに対して、『荘子』においては『老子』の書にみられたような天下や国家といった語がほとんど見られず、「荘子は宗教的人間としての立場に徹底している」という比較がなされている。
4.老子・荘子に対する印象
『淮南子』の一節に対して反感を覚えるか否か、即ち「政治的人間か、宗教的人間か」という視点は、老荘の違いを直感的に把握できる明快な指標だと思った。私は『老子』の現代語訳には以前触れたことがあり、本書を経て俄然『荘子』への興味が湧き、いくつかの現代語訳と解説書を読み漁りつつある。だから、老荘思想の理解という点ではまだまだ道半ばなのだけど、それでも一度『荘子』に触れてしまうと、『老子』でさえ世俗的な色彩が強く、処世術的な側面が強調され過ぎているように思えてくる。たしかに『荘子』では『老子』のエッセンスが一部受け継がれていると感じるものの、両者は似て非なる部分も多く、今となっては「老荘」と一括にすることには抵抗すら覚えてしまう。
ただ、こうした感触は私の個人的嗜好による影響が大きいのかもしれない。『荘子』の世界はとても刺激的で面白い。単に私の好奇心を満たしてくれるだけでなく、そこでは言葉の用い方から人間理解の深み・鋭さ、社会への眼差しに至るまで、これまで漠然と感じつつも言語化できなかったことが見事に表現されている気がして、「やっと出会えた」とも思える感慨があるからだ。要するに、私は『老子』よりも『荘子』が好きで、好みに合うわけだ。
5.自分はどの立場をとるのか
以上にみた筆者の説明と私個人の感想を踏まえると、『淮南子』の一節のような個人主義的・利己主義的な立場に対して、私自身はどのような考えを抱くだろうか。
私は筆者が徹底して宗教的な人間の立場を貫いたと評する荘子の思想に感銘を受けているわけだけど、かといって冒頭の一節に共感をおぼえるのかと問われると、すんなりうなずくことはできない。それに、以前は今以上に純粋な「政治的人間」であったような気がする。けれど、目の前にある様々な社会的課題の多さとその関係・構造の複雑さに打ちのめされるとともに、「諸課題の根底に横たわる核心的問題とは一体何であるか」という壮大過ぎる難問を抱えて頭を悩ませているうちに、「天下の乱れを憂えること」にすっかり疲れ切ってしまった。そうして次第に「宗教的人間」へと関心が移っていったのだと思う。だから、今はまだ「政治的人間」の立場を完全に捨て去ることも出来ず、若干の未練が残っている気がする。恐らくこれは必ずしも白黒つけられる問題ではないだろう。それでも、自分はどちらにより近いのか、日常的な思考・言動はどちらに基づいているのかと自問してみると、今はちょうど二つの間を揺れ動いている時期ではないかと感じた。
少なくとも今、「宗教的人間」の世界観に興味を抱いているのは事実だ。いくつかの本を読んでみて、荘子の面白さの一つは、彼が「宗教的人間」の要素を多分に含みながらも、決して宗教人そのものではなかった点にあるのではないかと思っている。つまり、荘子の思想には「利己的で非社会的」と思われる側面が多く含まれているにもかかわらず、「人は来世で救われる」のような神秘的な表現は一切見当たらず、そこにはむしろ、一縷の望みすら途絶えたかに見える過酷な現実を透徹した目で直視し、それでも尚逞しく生き抜く荘子の姿がありありと浮かび上がってくる。このような荘子理解を促したのは福永光司さんの『荘子―古代中国の実存主義』、『荘子 内篇』であり、これらの著作における荘子の描写・解説は、圧巻だった。
私自身、一般的な宗教(唯一神・人格神をたたえ、信仰すること)には馴染みがないし、これからも関わることはないと思うけれど、荘子を含め、本書の文脈を踏まえた(冒頭で仮定した意味での)「宗教的人間」の世界には、もっと触れてみたいという思いがある。荘子関連の本を読む中で、前田利鎌の遺著『宗教的人間』の主要部を収めた『臨済・荘子』も手にとった。荘子の部分は何とか読めたけど、臨済の方はまだまだ理解が浅い。まずはこの辺りの人からその言行を辿ってみると、何かヒントが得られるかもしれない。とりあえず『臨済録』でも読んでみるか。それにしても、中国古典は奥が深い。
