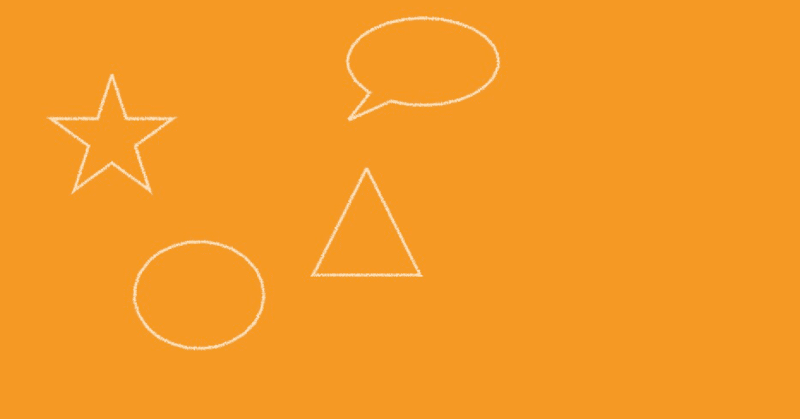
“産業財産権を受ける権利”という??
最近、次の文書を契約書でよく見るようになった。
・産業財産権を受ける権利/知的財産権を受ける権利
あれ?
7年近く知財関連の仕事をして、弁理士試験にも合格したが、このような使い方/表現はないと思うけど。
それで調べてみたら、まさか!!いろんなところで使われていた・・・
下記では、“産業財産権を受ける権利”の検索結果を示す。
“知的財産権を受ける権利”に関しても、文部科学省や厚生労働省の様式に、使われていた。
-----------
1。独立行政法人工業所有権情報・研修館
「知っておきたい特許契約の基礎知識」(*A)の共同研究契約の雛形に、次の文言があった。
− 特許、実用新案、意匠についての産業財産権を受ける権利
2。経産省
「戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)ICTグリーンイノベーション推進事業(PREDICT) 平成23年度 研究開発委託契約書 様式集」(*B)の様式11
3。NEDO
「focus NEDO」 2017 No.64(*C)
4。大学や企業の契約書雛形(省略)
5。その他
次のように定義をした上で使う場合もあった。
「産業財産権を受ける権利」とは、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利及び意匠登録を受ける権利ならびに外国における上記各権利に相当する権利を総称していい、出願中の産業財産権を含むものとする。
-----------
一点強調したいのは、特許庁のウェブサイトや特許庁が出した文書には、「産業財産権を受ける権利/知的財産権を受ける権利」のような文言が見当たらなかった。
特許法にも当然ない。
弁理士試験の勉強においても、このような文言はみたことがない。
でも、検索した結果からみると、少なくとも10年以上前から、契約書においては、使われ始めたと言えるかな。
特許庁としては、このような文言を認めていないと思うが、反対もしていないようだ。
言葉というのは、みんなが使うと正確なものになる。
「当たり前」が、「当然」に「当前」という字を当て、それを訓読みにして生まれ、使い続けることで普通になった、という説のように。
「産業財産権を受ける権利/知的財産権を受ける権利」というのも、近々普通の表現になりそうだ。
いや、もう既に当たり前の表現になったかもしれない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(*A):https://www.inpit.go.jp/blob/katsuyo/pdf/info/tebiki_1009.pdf
(*B):https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/predict/document/document.html
(*C):https://www.nedo.go.jp/library/FN64_ebook/HTML/index14.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
