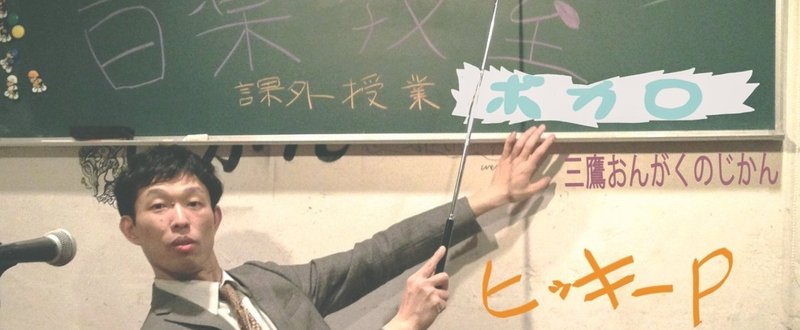
でたらめ音楽教室・課外授業《ボカロ》4の覚え書き
2018年1月27日(土)、三鷹市南口から徒歩数分。
スッパマイクロパンチョップさん(以下、スッパさん)、ヒッキーP(大高丈宙)さんが主催する
でたらめ音楽教室・課外授業《ボカロ》4
に参加してきました。
多少新幹線が遅くなり、三鷹駅に14時半頃到着。路面に雪が積もり残って寒々しかったですね。二回目なので「おんがくのじかん」まで早足ですぐに。
入場時の店内BGMに『Lost in the Fog』(ゆにPさん)が流れていて、これが私の大好きな名曲で、すでに元を取った気になれましたw 他にも何曲か流れてましたが曲名が出てこず……分かったのは『君がいる僕の住む町』(ムジカデリクさん)ぐらいかな。
主催者スッパさんがボカロと邂逅したのは、2017年8月と聞きました。今回でボカロ編のでたらめ音楽教室も4回目を数えますが、スッパさんがボカロの世界を知ってから、たった半年しか経っていないのですね。そのバイタリティに驚きます。スッパさん、2013年12月に行っていた(ボカロ以前の)『でたらめ音楽教室第1回』では、ベースだけの音楽とか、逆再生の音楽だけとかを集めて何時間も聴くような授業をしていたのだとか(面白そう……聴いてみたかったなあ)。
今回のお客さんは日取りのためか10人程度と前回より少なめでしたが、落ち着いた雰囲気でゆったり授業を聴けたのは大変良かったです。美味しいカクテルに舌鼓を打ちつつ、トーク開演に耳をそばだてます。
さて今回のゲストは、なんとボカロPのMSSサウンドシステムさん(以下、MSSさん)!
当日早朝(!?)に急遽頼まれてのゲスト出演ですとか。アドリブ力が半端ないです。MSSさんの曲は聴かせて頂いてましたが、シンリシュープリーム(XINLISUPREME)に評価されていた、というのは紹介で初めて知りました。
※シンリシュープリームは日本のロックミュージシャンで、ノイズ・シューゲイザーで世界的評価を受けているアーティスト(Wikipedia)。
**
1.2017年を振り返る
2.VOCALOIDアンダーグラウンドの発信
3.お客さんの曲を聴いてみよう
というお品書きはあったのですが、そこはでたらめ音楽教室、初手から脱線していきましたw まあ、大きな話の流れには沿っているのですけど、1.と2.は行ったり来たりしながら渾然一体となって進行していきました。
最初のお題は「ミックホップ」になりました。
これは、2.VOCALOIDアンダーグラウンドの発信の文脈ですね。
HIP HOPは「ラップ/MC」「DJ」「ブレイクダンス」「グラフィティ」の四つの要素で構成された、創造性を象徴する文化のことを指す。単にHIP HOPと言った場合、サンプリングや打ち込みを中心としたバックトラックに、MCによるラップを乗せた音楽形態を指すことが一般的であるが、HIP HOP MusicやRap Musicと呼ぶのが正しい。
ミックホップは上記のいずれかの要素を含み、かつVOCALOID、UTAU、CeVIO等の歌声合成ソフトウェア及びそのキャラクターを使用している作品を指す。そのため、音楽作品に限らず、上記キャラクターをMikuMikuDance等の3DCGムービー製作ツールやアニメーションなどでブレイクダンスをさせた作品、グラフィティ作品(スプレーやフェルトペン等を使用し壁などにアートを施したもの)なども、ミックホップに含まれる。
もともと「ボカロラップ」というタグは初音ミクが登場して間もない初期から存在しており、tysPさん、nak-amiPさん等の作品に付いていました。
しかし、「ヒップホップ」は必ずしも作品内に「ラップ」を必要とするわけではなくラップが存在しないものもあるそうです。そうした経緯から、「ボカロラップ」とは別に、2014年5月頃に「ミックホップ」というタグが使われ出したのが始まりのようです。
ミックホップ代表作として挙げられたのは、『初音ミクの証言』です。
元ネタはJヒップホップの名作『証言』。1994年に送り出された『DA.YO.NE』(EAST END×YURI)、『今夜はブギー・バック』(小沢健二、スチャダラパー)等のヒットにより日本でもラップが広まり、人口に膾炙したのは良かったのですが、軽快におしゃべりして適当に文末を揃えればラップだろという風潮も蔓延してしまったとか。それに対する怒り、ルサンチマンから、ストイックなヒップホップを目指し、LAMP EYEが1995年に発表したのが『証言』。
各MCが当時のヒップホップシーンに対して過激な言葉と音楽性でラップしたマイクリレーものです。発売当時、盤にはあっという間にプレミアが付き、ヘッズによる争奪戦が勃発。入手できなかったBボーイ(ラップミュージックの熱烈な少年ファン)が購入者を襲って奪い取る「証言狩り」まで起こったそうです。このように『証言』は日本語ヒップホップ界隈では欠かせない曲だそうで、2006年には『暴言』というカバーも出ています。当時の雰囲気については、参考記事もご参照ください。
◇DJ YANATAKE CISCO渋谷店『証言』アナログ放出セールを語る
https://miyearnzzlabo.com/archives/29527
◇D.O『証言』アナログレコード狩りを語る
https://miyearnzzlabo.com/archives/37618
◇Dommune LAMP EYE『証言』20周年記念番組「20年目の『証言』」まとめ
https://miyearnzzlabo.com/archives/40474
『初音ミクの証言』に話を戻します。
KAI-YOUでも紹介されていたとのトークから記事を拾ってきました。
◇ドープすぎるぜ…! HIP HOPの名曲「証言」を7人のミクがマイクリレー(KAI-YOU 2015.03.03)
http://kai-you.net/article/14043
"ヒップホップユニット・LAMP EYEの名曲「証言」を、ボーカロイドの初音ミクがリミックスした「初音ミクの証言」がニコニコ動画に投稿され、話題になっている。
ボーカロイドと本格的なヒップホップを融合させ、サンプリングやブレイクビーツといった要素を取り入れた新たなジャンル「ミックホップ」をテーマとした、総勢11人の参加者による大作だ。"
ちなみにドープ(dope)とは英語で麻薬。それぐらい病みつきになるぜってことでしょう。MSSさんの証言によりますと、最初はMAYROCKさんが重音テトラップ曲を作っていて、そこにMSSさん・しまさんが加わり、しまさんがポエトリーリーディングを入れたいと要望してサギシさんらが加わり、と次第にコラボが広がって出来ていった作品とのこと。最終的には、
LYRICS:やし,iNat,Torero,mayrock,でんの子P,松傘,sagishi07
BEATS:MSSサウンドシステム,neilguse-il
MASTERING:k■nie
DIRECTION:しま
錚々たるメンバーになっています。教室では、実際に『証言』を聴いた後、『初音ミクの証言』を流すという構成になりました。なるほど、以前に聴いた時と、音楽的なバックボーンを知りながら聴くのとでは、受け取り方も変わります。しっかりと『証言』の形式を踏襲しつつ、盛り込まれているのは2015年2月当時のボカロシーンを問い直す言葉。そういう意味では、シーンに刻まれるべき記念碑的作品と呼べるでしょう。MSSさんは、最初からそうしたポジションを狙って作ろうとした訳ではない、と仰ってましたが。
**
このような「ミックホップ」文脈が位置付けられてきた、ボカロアンダーグラウンドの流れをおさらいしておきますと。
2007~ 底辺P、最底辺P、辺境P
2008~ アングラ系
山本ニュー:サイケ、アシッド、ローファイ
2012~ 中学生ボカロP
2013~ マイナー・ハイセンス系
2014~ ミックホップ
2016~ チンアナゴ
2017~ イノセンス
キーワードを大雑把に挙げても、多少年代は前後するかもですが、このような感じでしょうか。(ヒッキーPさんの提示した表を、お話をもとに修正)
サンプリング・ミュージックに関して言えば、2010年には既に、その名もサンプリング・サンプリングさんという方がおられ、作品を発表されていたようですが、現在は削除済みだそうです。オケ借用の問題があったようです。
そして言わずもがな、MSSさんの『耳なりはフェンダーローズ』。(ニコニコ動画版、YouTube版)それまで、サンプリングに関してはボカロ界隈で見掛けなかったので、やってはいけないと思っていた……と。
この辺りの説明に関しては、すでに鈴木Oさんが、
◇VOCALOID音楽と引用の技法(2018/1/25)https://note.mu/suzuki0/n/n3c3ee2f43fad
というvocanote記事で、nak-amiPさんから始めて山本ニューさん、MSSさんまで含めて、ボカロにおけるサンプリング・ミュージックとヒップホップの文脈について書かれているので、大変オススメです。ぜひ読んでみて下さい。
**
続けて、1.2017年を振り返るコーナーも混ぜていきましょう。
初音ミク10周年というだけでなく、スッパさん達は2017年の名作として、『but the sky is blue』(yeahyoutooさん)、『アイドル』(Phhyunecoさん)を挙げています。また、スッパさんがボカロを聴いて回る要因となった、キュウさんのボカロ100選も。
スッパさんは、竹村延和氏が1998年に設立したレーベル「childisc」からアーティストとしてデビュー、アルバムを7枚もリリースされているだけでなく、childisc音源だけでのmixtapeを作っちゃったぐらいですし、ボカロのキャラクターに興味のない音楽ファン層に対しても訴求力のある「音楽の面白さ」にこそ説得力を感じるとのこと。
(訂正)御指摘を頂き、上記の文章を「聴いておられて」→「アーティストとしてデビュー~」へと修正しています。
在りし日の冨田勲氏は「初音ミクは面白いね」と言っていたそうですが、これは初音ミク現象・VOCALOID技術への言及であり、ボカロ音楽の音楽性に向けた言葉とはちょっと違います。
今でも、CD店では「一般的な音楽」/「VOCALOID音楽」は区別されてしまいます。ある意味で、ボカロを使うだけで「音楽ではない」と言われる。このあたりは、佐々木渉さん・しまさん監修の『別冊ele-king 初音ミク10周年』でも語られていたと思います。ボカロを使うことに意識的である必要がある。なぜボカロを使うのか?
スッパさん監修のボカロアルバムCD『合成音声ONGAKUの世界』が、3月14日P-VINEから発売されますが、ボカロPのライブイベントをやった時と同じような問題に悩まされたそうです。つまり、連絡が付かない! コアアカウントが無い! (ライブなんかできないし、人前に行きたくない……)と思っているのかどうかはさておき、匿名性を重視する傾向があるのですね。だから、この曲はぜひ入れたいが連絡付かないなあ……という作品は外して入れ替えた事もあるとか。
**
ボカロアングラとは、ボカロ曲の中でもランキングに居座りづらいタイプを指しますが、音楽的な限定はしていないとのことです。ヒッキーPさん主催で、2008年3月当時、ボーカロイドアンダーグラウンドカタログと銘打って、再生1万以下の個性的な作品を紹介していました。ライトなボカロクラスタの認知はカテゴリーランキングが大きな軸になっており、ランキングを転がりにくいアングラをカウンターとして捉えていたそうです。(再生数は認知度であるという考え方)
2007年8月以降、初音ミク発売に伴って多くのメディアが一時的にボカロに触れましたが、あくまでメジャーどころの表面だけ。数年前までは、単にボカロシーンのごく上澄みを掬っただけでも、もうそれだけでコアに理解しているフリができたし、メジャーな音楽(ボカロ以外の、主流の)に媚びていないぜ、という態度すら取れたのです。実際に、ボカロシーンの内側に深く入り込み、外側に伝えようとするメディアは少なかった。広辞苑のように網羅するまで行かずとも、「上から並べました」ではない、ディープなところを紹介してほしい。しかし、極少数ながらそういうメディアもあったのです。
(1)クイックジャパン(2007年12月)
当時数百再生で音楽性もボカロ的ではなかった、ちゃぁさんの『ミクイズム』を紹介。この記事は、sansuiPさんがボカロPになる契機となったそうです。
(2)ASCII.jp 四本淑三の「ミュージック・ギークス!」(2009年~)
四本淑三氏は、元ROCKING ON JAPANの編者で、インディペンデントなボカロシーンについてもメジャー・マイナーを問わずコラムで言及し、VOCALOID-SNS「にゃっぽん」(2008~2013年)等にも触れていました。
(3)ゲッカヨ(2010~2012年)
いわゆる底辺P対談・牢獄P特集など、ときに炎上案件まで踏み込むほど、編集長がボカロファンで、ボカロコーナーまで増刊したほど。残念ながら2012年に雑誌のゲッカヨは倒産するのですが……現在は、「ゲッカヨ・オンライン〜月刊歌謡曲●電子版」としてWebメディアで活動を続けているようです。
そして、GINGAレーベルの話が登場します。
大手レーベルは、2008年8月以降、kz『Re:Packaged』(EXIT TUNESコンピ)などでボカロのメジャーなヒット曲を取り上げてきました。しかし、2011年8月GINGAコンピが出るまで、流通に載せる側の人間で「ボトムまで含めたボカロシーン」を認知して動く人はいなかった、とヒッキーPさんは語ります。パンク・ヒップホップのような、草の根的なボトムアップからのインディペンデントな活動に、初音ミク登場から3年半たって初めて目を付けたのがGINGAレーベルでした。ヒッキーPさんが語ったGINGAのイメージは、お洒落な電子音楽(ビョーク系とか)、ブレイクコアとかセンス良いテクノの最先端、そして大丈夫Pなど一石投じる系。『Galaxy Odyssey』シリーズは、MSSさんによれば「ボカロアングラの登竜門的なイメージ」があったそうです。
ミュージック・ギークス! 第110回「ボカロシーンの鬼才を口説いたGINGAレーベルとは」(2012年12月22日)
ミュージック・ギークス! 第111回「シーンに挑戦するGINGAレーベルの音楽づくりにせまる」(2012年12月29日)
ミュージック・ギークス! 第112回「ボカロカルチャーに一石投じるヒッキーPに聞く」(2013年1月19日)
特に第110回の記事から引用するのですが、
曽根原 友達とか、家族とか、まだいないですけど自分の子供や孫に「おじいちゃんこういうことをやっていたんだよ」って、胸を張って見せられるものを作りたい。でも「それどうやって作ったの?」って言われた時に「上からな、順番に並べて行ったら、たまたまこうなったんじゃ」って、言うのは絶対イヤだと。
—— いや、実によく分かります。そうですよね。
曽根原 「おじいちゃんが、これむっちゃカッコいいと思ったからなんだ」なら伝わると思うけど。ランキングの数字が根拠だなんて、ボカロ文化がどうの以前に、俺がムリ。だから再生数は、ある時から見なくなりました。
というのは共感できますね。
ヒッキーPさんの恨み節(w)がここで入るのですが、CD発売前日に30~40人のボカロPにニコ生を持ちかけて6~7時間ほど宣伝番組をやったことがあると。しかし歌ってみた専門誌だけが記事を載せてくれて、他のボカロ関連雑誌はノータッチだったと。だったら、マイナーに目もくれないなら、「ボカロの全てに目を向ける」などと謳うなと……うーん、分かります。
当時の曽根原さんは、かなりマージナルなことにも手を出して、ディスクユニオンにもアニメイトにも置けないようなCDを出すなど攻めの姿勢でした。
「自分たちが楽しめる音楽がボカロにもあるんだ」というメッセージ、これはスッパさんのボカロの偏見が消えるmixにも通底しています。
今のボカロシーンは、メディアから推されるだけじゃない、作曲者主体のムーヴメント、色々とシーンを盛り上げながら見続けてきた個人からの発信が必要な時代になっています。
メジャーで取り上げられるトレンドが常に変わっていくのに対し、キャラソン・ネタ・物語音楽・高速ロック・オシャレナイーヴ、そしてボカロアングラといった各ボカロジャンルの雰囲気はそう大きくは変わりません。各ジャンルの内包する幅は広く、分厚い。
**
最後に、3.お客さんの曲を聴いてみようコーナーで〆となりました。
MSSさんの未発表曲『Killing me softly』。
(4/6追記)M3-2018春で頒布予定とのこと。
マルコさんのdemo(UTAU)。サウンドクラウド:marukosan
みっつうさん(@M1santhr0py)の「【初音ミクAppend(Solid)】UnDeRr0My0skiN / アンダーマイスキン【オリジナル曲】」。
(みっつうさん、少しだけ今回のレポも書いておられるようです)
スッパさんの「【雪歌ユフ】猫猫猫猫【オリジナル】」。
(可愛いタイトルに思えますが、実際はフラストレーションが溜まった曲で、ツイッターで社会性を考慮してあまりキツイ愚痴を言わずに「にゃーん」と呟く的な曲との解説でした)
nowismさんの全部テト曲、「【重音テトオリジナル曲】Give me POWER 4th【全部UTAU】」。会場からは絶賛の声でした。
後から手直しすることになると思いますが、とりあえずこれでレポートとしておきます。ではまたvocanoteでお会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
