
鑑賞者が創り出す絵画の空間
美術鑑賞にどっぷりハマっているが、制作という面からは全く関われないアートの世界。これからの人生で、私は芸術とどのように関わっていけるのか。
そんな問いを持って、たまたま古本屋さんで購入した冊子『芸術学の基礎』。
前回まで[映画]に見る【美学】、[音楽]に流れる時間について考えてきましたが、今回は 空間という概念を[絵画]作品から明らかにする試みです。
**********
“土地の広さを基準にして税金を課す” という必要から、空間上の長さの単位が公式に生み出されたそうです。
前回取り上げた「時間」と同様に、「空間」も これを必要とした人間にこそ意識され、その人の必要に応じた表象を持っているのです。
しかし現代社会を生きる我々…。時間は常に気にしているのですが、空間に対する意識はとても希薄になっているように思います。
去年から求められた “ソーシャル・ディスタンス” に戸惑ってしまったのも、これまで他人との距離感をほとんど意識していなかったことに原因があるのかもしれません。また、2019年に滞在したパリの街、そこに生活する人々が持つ空間は、明らかに私と違っていると感じました。うまく言葉にできませんが…。
これも「空間」と呼んでいいのでしょうか?
**********
新生児は、紙の上に並んだいくつかの模様が目・鼻・口の並びをしていれば特別の反応を示さないのですが、これが不自然な配列になっていると目を背けるという不快感を示すのだそうです。
新生児は平面上の記号が人間(母親)の顔を意味していることを理解できる
= 人間は生まれながらにして実在的な二次元の内に、仮象的な三次元(“錯覚としての空間”)を成立させることができるということなのですね。
ふむふむ。
そして逆にいうと人間は有史以前から、空間を平面上(二次元)に描写する技法を持っていた、ということでもあります。
では、画家たちは “錯覚としての空間” をどのように描写してきたのでしょうか。
<画家の描く空間>について考えてみたいと思います。
5世紀前半に描かれた『パンと魚の奇跡』の題材を視覚化したモザイク画です。今から見ると立体感に欠ける平面的な作品。ここに空間は描かれているのでしょうか?

教会を訪れる 字を読むことができない当時の人々にとって、教会の壁画には、聖書の場面が物語の通りに説明的に描写される(聖書の代役となる)ことが必要でした。
まだガラスを知らず、金属の輝きを見ることも稀であった当時の人々にとって、鮮やかな色でキラキラ輝くモザイク画は、信仰を駆り立てる最大の演出効果を上げたに違いありません。
制作者は、神の空間を見事に作り上げたのです。
“錯覚としての空間” 表現が画期的に変化したのは、何といっても15世紀のイタリア・ルネサンス。二次元の画面をいかに ‘本物’ のように表現するか…、遠近法の発明です。
アンドレア・マンテーニャ『死せるキリスト』(1480年頃)。
なんでしょう、この臨場感は…。

540年も前に描かれた作品ですが、のんびりと外の世界から眺めることは許されません。私はまさに今、十字架から降ろされたキリストの亡骸が横たわるこの現場に居合わせているのです。遠近法が不正確であろうと、そんなことは全く関係ありません。リアル以上の迫力に圧倒されて、見つめていると胸が苦しくて涙が出そうになるのです。
これがマンテーニャが描き出した空間なのですね。
レオナルド・ダ・ヴィンチ『最後の晩餐』(1495−1498年)

画面中心にある線遠近法の消失点は、奥に向かって消えてなくなる点ではありません。キリストの頭上から光が放たれるように、そこから前面に空間が広がり、2021年の自宅リビングで見つめるiPadの画面から、最後の晩餐の世界があふれ出してくるような気がするのです。
ダ・ヴィンチの作品はサイズの大小に関わらず、常に広い宇宙🌏を感じます。空間を描くのに長けていた画家であったと言えるのかも知れません。
絵画はその制作された地域や時代の、あるいは創造した個人の、空間の図式を表現している
絵画は “創造した個人の” 空間の図式を表現している…。なるほど面白いですね。
画家によって制作された絵画には、すでに画家の創造した空間が表現されているわけです。
デッサン力、色彩表現や構図だけでなく、画家に求められる「画力」の中に “空間の表現” も加えましょう!。
+++++++++++
渡邉晋輔先生と陳岡めぐみ先生の共著『国立西洋美術館・名画の見かた』に絵画の空間について触れた文章があったので、確かメモしていたはず…とノートを探してみました。
MEMO:「遠近法とは、“架空の世界に開いた窓のように見える” ということ」
MEMO:見るという行為は機械的なものでなく、きわめて知的なものであるため、私たちが対象を見るとき視点を固定することはありえない。しかし写真や絵画はどちらも視点(レンズ)を一点に固定して平面に対象を映し出すもの。
MEMO:仮設の空間構造、すなわち遠近法空間においてどのように画像の創意が発揮されてきたのかを見る=勉強することは大切。
ただし。
注意したいのは、絵画作品は遠近法などを使って画家自身が想像した空間を描写したもの。一点=画家の視点で提示してくれたものに過ぎない。
我々が見るべき空間は別にある。
よく理解できないままメモしていたのですが、絵画作品そのものに描写されているのは、画家が提示した空間にすぎない。鑑賞者である我々には、そこから感じ取るべき別の空間がある!ということですね。
「我々が見るべき空間は別にある」。素敵なフレーズに痺れました✨。
**********
では鑑賞者が見るべき空間とはどのようなものなのでしょうか。
<鑑賞者が見る絵画の空間>についての本書の記述です。
絵画における空間は個人の想像力の問題である
たとえば。
絵本、パンフレットやぬいぐるみとして登場するミッキーマウスは、大きさも姿勢も服装もさまざまです。それなのにディズニーが作り出す世界、我々自身が持つ映画のイメージやディズニーランドでの思い出などが結びついて、どこにいても同一対象の「あの」ミッキーマウスです。
同じように絵画における空間は、見る人の知識や経験、イメージなどを繋げた想像力によってつくられる!ということなのです。
ここ、面白いですね。一枚の絵画を見て、その人が何を想像してどれだけ自分の空間を広げることができるのか。
歴史、文化や宗教的背景、画家のバックボーンや作品の美術史的価値など…。これらについて知ること、そして多くの作品を観て感性を磨くことで、想像の世界を広げ、奥深く無限に広がる絵画の空間を作り出せるのです。
言い換えると、絵画における空間は、たとえ創作に携われなくとも鑑賞者が自分次第で如何様にも創りあげることができるわけです。
素晴らしい✨。
***********
自分に当てはめて こんなことを考えました。
目に見える容姿や身体という人間の実在とは別に、自分という人格があるとすれば、それは思考が育てる わたしだけの空間です。
絵画を鑑賞する、芸術に触れる、幅広いことに興味を持つ、本を読む、勉強することで想像力は厚みを増し、その中から何を取捨選択するかの判断にも役に立っていきます。そうやってわたしの人格が形成されていくのであれば、わたしだけの空間は無限に広がる可能性があるはずです。
とするならば。noteに美術エッセイを投稿すること=人格形成に役立ってるかも…。
下調べのため本を読んでいると知らないことがドンドン出てくるため、別の資料が読みたくなります。興味の対象は幅広いジャンルに及び、自分の断片的知識が連想ゲームで繋がっていくのがとにかく楽しいのです。
そして投稿に際して、自分の思考を冷静に整理しなくてはなりません。
よし、もう少しnoteへの投稿を続けていこう!と勝手な解釈を展開して、決意を新たにしました(笑)。
絵画鑑賞を通じて「ennobling enjoyment(心豊かにする喜び)」を感じている日々。自分の歩んでいる道が間違っていないのだと確信できました。
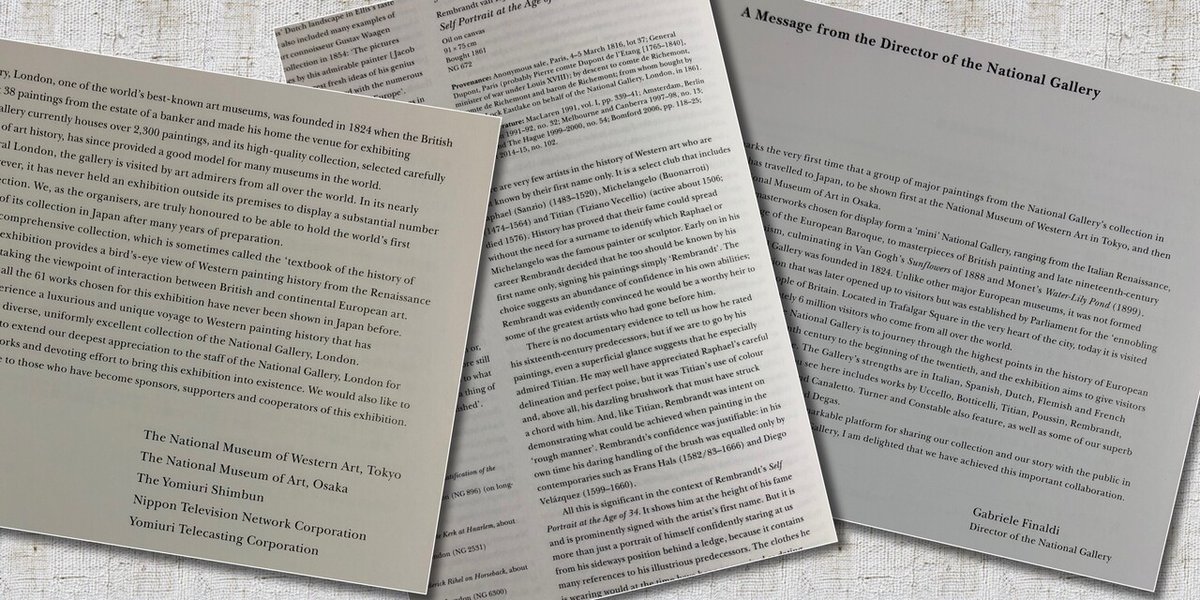
**********
最後に。実は本書から自分自身に対する戒めも読み取りました。
見晴らし窓のそばに立つことで、人は眺めを支配する。人は世界に所属しているというよりは、むしろ円の中心点から世界を組織し秩序づけているのだ。世界を遠近法的な風景として見るようになった人は誰でも、少なくとも幻の権力を享受している。なぜなら、単にその人がそこにいるというだけで、その人の目の前にある景観の要素はすべて一枚の統一的な絵にまとめられているからである。
空間を感じ取るということは、人間の自信の増大を意味し、また世界を操る自分の力への信頼を意味しています。
数歩進むだけで、自分が見ている世界は微妙に変化するのに…。そしてたとえ同じ場所に立ったとしても、見る人によって全く別の景色を感じるはずなのに…。世界の中心に自分がいるような気になってしまうのですね。
7〜8年前、毎日のようにSNSに写真を投稿して楽しんでいた時期があります。
今や1億総カメラマンの時代。スマホを開けば、誰かが撮影した世界中の素晴らしい景色や感動の瞬間を見ることができるようになりました。
そうなった途端に発信を止めてしまった私は、単に「こんなに素敵な場所、こんなに面白い瞬間の写真が撮れたんだよ!私ってすごいでしょ⁈」と自分を認めて欲しかっただけなのかも知れません。
現在夢中になっている美術鑑賞。
自分が感動したことを誰かと共有したい、同じように興味を持ってほしい!と、「見て、見て!この絵には、こんな歴史的意義があるんだよ。ほら、素敵でしょ⁈」と身近な人に理解を強要することが多々あります。
コラコラっ(笑)。
冒頭にも引用しましたが、
「空間」は これを必要とした人間にこそ意識され、その人の必要に応じた表象を持っているのです。
必要とする人間が 自分の必要に応じた「空間」を見つけることに意義があるのですよ!。これを肝に銘じておきます。
**********
長くなってしまいました💦。まとめです。
わたしが考える絵画鑑賞とは、
「画家が描写した空間の中に 鑑賞者が自分だけの空間を感じ取ることで完成する芸術活動」です。
そして今後の芸術との関わり方として、
もっと美術鑑賞を楽しみたいけどやり方がわからない!という美術初心者にとっての翻訳者のような役割を果たすことができたら良いなぁ…と漠然と考えている次第です。
<終わり>
おまけ。
“ソーシャル・ディスタンス” に必要な他人との距離感や、生まれ育った環境が全く違う他人への配慮、これらも意識して大切にしていきたい「空間」です。
想像力と思いやりを持つことでそれは形になる!のですから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
