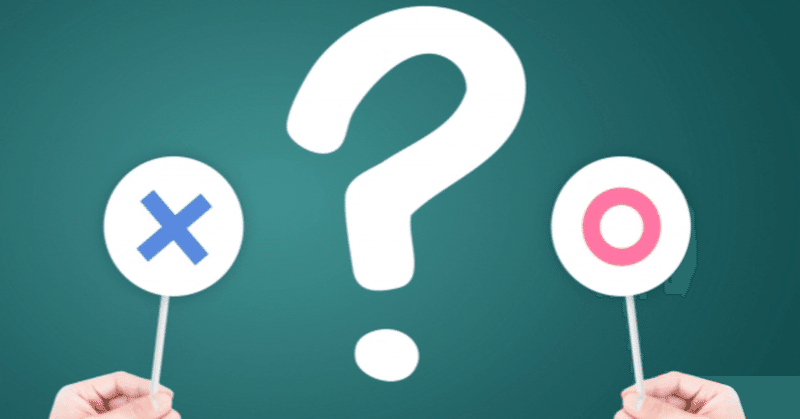
ライターが直面する「画像選定」の著作権問題について考えてみた
見逃しがちな「画像選定」の問題
ライターをしていると、「ん?この案件、大丈夫かな?」と思うものが時々あります。
ライターであれば文章が「コピペ」などの著作権法違反にならないように気を付けると思いますが、近年のウェブライティング案件では「画像選定※」など画像に関することを含むものがあり、その点に関してはライター自身も注意を向けにくく、知識も及びにくいところです。
(※ライターではない方向け説明:画像選定とは、ウェブ記事のアイキャッチや途中挿入の画像について、新たに制作するのではなく、既存の画像の中から選ぶ作業のことです。)
そもそも、著作権を含む知財分野については、個別具体的な問題も含め、裁判で実際に判例が出てみないと分からない部分もあります。
私は行政書士として基本的な知識を学んではきていますが、それでも、具体的なライティング案件を前に「万が一トラブルになったとき、どういう責任関係になるのだろう?私はここに参加して安全だろうか?」と迷うことがありました。
このnoteではライティング案件におけるいわゆる「画像選定」について、どのようなものが明らかに問題であり、どのようなものは避けておくのが無難であるか、私自身も調べながら整理検討してみたいと思います。
契約関係の整理
このnoteでは、あるウェブ記事に使われていた画像が、その画像の利用方法の点で著作権侵害になっていた場合を想定します。

そのウェブ記事を掲載しているサイトの運営者が自ら記事の全部を作成していたときは、間違いなくサイト運営者が責任を負います。運営者が個人であった場合はもちろんとして、運営者が会社であって、その社員に作成させていた場合も同様です。
一方、このウェブ記事を掲載しているサイト運営者が、業務委託によってライターに外注しており、問題の画像を選んだのがライターであった場合が、このnoteが問う場合になります。
したがって、責任を問われる可能性があるかどうかを検討しなければならない関係は、
発注者⇔被侵害者(画像の著作権者)
発注者⇔ライター
ライター⇔被侵害者
の3つとなります(2次下請以下である場合については、最後に特に言及するとき以外は想定しません)。

また、今回のnoteでは、ライター周りの実情に鑑み、特別な条項のある契約書は結ばれていないものとします。契約書は存在しないか、またはせいぜい定型的な契約書のみであるという想定です。
責任の所在が明らかと思われる例
明らかにライター責任と思われる場合
「画像選定あり」の案件の中には、特に選定するためのサイト等を示さず、問題のない範囲で選んでくださいとするものがあります。
このような場合に、ライターが自由に選んだ画像やそのライターによる提示方法(禁止されている改変をしたなど)が著作権を侵害していた場合、ライター側は一定の責任を負う可能性が高いです。
ライターが契約に基づいて完成させたものを納品する際には、一般的な理解として、「法的に問題のないものを納品する」は含まれていると考えられます。したがって、十分な成果物を納品できなかった=契約違反に当たると思われます。
被侵害者が侵害に気が付いたときには、発注者であるサイト運営者に連絡をし、損害賠償の請求や裁判を起こすなどの行動に至ると思います。
この際、発注者⇔被侵害者の関係では、発注者が自分の名前で出していた記事に侵害があったということで、たとえ外注によって作成していても確認を怠った点から、損害賠償責任を負う可能性は高いです。
一方、発注者は、ライターが法令に違反する画像選定をしたことで、「おまえのせいで損害賠償責任を負うという損害を被ったので、賠償をしろ」と言うことができそうです。したがって、発注者⇔ライター間で、ライターに責任が発生します。
また、ライター⇔被侵害者間においても、発注者が「画像を選んだのはライターであるからそちらに請求するように」と主張したとして、被侵害者がライターのほうに来たら、結果的にはライターが直接的に責任を負う羽目になる可能性はあると見られます。本来、直接の相手方は発注者であると思いますが、自由意志で画像を選んだ以上、ライターに直接来られた場合に「私ではなく発注者に請求してくれ」と言える根拠は少ないです。
なお、ライターの情報を発注者が提供したことや、発注者がきちんと確認をしなかったことについては、この場合にはライター側から発注者に対して、何らかの訴えや交渉をできる可能性は残ります。
明らかに発注者責任と思われる場合
画像選定先を指定されていたかいないかにかかわらず、ライター側が納品する際には引用のルールを守っていたが、発注者がサイトに掲載するまでの間に出典記載を削除するなどの行為をし、その結果として著作権侵害に至った場合も、分かりやすいです。ライターの作業後、リリースまでの発注者側の作業が問題であれば、その問題は明らかに発注者側に起因するので、発注者のみが責任を負うことになります。
問題となり得るのは、発注者側がライターに責任を押し付けようとしてきたときに、ライター側が問題のない納品をしたことをどのように立証するかです。
納品時点での原稿の下書きやキャプチャを一定期間保存しておくなど、目に見える形で「自分に責任がないこと」を残しておく必要があるでしょう。
一部責任を負う可能性がある例
発注者が指定した画像選定サイトが問題だった場合
発注者が「このサイトから画像を選定してください」と指定し、ライターがその中から画像を選んだ場合、このサイト指定は民法上の「注文者の供した材料」なのではないかと思われます。
第六百三十六条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
このため、指定されたサイトが商用利用不可の画像サイトであった場合など、サイトの指定そのものに問題があった場合で、ライター側もそれに気が付かないままで選定、納品したときは、ライターは発注者に対してその点の責任を負わないことになります。
ライターが「本当はダメなんだけどなあ」と気が付いていた場合は別です。
もし指定されたサイトの利用に問題があるかもしれないと思ったら、とりあえずメールなど記録の残る方法で相手に知らせることです。
と、ここまでは明確なのですが、ではこの場合に、何らかの理由で画像選定をしたライターに気が付いた被侵害者が、直接ライターに対して訴えてきた場合はどうなるのでしょうか。
民法上の規定はあくまでも発注者⇔ライター間での責任範囲を定めるもので、ライター⇔被侵害者間での責任関係については定めていません。
おそらくですが、発注者が指定していた以上、ライターが全部の責任を負うことはないと思います。しかし、問題に気が付かなかったことについて、一部の責任を負わされる可能性はある、と言えるのではないかと思います。
ウェブ記事のライティングとして受注している時点で公開されることは想定されますし、おそらく商用利用だろうというのも想定はできるはずなので、商用利用不可などの違反については、指示をそのまま受け入れて気が付かなかったことが「過失=ミス」とされる可能性が高いです。
契約が準委任であった場合
ここまで、業務委託契約が請負であることを前提にしてきました。
業務委託契約には類型が2つあり、請負とは仕事の完成を約束するもの、準委任はある行為をする約束をするもの、とされています。
ライティング案件でざっくり言うと、記事を作成して納品すると報酬が発生するというのが請負で、作業時間に応じた報酬が払われるものなどは準委任です。
準委任契約では、「善管注意義務」が自動的に発生します。善管注意義務は「善良なる管理者の注意義務」のことで、一般的な注意よりも厳しい注意を求める義務です。
このため、ライター側の確認不足などで著作権侵害に気づかず作業をした場合に、その過失について、請負契約の場合よりも厳しく問われる可能性があります。
ただし、準委任契約では成果物の契約適合性については問われないため、成果物自体が著作権侵害であるかどうかよりも、選定プロセスにおいて侵害にならないように十分に注意をしたかという観点が問題になりそうです。
引用として認められるかどうかが微妙である場合
ここまでは、指定されたサイトの利用規約に商用利用不可が記載されている場合や、フリーで利用できるとは思われないサイトの画像を引用記載なしで使用する指示の場合など、「知識がありよく気を付けていれば、ライター側で明確に侵害に気が付くことができる」パターンを想定してきました。
しかし、知財関連法は複雑で、個別の事例にあたって侵害かどうかが判別しにくいこともあります。たとえば、「引用」をするには単に引用元を示すだけでは足りず、引用部分が大半を占めていないことや、引用の必然性があることも、適切な引用となるために必要な条件とされています。特にウェブライティング案件では、昨今は見出しごとに画像を挿入させるなどやたらと画像を多用する事例が多く、この「必然性」の観点で問題がないかどうか微妙な場合も多いように感じられます。
画像選定を指示した発注者も、実際に選定を行ったライターも「適切な引用」であると信じて行ったのち、著作権者が裁判を起こし、結果として適切な引用ではなかったとされた場合に、ライターが責任を負うのかどうかが問題となります。
この点に関しては、ドンピシャの判例を見つけることができませんでしたが、やや近いような判例があります。
この判例によれば、サイトの記事の全部を管理・投稿していない場合でも、問い合わせの対応ドメインやサイト運営への関与などの点で管理者としての立場であったとすれば、記事の画像の著作権侵害について責任を負うとされました。
判例はあくまでも運営者であるかどうかが問われた例ですが、実際に関与できたかどうかが問われるという点でいけば、画像を選定したライターがどの程度の権限を持ち、その画像の利用方法(実際の記事での提示方法)についてどの程度知っていたかなど、具体的な状況が問われることになりそうです。
ライターが2次下請以下である場合
さて、最初に断ったとおり、ここまではあくまでもサイト運営者である発注者がライターに依頼する構造を想定してきました。
最後に、2次下請以下が存在している、もっと複雑な場合についても想定してみたいと思います。

まず、サイトの運営者Aが、外注先Bに対して「記事を納品してほしい」と依頼します。
Bは、ライターCに対して、実際の記事の作成と画像の選定を依頼します。

この際、Aが具体的な画像選定先を指定していたときや、Cが自由な意思で問題の画像を選んできた場合は、これまで解説してきた事例と類似になります。
それ以外の事例としては、何種類かのパターンが考えられます。
(1)Aは具体的な記事の内容・方法等について指示をしておらず、外注先であるBが独自に「このサイトの画像を使ってほしい」などの指定をCに対してしていて、そのサイトの画像の使用が規約違反であった場合。
(2)Aが指定した内容や方法で画像選定上の侵害が発生することが予期できたが、Bがそれについて異議を唱えないままCに依頼し、Cもまた意義を唱えずに選定した結果、侵害が発生した場合。
(3)Aが指定した内容や方法では侵害が必ず発生するとまでは予期できなかったが、Bがその解釈をする段階で侵害が発生する内容に読み替えてCに発注し、Cが指示どおりにした結果、侵害が発生した場合。
(4)A~Cのどの主体も侵害が発生することを予期はできなかったが、結果的に侵害が発生した場合。たとえば、A、またはAとBは適切な引用を想定していたが、1次または2次の下請の伝言ゲームと実際の作成の中で適切な引用から外れるような画像選定が行われた。しかし、下請による選定画像の著作権侵害は、Aが最終的にどのような形で運用するかを知らなかったために起きたものである。
いずれの場合でも、運営者Aは、納品された記事をきちんと確認しなかった点で、著作権者に対して責任を負い得ます。また、B・Cが問題があることに気が付いていたのに伝えなかった場合には、それぞれ自分に対する発注者A・Bに責任を負います。気が付いていなかった場合や、伝えたのに指示が変わらなかった場合には、B・Cはそれぞれ自分に対する発注者に責任を負いません。
一方、この下請け構造を知った著作権者が、B・Cに直接、賠償請求や訴訟をしてきた場合、B・Cが著作権者に直接の責任をどの程度負うかは、Aが構想している記事の内容・形態をどの程度具体的に予測できていたのか、著作権侵害を予測できた可能性がどの程度あったか等、個別の事情によることになりそうです。
下請関係が増えれば増えるほど、伝言ゲーム状態も増えますし、末端の人がよく知らないことも増えてきます。ただ、何も知らなかったということを証明するのはなかなか困難です。具体的にどのような指示がされていたのかなど、一定期間保存しておくことで、証拠として利用できる可能性が出てきます。
ライターが危険を避けるために気を付けたいこと
ライターにとって画像選定は副次的な(おまけの)業務なので、意識もそぞろに適当に行っている人もいるかもしれません。
しかし、本当にトラブルになりかねないのは、コピペなどが厳しくチェックされがちな文章よりも、軽いノリで多用されている画像のほうです。
そこで、ライターが画像選定を含む業務を受注するときには、以下のようなことに気を付けておくと良いと思います。
特に指定がない場合は、商用利用も可能なフリー素材のみで対応し、利用したサイトの名称や規約について報連相を行う。
指定された特定のサイトがある場合は、まず利用方法についてのページを確認する(規約を全部読まなくても、画像提供サイトであれば「利用について」などのページが用意されていることが多い)。問題があるときはメールなど記録が残る方法で伝える。
公式サイトや旅行サイトなど、画像提供に特化していないサイトを指定されたときは、引用元の記載をしっかりした上、コピーを保存するなど証拠を残しておく。また、記事の中での必然性を持たせるようにライティング段階で心がけ、発注者の構成上どうしても必然性が薄いなど問題がありそうなときは、メール等の記録が残る方法で伝える。
やばそうな発注者とは距離を取り、受注しない。
指示の内容、契約書など、明文でやり取りした内容は一定期間保存しておく。
もし発注者が海外の場合は、業務がどこの法令に従って行われるのか、万が一の場合の責任を誰が取るのかなど、不安なことはとりあえず聞いておきましょう。海外企業は、日本企業に比べてこのような直球の質問にも気を悪くすることは少ないです。むしろ聞かない=同意と思われることもあるので、積極的に聞きましょう。
ちなみに、ライターが著作権を放棄する約束をしていたとしても、著作権の放棄は「権利を行使しない」という約束でしかなく、実際に作業をした事実が取り消されるわけではありません。権利を放棄したから責任を負わないというわけではないので、そこは気を付けておきましょう。
発注者側が気を付けなければいけないこと
ライター側が災難を避けるのと同じくらい、発注者側だって訴えられたくはありません。
引用の条件や方法について、少しでも勉強しておくこと。外注しているから知らないでは済みません。
外注先から納品された記事は必ず自ら確認し、責任を持てる状態にすること。
外注先とのコミュニケーションを密にして、的確な指示を行うようにすること。
指示の内容が記録に残るよう、メールやチャット、各種のシステム等を活用すること。
万が一に備えて
気を付けてかかわっていれば、実際に自分が責任を負う事態になる可能性はかなり低くできます。
しかも、ウェブ記事が大量に出ていて、大量の画像がそこに使われている現在、よほど悪質な事例でなければ、実際に訴えられたり賠償を請求されたりする可能性はそれほど高くはありません。まして、著作権者が下請ライターのもとに直接来ることは、非常にまれとは思われます。
それでも発注者からの賠償請求も含め、理屈の上であり得なくはない以上、ライターとして「明日は我が身」には変わりありません。
万が一トラブルが実際に起きてしまったときには、頼りになるのは弁護士さんです。
損害賠償への備えや弁護士さんのことも、保険の活用や日ごろからの付き合いを通じて培っておければ、より良いと言えるでしょう。
最後に
このnoteのカバー画像は専用のフリーライブラリ「みんなのフォトギャラリー」からお借りし、説明用の画像はcanvaといらすとやで自作しています。
私の勉強不足の点もあると思いますので、このnoteの中で私が推測で述べている内容について、具体的な判例・事例などをご存じの方がいらっしゃいましたら、コメントにてお寄せください。
また、このnoteの内容だけを根拠に無謀な行動をとるのはおやめください。このnoteはあくまでも「危ない橋を渡らないため」に書かれたものであって、危険すれすれをすり抜けるためのものではありません。新しい裁判例や法改正で内容が変わっている可能性もゼロではありませんし、個別の状況によって結論が変わることもあります。実際の状況で迷いが生じたときは、ぜひ専門家を頼って、具体的な状況を説明して回答を仰いでください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

