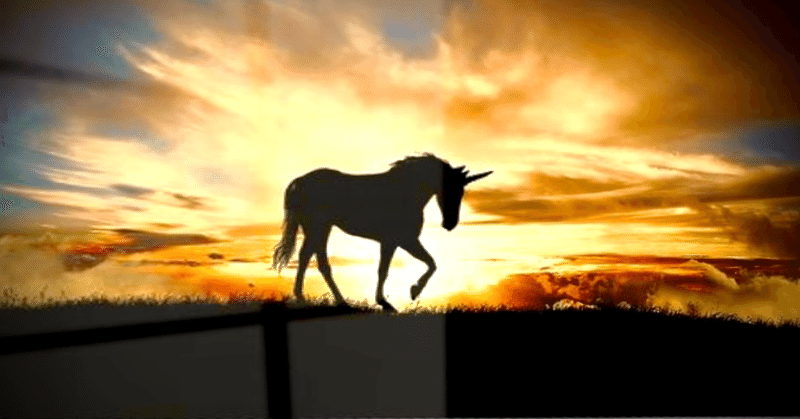
#創作大賞2023 「ロング・キャトル・ドライヴ 第一章 "ユニコーン編"

1893年 アメリカ東海岸
ボルチモア 〜 ガットリンバーグ
〜°〜°〜°〜°〜°〜°〜°〜°〜°〜°〜°〜
一、邂逅
1893年 米国メリーランド州
ボルチモア
俺の名前は
フェルディナンド・ランスキー
俺が
ユーレク・ボリセヴィチと知り合ったのは
ある出来事がキッカケだった。
17歳になったばかりの頃
港湾で働いていたユーレクは
親父の店ランスキー商会に
奇妙な石を持ち込んできたからだ。
みずぼらしい身なりをした
ユーレクに対し、
親父は明らかに蔑んだ目で値踏みしていた。
(俺は親父のこういうところが
大嫌いだった。)
ユーレクが言うには
「船の積荷作業をしていると、
船底に拳くらいの石つぶてが
ゴロっと落ちていた__ 。」
のだそうだ。
親父が鑑定した内容は
「これはガーネットだな。
しかし原石だから価値は乏しい。」
ユーレクは黙って聴いていたが、
内心は甘く見られていることに
勘づいていた。
原石の一部から露出している
煌びやかな箇所がある。
この鑑定士の前では
原石は紅い色を発していた。
(俺が日中に見たときは深い碧緑に見えた。
だか、この鉱石はどうだ?
今は燃えるような紅色を発している。)
(これはきっとすごい代物に違いない__。)
「で?いくらで引き取ってくれるんだい?」
とユーレクが訊ねる。
親父は、一瞬考えこんだ素振りを見せ
「ま、1ポンド45ペンスってところだな。」
※1890年代当時で約7万円程度
(この若造なら飛びつくだろうよ。)
と、たかをくくっていた。
ユーレクは微笑んだかと思うと
(この宝石商はかなり低く見積もっている。)
と悟り、
「ありがとう!
こいつはそんなに価値があるんだな?」
と言って、鑑定に出した石を
ササッと懐にしまいこんだ。
親父はユーレクが意外にも
飛びついてこないところを見て、
「坊や__ いいのかい?
至って良心的な見積りと思うがね?」
と親父は駆け引きをする。
ユーレクは
「またの機会にするぜ。オッサン」
と言ってテーブルを後にする。
親父は一瞬、気色ばんだが、
平静を装い
「あゝ またな。」とだけ応えた。
親父はユーレクが店を出ていくのを見届けると
「ちぇっ、ちぇっ、ちぇっ
あのガキめ!」
と舌打ちをして罵っている。
(親父が強欲ばりだからだよ。
それにしても、あのユーレクって奴
なかなかやるじゃないか!)
と俺は内心思っていた。
最初に出会った時のユーレクの印象は
物事に動じないナイスガイだなと
俺は彼に好感を持ったのだった。
・
・
・
・
俺は常に街のチンピラに狙われていた。
親父自身は商売が繁殖していることもあって、
地元では名も通り羽振りが良かった。
その息子である俺は格好の
金蔓に見えたに違いない。
ある日のこと、
ボルチモアのウォーターフロント近くで
数人の不良に囲まれてしまった。
「おとなしく金を出しな。」
リーダー格と思われる少年が
あらぬ因縁をつけてきた。
相手は4人いる。
まずは勝ち目が無さそうだ。
しかし、生来勝ち気な俺は
泣き寝入りすることを潔しとしなかった。
俺は驚いて尻もちをついたフリをする。
奴らは無様な俺の姿を見て嘲笑った。
「判ったよ。金を払うから勘弁してくれ。」
俺が懐から財布を取り出した瞬間
奴らは凝視する。
その刹那__
握りしめた道端の砂を奴らの顔面にめがけ
投げつけてやった。
「や、やりやがったな!」
奴らが怯んだ隙に俺は逃げ出す。
曲がりくねった路地や
塀をよじ登り、時には屋根づたいに
逃亡する。
奴らも追ってくる。
(しつこい野郎たちだ。)
やがて、逃げこんだ先の路地で
大きなリヤカーに荷物を積んで曳いている
少年がいた。
親父の店に来たユーレクだった__。
「事情は後で話すから、かくまってくれ!」
そういって俺はユーレクのリヤカーの
荷物の間に身を潜めた。
ユーレクは何も言わずに
身を潜めた俺の頭の上に
大きな空のバケツを被せてくれた。
追手が辿り着く。
「おい!さっきこの辺りに人が
通らなかったか?」
と訊ねる。
ユーレクは返事をしていないようだ。
「おい!お前?耳が聞こえないってのか?」と奴らのたれかが尋問する。
「. . . . . 。」
ユーレクは押し黙ったまゝのようだった。
「ちょっと、リヤカーの荷物を調べさせてもらうぜ。」
と声が聞こえた。
緊張がはしる__。
俺は目を瞑って祈ることしか出来なかった。
二、旅立ち
ユーレクは初めて声を発した。
「ここには俺の商売道具が入ってる。
だが指一本触れてみろ容赦はしないぞ。」
そう言うなり、リーダー格と思しき男の
胸ぐらを掴み、片手で軽々と持ち上げる。
圧倒的な力だった。
ユーレクは続ける。
「何のことか知らねえが、この界隈で
問題を起こすなら、俺が相手してやる。」
リーダー格の男は持ち上げられたまゝ
「は. . . 離せ. . . 苦しい. . . 。」
と呻いている。
その時だった。
警察官が巡回してきた。
「よぉ!ユーレクじゃないか。
どうしたんだい?そいつらは?」
ユーレクに持ち上げられた以外の連中は
散り散りになって、その場から逃げた。
ユーレクは男をゆっくりと下ろし、
「お前さんの探している奴さんは
ここに居るぜ。」
と言って、俺の頭に被せていたバケツを
取り上げた。
「で、こいつに何の用があるんだ?」とユーレクは男に訊ねる。
「な、何もねえよ。」と言い、
男はそそくさと退散するのだった。
・
・
・
・
「ありがとう!助かったよ。
俺の名前はフェルディナンド。
あんたの名前は?」
「俺はユーレクだ。って知ってるよな?
会うのは二度目だもんな。」
ユーレクと顔見知りの中年の警官は
キーンと言った。
「わしは、ユーレクの近くに住んでるのさ。」
と強いアイルランド訛りで云った。
「キーンさん。今日は助けて下さって
ありがとう!」
と俺は礼を云った。
「いやなに。大したことしてないさ。
お前さんも災難だったな。
ここら辺は、ああいった連中の巣窟さ。
だかな、このユーレクは苦労人のイイ奴さ。」
と云ってユーレクの肩をポンと叩いた。
ユーレクは
「そうだ。お前に相談したいことがある。
宝石商の倅せがれなら何か
解らないか?」
と云って懐からあの石を取り出した。
「あっ!あの例の紅色のヤツか?」
と訊ねると
「そうなんだ。実に不思議じゃないか?」
とユーレクは嬉々として碧緑色をした
不思議な石を眺めている。
「多分だけど. . . アレキサンドライトだね。」
と俺は答えた。
「ウチの親父も知ってたはずだ。
そいつはとても希少な宝石なんだ。
ガーネットじゃねえよ。そいつは。」
ユーレクはフフと笑って
「お前の親父さんにすんでのところで
安値に叩かれちまいそうだったぜ。」
アレキサンドライト__
近年、ウラル山脈で発見された
色が変化する宝石で、
皇太子の名前にちなむ。
「しかし、これほどの色変化するのは
お目にかかったことないぜ。」
と俺はユーレクの持っている石を
しげしげと眺めながら、
「どうだ?そいつは磨きをかけりゃ
超一級品の宝石になるぜ。
メキシコ国境付近のツーソンって街に
最高の研磨職人がいるんだが。」
とおよそ俺が知っている限りの情報を伝えた。
しかし、遠路で2300マイルある。
幌馬車で40日くらいは掛かる見込みだ。
ユーレクは少し考え込んだ素振りを見せたが
「ちょっと俺の家に寄ってくれないか?」
と言った。
「あゝ、いいとも」と即答した。
・
・
・
・
ユーレクの家に着いた。
ユーレクの母親エリザベスが
出迎えてくれた。
「母さん、ただいま。」
「あゝ、ユーレクおかえり。
あら!そこにいるのはランスキーさんの
息子さんでないかい⁉︎
お前!いつの間にこんな立派な方と
お知り合いになったんだい?」
エリザベスは愛らしい眼を円くして驚いている。
「さあさぁ、どうぞ。こんな汚いお家ですが
くつろいで下さいな。」
と満面の笑みで迎えてくれた。
ユーレクのおふくろさんのエリザベスは
薄化粧をし、身なりを整えて
暖かい手料理を作ってくれた。
気さくで話しも面白く
屈託のない人だった。
食事にはキーンも相伴させてもらっていた。
他愛のない話しから
垣間見えたのは
リズ(エリザベスの愛称)やユーレク、
そしてキーンの家族も
敬虔なカトリック教徒だった。
彼らは日曜日になっては
教会で祈りを捧げる。
心底、神を畏れ、健気に生きている
善良な心の持ち主だった。
(この世に、こんな健気な人達が居るんだ。)
俺はユーレクが羨ましく思えた。
・
・
・
・
リズは女手ひとつでユーレクを育てた。
リズはウォーターフロント近くの
貧相なスラム街に居を構えている
売春宿で働いていた。
港にやって来る船員相手に
リズは懸命に奉仕をして
爪の先を灯すように暮らしぶり
を支えていた。
そんな環境もあって
ユーレクは6歳の頃には
既に牛乳配達をしていたと云ふ。
まだ幼かったユーレクは
重い牛乳瓶の詰まった自転車を
その小さな躰で必死に押していた。
時に街に出ると、
心ない少年たちがユーレクに
罵声を浴びせかける。
「お前の母ちゃん、デ・べ・ソ」
ユーレクは悔し涙に暮れながらも
グッとガマンをしていた。
(ボクの母ちゃんはボクが守るから。)
ユーレクとはそういう少年だった。
ユーレクの目下の夢は__
「この不思議な石を研磨して、
おふくろにイイ暮らしさせてやりてえな。」とツーソンへの旅を夢見ていた。
そう。彼は常に利他の心を持っていた。
・
・
・
・
リズは少し遠くを見つめて
「ユーレク?お前はアタシの誇りだよ。
ランスキーさんとお行きなさい。
若い内に広い世界を観るんだよ。」
キーンのおやっさんも頷いて
「リズの言う通りだ。ユーレク、
留守は任せておいてくれよ。」
「決まりだ!ユーレク。
俺とお前でロング・キャトル・ドライヴ
に出発だ!」
と俺は促すと
ユーレクは涙を流していた__ 。
三、グリズリーの親子
俺たち2人は生まれ育った
ボルチモアから出発する。
俺は親父には、「しばらく旅に出る。」
とだけ云った。
家の女中に頼みこんで
幌馬車や旅支度の一切を段取りした。
旅の無事を祈るために
俺とユーレクはリズとキーンの四人で
教会に向かう。
教会で祈りを終えた後、
リズはユーレクに銀のロケットを渡した。
「神のご加護があらんことを__ 。」
ユーレクとリズにとっては
生まれて初めての惜別の時だった。
心静かに別れを惜しむ。
「元気でねー!」
リズは手を振って見送ってくれた。
キーンは教会の鐘を鳴らして
旅立ちを祝ってくれた。
幌馬車が動き出しても、俺たちは
いつまでも手を振り続けていた__ 。
・
・
・
・
俺とユーレクの共通点と言えば
ルーツがポーランドからの移民だった。
俺の親父は大酒呑みであった。
おふくろは早くに亡くなっていて
豪放磊落ごうほうらいらくな親父は若いメイド達に
手を付けては色欲沙汰が止むことがなかった。
しかしながら、
親父は商売上手で名が通っており
ヨーロッパから運びこまれた宝石を
街中の金持ちに売り付けていた。
親父の鑑定眼は確かだったようで
ロードアイランドに別荘を持つ
セレブ達にも注文があったほどだ。
俺と言えば、
経済的には何の気苦労もなかったが
およそ母親と云ふものを知らず
親父の手付けのメイドが義務として
情と云ふものを感じられることもなく、
無味乾燥に育てられた。
ガキのころから勝ち気で
生意気だったこともあり、
いつも親父からの仕置きで
生傷の絶えない少年だった。
誰も俺のことを愛してくれなかった。
いつか家出をしたいと感じていた。
そう__。
俺は、愛情に飢えていたのだ。
それに比べると、
ユーレクの家は貧乏ではあったが、
神を信じ、素朴だか愛に溢れている。
俺にはない、彼の持つ人間性に、
俺は惹かれていたのかも知れない。
・
・
・
・
俺たちはまるで違う境遇で育ったがウマが合った。
ボルチモアでの生活から一転し、
心が解放されたかのようだった。
俺は御者台で馬車を操り、
ユーレクは馬に跨って進む。
見晴らしの良い景色を眺め、
心地良い風に吹かれるように。
道中はお互いの想いを腹臓ふくぞうなく語り合った。
アパラチア山脈の峠を越える道中、酷い雨に見舞われた。
このまま旅を進めるには
天候も厳しそうだった。
「ユーレク!今日はこの辺りで
一息ついた方が賢明だな?」
と御者台から声を掛けた。
ユーレクは馬上でテンガロン・ハットから雨を滴らせながら
しかめっ面をして頷いた。
「あゝそうだな、フェルニー!
ここいらで休むとしよう。」
空き家となっている掘立て小屋に
風雨を凌ぐため雨宿りした。
びしょ濡れになった俺たちは
馬たちを休ませるために
馬房に繋ぎ留めた。
俺たちはすっかりと
躰が冷えきっていたので
温かい食事を摂ろうと
軒下で薪を焚いてチリコンカン※を作った。
※豆、野菜、肉の煮物
俺とユーレクは
温かいチリを頬張りながら
旅の疲れを癒し、暖をとった。
ミルで豆を挽き
薄めのコーヒーを淹れて
ようやく一息ついた。
マグカップから
ほのかな湯気が立ち込める。
湯気ごしの向こう側に居る
ユーレクは帽子を目深に被り、
眠りについているようだ。
いつしか俺も
毛布に包まり目を閉じた。
・
・
・
・
「起きろ!」
ユーレクが鋭く低い声を発した。
小屋の外で物音が聞こえる。
「たれか居る. . . ⁉︎」
どれくらい眠っていたのだろうか?
辺りはすっかりと夕闇が落ちていた。
俺とユーレクは目を見合わせて
息を潜め、用心深く窓の外を見る。
暗がりの中で何かが蠢うごめいている。
雲間から月明かりが照らした時、
そこに居たのは手負いの子熊だった。
かなり弱っていたので、近づいてみると
身体のそこいら中が爪で引っ掻いたような
傷があった。
グリズリー《ハイイログマ》の習性は
子熊は通常は母熊と群れを為している。
オスの熊は一切面倒を見ないどころか、
時に子熊を襲うことだってあると云ふ。
この子熊もどうやら父熊に襲われたのだろうか?
俺はこの子熊に自分の境遇が重ねて見える。
「なぁ、ユーレク?この子熊. . . 手当をして
やりたいんだけど。」
と俺は云ふ。
ユーレクは少し黙って考え込んだが、
「わかった。ただ親熊が来るかも知れない。」
掘立て小屋の少し離れた所に
犬小屋のような小さな小屋を拵えて
子熊が回復するまでの間、
エサを与えることにした。
グリズリーは人間と同じ雑食性だ。
俺たちの食事を少しずつ残して、
子熊に与えると、
余程、腹が空いていたのかペロリと平らげた。
子熊は3日もすると、すっかり元気になった。
子熊は俺たちにすっかりなついていた。
しかし、いつまでもここに居るわけには
いかない。
「ユーレク?
俺のわがままを聴いてくれてありがとう。」
子熊も元気になったこともあり、
明日の朝に出発することを決めた。
・
・
・
・
翌朝、目を覚ますと
子熊は居なくなっていた。
最後のエサをやろうとしたが、
子熊の方から自然へと還っていったのか。
ユーレクは俺の肩をポンと叩き
「フェルニー。行こうか?」
と澄んだ瞳で俺を促した。
「あゝ、では出発だ!」
俺たちは、ピッツバーグに向けて
幌馬車を走らせた。
その時、馬上からユーレクが
「フェルニー!あすこを見ろ!」
と叫んだ。
あの子熊と母熊が
草原の向こうで佇んで、こちらを見ていた。
「フェルニー!きっとお前に礼を
言いに来たんだよ!」
と御者台の俺に向かってウインクをした。
俺は
「まるで、リズとユーレクみたいだな!」
と、皮肉交じりにからかって見せた。
「アハハハ!」
俺たちの笑い声が
アパラチアの風と共に響いていた。
幌馬車は次の目的地、ピッツバーグを目指す。
グリズリーの親子たちは
俺たちの姿が見えなくなるまで
いつまでも佇んでいた__。
四、合流する夢
俺たちは、
ペンシルベニア州にある
ピッツバーグの街に到着した。
街の中心部には大きな二つの河川が流れ、
夕暮れ時には黄昏に染まる河川に
三角州の街並みが浮かぶようで印象的だった。
ピッツバーグの街は独立戦争の後、
急速に発展した。
幾つもの工場が林立し、
モクモクと煙突から煙を吐いている。
時代はまさに変わろうとしていた。
ゴールドラッシュの熱狂は収まり
鉄鋼業へと技術革新が進もうとしていた。
ピッツバーグの街にはヨーロッパから
たくさんの入植者が新天地を求めて
夢を追って集まってきている。
ダウンタウンの街は活気付いていた。
停泊するための馬宿が整備されており、
レストランやバー、ダンスホールもあった。
俺は旅に出る前、
親父が溜め込んでいたヘソクリから
ソヴリン金貨を5枚無心していた。(現在の価値で約27万円)
俺は、親父のヘソクリ金貨を
"LIFE"と名付けていた。
「なぁ、ユーレク。ここで一つ
"LIFE"を使ってご馳走を食べないか?」
と俺は提案した。
ユーレクは
「長い旅だから、無駄遣いはよそうぜ?」と言った途端、
「キュー」とユーレクのお腹が鳴った。
「アハハ!お腹は正直だな。
俺に任せとけって。
街中以外では"LIFE"の使い途もないし、
小銭に崩しとこうぜ。」
街の中心部である
メキシコ戦争通りと云ふ名の
メインストリート沿いにある
馬宿に泊まることに決めた。
カウンターの呼び鈴を押すと、
奥からは、厳つい面構えの主人が
出てきて、
「今夜はここで泊まるのかい?」と怪訝そうな顔で訊ねる。
「いくらだい?」と訊いた。
「一人、14ペンスだ。」と主人は云ふ。
俺はソブリン金貨を一つ取り出して
手渡すと、
宿の主人は目を丸くして姿勢を正し
「ピッツバーグの街へ、ようこそ!」
と、丁重に案内してくれた。
俺は内心
(まったく世の中、現金な奴ばかりだな。)
と思っていると、
宿の主人の態度の豹変ぶりを見て、心なしかユーレクはクスッと笑っていた。
・
・
・
・
俺たちは部屋に着いて旅塵を落とし、
新しい服に着替えてから、夕食を共にした。
大きなステーキと山盛りのフレンチフライを
頬張ることで、ようやくお腹も満たされた。
この馬宿にはバーがあり、俺もユーレクも
お酒を飲んだことがなかった。
好奇心と云ふものは際限がない__。
「どうだ?バーに行ってみないか?」とユーレクに訊くと、
ユーレクは
「そうだな。ものは試しに行ってみるか!」
と云って親指をグッと突き立てた。
俺たちはカウンターに座ると、
「何をお飲みになりますか?」
バーテンダーが訊いた。
俺は生まれて初めてビールを注文した。
冷えた銅製のジョッキに注がれて
泡立っている。
一口飲むと、経験したことのないビールは
とても苦かった。
「おぇぇぇっ! ぺっぺっ!
これが大人の味なのか?
不味すぎるぞ!」
と経験のない味に悶絶していた。
バーテンダーは笑いながら、
「その苦味が解るようになれば大人になった
証でございます。」
「お連れの方は何になさいますか?」
ユーレクは俺の様子を見て
「ミルク. . . 。」を注文した。
(ユーレクの裏切り者め!)
あまりのビールの不味さに
俺は後悔していた。
すると、そのやりとりを横目で観ていた一人の若者が声をかけてきた。
歳のころは20歳くらいだろうか。
「お前ら面白いな!俺の名前は、マイケル
よろしくな。」
マイケルは西部で生まれ育ちカウボーイを
目指したものの
パシフィック鉄道が開通し、カウボーイの
仕事そのものが無くなったため、
新たにこの界隈の工場で働き始めたと云ふ。
「これからは鋼の時代だぜ!」が
マイケルの口癖だった。
「ところで、お前さん達の夢は何だい?」とマイケルが訊ねる。
(俺自身の夢って、何だろう?)
俺は何も答えられなかった。
ユーレクはじっと考えこんでいたが、
「俺はフェルニーと一緒に
大切な探しものを見つけるために
西部のある街に行くんだ。」
とだけ言った。
マイケルはうなづいて
「お前たちは良いバディ同志だ。
この先の旅の幸運を祈るぜ。」
次の目的地は
セントルイスかナッシュビル
どちらを経由するか?
マイケルのアドバイスによると、
「装備を充実させる」には
セントルイスが良いと云ふ。
「だかな、人間は選択を迷う時もある。
そんな時はこうするんだ。」
マイケルは
コイントスをやってみせる。
「流れに任せることも必要なのさ。そういうものなんだよ。人生ってヤツは。」
俺たちは明日の出発に備えて
眠りに着くことにした
・
・
・
・
あくる朝、ユーレクは少し散歩に行こうかと
誘ってきた。
俺とユーレクは小高い丘へと登り、
ダウンタウンの街全体を見渡す。
「なかなか見晴らしが良いな。」
と云ってユーレクは懐から後生大事に
不思議な石を取り出して風景の光を受けて輝く
色変化をしげしげと眺めていた。
(あいつには確かな夢がある__ 。)
それに比べて俺はどうだ?
俺が旅に出たのは、ボルチモアでは
居場所がなかったからだ。
常に金持ちの息子として、嫉妬の対象として
町の不良からは目をつけられていたし、
我が家に居ても、およそ愛情からは程遠く
子供の時から振り返ってみると
たれにも存在を認めてもらえない
透明人間のようだった。
そんな現実から逃げ出したかったのだ。
ネガティブな理由に端を発し
ユーレクやマイケルのように
自主的な意志がある人間とは違って、
俺は常に漠然とした不安に苛まれていた。
(生まれ変わりたい. . . 。)
そんな物思いに耽っていると、
ユーレクが声を掛けてきた。
「なぁ?フェルニー。この二つの川は
俺とお前みたいだと思わないか。
それぞれ考えは違ってても良いんじゃないか?
だけど川はひとつに合流するんだよ。
そして生きるための水沫が生じるんだ。
つまりは、お前の夢ってのは、
俺の見る夢と同じなんだよな。
きっと__。」とユーレクは微笑んだ。
昨夜のマイケルの問いに答えられなかった俺に
ここに連れてきて言いたかった意味を
ユーレクなりに伝えたかったのだろう。
(ユーレク。お前って奴は. . . 。)
俺の中にあるモヤモヤしたものが
少し晴れたような気がした。
人生の合流地点に
俺たちは今、居るのかも知れない。
五、ユニコーンの夢
セントルイスへと向かう途中、
イリノイ州スプリングフィールドで
俺たちは野営することに決めた。
二人での旅もようやく慣れてきた。
焚き火を囲みながら
広い草むらで大の字になって寝転がってみる。
満点の星空を眺めていると、
まるで星が降ってくるかのようで、
気分が良い。
少し離れた所に
エイブラハム・リンカーンの墓地が
あり、
高く聳え立つオベリスク《石碑》が
見える。
「人民の、人民による、人民のための政治」
俺たちが生まれる以前__
このアメリカを形づくるために
内戦で多くの犠牲をはらって血を流した。
歴史とはそのような過去の上に
成り立っている。
今、こうやって俺たちが旅に出られるのは
まこと幸福な時代と言えるのかも知れない。
そんなことを考えている内に
俺たちはウトウトと眠りに着いた。
・
・
・
・
夜明け前に目を覚ますと
東の地平線が白々と薄明を照らしていた。
ユーレクは既に起きていた。
目覚ましに熱いコーヒーを淹れてくれた。
ユーレクは神妙な顔つきで
「不思議な夢を見たんだ。」と云ふ。
ユーレクは夢で見た内容を俺に語った。
どこか片田舎の風景の中にある
牧場での出来事を傍観している自分が居る。
牧場の道沿いには
ナッシュビルへの行き先を示す
標識がほんやりと見えていた。
牧柵の中に馬が群がる。
安息の地で草を食み
次の遊牧地へと秩序正しく移動する。
そして安らかに大地へと還る。
そんな安住の地に悲劇が襲う。
ある日__
獰猛なコヨーテ《ソウゲンオオカミ》
が牧柵に入ってきた。
その鋭い爪と牙を以て襲いかかり
か弱き一頭の馬は為す術もなく
餌食となった。
悲劇は繰り返す。
牧柵には無抵抗の食糧がある。と、
そんな噂を耳にした別のコヨーテ達も
次々と牧柵を乗り越えてくる。
牧柵の中の馬たちが次々と
コヨーテの餌食になっていく。
コヨーテの襲来は止むことなく続く。
逃げまどう馬の仲間の中に
或る一頭の馬の切実な願いがあった。
抵抗もなく餌食となるあわれな同胞を見て
「強くありたい。」と願った。
すると彼の頭には、
一夜にして巨きな角が生えた。
その鋭利な角を以て
「我が汝らを助けたもうぞ。」
と仲間を守る決意をする。
仲間の馬たちは、異形とも言える
彼の変貌ぶりに驚いていた。
しかし、状況は切迫していた。明くる日もコヨーテの群れは
牧柵を越えてやってくる。
彼は仲間を守る一心で
闘いを挑む決意であった。
巨きな角でコヨーテ達を串刺しにして
なんと退けてみせたのだ。
仲間たちは彼の変貌ぶりに驚きつゝも
コヨーテの脅威から守ってくれる
頼もしさを受け入れた。
形勢は逆転した。
角が生えた異形の馬は
コヨーテと闘い続けた結果、
やがてコヨーテの群れは
襲いに来なくなったのだった。
牧柵の中に平和が訪れた。
しかし、異形の彼は
その巨きな角が"異端"扱いされてしまう。
やがて彼の周りには、
たれも近づかなくなった。
巨きな角を持つ馬、すなわち
ユニコーンは
二度とみんなの前には
姿を現さなくなった__。
・
・
・
・
そしてユーレクが夢から目醒めると
不思議な石が
「紫がかった光を発していた。」
と云ふ。
「なぁ?フェルニー、どう思う?」
とユーレクが訊いてくる。
「エラく不思議な夢をみたんだな?
それって神の思し召しってヤツじゃない?」
と俺は信心深くはない人間だったが、
ユーレクには直感めいた感性と言うか、
旅を通して、彼の内面を知るほどに
そんな風に感じる場面が多々あった。
俺たちは、当初は
マイケルのアドバイスを受けて
セントルイスに向かう予定だった。
しかし、ユーレクが見る夢は
ナッシュビルを示唆している。
俺たちは以前のマイケルの話しを思いだした。
「なぁ?ユーレク、その夢の吉凶を
コイントスで占ってみないか?」
と俺は提案した。
ユーレクは頷きながら
「そうだな。迷った時は"運"任せだな。」
俺は懐から、ソヴリン金貨を取り出して
「女王陛下が"表"つまり吉だ。
そして盾が"裏"になるから凶だ。」
俺は金貨をユーレクに渡し、
「やってみなよ。」と促した。
ユーレクは親指で金貨を弾くと
ピーンと音が響き、クルクルと宙を回転し
ユーレクの手の甲に載った瞬間に
片方の手のひらで覆う。
「さあ、どうだ?」
ユーレクがゆっくりと手のひらを
開けると
ヴィクトリア女王の横顔の模様だった。
「"表"だ!」
「これって、やっぱり神の思し召しだよな?」
と俺が訊ねると
「妙に胸騒ぎがする。」とユーレクは云ふ。
お互いの顔を見合わせながら、
ゆっくりと頷いた。
「ナッシュビルへ!」
偶然にも同時に同じ言葉を発した。
俺たちは進路を西南西へと向けて
ナッシュビルの街を目指すことに決めた。
俺たちは馬車を走らせ次の目的地
ナッシュビルへと向かう。
旅を共にする俺たちには
前進気鋭の活力がみなぎっていた。
ユーレクの持つ石が惹き寄せる
運命の織りなす
不思議と云ふものであろうか__。
「あばよ。大統領!」
偉大なる元大統領のオベリスクが
視界から消えていく。
過去は墓碑銘となって
静かに見守っているかのように。
未来とは__
今、俺たちを縛りつけるものは何もない。
・
・
・
・
ボルチモア ランスキー邸にて
コンスタンティ・ランスキーは
息子のフェルディナンドが
突然、旅に出たことに
当初はあまり関心を示さなかった。
フェルディナンドが家出することは
過去にもしばしばあり、大抵は狂言で、
お金が切れるとすごすごと舞い戻ってくる。
そのようにタカを括っていたのだが、
ところが今回ばかりは様子が違う。
ことあるごとに反抗の姿勢を示す息子には
ほとほと手を焼いていたが、
居なければ居ないで心配であった。
コンスタンティは
ポーランドから新天地アメリカに入植した頃は
苦難の連続で、若い頃から懸命に
世間の風に吹き飛ばされまいと
歯を食いしばって生きてきた自負がある。
放蕩三昧の息子フェルディナンドは
何処へ姿を眩ましたのであろうか?
「愚かな息子め. . .。」
コンスタンティは独り言を呟き、
女中を呼ぶベルを鳴らすのだった。
六、追跡
「ご主人さま。お呼びでございますか?」
ランスキー邸のハウスキーパーである
オリヴィア・ミラーは長年にわたって、
この男に仕えている。
「フェルディナンドのことなんだが、
もうかれこれ半月ほど姿を見ない。
奴のことで知っている情報があれば、
俺に知らせるんだ。」
とコンスタンティは言い放つ。
オリヴィアは
「わかりましたわ。」
そう言って、主人の意とする旨を理解し、
踵を返すように退いていった。
コンスタンティは
オリヴィアに任せておけば
他に居る女中達の取り仕切りも厳しく管理し、
如才ない仕事をすることを知っていた。
オリヴィアは女中達を玄関ホールに呼び集め
「たれかフェルディナンドさんのことを
知っていたら教えてちょうだい!」
しかし、女中達は押し黙っていた。
オリヴィアは舐め回すように
女中達一人ひとりの顔を凝視する。
「匿っていたりしたら、解雇にするわよ!」
と語気を強める。
女中のうちの一人がワナワナと震えだす。
オリヴィアは、その女中の前で
射抜くような目つきで睨む。
「あなた?何か知っているわね。」
・
・
・
・
その頃、俺たちは
デイトナ〜シンシナティの街並みを過ぎ、
オハイオ川沿いを進んでいたが、
運悪く、川が氾濫する程の大雨に遭った。
道中、水浸しの悪路を進まざるを
得なかったせいで、
幌馬車の車輪がぬかるみに嵌まった。
ユーレクは馬上から
「おーい!フェルニー、大丈夫か?」
と心配している。
俺は手綱を振るって、馬たちを励ますが
馬たちも脚がぬかるみに取られているのか
なかなか前に進めないでいた。
俺は御者台から降りて、
「おーい!ユーレク。後ろから馬車を押すから
手綱を持っておいてくれないか?」
と声をかける。
後ろから懸命に馬車を押すがびくともしない。
「あゝ、チキショウ!
こんなところで立ち往生かよ!」
雨に打たれていることもあり、
俺は焦りと苛立ちが募る。
ユーレクが
「こいつは災難だ。フェルニー代わってみろ。
俺は六つの頃から、重い牛乳瓶を
押してたんだから。」
ユーレクは俺と交代して
後ろから馬車を押し出すと、
ジリジリと車輪が動き出す。
(すごい力だ__。)
「今だ!車輪の下に板を入れてくれ。」とユーレクが叫ぶ。
「ユーレク。合点だ!」
俺は馬車内から薄い薪の板を取り出して
車輪に噛ませると
「うぉぉぉぉぉっ!」とユーレクが
さらに気合いを入れる。
すると馬車の車輪が板の上に乗り上げた。
すかさず、俺は前方に回り込んで、
馬の手綱を引っ張り、馬を誘導すると
幌馬車はようやくぬかるみから脱出した。
しかし、これで終わったわけではない。
豪雨の中、俺たちは泥だらけになって
まるで、色のないグレーの世界を
彷徨っているようで
殺風景な道のりが続くのだった。
いつもは軽口を叩いている俺たちも、
さすがにこの状況が続くことに
辟易としていた。
お互いに無言のまゝで
どれくらい歩いたのだろう。
いつの間にかルートを見失ってしまったのか。
豪雨の中では進んでいる方向すらも覚束ない。
あたりも段々と暗くなってきた頃、おぼろげに建物が見える。
「ユーレク!何か建物があるぞ!」
生きた心地のしなかった俺は、
人間の営みを感じられることに、
ようやく元気が出てきた。
「あゝ!橋だな。あすこで少し休もう。」
とユーレクもやれやれと安堵していた。
片田舎には屋根付きの橋がある。
俺たちはそこで雨露をしのぐことにした。
「とりあえず一休みしよう。」
馬たちの手綱を橋の欄干に括り付け、
びしょ濡れになった服の水気を
雑巾搾りをしていた。
幸いにも幌馬車の中には、
少なからず着替えもあり、
乾いた服の軽やかさがこれほどまでに
有難いと思えることも、
この旅における過酷な経験と言えるだろう。
俺たちは幌の中に入り、身を寄せ合うように
横になった。
ウトウトとしていると、
ユーレクが肘鉄を突いて、唇に人差し指を当て
(静かに__)
と目で合図を送る。
すると、橋を渡ってくる何者かの
足音が近づいてくる。
俺たちは息を潜めて、キャンバス地の布に
全身を覆い隠すようにしていた。
「ハァハァ. . . たれか居るのか?」
幌の外で何者かの声がする。
その声は、嗄しわがれている老人の声に聞こえる。
「ここは天下の往来じゃ。
しかしながら、この豪雨じゃ。
致し方なかろうなぁ. . . 。」
とボソボソした声が幌の中に聞こえてきた。
その時である__ 。
何者かが覆い被さってきた。
鈍い音がしたと同時にユーレクの
呻き声が聞こえた。
(どうなってんだ?一体?)
頭に鈍い衝撃がはしった。
一瞬にして、意識が遠のいてゆく。
俺にはその後の記憶がまるでない。
・
・
・
・
舞台はボルチモアに戻る。
リズは日曜日になると、
教会に行って礼拝する。
今、生きていることへの感謝を捧げるのだ。
欠かすことのない習慣である。
そして、聖歌を歌う。
リズの心は平らかに、神への信心に満ち溢れる。
(ユーレクはきっと元気でやっている__。
あの子には随分と苦労をさせてしまったが
いつも優しい微笑みを私に与えてくれたわ。)
ユーレクはようやく人生が開かれた。
それは、モーゼが紅海を渡る際、
海が二つに分かれるように。
(偉大なる主よ。どうかユーレクに
神のみ名の下、ご加護を与え給へ、
アーメン__。)
教会には聖歌を歌うために、いつもの馴染みの
メンバーが集まるのだが、
今日は、初めて礼拝に訪れた女性が来ていた。
痩せ型の目元の涼しげな中年の女性が
聖歌を歌いに来ている馴染みの連中と
和やかにあいさつを交わしていた。
女性はリズにあいさつに来た。
リズはにこやかに自己紹介をする。
「初めまして。
エリザベス・ボリセヴィチです。」
軽く手を握って、あいさつを交わした。
女性も自己紹介をする。
「初めまして、オリヴィア・ミラーです。」
七、肝喰いクロウ
冷たい水滴が頬に当たる感覚で
俺は目を覚ました。
雨漏りのする納屋のようなところに居る。
一体、ここは何処なのだろうか?
昨夜、誰かに殴られてから
どれくらいの時間、意識を失ってたのか。
状況を把握することが出来ないでいた。
「おーぃ!ユーレク居るか?」
試しに呼んでみたものの返事がない。
(やれやれ。一体どうなっちまったんだ?)
納屋の外へと出てみると、
昨夜から降り続いた豪雨は
すっかりと晴れ上がり清々しい空気だった。
どうやら現在、此処は人里離れた
辺鄙へんぴな山奥に居てるようで、
母屋と思しき山小屋が見える。
そろりと近づいてみると、
小屋の中から人の声が聞こえてくる。
「爺さん、大丈夫か?」
と聴き覚えのある声だった。
扉を開けてみると、そこにユーレクが居た。
「ユーレク?一体どうなってるんだ?」
と訊ねると
「どうやら、俺たちはあの橋の中で
襲撃されたところを、この爺さんが
助けてくれたんだ。」
とユーレクは云ふ。
身長6フィートを超える
黒い肌をしたアフリカ系の大男で
齢60歳くらいの老人が横たわって
おり、
熱にうなされて眠りについていた。
ユーレクが云ふには
「お前がノビている間に、俺は賊と
揉み合っているところを
この爺さんが助太刀をしてくれた。」
と顛末を話してくれた。
ユーレクは
「だがな。この爺さんは賊に傷を負わされて
今じゃ、この有り様さ。」
と老人のズボンの裾を捲り上げると
ふくらはぎに負わされた深手の傷を見せる。
「やぁ、これは酷いな。
膿んでしまったら大変だよ?
何か強い酒で消毒しないと。」
と俺は小屋中を探し回ったが、
この老人はお酒を嗜む習慣がないらしく、
見当たらなかった。
「フェルニー。一走り買い出しに行って
くれないか?」
とユーレクは云ふ。
「わかったさ!少し待ってなよ。」
俺は馬を駆って、民家のある場所を
探し回った。
・
・
・
・
4マイルほど離れたところにマディソンの街が
あった。
ダイナーの看板が掛かっている店を見つけ
まだ、開いていない酒場の扉を叩く。
すると、怪訝そうな顔した店主が扉を開けて訊ねてきた。
「なんだい?何の騒ぎだい?」
俺はは早口で捲し立てるように
「おじさん!お願いだ!
ここから4マイルほど離れたところに
屋根付きの橋の近くに住んでいる爺さんが
酷い怪我なんだ!」
と助けを求めると、
店主は扉をピシャリと閉めて、怯えた声で
「それは、お前!肝喰いクロウじゃないか?
関わりたくねえ!」
(えっ?何と言った肝喰いだって?)
俺はもう一度、扉を叩いて懇願する。
「強いアルコール、ガーゼをくれないか?
賊にやられて傷が膿んできそうなんだ!」
「. . . . . 。」
返事がない。
俺が諦めかけた時、
店の店主が扉を開けてくれた。
「坊主。あの黒人の老いぼれは
危ない奴なんだ。
人間の生き肝を喰らうおぞましい奴だぜ。
放っておけば良いさ。若いのにあいつの餌食に
なるこたあない。」
と店主が声を潜めて話してくれた。
(何と云う事だ!ユーレクが危ない。
しかし、待てよ?
たしかユーレクが云うには
あの黒人の爺さんが助けてくれたって. . . 。)
「おじさん。忠告ありがとう。
充分気をつけるさ。
だけど、俺の友達が待ってくれているから
強いアルコールだけもらえませんか?」
と云って俺は5ペンスを店主に渡すと
店主は態度を変えて
「ちょいと待ちな。」
と云って店のカウンターの奥から
ボトルを持ってきた。
「これはバーボンの原酒だよ。
60度はあるから、引火に気をつけな。」
とボトルとガーゼタオルを持ってきてくれた。
「おじさん、ありがとう!恩に切るぜ。」
と云って馬上から礼を云った。
俺は手綱を引き絞って、
早駆けにユーレクの居る山小屋へと
引き返す。
道中、あの店主の云ってた言葉が
頭の中で思い出す。
(肝喰いって. . . 、あの爺さん何者なんだ?)
・
・
・
・
山小屋に着くと、
"クロウ"と呼ばれる老人は
高熱でうなされていた。
「ユーレク!もらってきたぞ!」
とバーボンのボトルとガーゼタオルを渡す。
ユーレクは
「サンキュー!」と云って
ダッチ・オーヴンで熱湯を沸かし、
ガーゼを浸して煮沸消毒を始めた。
手慣れた手つきで、鉄串を使って
消毒したガーゼを絞り、
さらにバーボンの原酒を浸したガーゼを
老人の患部に手当てをした。
ユーレクは
「石炭酸フェノールをくれないか?」
と要求する。
馬車には石炭酸フェノールが積んである。
ユーレクは手際良く
少量の石炭酸をバーボンで溶かし
煮沸した湯に入れる。
すると、絵の具のような芳香の湯気が
小屋の中に立ち込める。
ユーレクは
「こうやって小屋の中を消毒しておくのさ。
母さん仕込みさ。」
と説明する。
(手慣れたもんだな。)
と俺はしきりに感心していた。
俺とユーレクは老人を看病しながら、
街で聴いた"肝喰いクロウ"の話を
ユーレクに話してみた。
「なぁ、ユーレクはどう思う?」
と訊いてみる。
ユーレクは目を丸くしながら、
「マジかよ?そんな風にはとても思えないな。」
と考え込んでいた。
・
・
・
・
それから3日もすると、
クロウ老人の病も峠を越えた。
脚に負った傷の化膿も止まったようだ。
ユーレクはトウモロコシの粥を作っては
クロウ老人に食べさせてやっていた。
(ユーレクの癒しの力はすごいな。)
思えば、子熊にせよ、俺自身にせよ、
そして、この老人の回復ぶりはどうであろう。
クロウ老人は、ようやく落ち着き
話しかけてくるようになった。
「若ぇの。賊はどうなった?」
と訊ねてくる。
ユーレクは
「あぁ、俺と揉み合っている内は
わかんなかったけど、
爺さんには怪我を負わせやがったが、
爺さんの顔を見るなり血相を変えて
逃げ出しやがったよ。」
クロウ老人は
フォッフォッフォと笑い声を上げて
「そうだったのか。ならば良かったの。」
と微笑みを見せる。
俺は思い切ってクロウ老人に訊ねてみた。
「街じゃ、爺さんのことを"肝喰いクロウ"
と呼んでいたぜ?」
するとクロウ老人は
「あぁ。たしかにな。
俺はそう呼ばれていたんだよ。
だが、俺はそんなことはしていない。
でも北軍の奴らには、そのように呼ばれ
俺は怖れられていたよ。
戦時中は却って都合が良かったんだ。」
俺とユーレクは顔を見合わせて
「爺さん?昔、何かあったの?」
と訊ねると、
クロウ老人は
「俺は内戦の時に北軍側についたんだ。
いや、つかざるを得なかったんだ。」
クロウ老人は過去をポツリポツリと
語り始めるのだった。
八、綿摘みの詩
1862年 ルイビル
エレミヤ・"クロウ"・ジェファーソン
の話に移る。
彼はアフリカ系の純血で、ルイビル郊外のプランテーションで雇われている
いわゆる奴隷労働者であった。
ルーク・アレン・シューメイカーと言う
大地主のプランテーション経営者の下で
雇とわれていた。
エレミヤは他のアフロ・アメリカンの仲間達と
良く学び、働き、良く遊んだ。
シューメイカー家は他の大地主とは違い、
召し抱えた者たちの待遇を家族同様に扱った。
美味しい料理が並ぶ食卓を共にし、
収穫を喜び、綿花は飛ぶように売れていった。
豊穣の恩恵は大いなる富をもたらした。
・
・
・
・
広大にどこまでも続く綿花畑に
爽やかな初秋の風が吹き渡る。
「エレミヤ!ふわふわのコットンだよ!」
エレナは地主シューメイカー家のひとり娘で、
4歳になったばかりである。
朔果したコットン・ボールの実が
弾けているのを見つけると、
ふわふわの綿毛を小さな手のひらに乗せて
はしゃいで走り回っている。
「お嬢様!その綿毛を授けてくれますか?」
綿毛と戯れるエレナに優しい声をかける。
エレナは
「はい!エレミヤにあげゆ!」
小さな手のひらを差し出して
ニッコリと微笑む。
エレミヤは
「お礼をしましょう。」
と、器用に野の花で花かんむりを拵えて
エレナの可憐なブロンドの髪に
そっと戴せてみせる。
「エレナお嬢様。お似合いでございます。」
「わぁーい!エレミヤありがとう!」
エレナは満面の笑みを見せるのだった。
今年もそろそろ収穫の時期が来る。
俺たち下働きの者たちが
総出で綿毛を手摘みする、この時期ほど
美しく壮観な眺めはないであろう。
この世に永遠というものがあるならば__ 。
・
・
・
・
この頃、国を二分する内戦が勃発していた。
やがて、奉公しているプランテーション経営も
戦禍に呑み込まれてゆく。
北軍が東海岸を制圧し、
綿花の輸出が途絶えてしまったのだ。
以前のように、
一緒に食卓を囲うことがなくなり、
トウモロコシを少しづつ分け与えられる
粗末な物へと代わっていった。
それでもクロウは
遮二無二に奉公を続けていた。
(俺は全身全霊を傾けて、最後の血の一滴まで
この方にご奉仕しよう。)
と、エレミヤは決心していたのだ。
ある日のこと
情勢はルイビル界隈にまで及び
軍同士の衝突が続いていた。
雇い主のルークは
「エレミヤ。今まで我が家に仕えてくれて
本当に感謝している。
だが、今のままでは経営は立ち行かない。
わかってくれるな?」
「旦那様?このエレミヤは今まで大変
可愛がってもらいやした。
私はこの大地の塩となって、
身を捧げるつもりでございます。
後生ですから、私をお雇い下さいまし。」
と懇願するエレミヤであったが、
ルークは首を横に振り、
「荷物をまとめるんだ。」
と状況は変えることが出来ないと
諭すのであった。
それから数日後__
「エレミヤ?ホントに行っちゃうの?」
エレナは泣き喚いていた。
「エレナお嬢様。
エレミヤは果報者でございます。
あと数日したら私は旅立ちます。
遥か彼方のお空より、お嬢様の幸運を
お祈りしております。」
と微笑みながら言い聞かせるのだった。
(エレナお嬢様. . . 。)
運命と云ふものは、時に残酷である。
・
・
・
・
エレミヤが旅立つ前日のこと、
エレナの姿が見当たらない。
綿花畑に行ったまゝ帰ってくる気配がない。
シューメイカー家は、すでに奴隷労働者に
暇を出しており、
エレナの両親であるルークとキャサリン、
祖母のローズと家政婦のセリーヌ
そして、エレミヤを含めて
合計5名を残すだけだった。
脚の悪いエレナの祖母ローズに留守を任せ、
ルークとキャサリン、家政婦のセリーヌと
4人で、広大な綿花畑で
迷っているに違いない
エレナを捜索した。
秋が深まるにつれ、乾燥し身が切れるような
寒さになる。
(エレナお嬢様。寒かろう?寂しかろう?)
エレミヤは明日発つことも忘れ、懸命に
エレナを探し出す。
「エレナお嬢様ーっ!」
その時、パンと銃撃音がした。
慌てて音のする方に行くと、
そこにはエレナが血塗れで横たわっていた。
(こ、これは一体?)
一目瞭然な程にエレナの腹部は
撃たれたばかりの銃創がある。
エレミヤは気が動転し、止血しなければと
両の掌でエレナの腹部を必死に押さえていた。
嗚咽が止まらない__。
生温く流れる血を懸命に止血する。
エレミヤは凄惨なエレナの姿を見て
嘔吐を繰り返し、口元を血塗れの手で拭う。
今度は葉擦れ音と共に
馬が駆ける足音が近づいてくる。
騎兵隊員が到着して発見したのは、
掌と口元を血糊で真っ赤にしたエレミヤが
懸命に止血をしている姿だった。
だが、騎兵隊は夥しい血糊を口元につけた
エレミヤを見た瞬間、
人間の生肝を喰らうおぞましい光景に
見えてしまったのだ。
「お、お前?食べたのか. . . ⁉︎」
騎兵隊員も気が動転し、
慌てて銃口をエレミヤに向ける。
「違う!俺は何もしていない!」
内戦の小競り合いがこの地にまで及び
運悪く流れ弾にあたってしまったのだろうか。
エレミヤの弁明は届かずじまいに__ 。
運命の歯車がギシギシと音を立て
容赦なくエレミヤから幸せを
奪っていくようだった。
エレミヤは無実の罪で北軍に連行され、
戦争捕虜となった。
そして、南北戦争が激化していく中で、
エレミヤは常に戦場の最前線へと
駆り出されゆくのだった。
(いっそ、死にたかった。俺の人生は__
絶望の闇だけが広がっていた。)
一瞬にして、運命の落とし穴に嵌まったのか
エレミヤは、常に捨身で戦場に臨んだが
皮肉なことに、戦果を上げていく。
北軍の連中からは、過去の経緯から
"肝喰いクロウ(カラス)"と揶揄され
敵軍にもそのおぞましい噂は広まり、
両軍から怖れられる存在となった。
しかし、戦争が集結すると
"肝喰い"のレッテルを貼られたまゝ
世間から忌み嫌われ、人里離れた山奥で
人目を忍んで生きて行かざるを得なかった。
ここまでがエレミヤ__
すなわち、クロウ老人が語った内容である。
・
・
・
・
爺さんの憐れな過去に
俺は涙が溢れて止まらなかった。
「ひどい誤解だ. . . なんてことなんだ!」
ユーレクも俯いて拳を握りしめて
涙を流していた。
クロウ老人はすっかり話し終えると
少年たちの純真無垢な涙に触れ
心を覆っていたどん底の暗闇から
かつて愛して止まなかった
一面の綿花畑のような晴れやかな風景へと
心が洗われていくようだった。
クロウ老人は
「これは俺が与えられた運命なのだ。
だけどな、お前たちに会って
久しぶりに人の温かみに触れられたよ。
主の導きに感謝いたします。」
と微笑み交じりに俺たちを抱擁をする。
クロウ老人の黒く分厚い手のひらから
情愛の念が脈打つように二人に
伝わってきたのだった__。
・
・
・
・
翌朝、すっかりと元気を取り戻した老人は
俺たちの出発のはなむけをしてくれた。
「もう俺はこの先長くない。
だけど、お前たちは若い。
幸せの一粒が万倍へ広がる可能性がある。」
クロウ老人はそう云って、綿花の種を
手渡してくれた。
「爺さん!達者でなー!」
俺たちは手を振って別れを惜しむ。
次はナッシュビルへと向かう。
俺たちは不思議な夢によって導かれたのか。
人の一生と云ふものは
常に何が起こるか解らない。
「なぁ、ユーレク?
夢で見たユニコーンって、
もしかすると、あの爺さんなのかな?」
と訊いてみる。
ユーレクは
「俺もそう思ってたんだ。
"人間万事、塞翁が馬"ってやつよ。」
と誇らしげに俺に説明する。
「何?それ?どういう意味?」
と訊いてみると
「昔、母さんから聞いたんだ。
人生ってどう転ぶか解らないって、
古いシナの国のことわざさ。」
とユーレクもイマイチ解っていなかった。
「見ろよ、フェルニー!ほら!」
とユーレクが指を指す。
そこには、白く美しい綿毛が風に揺れる風景が
どこまでも続いていたのだった。
九、フラッシュ・バックする幻影
日曜日は教会で祈りを捧げる__ 。
敬虔なカトリック教徒である
エリザベスにとっては
ごく当たり前の習慣である。
最近、入ってきたオリヴィアも
すんなりと人の輪に溶け込んでいた。
彼女は気配りが効いていて、
面倒見が良い姐御肌の雰囲気があった。
エリザベスもいつの間にか、
他愛のない話しや身の上話をする間柄に
なっていった。
「息子さんはお元気なの?」
とオリヴィアは訊ねる。
「ユーレクね?ええ、もちろんよ。」
エリザベスは答えた。
「今は少し離れて暮らしているけどね。」
しかし、多くは語れない。
ユーレクとランスキー氏の息子からは
旅に関することについては
固く口止めされているからだ。
「オリヴィア、ありがとうね。
私の息子は元気にしていると思うわ。」
「そう?なら良かったわ。」
オリヴィアも深くは聞き出そうとしない。
しかしながら、言葉の端々から巧みに
情報を引き出しながら、考えを巡らせる。
(ユーレク・ボリセヴィチ. . .
たしか宝石鑑定の名簿にあったわね。)
オリヴィアはこの界隈で消息を絶った
フェルディナンドの情報収集をするために
教会のコミュニティに潜入したのであった。
彼女の頭の中には、ある考えが
確信に変わりつゝあった。
1.フェルディナンドの消息を追うにあたり、
このウォーターフロント界隈から馬車で
旅立ったこと。
2.ユーレク・ボリセヴィチは
宝石鑑定に来店していたこと。
3.ユーレクもこの街から居なくなったこと。
(おそらく、フェルディナンドさんとユーレク
は何らか関係があるに違いないわ。)
オリヴィアは勘が鋭い女だった。
(ご主人様に報告しなければ. . . 。)
・
・
・
・
「ハックション!」
俺は鼻水が垂れるくらいの
大きなクシャミをした。
「アハハハ!
誰かに噂されているんじゃないのかい?」
とユーレクが茶化してきやがる。
「ごあいさつだな?きっと良い噂だよ!」
と俺はヒョイと肩をすくめてみせた。
晴れ渡る空の下、調子が良い時は軽口も弾む。
「よし!ユーレク?
この川を渡ればナッシュビルにつくぜ!」
とまだ見ぬ街並みに俺たちは
期待を寄せていた。
「フェルニー?どうやら問題がある
みたいだぜ?」
とユーレクが遠目に進路の先を窺っている。
ナッシュビルへ到着するには
ケンタッキーとテネシーの州境の南にある
カンバーランド川を渡らなければならない。
ユーレクが云ふには
どうやら"ウッドランド通り橋"の上で
渋滞が起きているようだった。
「様子を見に行ってみようぜ!」
俺たち二人は橋の欄干に馬を繋ぎ留め
渋滞の橋上を進んで見ると、橋の真ん中で
牛の群れが動かないでいた。
立ち往生している馬車の馭者ぎょしゃが
「F××k off ! 」と
汚い言葉で怒鳴り散らしていた。
「一体どうなちまったんですか?」
馭者に訊ねて見ると
「坊主!見てみなよ。どこかの牛追い業者が
干草ごと牛を置いていきやがった!」
と呆れ顔で教えてくれた。
橋の上は、干草が散乱しており
牛が脱糞したのか、至るところに
糞が踏みにじられて酷い有り様だった。
「こいつは酷いな?天下の往来が台無しだ。」
俺とユーレクは
立ち込める悪臭に耐えながら
向こう岸の橋のたもとまで
向かおうとする時だった。
すると、「おい⁉︎」と云って
ユーレクが一瞬立ち止まる。
「どうかしたのか?」
俺はユーレクの挙動が気になった。
ユーレクは茫然と橋の先を眺めて立ち尽くす。
「おい!ユーレク?大丈夫か?」
と声を掛けると
ユーレクはハッとした表情で
我にかえった。
そして
「フェルニー?お前には見えたか?」
と訊ねてくる。
「なんだってんだ?何も見えやしないけど。」
と橋の先に目を凝らせてみても
ありふれた街並みが遠くに見えるだけだった。
ユーレク曰く
「橋の向こうに白い人影が居た。」
と云ふのだ。
「小さな双子の女の子だった。
まるで記憶がフラッシュバックしたように
一瞬、時間が止まったみたいなんだ。」
とユーレクは説明してくれた。
「橋の向こう岸まで行ってみよう。」
俺たちは幻影の跡を追うように
橋を渡ることにした。
すると、そこには幌馬車が横転していた。
放馬したようで馬は居なかった。
倒れた幌馬車の中に馭者達が倒れている。
俺とユーレクは声を掛けた。
「おい!大丈夫か?」
だが返事がない。
どうやら気を失っているようだった。
幌馬車の中に閉じ込められている馭者達を
二人掛りでなんとか外に引きずりだした。
一人は痩せ型の中年男性で、
もう一人は背の高い青年だった。
「おーい!大丈夫か?」
と身体を揺すってみると、青年の方が
先に目を覚ました。
「イタタタ. . . あれ?君たちは?」
青年は事態を知るまで呆気に取られた様子で
キョトンとしていた。
「一体、何があった?」
と訊ねてみると
青年は
「橋を渡っている最中に、橋の真ん中に
白い服を着た二人の少女が居た。」
と云ふ。
「すると、突然に馬達が荒れ狂うように
駆け出し、手綱をしごいても言うことを聞かず
御しきれなくなってしまったのさ。」
ユーレクは青年の云ふ内容に耳を傾ける。
そして、確信したように
「君にも見えたんだね?
白い双子の女の子たちが。」
と訊き直していた。
俺には見えてなかったもの__
不思議な出来事の予兆がしてならなかった。
十、憑依
後ろ姿で橋の上に立っている
双子の少女たち__
馭者とユーレクが見た双子の少女
若い馭者とユーレクの目撃した内容は
ことごとく一致していた。
しかしながら、
俺には全く見えていなかった。
ユーレクの妄想かと思いきや、
目撃者がもう一人現れたことで真実味を帯びる。
そして、もう一人
中年男性の馭者の様子が気になった。
「叔父さん!起きるんだ。」
若い馭者が大声で呼びかけても、
身体を揺すっても気を失ったまゝだった。
ユーレクは
「相当強く頭を打ったんじゃないのかい?」
と中年馭者の頭をさすりながら、
打撲した部分を探していた。
しばらくすると、
「うぅぅ. . . 。」と呻き声を発して、
ゆっくりと瞼を開けたのだった。
「あゝ!良かった。叔父さん!」
若い馭者は安堵したのか、ヘナヘナと座り込み
どっと疲れが出た様子だった。
ユーレクは
「意識が回復しても油断は出来ないんだ。
しばらく横になって休んでおくんだね。」
と青年に声を掛けると、
「さあて!その間は俺たちがこの牛たちの渋滞を何とかしなきゃな。」
とユーレクは俺に向かってウインクする。
「あゝ合点だ。ユーレク。」
と相槌を打った。
「馭者さん。
ここは俺たちに牛たちの誘導を任せて、
アンタは叔父さんのことを看てやってくれ。」
と言う訳で
俺たちは事故の始末を請け負った。
・
・
・
・
俺たちは、橋の上に群がる牛達を
どうにかして誘導しなければならなかった。
牛を驚かせてはいけない。
暴れ出したら、もう手に負えやしない。
ユーレクが云ふには
「牛は目が離れているから正面はほとんど
見えやしない。」らしい。
「繊細な生き物だから正面から近づくと
怖がって敵と見做される。」
とのことだった。
俺はそろりと牛の背後から側面へと近づく。
ユーレクが
「止まれ!」と俺を制する。
すると、俺の眼前に
牛の後肢がブンっと目にも止まらぬ速さで
駆け抜けていった。
「ヒエッ!あぶねー。」
俺はすんでのところで、強烈なフックを
見舞われる羽目になるところだった。
ユーレクは
「云い忘れてたけど、牛は臆病だから
腹回りより後ろに立つと回し蹴りする習性がある。」
とのことだった。
「こうするんだよ。」
ユーレクは干草を手に取り
牛に良く見える位置から近づいて
干草を食むように促す。
牛が干草を食むと、
優しく撫でるようにスキンシップを取り、
牛を誘導するのだった。
(へぇ〜 . . . 上手いもんだな。)
とユーレクの手際の良さに感心していた。
俺たちはあっと言う間に牛の誘導を終えて
橋の渋滞を解消することが出来た。
怒鳴り散らしていた馭者も、
「坊主たち!ありがとうな。」
と礼を言って、1ペニーづつチップを呉れた。
「わぁーお!いいのかい?ヒャッホー!」
と俺は生まれてはじめてチップもらうことに
人のために役立つことに__
喜びを感じたのだった。
・
・
・
・
俺たちも橋を渡らなければならない。
(俺たちの馬も暴れ出すのだろうか?)
俺は馭者台から慎重に馬車を進める。
ユーレクは馬上から見守っていた。
橋の真ん中あたりに来ても、俺には少女の姿は
見えやしない。
カンバーランド川の雄大な流れが美しく、
何事もなく渡ることが出来た。
橋を渡り切り
先ほどの馭者たちのところへと歩み寄ると、
中年馭者の意識も戻っているようだった。
「やぁ!牛たちも無事だし、叔父さんも
無事だったか?」
と訊いてみると、
若い馭者は
「あゝ、元気になってくれたのは良かったが
少し問題があってね . . . 。」
「いったい、どうしたって云ふのだい?」
とさらに訊ねる。
すると
中年の馭者が
「あなたたちは誰?
ワタシをどうするつもり?」
と云ふ。
若い馭者は
「俺だよ!カルロスだよ!
忘れちまったのかい?パコ叔父さん!」
「はじめまして!俺はフェルディナンド・ランスキーと云います。」
「俺はユーレク・ボリセヴィチです。」
俺たちは中年馭者のパコ叔父さんに挨拶した。
すると__
「あなたたち誰?ワタシはソフィア . . .
ソフィア・エイプリルレインよ。」
と女性のような美しい気品のある言葉遣いで
話し出すのだった。
若い馭者__カルロス・エンリケは
「冗談はよせよ!叔父さん?」
とお手上げといった様子で天を仰いだ。
「さっきから、ずっとこんな調子なのさ。
よほど打ちどころが悪かったに違いねえ。」
カルロスはすっかり参った様子で
ため息をついた。
俺とユーレクは目を合わせながら
奇妙な出来事を飲み込めないでいた。
中年男性はフランシスコ・ディアスという
牛追い業者で甥のカルロスと共に
ナッシュビルの街へ牛を売り捌く予定だった。
頭を強打したのが原因なのか、
今は全く別の人格のソフィアという女性に
なっているのだろうか?
ユーレクはふと何かを閃いたらしく
優しく声を掛けた。
「ソフィア?俺たちは怪しい者じゃない。
ところで君ともう一人誰か居なかったかい?」
すると、中年男性の姿をしたソフィアが
話し出す。
「アレクサンドラを知らない?」
「ひょっとして双子の姉妹のもう一人かい?」
とユーレクは優しく訊ねる。
その様子はまるで女の子に
話しかけている様子に見えた。
ソフィアと名乗る中年男性は
少し震えながらであったが、ユーレクには
心を開いたらしく
「アレクサンドラ . . . 許して . . . 。」
と息を詰まらせながら、
しくしくと泣きだすのであった。
十一、アルビノの双子姉妹
ユーレクはかがみ込むようにして、
泣き出すソフィアをなだめている光景は
傍目から見ると滑稽に映るかも知れない。
大人である中年男性がさめざめと泣いていて
少年が頭を撫でて慰めているのだから。
ユーレクはとても親身になって
ソフィアの話す言葉に耳を傾けていた。
「アレクサンドラって、君の双子姉妹かい?」
とユーレクが訊ねると
「そうなの。アレクサンドラはアタシにとって
双子の姉なの。」
とソフィアは話し始める。
「許してって . . . いったい何かあったの?」
とユーレクは問いかける。
ソフィアは首を振り
「ううん . . . 。何でもないのよ。
優しくしてくれてありがとう。
貴方たちのお名前は?」
ユーレクは
「俺はユーレクっていうんだ。
そして、こいつはフェルディナンド。
フェルニーって呼んでる。」
「あゝ、よろしくな。ソフィア。」と俺はユーレクの話の展開に合わせた。
今は中年馭者の姿をしているが、
どうも中身は育ちの良い令嬢といった風で
上品で繊細な物腰だったからだ。
二重人格__
たしか、そのような話を聞いたことがある。
子供の頃に読んだ「ジキル博士とハイド氏」
を彷彿とさせるような不思議な出来事が
現実に起こっているのだった。
カルロスは、にわかに受け入れ難かったことで
パコ叔父さんことソフィアのことは
俺たちがしばらく預かることで
諒承してもらった。
・
・
・
・
俺たち一行は
ナッシュビルのダウンタウンに到着した。
ナッシュビルは州制100周年記念万博が
数年後に予定されており、街の至る所で
建造物の工事が始まっていた。
そのこともあり、ナッシュビルの街は
職を求める労働者で賑わっていた。
カルロスたちが連れてきた牛21頭は
肉質が良いことと、この活気ある街での需要が
増えていたことも重なり、
思いのほか高値で売り捌けたらしく、
カルロスは上機嫌だった。
「パコ叔父さん。やったぜ!
高く売れたよ。」
しかし、本来は叔父さんであるはずが
今は違う人格の少女ソフィアであることを
うっかりと忘れてしまっていた。
およそ労働報酬とは無縁の価値観なのか
首を傾かしげるような仕草を見せるだけで
武骨な青年カルロスには
未だに心を開いていなかった。
俺はその場の緊張を感じ取り
「カルロス? すごいじゃないか!
テキサスからの長旅の甲斐があったね。」
と労った。
カルロスはニッコリと微笑んで
「助けてくれたお礼に今夜はご馳走するよ。」
カルロスは豪快なナイス・ガイであった。
ナッシュビルでも一番と名高い
マックスウェル・ハウス・ホテルの
レストランを予約してくれたのだった。
「ヒュ〜 ♪ 身嗜みだしなみを整えなきゃ!」
とユーレクは久しぶりのご馳走に
ありつける期待で心から楽しんでいるように
明るく振る舞っていた。
ソフィアは少し憂うような面持ちで
「マックスウェル・ハウス. . . 。」
と呟いて物思いに耽る。
(ソフィア . . . 。
お前はいったい何者なのか?)
俺は雰囲気を壊さないように気遣いながら
裏腹に心の中は謎で渦巻いていた。
ホテルに到着すると、コリント式円柱の玄関が
豪奢そのものであった。
スチーム暖房の効いた
暖かく心地良いメイン・ロビーには
至る所に贅が尽くされており
マホガニーの高級家具、黄銅の装飾、
目を見張るような煌びやかな鏡など
シャンデリアとガスランプの仄かな灯りに
照らされて気品が満ち溢れていた。
「さあて、危ない所を助けてもらって
感謝してるさ。
おかげさまで牛も高値で売れたし、
ほんのお礼だ!たんと召し上がってくれよ!」
カルロスは気前の良い若者だった。
前菜やステーキを頬張りながら、
テキサスから牛追いの道中は鉄道を使わず
俺たちと同じく、昔ながらの幌馬車による
移動だったらしくお互いの旅にまつわる
エピソードを交えながら談笑した。
ようやく気持ちも落ち着いたのか、
パコ叔父さんこと別人格のソフィアも
少しづつ心を開いているようだった。
ソフィアは生い立ちを話し始める。
・
・
・
・
1845年
ノックスビルの東へ32マイル離れた所に
ガットリンバーグと云ふ山あいの村があり、
そこにはヴァレリーと云ふ妊婦が住んでいた。
彼女の夫イーサンは、妊娠5ヶ月の時に
彼女の女友達であったカトリーヌと恋仲になり
彼女を捨てて駆け落ちしてしまった。
失意の日々を送っていたヴァレリーだったが、
(お腹に居る新しい生命は
なんとしても護らなければ。)
と、気丈に振る舞うのであった。
そんな彼女を憐れんで周囲の村人たちが
身重の彼女を支え合って、その暮らしを
保護していたのだった。
出産の前夜のことである。
彼女は不思議な夢をみる。
巨きな角を持つ白毛の馬が現れる夢だった。
美しい毛並みをしたユニコーンは
自らの鋭利な角で前肢の先を突いてみせる。
白い前肢から蒼白い月のように輝いた
血が滴り落ちる。
「我、汝を助けたもうぞ__ 。」
と頭の中で声が響く。
ユニコーンの意思に言うがまゝに
高々と前肢を上げた、
その下にヴァレリーは顔を仰向け
銀青色Azureの血滴を
その口に含むのだった。
ヴァレリーが飲み干したのを見届けると
ユニコーンは嗎いななき
周囲の山脈の隅々まで、鳴き声が
響き渡ったかと思うと
不思議の夢の中で忽然とユニコーンは
その姿を消した__ 。
ヴァレリーは翌朝には産気づき
その分娩に立ちあった周囲の者は驚嘆した。
ヴァレリーは雪花石膏アラバスターのように
白く透けるような美しい肌の双子姉妹を
産み落としたのだった。
双子の姉妹は先天性のメラニン色素が欠乏した
アルビノであった。
母ヴァレリーは、
姉はアレクサンドラ、妹にソフィア
と名付けた。
村では美しい双子姉妹と評判になっていった。
噂は広まり、
隣町のノックスビルからわざわざ双子姉妹を
観に来る者まで現れるほどで
アレクサンドラとソフィアが天真爛漫に
山あいの草原を駆け抜ける姿を観た者は
「ガットリンバーグの双子姉妹の佇まいは
この世の天使が戯れているようだった。」
と云わしめる程だった。
彼女たちは日に日に美しく成長を遂げる。
・
・
・
・
「だけど、或る出来事が私たち姉妹を
離ればなれにしてしまったの。」
ソフィアは遠い目を潤ませるようにして、
語り始めるのだった。
十二、霧夜のワルツ
1859年
ガットリンバーグの天使と云わしめる
美しいアルビノの双子姉妹
アレクサンドラとソフィアは14歳となった。
アラバスター彫刻を彷彿とさせる
透明な白い肌__
彼女たちの存在は宗教絵画から
飛び出してきた天使と思える程に
その美貌はこの世の奇跡と云ってよかった。
ノックスビルはおろか遠くの都会からも
噂を聞いた人々がアレクサンドラとソフィアを
一目観ようとこの街に訪れるのだった。
しかし、双子姉妹は人々から好奇の目で
観られることに辟易としていた。
そんな日々を過ごす中で
ガットリンバーグの街に一人の紳士が訪れる。
彼の名はジェームズ・エイプリルレインという
ホテル事業で大成功を治めた
初老の大富豪だった。
ジェームズは保養目的の旅行で
グレート・スモーキー・マウンテン
を
散策するためにふもとにある
この小さな村に訪れていた。
このガットリンバーグの村を拠点に
広大な原生林が広がる景勝地へと
アクセスするのには丁度具合が良かったのだ。
彼はビジネス相手からの薦めもあり
この地に訪れた。
見晴らしの良い尾根から見渡す風景は
噂に違わぬとおり
山脈には常に雲や霧が薄らとかかっており
その幻想的な光景は感動的であった。
その時である__ 。
ジェームズの視界に白い何かが見えた。
それは二匹の白い動物のようであるが
ジェームズにはそれが何か良く判らなかった。
二匹の動物は戯れるように山あいの草原を
駆け回っていた。
よくよく目を凝らすと人のように見える。
やがて、ジェームズの居る
この尾根まで近づいてくるではないか。
「こんにちは!おじさん。」
と声を掛けてきたのは
白く美しい二人の少女__
アレクサンドラとソフィアであった。
雪花石膏アラバスターのように透き通る白い肌
すみれ色をした美しい瞳
プラチナブロンドの髪が風になびいていた。
(この世でこんなに美しい少女は
見た事がない。)
と内心は思いつゝも、そこは海千山千の紳士
平静を装って
「お嬢さん達。ここには良く来るのかい?」
とさりげなく声を掛けてみた。
「私たち、ふもとの村で暮らしているの。」
と、少女たちは微笑んで答える。
その透き通るような微笑みに
ジェームズは一瞬で心を奪われた。
(こんなに美しい姉妹が、私の滞在している
村に住んでいるのか。)
ジェームズは
「マドモアゼル、私もふもとの村にしばらく
滞在している者です。
旅先で偶然にも出会ったことが嬉しくて
神の思し召しのように思います。
また、ふもとの村でお目にかかれるのを
楽しみにしておりまする。」
ジェームズの紳士的な振る舞いは
少女たちからすれば
いつもの野次馬のような来訪者と違い、
丁重に対応してくれるこの紳士の態度に
好感を持ってくれたようだった。
少女たちは何か相談しているようだが
少女の一人が
「あら?まあ!そうなんですか?
ふもとの村までご一緒しますわよ。」
と案内をすると言ってくれたのだ。
「メルシー、マドモアゼル」
と茶目っ気たっぷりに
ジェームズはひざまづいて敬礼をしてみせた。
・
・
・
・
ジェームズ自身は
事業では成功を治めたものの
若かりし頃は家庭を顧みないことが災いし、
一度目の妻とは離縁していた。
二度目の妻との間に一女を授かったものの、
病弱であった娘はわずか11歳で夭折し、
その後は子供を授かることがないまゝ
二度目の妻にも先立たれてしまっていた。
(この姉妹を家族に迎え入れたい__ 。)
しかし、この胸のときめきはどうだろう。
それは家族を失ったうら寂しさとは異なる
ある種の感情が芽生えていた。
男の性としての__
美しい女性を観た時に直情的に
我が手中に納めてみたいと云ふべき
性的衝動リビドーが沸々と湧き上がる。
それは美術蒐集家、或いは獲物を狙う狩人
と言っても差し支えないほどの
"狂"の情念が迸ほとばしる。
アレクサンドラとソフィアという
この世の奇跡が現身うつしみとなった姿を
一目見ただけで__
ジェームズは自身の中で
晴天の霹靂へきれきに撃たれたが如く
体内に電流が駆け巡るのを感じたのだった。
・
・
・
・
ジェームズはガットリンバーグに滞在中は
ナッシュビルの都会から来た名士として
笑顔と紳士的な振る舞いを絶やすことなく、
高額なチップをはずむこともあり、
村中の人々からの尊敬と信頼を集め出した。
彼は人を懐柔することに長けていた。
もはや天稟の才と云っていい。
純朴な村人たちの心を掌握するのは時間が
かからなかったが、
彼は戦略的で用意周到な男であった。
ジェームズはビジネスの合間を縫って
三年の月日をかけて、
春と秋に長期滞在をする度に
村人が総出で歓迎するまでに信用を勝ち得た。
アレクサンドラとソフィアはもちろん
母のヴァレリーまでもがジェームズに心酔し、
彼が訪れる度に我が家に歓待するまでに
関係を深めていったのだった。
1962年
アレクサンドラとソフィアは17歳となり
少女と大人の境界にある過渡期ゆえの
美しさを讃えている。
(機は熟したであろう。)
ジェームズはヴァレリーに求婚をする。
「私と余生を供に__ 。」
決して裕福ではないヴァレリー一家としては
まるで夢のような申し出であった。
ジェームズは事業は成功しているものの、
妻に先立たれた寡夫やもめであり、
彼の元から幾度も幸せの青い鳥が
離れていった過去の打ち明け話を聴いて
ヴァレリーの母性本能に火を付けた。
ユニコーンの夢を見たあの時と
まるで同じような蒼白い月が輝く夜
人生に傷ついた二人は
お互いを求め合う
ジェームズとヴァレリーは
唇から伝わる電流に
湧き上がるような鼓動を重ね合わせて
心も身体も一つとなる
黄金色をした蜂蜜が溢れ出し
二人の間を隔てていたものを
甘く溶かしていく
お互いに背負ってきた
今までの悲しみを癒し合うように
ワルツを踊る二人を
グレート・スモーキー・マウンテンの
シルクのような霧が包み込む__
・
・
・
・
ヴァレリーはジェームズの求婚を受け入れた。
結婚式は、村のバブテスト教会で執り行われ、
村中の人々が総出で祝福に駆けつけるほどで
アレクサンドラとソフィアも
幸せの歓声に包まれたのであった。
その後、
一家はナッシュビルに移り住む。
双子姉妹はエイプリルレイン家の令嬢として、
都会的に洗練されたマナーや教育を叩き込まれ
美しいデザインのドレスや
身に付ける煌びやかな装飾品も
ソフィストケートされた物へと変化していく。
ほどなく双子姉妹は
その透き通るような美貌と
洗練された立ち居振る舞いで
出会った者を魅了する。
誉れ高き "サザン・ベルSouthern belle" 《南部の美女》の
名声を得るのだった。
十三、巴里から来た男
ソフィアの追憶から
新たに登場するひとりの哀れな若者__
ヒューゴの物語を語らねばならない。
彼の名はユーゴ・サン=シモン
アメリカの地ではヒューゴと呼ばれていた。
二十八歳の端正な顔立ちをしたパリジャンで
黒髪をした覇気のある若者だった。
1863年のある日__
ヒューゴはジェームズを訪ねてきた。
彼は、はるばるヨーロッパから
海を渡って来たばかりである。
ナポレオンⅢ世統治下のフランス政府は
アメリカで国を二分させる南北戦争が
勃発した当初は
北軍側の大義名分が希薄だったこともあり、
優秀な司令官を擁する南軍が
有利との見方が強く、
新大陸に渡航する若者に対して、
積極的に南軍に加担する動きを水面下で
働きかけていた。
エイプリルレイン家は
建国当時、アメリカに入植する以前は
出自がフランスである。
アメリカ南部の人々に色濃く残している
フランスの血筋を受け継いできているという
出自の神話と云ふものを誇りとしていた。
そのような背景もあり
ジェームズは慈善事業として、
フランスから新天地を求めてやってくる
同郷の入植者が生計を立てていけるように
仕事のあっせん````を行っていた。
しかし、リンカーン率いる北軍が
「奴隷を解放する。」と云ふ世論を
推し進め、
人道的な観点から次第に支持を増やし
各地で展開される戦闘で勝利を重ねていく。
ジェームズが経営するホテルは
苦戦が続く南軍側の要請により、
野戦病院として、所有していたホテルを
提供せざるを得なくなった。
そればかりか、フランスから来た若者たちを
南軍の兵士として__
あっせん````を求められていた。
ヒューゴは__
そんな国内事情を知る由もなく、
新天地に夢と希望を馳せて
はるばるとパリの街からやってきた。
政府の思惑などは
何も聞かされぬまゝに
エイプリルレイン家の当主ジェームズに招かれ
屋敷に案内されたのである。
(アメリカに到着して、
すぐにこのような待遇を受けるとは__
まるで運命の扉が開かれたように
幸先が良いな。)
とヒューゴは嬉しさが込み上げる。
名家の屋敷に相応しい広々とした玄関ホールは
見事な大階段があり、荘厳な雰囲気だった。
(余程の名士に違いない。)
ヒューゴは
同郷の成功者からの手厚い歓待を想像し
期待に胸を弾ませながら
当主の出迎えを待っていた。
その時__
玄関の二階にある渡り廊下を見上げると
一瞬、白い人影が通り過ぎた。
ヒューゴは最初は気のせいかと思っていた。
ほどなく、執事が現れる。
「ようこそ。このたびはフランスから
はるばる長い旅路をご苦労様でした。
主人のジェームズが部屋で待っております。」
・
・
・
・
執事は書斎の前まで案内すると
「ご主人様。ただいまシモン氏が
お越しになられました。」
「あゝご苦労だったね。」と、
部屋の奥から人懐っこい声が聞こえる。
ヒューゴが考えていた厳めしい人物像と違い
意外にも茶目っ気たっぷりの笑顔と
人懐っこい愛嬌のある紳士が現れた。
「私はジェームズ・エイプリルレインです。
ヒューゴ君。長旅ご苦労様だったね。」
とジェームズは握手を求めた。
ヒューゴは
ジェームズの人となりとフランクな対応に
少しずつ緊張が解れていった。
「このたびはお招き頂き、
ありがとうございます。」
と、ヒューゴも手を差し伸べて
握手を交わした。
ジェームズは紳士然とした、
親切な柔らかい口調で語りかけてくる。
「君はパリから来たんだね?
最初に言っておくが、アメリカの__
ことに南部の風習ってものは
パリの都会のように洗練されてないんだよ。
必然、人間の気象も荒々しいし
街の外れに出れば、
インディアン達や野生動物が
いつ襲ってくるとも限らない。
だからこそ、我々同志が力を合わせて
助け合わないと生きていけないんだ。
もし、君に困ったことがあったら
いつでも私を頼って来てくれたまえ。」
異国に来たばかりの若者にとって
地元の名士から支援を受けられることは
心強さを感じられた。
「エイプリルレインさん!
ありがとうございます。」
とヒューゴは笑顔で応えた。
ジェームズは
「せっかくだから、
今晩はゆっくりしておいきなさい。」
と云うと
「シモンさんをゲスト・ルームに案内して。」
と執事に云い渡した。
・
・
・
・
部屋へと案内をしてもらう際に
執事が云うには
「南部のおもてなしとは、
"皆を平等に愛する"をモットーに
一部のお客様だけを特別待遇することは
普段は滅多にございません。
ご主人様はあなた様のことを
余程お気に召されたかと思われまする。」
これは、エイプリルレイン家の常套句で
いわゆる社交辞令である。
ゲストに対してかける言葉の一言一句にも
ホスピタリティを感じさせる
しつけや教育が行き届いている。
ヒューゴにしてみれば
そんなことは露知つゆしらず
(アメリカとは__
希望に満ち溢れている新天地へと
俺は到着したんだ。)
と感銘せずには居られなかった。
部屋に案内されて
ヒューゴはようやく一息ついた。
・
・
・
・
ディナーが始まった。
執事にダイニングに案内されると
そこにはジェームズ夫妻と
ハッと目を見張るほどの白い肌の
双子姉妹が出迎えてくれた。
ジェームズは家族を紹介する。
「ヒューゴ君。紹介しよう。
妻のヴァレリーと
娘のアレクサンドラとソフィアだ。」
「ようこそ。ナッシュビルへ__ 。」
美しい双子姉妹の佇まいは、そこに居るだけで
その場の雰囲気を華やかにする。
ヒューゴは
息を呑むような美しさに声を失っていた。
ジェームズはフフと微笑み
「ヒューゴ君。
これが"南部のおもてなし"なのさ。」
ディナーは盛り上がった。
ヒューゴは粋なパリジャンで
アレクサンドラとソフィアにとっては
片田舎で育ったこともあり、
ヒューゴからユーモアたっぷりに
パリの街並みの美しさや
洗練された文化について話を聞かされて
すぐに打ち解けるのであった。
ヒューゴにとってこの双子姉妹との出逢いは
運命的なものを感じる。
(この方達と出逢えたことは幸運だ。
また逢いたい . . . 。)
ヒューゴは
ジェームズの畳み掛けるような人心掌握術に
完全にノックアウトされていた。
嵐の前の静けさ__
ヒューゴと云ふひとりの若者の出現は
双子姉妹にとっても運命的であった。
時代の流れの中で
何かが大きく変わろうとしていた。
十四、密談
「ねえ?ソフィア。今夜お見えになった
ヒューゴさんって面白い人だったね。」
姉のアレクサンドラに
アタシ(ソフィア)は
ヒューゴについての印象を訊かれてた。
父であるジェームズが招いてくる来訪者から
物珍しい眼差しで見られることは
当初は抵抗があったけれど
いつの間にか、
この環境に慣れてしまっていた。
ヒューゴは、はじめこそ緊張からか口数は少なかったが、他の来訪者と違って
一度打ち解けると裏表のない性格で屈託なく接してくれることが嬉しかった。
今でも
ヒューゴの話してくれた失敗談が
面白可笑しくて
思い出すとクスっと笑いが込み上げる。
ヒューゴの話はこうだった。
・
・
・
・
僕の住んでいたパリの街から
200kmくらい南下すると
シャヴィニヨルって村がある。
ロワール川沿いにある
緑のキレイな村だったよ。
親戚のピエール伯父さんは、そこで特産の
シェーブル・チーズ(山羊乳)を
作っているフェルミエ(酪農家)だったんだ。
毎年、夏になると伯父さんのところに行くと
美味しい白ワインとシェーブル・チーズに
ありつけたって訳さ。
伯父さんは"クロタン"って云ふ特産チーズを
村に売りにいくんだけど
ある年のことだ。
ピエール伯父さんところに住んで居る
小さな従兄弟アンリが
一緒に行きたいと駄々をこねだした。
馬車で村まで行く道中のことだった。
アンリの奴は売り物のチーズを
つまみ喰いしてたらしいんだ。
そして村に着いてからも
アンリはヘマをして、チーズを運ぶ時に
ひっくり返してしまった。
ピエール伯父さんは仕方なく
拾って箱につめ込んだが、
「あれ?ひとつ足りないぞ?」
と首をかしげる。
アンリの奴は伯父さんに叱られると思ったのか
偶然にも道端に落ちていた
本物のクロタン(馬糞)を奴は見つけた。
こともあろうに
「父上!あったよ!」と云って
アンリの奴は箱に詰め込んだのさ . . . 。
毎年、夏になるとお店の店頭には
美味しそうなチーズが並ぶ季節だ。
ピエール伯父さんは威勢よく
「ボンジュール!ムッシュ。
今年の夏も最高のチーズ__
クロタン・ド・シャヴィニヨルを
お届けに参りました!」
お店の店主が出てきて
「ピエールの旦那!いつもありがとよ!
今年の出来はどうだい?」
「あゝ任しときなって!
アンリ?チーズを持ってきな。」
とピエール伯父さんはアンリに云いつける。
アンリは内心
(これはまずいことになったぞ . . . 。)
と思いながら後には引けない。
恐々とチーズを運んでくるアンリ
奴がチーズを持ってきた途端に
辺りには異質の匂いが広がりはじめる。
「おい!ピエールの旦那?
なんだか臭わねえか?」
と店主が云ふ。
「ホントだ?なんかおかしいぞ?」
とピエールが鼻をヒクヒクさせる。
どう考えてもチーズの箱から匂ってくる。
ピエール伯父さんは不審な挙動をするアンリを
ジッと見つめる__ 。
もう隠し切れないと思い、アンリは白状した。
「アンリーーッ!」
伯父さんは目を剥いて、お仕置きに
アンリはお尻を叩かれまくったそうだ。
・
・
・
・
そんな笑い話しを交えながら、
ヒューゴは夢を語る。
「僕もアメリカで牧場を開いて酪農をするさ。」
と笑顔で話してくれた。
母のヴァレリーやアタシたち双子姉妹は
この青年の飾り気のない人柄を気に入った。
ジェームズが支援する色々な仕事の紹介で
ヒューゴが訪れてくるたびに
彼を食事に招いては、フランスでの出来事を
彼なりの諧謔ユーモアを織り交ぜては
話に花を咲かせるのだった。
ヒューゴのお気に入りは
シェーブル・チーズの入ったサラダで
胡椒・タイム・月桂樹・ネズの実・ニンニクを
と共にオリーブオイルに漬けたチーズを
野菜に絡めた前菜料理でアレクサンドラの
得意料理のひとつだった。
ヒューゴはいつも美味しそうに食べてくれたし
いつしかアレクサンドラはヒューゴのことを
想うようになっていった。
アタシもヒューゴと居ると楽しかったし、
彼を想う気持ちが自分の心の中で芽生えている
ことに気付いていた。
そう__
アタシたちはいつしか同じ人を
好きになってしまった。
・
・
・
・
ジェームズはニューオリンズに居る。
彼はフランス領事館に赴いていた。
政府からは執拗に若者たちを
連合国(南軍)への志願を取り付けるように
督促されていた。
領事館側としてはフランス本国の意向として
アメリカを元の分割地帯に戻すように
促されていたからだ。
ジェームズと云ふ男は元々は争いを好まない。
しかし、自分自身の内に流るゝフランスの血に
誇りを持っている。
ジェームズ自身が持つ、人心を操る交渉術で
これまでに何百人もの若者たちを
南軍に送り込んできた。
そのこともあり、エイプリルレイン家は
フランス政府からの信頼も厚く、
現在の地位を築いてきたのも
紛れのない事実である。
彼は核心を言葉にせずとも、若者を懐柔し、
その優雅な佇まいでたちまちに信頼を勝ち取り
ジェームズの信奉者となったところを
言葉巧みに若者の愛国心に火を焚きつける。
そして、多くの若者たちが前線に送り込まれ
命を散らしていったのだった。
ヒューゴも__
その内の一人に過ぎなかった。
・
・
・
・
ある日、ジェームズはヒューゴをディナーに
誘った時のことである。
アレクサンドラは
いつものように父ジェームズの書斎に通される
ヒューゴの姿を見掛けた。
(ヒューゴに逢いたい . . . )
アレクサンドラの想いは募るばかりであった。
(ごあいさつだけでも . . . )
と書斎の扉を叩いてみる。
しかし、返事がない。
アレクサンドラは恐る恐る扉を開けてみると
薄暗い部屋の中にはたれも居ないのである。
(あれ? さっき確かにこの部屋に入って行く
のを見掛けたばかりなのに。)
ジェームズは読書家であり、
夥おびただしい数の書物が本棚に並べてある。
アンティーク調の本棚の一部が扉になって
光が漏れている。
何やら話し声が聞こえてくる__ 。
声の主はジェームズとヒューゴであった。
(こんなところに隠し部屋があったなんて。)
アレクサンドラは不審な想いで
部屋の中から漏れてくる会話に耳を澄ませる。
「ヒューゴ君。どうだろうか?
君の意見を聴かせて呉れないか?」
とジェームズの声がしてくる。
「 . . . . エイプリルレインさん。
やはり俺は軍隊には入りたくありません。」
とヒューゴが云ふ。
「そうかね。ヒューゴ君、残念だが
これ以上の議論は私もしたくない。
私は君を息子のように思っている。
私の出来る限りの力添えをしたいと思ってる。
我がフランスの同胞の名の下に
君の決断は尊重するつもりだ。
いや、今夜はもうよそう。
ヒューゴ君。今夜も共に乾杯しよう。
私たちは君を家族のように思っているし、
心待ちにしていることだから。」
ヒューゴは押し黙ったまゝ
指を目に当てて
ひどく思い悩んでいる様子を見せて
「エイプリルレインさん。
あなたのご恩に報いたい。
もう少し気持ちを整理させて頂けませんか?」
と呟くように声を出した。
ジェームズは大きく頷いて
「良い返事を期待しているよ。」
と優しげな声を掛けながら、
両手の掌でヒューゴの手を包むようにして
背中を軽くポンポンと二度叩いた。
アレクサンドラは
父ジェームズが祖国のために仕事をしていると
しか聴かされていなかったが、
ヒューゴを__
彼を戦場に送り込もうとする意思があることを
知ってしまったのだった。
「さあて!今宵も娘たち共に
楽しいひとときを過ごそうではないか!」と、
ジェームズが席を立ち上がる素振りを見て
アレクサンドラは急いで部屋を後にした。
・
・
・
・
妻のヴァレリーは
夫ジェームズの仕事には
口を出さないように気を遣っていた。
娘であるアレクサンドラとソフィアにも
「父上様のお客様には心を込めて
歓迎するように。」と
常日頃から言い含めていたのであった。
アタシは無邪気なものて
「また、ヒューゴさんが来るのね?」
と楽しいディナーの時を待ち侘びるように
心をときめかせていた。
しかし、今になって思い返せば__
あの時のアレクサンドラの様子が
少しばかり違っていたことを
気が付くことが出来なかった。
アレクサンドラは何かを思い悩んでいた。
十五、ワイン色の虚実
その夜__
ヒューゴはいつものように
明るく屈託のない話で場を盛り上げていた。
母ヴァレリーとアタシたち姉妹は
いつもと変わりなく手料理を振る舞い
歓談に花を咲かせる。
ジェームズは地下にあるカーヴから
大切にしまってあった
自慢のコレクションの中の
ブルゴーニュ産のワインを開栓する。
「さあ!ヒューゴ君。今宵はとっておきの
フランス・ワインを我ら同志のために
乾杯しよう。」
ジェームズは
ワイン・グラスを揺らしながら
芳しい薫りを愛でるようにして
口に含んでいく。
ヒューゴも同じく
ワインを口に含んでみる。
高貴な薫りがする。
ヒューゴにとっては郷愁と云っていい。
華やいだパリの街並みが目に浮かぶ。
喉元を過ぎゆくにしたがい
紅の血潮が身体中の隅々まで流れていく。
まるで心と身体が溶けるように
酩酊する感覚であった。
宴もたけなわになった頃合いで
ジェームズは騎士道について語り出す。
ジェームズは
ワイングラス越しに映る
ヒューゴに向かって問いかける。
「時にヒューゴ君。
騎士道で最も必要な物はなんだと思うかね?」
ジェームズが発する問いかけは
ヒューゴにとって、南軍への帰属を促すように
聞こえてくる。
窓を背にしたジェームズの背景から180°旋回し
ヒューゴが答える番へと場面が切り替わる。
ヒューゴは
「忠誠心、名誉と礼節です。」と答えた。
少しの沈黙の間__
ヒューゴの背中の向こう側にある
格調高い振り子時計がチクタクと
時を刻む音が聞こえてくる。
「ヒューゴ君。何かが足りない気がする。」
声の主の方__
ジェームズへと、またもや場面が
180°旋回する。
ジェームズはワイングラスを見つめながら
「貴婦人への愛だ。」と答える。
ヒューゴは
「愛?それは何故に
そう思われるのでしょうか?」
ジェームズは
「強きをくじき、弱きを助く。
私は思うに、これがすなわち
愛であり騎士道たらしめる所以なのだ。」
ヒューゴは激しく酩酊しているのか、
ジェームズとの会話の間、
時計の時を刻む音がだんだんと大きくなる
感覚に襲われる。
会話する二人以外の背景が
走馬灯のようにぐるぐると巡り回っている。
(今夜は酔いが回っている。)
とヒューゴが思った矢先のことである。
ジェームズが
「君が軍に帰属するならば__
我が娘を娶らせようではないか。」
その瞬間__
巡り回っていた世界はピタリと止まり
ヒューゴの背後にある振り子時計が
静寂を破るように鳴りだした。
ジェームズは
ジーッとヒューゴを見つめる。
ヒューゴにとっては、心の奥底まで
見透かされているように思えた。
母ヴァレリーや双子姉妹も
ジェームズの言葉に呆然としていた。
アレクサンドラは
ヒューゴを見守るように遠い目をしている。
一瞬、ヒューゴと目が合う。
彼の瞳に宿る一抹の不安をアレクサンドラは
感じとっていた。
一同が沈黙をする中で
時計の鐘の音が鳴り響いていた。
ジェームズは
「私も酔いが回ってきたようだ。
だがな、私は本気でそう思っている。」
と付け加え
結論は急がない旨を皆に伝え、話題を変えた。
それからはいつもの調子で歓談は続く。
夜更けになって
「エイプリルレインさん。
お気持ちありがとうございます。
今宵はお招き頂き光栄でした。
それでは皆さまありがとうございました。」
ヒューゴはそう云って
夜の帳の中を帰路につく間
(このまゝではいけないな . . . 。)
と考えこむ。
帰路を照らす月明かりが
薄曇りの空におぼろげに光っている。
ヒューゴの胸中を察するかのように
夜空も優しさと哀しさが入り乱れる。
どこか遠くでコヨーテの遠吠えが
幽かに聞こえていた。
・
・
・
・
それから数日後
ヒューゴが南軍へ帰属したことを
ジェームズから知らされる。
ジェームズは
「アレクサンドラ、ソフィア。
明日はデビュタント・ボールだ。」
《上流階級の舞踏会》
いわゆる社交界デビューであるが、
参加条件は厳しく名家の子女に限られる。
デビュタントとは__
つまるところ、大人のレディーとして認められ
恋愛結婚の対象となったことを宣言することに
他ならない。
「お前たちなら、きっと社交場の華となる。」
とジェームズは云ふのである。
(ヒューゴとの約束はどうするの?)
アタシが思ったと同時に
アレクサンドラが訊ねる。
「ヒューゴは軍隊に入ったの?
なら、アタシは舞踏会には行かないわ。」
アレクサンドラが継父の意向に反抗したのは
初めてのことだった。
ジェームズは
「おや?ヒューゴ君は単身フランスから来た
ただの労働者だよ。
しかし、今回のデビュタント・ボールでは
南部でも有数のプランテーションの子息が
一堂に会する。
お前たちなら、もっと素晴らしい婿殿が
相応しいのだよ。」
と諭すように云った。
当主であるジェームズの決定は絶対だった。
「準備をしておくように。」
ジェームズはそう言い残して
この場から立ち去っていった。
アレクサンドラは
あの密室での会話を聞いて以来、
継父ジェームズの肚黒さと云ふものを
許すことが出来なかった。
(哀れなヒューゴ . . . 。)
アタシには母ヴァレリーの様子が
なんとなく寂しげに見える。
アレクサンドラは大粒の涙を流し
「私. . . 。聴いてしまったの。
ヒューゴさんは軍隊には入りたくないって。」
とすっかり憔悴しきってしまった。
アタシは心の中で
(ヒューゴさんはどう考えているのだろう?
男の人って、プライドとか立場に捉われて
物事を決めてしまいがちだから。)
双子と云っても
アタシとアレクサンドラはずいぶんと
性格が違っていた。
姉のアレクサンドラは繊細だけど、
大胆な行動力を持ち合わせていた。
アタシは、そんな姉のことを尊敬していた。
長所短所は表裏一体で
まるで性格の違うアタシ達姉妹は
お互いのバランスを補いながら
支え合ってきた。
(ヒューゴさんのことも心配だけれど)
「アレクサンドラ . . . 。
泣かないで?お願いだから。」
アタシはアレクサンドラの背中をさすり
ハグをする。
そして、母ヴァレリーも
アタシ達姉妹を無言で抱きしめるのだった。
・
・
・
・
ヒューゴは南軍に帰属することとなった。
その日を境に、
アレクサンドラは吹っ切れたように
父が連れてゆく社交場で輝きを見せた。
白いドレスコードにアルビノの肌色は
眩ゆいばかりの存在感を放ち
史上最高のサザン・ベルと周囲の羨望を
一身に集めるのであった。
ある男がアレクサンドラに声を掛けてきた。
「はじめまして。ジェイコブ・ロバーツです。
あなたのような
お美しい方にお目にかかれて光栄です。
ご一緒にダンスは如何でしょうか?」
アレクサンドラも笑顔を振る舞い
「あら?はじめまして。
アレクサンドラ・エイプリルレイン
と申します。」
ジェイコブは
(この女をモノにしたい。)
その透き通るようないで立ちを見た途端に
ジェイコブの中にある強欲の炎が渦巻くのを
感じた。
姉はジェイコブにエスコートされて
アメリカンスムースと呼ばれる社交ダンスを
踊りだす。
ジェイコブはよほど慣れているのか
ダンスもかなり上手であった。
アレクサンドラは
ジェイコブに身を預けている間、
とてつもなく虚ろであった。
(なにもかも、父上の掌の上で
踊りを続けなければならない。)
ガットリンバーグからナッシュビルへ来て
約1年が経つ。
(幸せとはなんだろう?)
ヒューゴを失ってしまってはいけない。
(彼を助け出さなければ . . . 。)
アレクサンドラの中に芽生える
ある沸々とした想い__
あの時のアタシには、
姉が破滅していくことを
止めることが出来なかった。
十六、枯葉
アタシ達双子姉妹が社交界にデビューしてから
ほどなくして、縁談が殺到するようになる。
光は輝くほどに、影もまた濃くなる__ 。
アレクサンドラは後悔していた。
あの舞踏会で知り合ったジェイコブが
執拗に執着してくるのだ。
ジェイコブはたびたび家に訪れるのだが
アレクサンドラは関わるまいと居留守を使い
無視を決め込んでいた。
「ねえ?ソフィア。
わたしが居なくなってもビックリしないで。」
とアレクサンドラが云う。
「えっ?突然どうしてそんなこと云うの?」
と問い返す。
「このまゝだと . . . ロバーツさんとの縁談
父上様に押し切られてしまうのよ。」
とアレクサンドラは思い詰めていた。
「ジェイコブさんのことね?
凄い大金持ちの御曹司だから、
父上様が話を進めたがっているみたいね?
アレクサンドラはあまり気乗りしないのね?」
と訊いてみた。
「わたし . . . ヒューゴさんのことが
ずっと頭から離れないの。」
とアレクサンドラは涙ながらに告白する。
「そうね。ヒューゴさん、
あれではあまりにもお気の毒だわ。」
アタシも同感だった。
・
・
・
・
ジェームズがかつて経営していたホテルは
南軍へ提供し、
現在では野戦病院として利用されていた。
ある日、病院が人手不足ということもあり
ジェームズは家中の使用人から何人かを
応援に出した。
また、慈善事業家としての面子を保つため
アタシ達姉妹を慰問の目的で訪問するように
云い渡された。
アタシ達は父上様の命を請け
病院に到着すると、
野戦病院の中は予想以上にごった返していた。
戦場で怪我をした兵士に付き添う者
到着した物資の分配をする者
野戦病院の清掃をする者
ありとあらゆる仕事を
こなさなければならない。
アタシ達姉妹は、傷ついた人達に
声を掛けたり、話を聴いては慰めたり
包帯を巻く、食糧の提供など雑務の応援を
手伝った。
アタシは
(屋敷の窓奥深くに暮らしているよりも
こうしてたれかの助けのために施す方が
性に合うみたい。)
その時である__ 。
見覚えのある顔を見つけた。
ヒューゴであった。
アレクサンドラは
「ヒューゴさん ⁉︎」
と云って駆け寄っていった。
ヒューゴは
アレクサンドラやアタシ達の姿を見ると
そそくさと足早に立ち去ろうとした。
「待って!お願いだから . . . 。」
とアレクサンドラが声を掛ける。
ヒューゴは一瞬立ち止まる素振りを見せ
しばらく考えている様子だったが
振り返ることなく、背中を見せたまゝ
立ち去ってしまった。
アレクサンドラは
その場にしゃがみ込んでしまった。
嗚咽が止まらないまゝで__ 。
・
・
・
・
ヒューゴは
南軍ジョン・ベル・フッド中将率いる
テネシー軍に配属されている。
戦況は日に日に北軍有利の状況であった。
ヒューゴは衛兵として、前線と本営の伝達を
任されていた。
(エイプリルレインさんとの約束がある。)
ジェームズ曰く
「娘を戦争未亡人にする訳には行かぬ。」
と釘を刺されていたからだ。
(たしかに一理ある。)
ヒューゴはもっともだと思っていた。
(戦争が終わるまでは生き延びなければ。
今は我慢のしどころなのだ。)
ヒューゴはそうやって
自分に言い聞かせていた。
・
・
・
・
ヒューゴとの思いもよらない再会を
果たしてからというもの
アレクサンドラは来る日もくる日も
ヒューゴが野戦病院に現れることを
期待して通い詰めていた。
また、一方では
ジェイコブも事あるごとに
エイプリルレイン家に立ち寄っては
アレクサンドラとの面会を希望してくる。
しかし、ジェイコブにとっては
アレクサンドラはいつも留守で
取り付く島もなく、なしのつぶてである。
ジェイコブは
ついに堪忍袋の緒が切れた様子で
「アレクサンドラは何処に居る?」
と執事に凄んでみせる。
この男は元来、何不自由ない環境で
我儘の限りを尽くして生きてきた。
(俺になびかない女は居ない。)
アレクサンドラのような
思い通りにいかない女は
今までに出会ったことがなかった。
それ故に、この男の欲望を一層と駆り立てる。
異様な執着心であることは
傍目に見ても感じられた。
エイプリルレイン家の執事は
この危険極まりない御曹司を
これ以上、放置することは出来なかった。
(ご主人様に知らせなければ。)
一方、ジェイコブは
アレクサンドラに会わせてもらえないことで
「ロバーツ家の名誉に泥を塗った。」
と激しくエイプリルレイン家の対応を非難し、
アレクサンドラと会うために
ロバーツ家の下僕たちを使って探し出す。
"可愛さ余って憎さ百倍"と云ふ諺ことわざがある。
まさに、この男の感情は__
舞踏会で抱いた胸のときめきから一転し、
いつの間にか、どす黒い感情で渦巻いていた。
・
・
・
・
ある雨降る日のこと__
アレクサンドラはいつものように
ヒューゴと再会するために病院に行く。
相変わらず病院は
人いきれ````でむせかえるように慌ただしかった。
その時である。
ひとりの負傷兵が担架で運び込まれた。
ヒューゴであった。
彼は前線で足に傷を負ってしまっていた。
命に別状は無いものの歩くことが出来ずにいたのだ。
アレクサンドラは担架に駆け寄り
「ヒューゴさん!やっと逢えた。
なのに . . . 怪我をしてしまってるのね?」
ヒューゴはアレクサンドラの献身的な行動に
観念したのか、本心を打ち明ける。
「黙っていてゴメン。
戦争が終われば__
僕は君にプロポーズをしたかったんだ。」
とヒューゴはアレクサンドラへの想いを
打ち明けるのだった。
「わたしもよ。ヒューゴさん!
ずっとこの日が来るのを待っていたの。」
アレクサンドラは
笑顔を見せながら落涙していた。
それからアレクサンドラは
家に帰ってこなかった。
彼女はヒューゴの側で看病を続けているのだった。
ヒューゴは幸いにも傷はあったものの快活さを
失うことはなく
次第にヒューゴも彼女の人柄に
強く惹かれてゆくのだった。
アレクサンドラは
ヒューゴから聴くパリの街並みの話が
大好きだった。
都会の憧憬に想いを馳せながら
「この戦争が終わったら__
パリの街を案内してやるさ。」
そして、名残り惜しそうに
「しかし、傷が癒えたら
僕は隊に戻らなければならない。」
アレクサンドラは
「いや . . もう少し一緒に居て . . . 。」
ヒューゴは無言で
きつく躰を抱きしめる。
そしてヒューゴはアレクサンドラに口づけを交わす。
ふたりのためだけに時が止まる__
キスをしている間
ふたりはシャンゼリゼ通りを共に歩み
モンマルトルの丘から観る
茜色から薄紫に染まる空の下で
パリの街中に煌めく幻想的な灯火のように
ふたりの愛が燦々と輝く。
いつしか、ヒューゴとアレクサンドラは
熱い抱擁を交わす。
ふたりの間に幸せの絶頂が波打つように
流れていくのを感じる。
ヒューゴの胸に頭をもたれかけ
アレクサンドラはこの上なく幸せを感じる。
(もう、わたしを離さないで__ 。)
夜の帳は落ちていった。
・
・
・
・
ジェームズは執事から
「ジェイコブは異常者かも知れない。」
と話を聞いた。
ジェームズは
「ソフィア?
アレクサンドラはいつも何処に居る?
お前が知っていることを教えてくれないか?」
アタシは
「ごめんなさい。知らないの。」
アレクサンドラが
ヒューゴとの逢瀬を叶えるために
足繁く野戦病院に通っていることを
黙っていた。
アタシとヒューゴとの関係は
姉ほどには思い詰めることは無かったし、
アレクサンドラに忖度する訳ではなかったけど
姉の一途な想いに心を打たれて
距離を置いて見守ることにした。
(これでいいんだわ__ 。)
窓の外には秋の終わりを告げる
一枚の枯葉が枝にしがみついている。
北風が運び去るのを見届ける__ 。
ゆっくりと 音もなく
ヒューゴへの想いは
胸の中から消し去っていくしかなかった。
(アレクサンドラ . . . お幸せに。)
この時、アレクサンドラを襲った悲劇を
アタシは知る由もなかった。
十七、絹の繭
冒頭より__
現在ではV・I・P御用達と名高い
マックスウェル・ハウス・ホテルには
南北戦争にまつわる悲しいエピソードが
人々の言い伝えによって残されている。
1863年9月__
何人かの南軍捕虜が階段が壊れて亡くなった。
ホテルはまたサザン・ベルと
南北戦争の衛兵だったとされる
ふたり兄妹の幽霊が出るとされた。
ひとりの女性をめぐり
嫉妬に駆られたひとりの男性が
兄妹を殺し、
遺体を運んでいるうちに
階段が壊れて亡くなったとされている。
Maxwell House Hotel
Wikipediaより
そのマックスウェル・ハウス・ホテルにて
ソフィアの話が
いよいよ佳境に差し掛かかろうとした
矢先のことである。
「少し一息つかせて頂けるかしら?」
とソフィアが申し出た。
ソフィア自身は話の続きがあるようだった。
しかしながら、
躰自体はパコ叔父さんの口を借りて供述するも
強打した頭部や長旅の疲れもあって
顔色に疲労の色が滲んでいるようだった。
カルロスは気を利かせて
ソフィアに諭すように話しかける。
「どうだろう? 夜も更けたことだから、
今晩はここらへんで。」
ソフィア(パコ)はうなづいた。
「それと今夜は遅くなった。
今夜は君たちも一緒に泊まりなよ?」
と俺たちに声をかけてくれた。
俺とユーレクは顔を見合わせて頷いた。
お互いに異論はなかった。
「あゝカルロス、いいともさ。
気遣ってくれてありがとうな。」
と礼を云った。
こうして、今夜は贅沢にも俺とユーレクは
ホテルに滞在することになった。
・
・
・
・
眠りに着くまでの間__
今日一日を振り返ってみても
橋の渋滞騒ぎから牛を曳いて集めたりと
躰はクタクタになっていたのだが、
ソフィアの話しを聴いてしまったせいなのか
部屋の灯りを暗くして目を瞑ってみても
俺はなかなか寝付くことが出来なかった。
二重人格、または霊的に憑依した__
と思われるソフィア
パコ叔父さんが
完全に別人格になりきっていたこと自体が
衝撃的な出来事であったし、
聴いた内容も、取り繕った感じもない。
しかし、ソフィアの話の中で
気になる部分があった。
「なあ?ユーレク。起きてるか?」
と声を掛けてみる。
「あゝ、起きてる。」
とユーレクから返事があった。
ユーレクもまた眠れないでいたらしい。
「ユーレク、不思議に思わないか?
以前にユーレクが見た夢の話しと同じで
ユニコーンが現れるってところ。」
と訊いてみる。
ベッドで横になっているユーレクも
「全く同感さ。俺たちがここに来たのは
その夢と関係しているのかも知れないな。」
と答えてくれた。
その時である。
たれか部屋の前を
通り過ぎていく足音が聞こえる__ 。
夜更けも午前1時を過ぎた頃である。
俺とユーレクは顔を見合わせる。
何者かが通り過ぎていったことを確かめようと
そろりと自室の扉を開けてみると
廊下にはたれも居ない。
仄ほのかな灯りに照らされた暗い廊下が続くだけで
夜のホテルは静まりかえったように
不気味な空気を醸し出している。
(たしかに気配がしたはずなんだけど?)
何故かは解らないが
この廊下の先にある何者かの存在に
惹き寄せられるように
俺とユーレクは
真夜中のホテルを探索することにした。
廊下の先にある階段付近まで来てみると
何やら囁ささやく声が聞こえてくる。
それは言葉としては聞き取れなかった。
身を乗り出して、階下の階段の踊り場付近を
目を凝らして見る。
そこには白髪の美しい女性の姿が
揺らめいて見えていた。
それはこの世のものでは無かった。
そのいでたちは周りの風景に溶けこむように
絹の繭で形造られたような光沢を放ちながら
半分は透けて見えているのだ。
そして、消え入るように幽かな声が聞こえた。
「んごごぐが . . . ヒューゴさん . . . 何処に . . . 居る . . 」
ユーレクは
「君はいったい、何者だ?」
と声をかけた。
人の姿をした絹繭の煙は
ノイズ混じりの声で頭の中に語りかけてくる。
「ヒューゴさん . . . ぐがが . . . 何処に . . . 居る . . . のぐぐ . . . 私 . . . 彼を探して . . . ぎごご . . . いるの . . . 」
「君は . . . ⁉︎ ソフィアかい?」
俺は恐る恐ると訊ねてみた。
「彼を探して . . . ぐががごご . . . カンバーランドの . . . 川の底へと . . . 」
と云ったきり寂しげなオーラを発していた。
次の瞬間__
絹繭の煙は躰をのけぞらずようにして
目の前から忽然とその姿を消してしまった。
「. . . ⁉︎ 」
またもや
俺とユーレクは目を見合わせる。
「見た . . . よな?」
と俺は生唾を飲み込むようにして
ユーレクに問いかける。
「あゝ、見たともさ . . . 。」
ユーレクも頷いて呆然としていた。
俺たちは幻を見たのだろうか?
その夜__
それきり、その女性の姿をした絹繭の煙を
見ることはなかった。
・
・
・
・
翌朝になって
ホテルの従業員に昨晩の出来事を話してみる。
従業員は少し困ったような顔をして
「少しホテルの外へ出られませんか?」
と促された。
人目の付かない場所に移動すると
従業員はため息混じりに
「お客様。このホテルは幽霊が出ると云う噂は
ご存知なかったのですね?」
従業員曰く
どうやら以前から地元では有名な話で
ここのホテルに幽霊騒ぎがあったことは
市中の人々の言い伝えとなっていたのだった。
噂に尾ひれはひれ付いて、巡り巡って
いつしか、
衛兵とサザン・ベルはふたり兄妹と云うことで
「兄妹は近親相姦の恋仲で
世間の目を苦にしたことから心中した。」
と云い伝えられて
人々の間では定着していると云う。
ホテルの従業員たちの中では
ふたりは兄妹などではなく、かなりの家柄の
御曹司が恋仲のふたりに嫉妬して
凶行に及んだ、または関与していたのでは?
と噂されていた。
「それは、従業員の仲間の方も
あの幽霊と話をしたんですか?」
と訊いてみた。
従業員は首をコクリと頷き
「"ヒューゴという男を探している。"と
夜な夜な女性のすすり泣きが聞こえるって
私たちの間では、そう認識してます。
オーナーからは"かなりの家柄の御曹司"は
緘口令かんこうれいが出されており
固く口止めをされているんです。」
俺とユーレクは昨夜の出来事は
幻なんかじゃなかったと確信に至り、
ソフィア(パコ)の供述と合致しており
昨日の出来事や噂の断片を繋ぎ合わせると__
タブーにされている事実が浮かび上がる。
「ユーレク?何の因果か分かんないが、
俺たちエライことに巻き込まれているような
気がしないか?」
「神の思し召しってヤツだよ。フェルニー。」
ユーレクは口元に微笑みを浮かべるのだった。
十八、慟哭
一晩明けると
パコ叔父さんは
すっかりと正気を取り戻していた。
俺たち四人は
ホテルのレストランで
英国風のフル・ブレイクファストを注文し
食卓を取り囲んでいる。
パコ叔父さんは
熱々のトーストに
マーマレードをたっぷりと塗り
嬉々とかじりついて
「おほぅ!こりゃ美味しいねー!」
陽気なスペイン系アメリカンらしい快活さを
取り戻しているようであった。
不思議なもので昨日の間、
ソフィアという女性の別人格だったことは
全く記憶に無いらしい。
「いやぁ〜、
君たちにはすっかり世話になったねぇ!」
パコ叔父さんはカルロスから
卸した牛追い業務の売上げ高の報告を受けて
至極ご満悦の様子だった。
・
・
・
・
俺たちは深夜の出来事について__
ソフィアもしくはアレクサンドラ
と思しき残留思念が伝えようとしたメッセージ
ソフィアに真意を問うことで
彼女自身が知っている深い意味を
訊いておかなければならないと思っていた。
しかし、それも叶わなくなったようだ。
カルロスは俺たちの話を聴こうと
話題を向けてくれた。
「それで?夜中に幽霊を見たんだって?」とカルロスが問いかける。
「そうなんだよ。
ここのホテルのもっぱらの噂ではあったけど
俺たちは本当に目撃したんだから . . . 。
このホテルこそが
過去に野戦病院の舞台だったこともあり、
ヒューゴの行方を探す霊が現れるらしいぜ。
昨日のソフィアの話しと当てはまるんだよ。」
と俺は熱を込めて云った。
ユーレクは付け加えるように
「たしか、"カンバーランドの川底に"って
云いたげだったような . . . 。」
と思い出していた。
俺たちが話している間中、
パコ叔父さんは神妙に耳を傾けていた。
カルロスは
「カンバーランドの川底って、行っても
どのあたりか見当もつかねえや。」
俺たちが途方に暮れていると
パコ叔父さんは
「だったら、ふりだしに戻って
ウッドランド通り橋に行ってみることだな。」
と云ふのである。
「なるほど!」
俺たちとカルロスはパコ叔父さんの言葉に
背中を押されるように頷いていた。
事の発端であった橋の上に行ってみれば
何かわかるかも知れない。
パコ叔父さんは
「今度はワシがお前たちを助ける番だよ。
ワシに考えがある。
街に行って色々と調達するから
後で橋の下で落ち逢おう。」
・
・
・
・
俺とユーレク、カルロス、叔父さんの4人は
ウッドランド通り橋のふもとに集合した。
事の発端とも言える
橋の中ほどまで歩いていく。
「昨日は確かこの辺りだったような?」
(相変わらず俺には特に何も感じないな。)
と思っていた矢先である。
急にあたり一面の空に黒雲が広がりだす。
目に見えるもの全てが色を失ったかのように
モノクロームの光と闇が覆いだす。
ユーレクが
「熱っ!」と呻いた。
おもむろに懐から原石を取り出すと
蛍光色を帯びた光を発している。
それは光に反射した輝きとは違い、
自ら発光していた。
原石から発せられたその霊的なオーラが
絹の繭のような煙となって
人の形を為しているように見える。
突然、フラッシュバックが始まる。
サブリミナルな映像が矢継ぎ早に
目に浮かんでは飛び込んでくる。
(これはいったい?何が起こっているんだ?)
俺はその場で気絶してしまった。
・
・
・
・
気が付くと、俺は病院の中に居た__。
望遠鏡のように視界が狭く、
ピントもおぼろげである。
まるで、たれかの記憶の中を
壁穴から覗いているような感覚だった。
ジェイコブは
アレクサンドラが野戦病院に居る
と聞き付けて駆けつけていた。
しらみつぶしに夜の病院内を探し回る。
悲劇の扉が開いた__ 。
ジェイコブの目に映っているのは
負傷兵とアルビノの美しい女性が
裸で抱き合う姿だった。
ジェイコブは逆上した。
頭に血が昇り、瞳孔の開いた眼に
陽炎のような視界が揺らめいている。
女が何か叫んでいるが、よく聞こえない。
ジェイコブが気がついた時
負傷兵の男が血塗れになって横たわっている。
「これでお前は俺のものだ。」
と薄ら笑いを浮かべるジェイコブは完全に常軌を逸していた。
「俺はまた迎えに行くからな。」
と云って
手下を従えて夜の病院から去っていった。
・
・
・
・
ヒューゴは事切れていた。
ヒューゴの屍の側で
アレクサンドラは慟哭していた。
声にならない叫びを上げ続けている。
哀しみに暮れたアレクサンドラは
幸せの時間を無残に奪われていった。
魂が抜け切って虚しくなった彼女は
意味不明の行動を取っていた。
夜の病院から外へ向かう非常階段へと
ヒューゴの屍を運んでいた。
その時、階段が突然崩壊する。
アレクサンドラはヒューゴの屍と共に
奈落の底へと堕ちてゆく。
アレクサンドラがこの世で最後に見たのは
カンバーランド川の水底へと堕ちていく
ヒューゴの姿だった。
手を差し伸べても届かない。
愛する人の姿が
自分の吐く息が泡となって
視界をかき消していく。
やがて、アレクサンドラも力尽きる。
カンバーランド川に弛まなく水は流れ
白く漂うアレクサンドラの屍が
ふたりを引き離すように
漂い流されてゆく。
翌朝、アレクサンドラは溺死体となって
発見された__ 。
・
・
・
・
「フェルニー!大丈夫か!」
ユーレクの声に呼び戻されで目を覚ました。
(なんだ . . . ⁉︎ 怖ろしい光景だったが?)
俺は気絶している間に見た光景に震えながら
皆んなに話して聞かせると、
奇遇にも、俺を含めて4人共に
同じ映像を観たようだ。
「ユーレク?これって一体?」
と訊いてみると
「サイコメトリーいわゆる残留思念だな。」
ユーレクはこの原石を拾ってから
たびたび、そのような事があったらしい。
「しかし、
これほどまでに強烈な思念は観たことない。」
ユーレクの話する間、
カルロスとパコも呆気に取られていたが
パコ叔父さんが
「この話、知ってるぜ。
もう30年も前の話で、ガキの頃だったか
白い溺死体が流れてきて、検分すると
それが、当代随一のサザン・ベルだったって
話さ。」
ソフィアにしろ、アレクサンドラにしろ
およそ伝えたかったに違いない話の全容は
掴めたような気がした。
・
・
・
・
パコ叔父さんはナッシュビルの街で
色々と物資を調達してくれた。
「ワセリンを用意してきたぞ。
小春日和とは言え、潜水するにも水温が低い。
潜るにはワセリンを身体中に塗りたくって
体温が低下するのを防ぐんだ。」
さらに、パコ叔父さんは
ガンベルトからいくつか弾丸を取り出して
「この弾丸から火薬をこうやって取り出して
仕入れてきた石灰と樟脳カンフルを混ぜるんだ。」
すでに配合した火薬を染み込ませた綿を
木の棒先にくくりつけた何本ものトーチを
用意してくれていた。
「見ろ!」
と云ってトーチの先を川の水に浸してみせる。
しばらくすると、バチバチと音を立てて
なんと水中で灯火が点された。
カルロスは
「すげぇや!叔父さん!」
と感嘆の声を上げる。
パコ叔父さんは
手製の水中トーチの灯りを満足そうに見つめ
「これで、暗い水底でも灯りが照らせるさ。」
さすがは経験豊富であった。
俺とユーレクは
年季の入った知恵を惜しみなく披露する
パコ叔父さんをあらためて見直したのだった。
俺とユーレクはさっそく
全身にワセリンを塗りたくる。
ヒンヤリしたゲルが冷たかったが
やがて全身が温かみに包まれ、
時折吹く北風も寒く感じなくなった。
目指すは橋の中ほどの最深部を目指す。
ロープを腰に巻き付けて、橋上からカルロスとパコ叔父さんに引き上げてもらう。
「さぁ!行くぞ。フェルニー!」
ユーレクの掛け声と共にカンバーランド川に
飛びこんだ。
予感は的中した__ 。
水中トーチが照らす川底に待っているのは
寂しげな骸むくろの人影が横たわっていた。
十九、泡沫に消えゆく幻
川底には仄かな灯りに照らされて
男が横たわっている。
(コポポ . . . コポポポ . . . )
俺の吐く息が泡となる音が聞こえるだけで
静寂が広がっている。
およそ20メートルほど潜った水底には
何者かの屍が横たわっていた。
(これがヒューゴの
成れの果てなのだろうか?)
南北戦争の時代から30年が経過しており
白骨化することなく人の姿を留めていることが
奇跡である。
俺は息が苦しくなってきた。
(だめだ。息が持たない。)
俺はいったん水面に顔を出そうと
浮上する。
「ふはぁー . . .」
俺もユーレクもほぼ同時に水面に顔を出して
息継ぎをしていた。
カルロスとパコ叔父さんは
俺たちが川面に浮上している間は
躰に結んだロープを引き上げてくれている。
浮上中は橋上からロープで吊ってもらうことで
地上との連携を取る際に体力を温存し
潜水による川底の捜索を
より安全に行なうことが出来るからである。
「おーい!どうなっている?」
橋上からカルロスが声を掛けてくる。
「たれかの屍があるみたいだ!」
と俺は叫んだ。
ユーレクも神妙な面持ちで深く頷いていた。
パコ叔父さんは
代わりの水中トーチとロープを投げ入れて
「そのロープをホトケさんDrowning manに結えてくれ。」
「任せときな!」
俺とユーレクはふたたび川底へと潜る。
水中トーチで川底を照らしながら
先ほど遭遇した人影を探索する。
俺もユーレクも水中に潜って居られるのは2分が限界だ。
深く潜るほどに水圧も増して頭の中でキーンと
圧迫されるような耳鳴りがする。
その時、
ユーレクが指を差した先に人影が見えた。
その人影はひどく孤独であった__ 。
世界広しと云へども
これほどまでに人目から切り離され
或いは忘れられる存在とは
このことであろうか。
息苦しさが度を増して襲ってくる。
躰は水圧で軋むかのようで
全身が悲鳴を上げ始めた。
俺たちは
川底の屍に用意していたロープを結える。
ぬめっとした感触がする。
腐敗が相当に蝕んでいるのだろう。
何とか縛り上げることに成功した。
(可哀想に。あともう少し . . . 待ってろよ。)
ユーレクと合図を交わし
一目散に水面に浮かび上がろうと泳ぎ出した
瞬間の出来事であった。
屍の口元から無数の泡が吐き出される。
「⁉︎」
信じがたいことに
またもや残留思念のような映像が
頭の中に訴えかけるように
フラッシュバックする。
・
・
・
・
「ママmaman! ママmaman!」
小さな男の子が走り回っている。
街並みはカラフルなカフェやマルシェが
色とりどりの花束のような軒並みで街を彩っている。
「ママmaman!お菓子作ってくれるの?」
と小さな男の子は嬉しそうにはしゃいでいる。
母親と思しき女性は
しゃがみ込んで男の子の目線に合わせて
ニッコリと微笑んだ。
「そうよ。ヒューゴ。
あなたがお利口さんだからママがお菓子を
作ってあげるからね。」
「わぁーい!ママ大好き!」
男の子は満面の笑みで街並みを走り回る。
「おーい!坊や。ちょっとこっちにおいで。」
花屋のおじさんが男の子を呼ぶ。
「なあに?」
男の子は花屋のおじさんに呼ばれると
一輪の小さな花を手渡された。
男の子は神妙な面持ちで
花屋のおじさんの言うこと聴いていた。
「うん!わかったよ。おじさんありがとう。」
男の子は母親に歩みより
背伸びをして母親のブラウスの胸ポケットに
ラベンダーの花を挿した。
「あら?小さな紳士さん、ありがとう!Merci Monsieur」
胸のすくような花の香りが鼻腔をくすぐる。
男の子は母親に頭を撫でられて
手のひらから伝わる優しい温かさに
無垢そのものの眼差しを向ける。
「エヘヘッ!」
青空は目映く__
男の子の笑い声が街並みの雑踏に
溶けてゆく。
泡はプクリと音を立てて
水面へと消えていった。
・
・
・
・
パリ市街の北にあるモンマルトル近く
窓からぶどう畑がよく見える
部屋の一室に場面は移る。
「お母さん。俺はアメリカに行くよ。」
青年は決心を固めていた。
まだ見ぬ夢の果てにあるもの__
若さとは時に無謀であり
愚かに映るのかも知れない。
「ヒューゴ . . . 私は離れていても
いつも見守っているわ。」
母親は息子を抱きしめる。
(今生の別れになるかも知れない。)
ふと、母親の心に一瞬不安がよぎる。
言葉は裏腹に
不安な心をかき消すようにして
「神のご加護があらんことを__ 。」
窓から入る風がテーブルに置いてある
聖書のページをハラリハラリとめくっていた。
"箴言4章:23節 力の限り、見張って、あなたの心を見守れ。いのちの泉はこれから湧く。"
と書かれているページに目が留まる。
「ヒューゴ . . . あなたは私の宝よ。
その心のまゝに生きててちょうだいね。」
母親は愛する我が子の巣立ちを祝福した。
いつか見たラベンダーの押し花が
聖書のしおりとなっている。
「お母さん . . . お母さん . . . ありがとう。」
そして、またひとつ
泡がプクリと音を立てて消えていった。
・
・
・
・
さらにまた、
白く美しいアルビノ女性の場面に切り替わる。
「少し外の風に当たろうか?」
青年は負傷した足の具合もずいぶんと回復し
「松葉杖も慣れておかないとな。」
と笑顔を見せる。
その美しい女性はにこやかに微笑んで
「ヒューゴさん。付き添うわ!」
ふたりは
非常階段の踊り場に出てみると
眼下にはカンバーランド川が広がる。
秋の風がプラチナブロンドの髪を靡かせる。
「気持ちの良い風ね。」
そして、女性はそっと
頭を青年の肩に寄せる。
思わず青年は
持っていた松葉杖を落としてしまう。
少しよろけた瞬間
女性は寄り添うように青年の身を支える。
「ごめん . . . 。」
と云って青年は階段の手すりを掴もうとする。
女性は耳元でささやくように
「いいの . . . 。このままでいいの。」
そういって固く抱きしめる。
言葉は要らなかった。
女性は青年の耳たぶにくちづけをすると
青年は女性の肩に手を回して
目を見つめ合いながら
何か愛の言葉をささやいている。
くちびる同士が微かに触れ合う。
ふたりは情熱的なフレンチ・キスを交わして
絡み合う舌から伝わる脳天が痺れるような
幸福感に満ち溢れる。
ふたりを見守るように
カンバーランド川は静かに流れを湛えていた。
そして
泡はひとつひとつの想い出を包みながら
透き通る青の世界に弾けて消えてゆく。
水面から射す陽光が
無数の泡を乱反射させていた__
・
・
・
・
俺たちは不思議な感覚に包まれながら
ようやく水面に顔を出した。
カルロスたちは俺たちが浮上するのを見届け
「おーい!どうだった?」
と声を掛けてくれた。
俺とユーレクは親指をグッと突き立てた。
「首尾よく行った!このまま岸まで
ホトケの
誘導をたのむ!」
と地上向かって伝える。
カルロスたちは慎重にロープを引き上げながら
ダウンタウン側の船着場まで誘導する。
俺たちは岸まで泳ぎ渡り、陸に上がると
カルロスたちが携えているロープをゆっくりと
引き上げはじめる。
水面に褐色に朽ち果てた人の形をした物体が
浮かんでくる。
水底で見たものとは違う__ 。
激しく腐敗が進行したさまに
俺は思わず目を背けてしまった。
(こんなになるまで . . . たれにも気付かれずに
とても寂しかったろうに。)
ヒューゴの希望の翼は哀れにも
打ち砕かれたのだ。
俺とユーレクが見たものは
ヒューゴと云ふひとりの青年の儚き夢__
泡となり潰えてゆく幻をみたのだろうか。
俺たちの引き上げた亡骸は波紋を呼ぶ。
ナッシュビルの街は人々の噂が飛び交い
騒然とざわめき出すのだった。
二十、繋がった刻印
《Je t’aime pour toujoursわたしはあなたを愛しつづける___》
カンバーランド川岸の港は
物資運送の要衝として
港湾には人々の活気が漲みなぎり往来も多かった。
俺たちは遺体を引き上げたため
港湾で働いている人々を驚かせたと同時に
好奇の目を引いてしまい
あっと言う間に野次馬が群がってきた。
パコ叔父さんはしどろもどろしながら
事の顛末を尋ねられては応対に苦慮していた。
「いやぁ〜 . . . 川に大切な形見の指輪を
落としちまってな . . . 。
この子たちに探してもらったら、
"人影がある。"
って云ふんで引き上げてみたら . . .
今じゃ、この騒ぎだ!」
「結局、指輪は見つからなかったけどな!」
と肩をすくめてみせる。
やがて、治安を取り仕切る郡保安官の連中が駆けつけてきた。
地元ナッシュビルではちょっとした事件となった。
・
・
・
・
野次馬の群衆の中に
あるひとりの初老の男がいた。
彼は愛想が良く人懐っこい雰囲気で
野次馬たちをかき分けて近づいてくる。
「おい。若わけぇの。
そのホトケさんDrowning manをよく見せてくれないか?」
と俺に声を掛けてきた。
彼の名前はトーマス・オーウェンと云い
既に引退しているものの
元々は腕利きの郡保安官だったらしい。
「あゝ、いいともさ。」と
気丈に返事をしたつもりだったが、
すっかりと腐乱している遺体を前に
色を失った顔つきをしていたのだろうか。
トーマスは俺を労わるように語りかける。
「若わけぇの。
余程ショックだったんだろうが、
お前さんはよくやった!偉いよ。」と云って
ホトケさんDrowning manをまじまじと観察している。
すっかりと腐乱した亡骸には
左手の薬指に
黒くくすんだ指輪が見える。
トーマスはおもむろに
亡骸から指輪を取り外そうとする。
それを見ていた若い保安官補が注意を促す。
「あぁっ?そこのおじさん!
検分してるから勝手に遺体に触らないで!」
トーマスは穏やかに
「あぁ?分かっているとも。
ところでお前さん。この仕事は駆け出しか?」
若い保安官補は
「アンタ何者だい?
関係ない者はあっちに行ってな!」
と息巻いた。
トーマスは
「いやぁ. . . そう言われると詮もない。
ワシはな。昔この辺りを取り仕切っていた
保安官のオーウェンって言うんだ。
30年前にサザン・ベルの溺死事故ってのが
当時、ワシの抱えていた事件があったが
どうにも理由は判らんが捜査は中止になって、
その時に亡くなったサザン・ベルの指輪が
今そこにあるホトケさんDrowning manの指輪にそっくりなのさ。
その指輪をよく見せてほしいんだ。」
若い保安官補は
「ああ!オーウェン保安官でありましたか!
大変失礼しました。
ボスよりかねがねご高名は伺ってました。」
そう言うなり保安官補は
亡骸から指輪をそっと抜きとってトーマスに
手渡した。
トーマスは相槌を打って
指輪に付着していた垢や埃を払い落とし
経年劣化した表面を丹念に磨きだした。
その様子は
往年の保安官の目つきに戻って鋭さがあった。
食い入るように指輪をしげしげと眺めている。
「やはりな . . . 。」
指輪の裏側に刻印が彫ってある。
《Je t’aime pour toujours 〜Alex to Hugo 》
トーマスはあの30年前の事件のことが
想い出されるのだった。
・
・
・
・
以下、トーマスの回想による__。
1863年 秋
ナッシュビルのダウンタウンから
約5kmほど離れたカンバーランド下流に
美しい白い肌をしたホトケさん溺死体が発見された。
ワシは当時
ディヴィッドソン郡の保安官Sheriffで
駆けつけたころにはすごい人だかりだったさ。
野次馬たちが口々に噂をし始めていた。
「アレはサザン・ベルのアレックスだぞ⁉︎」
そんな言葉が飛び交っている。
ワシは群衆を掻き分けて発見現場に行くと
そこには見たこともないような
ひときわ美しい白い肌の亡骸があった。
濡れた水滴が朝陽に照らされ乱反射している。
(不謹慎だが、これほど美しい亡骸は
見たことがない。)
"サザン・ベルのアレックスと言えば
当代随一の絶世の美女"と名を馳せていた。
検死が進むにつれ
彼女の死因については目立った外傷はなく
純然に"溺死"であることが判明した。
また、身につけていた遺品には
左手薬指に指輪をはめていたことだった。
《Je t’aime pour toujours 〜Hugo to Alex 》
指輪にはフランス語と英語を織り交ぜた
刻印が施してあった。
(これはエンゲージリングに相違ない。)
ワシは事故と事件の両面で
まずは指輪の贈り主であるヒューゴの
居場所を探さなければならなかった。
事故起こった翌日
遺体はナッシュビルの名士と名高い
エイプリルレイン家の双子の姉である
アレクサンドラ・エイプリルレインと
断定した。
当時は、南北戦争の真っ只中であり
戦死した兵隊の亡骸と共に
彼女の亡骸は荼毘だびに付された。
この頃、当主のジェームズは
敗色濃厚の南軍側に与していたこともあり
自宅の屋敷を不在にしていたことが多く
ワシがエイプリルレイン家に訪問した際は
すっかり憔悴し切った母親を支えるように
対応してくれたのは、
もう一人のサザン・ベル__
ソフィアだった。
ワシは事の顛末を告げ、
「ヒューゴと言う人物を知っているか?」
と問うてみた。
ソフィアはひどく悲しそうな顔で
「ええ。彼とは家族ぐるみで食事もしたわ。」
と答えた。
「ヒューゴさんに姉はとても一途な恋心を
抱いていたのがアタシには手に取るように
判っていたのよ。
保安官さん?
この指輪がアレクサンドラの遺品なのね?
ヒューゴさん . . . 脚にケガしてらして
病院で手当をしていた間はアレクサンドラが
付きっきりだったはずなのに . . . 。」
ソフィアは気丈な娘だったが
躰を震わせるようにして悲しんでいるのが
ワシも見ていて辛かった。
「左様でしたか。
辛いことを想い出させて悪いのだが
、
他に何か思い当たる出来事はなかったかな?」
ソフィアは沈んだ声で
「姉にはもう一人の婚約者が居たの。
ロバーツさんって言う
テキサスの名家のご子息__
たしかジェイコブってお呼びしてましたわ。」
「ほほぅ。どんなお方か覚えてますか?」
「とても情熱的に__
我が家にお足を運んでいらしたのだけれど
アレクサンドラは会いたくなかったみたい。」
「なるほど。ジェイコブさんとどのように
知り合われたのですか?」
「とある社交場でのパーティーです。
たしか . . . 姉とダンスを踊ったのが
知り合ったキッカケで . . .
それからと言うもの継父から縁談を薦められ
姉は苦悩してましたわ。」
「これはアレクサンドラさんの遺品です。」
ワシは亡骸から抜き取ったエンゲージリングを
ソフィアに手渡した。
ソフィアは指輪に刻まれた刻印を
眺め
「ヒューゴさんは姉を裏切るようなことをする
御方ではございません。」
ソフィアは憔悴しており
とても悲しそうな声だったが
キッパリとした口調で云ふのだった。
ワシはソフィアと語るほどに
純粋に姉を慕う気持ちが溢れてくることを
感じずには居られなかった
それからワシは
テキサス名家の御曹司
ジェイコブ・ロバーツへの接触を試みたが
当時、南軍側の要請によって
サザン・ベルの溺死事件は
デイヴィッドソン郡保安局としては
事故として処理するように沙汰止みとなった。
ワシがあの時感じた"勘"はざわついたまゝ
真相は闇に葬られようと
していたのかも知れない。
・
・
・
・
話は1893年 現代に戻る。
「ありがとよ!」
トーマスは若い保安官補に礼を云った。
「あの . . . オーウェンさん?」
俺は当時のトーマスの話を聞いて
ソフィア(パコ叔父さんの口を借りて)の話と
あまりに辻褄が合っており、
ソフィアの所在を訊いてみた。
トーマスは虚しく首を横に振り
「エイプリルレイン家は滅亡したんだ。
ジェームズは南軍側を支援していたが
戦争に巻き込まれて亡くなったのさ。
ソフィアは母親ヴァレリーと共に
故郷のガットリンバーグで余生を暮らしたが
ほどなく亡くなったと噂で聴いたさ。」
トーマスは
「どうやらお前さんたちは
ソフィアと縁があるようだな?
俺はこの通り
すっかり年老いてしまったが
あの時のソフィアの言葉が確信に至ったよ。
これはやはり事件だったんだと。」
ユーレクは黙って聞いていたが、
意を決するようにトーマスに尋ねた。
「オーウェンさん?
郡保安局に頼んで、ヒューゴのお骨を
アレクサンドラのお墓に弔いたいんだ。」
トーマスは笑顔を皺くちゃにして
「若わけぇの!お前さん立派だよ!」
トーマスは俺たちに見せまいと
後を向いてシャツの袖で涙を拭っていた。
トーマスは懐から大切にしまってあった
エンゲージリングを取り出して
俺とユーレクに託した。
「これはお前さんたちに託したよ。
今は内戦の時代
人々の心も荒んでいる。
だけど、お前さんたちは心の耳を澄まして
とてつもない物を見つけたんだから。
・
・
・
・
カルロスとパコ叔父さんとは
ここでお別れだった。
「本当に良いのかい?
ナッシュビルからガットリンバーグまで
目的地と反対方向に220マイルほど東に
戻らなきゃなんねえぞ?」
俺とユーレクは
「いいんだよ!こちらこそありがとう!
アンタ達のおかげで不思議だけど貴重な体験
させてもらったよ。」
「達者でな!坊やたち。」
パコ叔父さんはまた新たな牛追いの仕事へと
西へと戻っていく。
俺たちはガットリンバーグへと旅路を東へと
そこに何が起こるかは解らないけれど
行かずには居られない。
トーマス・オーウェンは別れ際に
ニーチェの詩を贈ってくれた。
世界には、きみ以外には誰も歩むことの出来ない唯一の道がある。
その道は何処に行き着くのか、
と問うてはならない。
ひたすら進め__ 。
「 adiós amigo!さらば友よ」
カルロスと交わした別れの言葉が
夕焼け空に高くこだましていた。
二十一、狙撃
俺とユーレクがナッシュビルの街を離れてから
一週間が経つ。
双子姉妹を巡る不思議な縁に導かれて
俺たちはヒューゴの遺骨を
ガットリンバーグの地下に眠っている
双子姉妹の下へと届けようとしている。
目的地ツーソンと逆方向に進路を取りながら
俺たちはそれぞれの運命を噛み締めるように
東へと歩みを進める。
思えば
ユーレクと共に旅を始めて以来、
予測不能の出来事によく遭遇するし、
思いもよらぬトラブルに巻き込まれたりする。
俺からしてみれば
ユーレクの選択する行動がこのような
因果関係を生じてさせているように思える。
そのユーレクはテンガロンハットを目深に被り
馬上で夕焼けを背にして、
穏やかな眼差しを讃えている。
ユーレクの持つ何か__
それはとてつもなく澄んだレンズ越しの
独特の視点で現実世界を見ている。
ゆえにこの旅を通して目に映るもの全て
この年端も行かない17歳の俺にとっては
研ぎ澄まされた一瞬いっしゅん
時の流れが
眩しく輝いているように思えた。
・
・
・
・
ナッシュビルから東へ180マイルほど行くと
アパラチア山脈の西麓にある
ノックスビル《Knoxville》の街に着いた。
この街のダウンタウンは開拓史より
アパラチア山脈から西へと目指す旅人たちの
宿場街として賑わいを見せている。
「なぁ、ユーレク?
ずいぶんと野宿続きだったから、ここいらで
泊まるところ探そうぜ。」
「あゝそうだな。フェルニー。
ノックスビルのダウンタウンで
いったん旅塵を落とそうか。」
俺たちは目抜き通りを進みながら
今晩泊まる馬宿を探していた。
その時である__。
パンと銃声音が街に響き渡った。
人々が蜘蛛の子を散らすようにして逃げ惑う。
それから数発の銃声音が響き渡る。
ユーレクは下馬して
「フェルニー!逃げろ!」と叫んだ。
俺は一瞬何が起こったのか理解出来なかった。
ともかく幌馬車を停めて馭者台から飛び降り
銃声の聴こえた方角の反対側へと
幌馬車の陰に身を潜めた。
ほどなくユーレクが逃げ惑う群衆を掻き分けて
血相を変えて走ってくるのが見える。
「ユーレク!早く隠れるんだ!」
ユーレクが倒れ込むようにして
同じく幌馬車の陰に身を潜める俺の居る所に
駆け込んできた。
「痛っ . . . つつ。」
ユーレクは脇腹を押さえ
「どうやら流れ弾を喰らっちまったぜ。」
と打たれたばかりの銃創を見せた。
血が滲み出している。
俺は気が動転しそうになるのを
ユーレクは微笑みながら
「大したことない。かすり傷さ。」
「なら、良いけどさ?
万が一ってこともあるから。
バーボンの原酒で消毒しておこう。」
と俺が立ち上がった瞬間に
またもや銃声が鳴った。
目の前の幌に弾丸が貫通した。
「伏せろ!フェルニー!」
とユーレクが叫ぶ。
それから数発の銃声が鳴り、幌に次々と
穴が開いてゆく。
あきらかに宣戦布告である。
「おい?ユーレク?
これって俺たちが狙われているのか?」
ユーレクはゆっくりと首を縦に頷いて
「あぁ . . . どうやらそのようだな?」
「どうするんだよ?俺たち!」
幌馬車を盾にして、この現状を打破しようと
俺たちはお互いの気色ばむ顔を
見合わせていた__。
二十二、甦ったフライング・ハイ
フェルディナンドとユーレクの少年二人が
ナッシュビルの街から出発した時に話は遡る。
ナッシュビル
デイヴィッドソン郡保安局にて__
トーマス・オーウェンは
長年に渡り腑に落ちなかったことがあった。
30年前のサザン・ベル溺死事故である。
当時、ソフィアの供述や病院内の目撃者も居り
その真相については
ヒューゴなる人物が何らか関与していると
当時から捜査していた。
アレクサンドラを取り巻く
もう一人の男ジェイコブ・ロバーツについて
当時からトーマスは不審に感じていたし
巷でのジェイコブの素行も評判は芳しくなく
事情聴取をしようとした矢先のところで
上層部からの指示によって
「事故として扱うように。」
沙汰止みとされた。
詳しく調査出来ず仕舞いであることが
長年の心残りであった。
そして
今回、二人の少年達が引き上げた
ヒューゴは亡骸となって発見されたのだ。
ヒューゴの遺体は
メディカル・エグサミナー《検死官》の
司法解剖にかけられて
トーマスはその結果報告を興味深く見ている。
長年にわたる遺棄されていた亡骸のため
見た目かなりの腐敗が進んでいたものの
不思議なことに肺には溺死を示す胸水が見られない。
(この保存状態は奇跡と云っていい。)
とトーマスは報告を読みながら驚いていた。
さらにつづけて
頭部、左大腿骨に
打撲と見られる骨の損傷が多く見られ
特に頭部は陥没するほど強打されたのか
頭蓋骨の一部が黒ずんでいた。
つまり溺れる前に既に死亡しており
死因は激しい外傷によるもの
と報告された。
また遺留品から軍隊手帳が見つかり
南軍テネシー軍所属のユーゴー・サン=シモン
と身元が判明した。
死亡する直前まで足を負傷しており、
野戦病院で療養中の記述が記録されていた。
手帳の日付は奇しくもアレクサンドラが
溺死体で発見された前日まで記載されていた。
そして指輪の刻印を示す
アレクサンドラとヒューゴの関係
ソフィアの供述から恋仲であることを
聴かされている。
おおかたの予想では二人は心中を図ったかと
思われていたのだが
(死因が違う?
二人が心中でなかったとすれば . . . )
ヒューゴは何者かに殺められたのであろうか?
この元保安官である老人は考えを巡らせる時
普段は温厚で飄々とした人物なのだが
いざ集中すると眼光に鋭く凄みのある
目つきに変わる。
これは事件を追う時に見せるトーマスの癖で
わずかな糸口から一気に真相に迫る
鮮やかな事件解決の手腕から
獲物を狙って空から襲いかかる鷹に例えられ
"フライング・ハイFrying highと言う二つ名で呼ばれた。
(アレクサンドラについては事故ではなく
やはり事件に巻き込まれてしまったのか?)
トーマスの頭の中で点と点がつながった。
その捜査線上には以前から目を付けていた
南部の富豪ジェイコブ・ロバーツ氏の容疑が
浮かぶのであった。
彼らのような上流階級の人間は
政治権力ともつながっており
触れてはならぬ聖域にメスを入れるようで
一介の保安官の力では及ばざる
境界の向こう側にはただならない報復が
付きまとうであろう。
・
・
・
・
トーマスは
何故かソフィアの知り合いだと名乗り出る
突然現れた少年二人の申し出により
荼毘に付されたヒューゴの遺骨と
遺留品の指輪を手渡した。
その純粋無垢な心根の優しさに触れて
古参の元保安官はかつての"たぎる情熱"を
思い出した。
そしてトーマス自身は
事件を結びつける遺留品は必ず上層部によって
揉み消されることを悟っていた。
トーマスの前に現れたこの少年二人は
まるで神が差し向けた運命の出会いのように
不思議な運命に導かれているように思える。
かつてのもう一人のサザン・ベル__
ソフィアやエイプリルレイン家の
無念を晴らせるのは
彼ら二人以外には考えられなかったのだ。
未来とは__
目に見えなくとも何かを信じられる力
元保安官としてのキャリアの晩節にあって
(人が正しく生きる道に他ならぬ。)
トーマス・オーウェンは少年二人を見送った後
ヒューゴ・サン=シモンの件を殺人事件とし
真実を白日の下に晒すため捜査を開始した。
過去のサザン・ベル溺死事故から調査続けて
この度のヒューゴの死因と遺留品
それらから結びつける事象に関与している
数々の証言から
ジェイコブ・ロバーツ氏の逮捕に
踏み切るのだった。
(権力に屈することはあってはならない。)
トーマスの眼光は鋭く光っている。まさに獲物を狙う鷹のようであった
・
・
・
・
ミシシッピ州 メンフィス郊外
ロバーツ邸にて
「ご主人様ァ!大変です!」
執事は息を荒げて
主人の居る部屋の扉をノックする。
「何の用だ。」
部屋の奥から主人の声がした。
「ご主人様に州公安局より来客です。」と
執事は回答する。
「何だァ?俺は取り込み中なんだ。
小役人どもは追い返してしまえ。」
と部屋の中で主人が怒号を発する。
(やれやれ . . . いつものヒステリックだ。)
執事はいつものことながら、なだめるように
「州保安局長のブラウン様が緊急とのことで
お越しになっております。」
しばらく無言の時間があり
ほどなく、女性が身だしなみを整えるのも
そこそこで大急ぎで部屋を追い出された。
「‼︎」
女性と一瞬鉢合わせしたが
彼女は気まずそうに気を取り直して
「ごめんあそばせ。」
と云ってそそくさと退散した。
「入れ。」と主人の声がする。
部屋の中では
書斎とベッドルームが隣接しており
ベッドルームの片隅には、何やら怪しげな
拷問器具のようなものが散乱していた。
この猟奇的嗜好のある主人__
ジェイコブ・ロバーツは身だしなみを整え
「州保安局長が直々とあらば
仕方がなかろう。」
冷たく低いくぐもった声で
「なにごとであるか。」
不機嫌そうに
玄関ホールに向かうのであった。
二十三、忍び寄る影
玄関ホールに赴くと
スキンヘッドをした恰幅の良い中年男性が
屋敷の主の登場を待ち侘びていた。
「ようこそ!ブラウン局長。
本日はどのような件でお出ましなんだい?」
ジェイコブは端正な顔を綻ばせて応対する。
快活な笑顔からは白い歯を覗かせるが
目は少したりとて笑っていない。
保安局長のブラウンも
友好的な素振りを見せるように
分厚い手のひらを差し出して握手を求めた。
しかし、内心では
(この威圧感がどうにも苦手だ。)と伝えなければならない重苦しい内容に
辟易としていた。
「急ぎ駆けつけたのは他でもない。
隣のディヴィッドソン郡の保安局から
連邦逮捕状が送られてきたので馳せ参上した次第です。」
とブラウン局長は言った。
「それも30年前のサザン・ベル溺死事故と
関連づけて閣下の身柄を拘束するようにと
電報が届いてますが如何いたしますか?」
ブラウン局長は司法を執り行う立場であるのに
あらかじめ容疑者に相談するのは
元来、あるまじき行為であろう。
それほどまで
この辺りの司法権は建前上の組織であり
ロバーツ家の息のかかった者で殆ど牛耳られ
実質的にはロバーツ家の私設警察と云っても
云い過ぎではなかった。
「何を今更そのような事をほざく者が居る?
だが我が友よ、忠告ありがとう。」
ジェイコブは
「こういったことに親友の君を煩わせることが
あってはならないからね。」
と余裕の微笑みを浮かべるのであった。
・
・
・
・
ジェイコブは州都ジャクソン生まれである。
ロバーツ家は曽祖父の代に
フランスからの入植者で
いわゆる"ヌーベル・フランス"の潮流を
受け継いできた家系であり
ミシシッピで最大の綿花プランテーションを
保有していた富豪である。
彼ら一族は
綿花プランテーションの商売を拡大するため
隣のテネシー州メンフィスに近い州境の郊外に
大きな邸宅を構えて
ミシシッピ川流域での水運事業に乗り出した。
これが大当たりで
莫大な財産を築く契機となる。
さらにはディープ・サウスにおける人身売買の元締めとして
富と権力をその手中に納め
ビジネスを巨大化させたのであった。
人々は彼らロバーツ家一族を
"コットン・キング"と呼び
畏れられる存在であった。
南北戦争では積極的に南軍を支援した。
結果的に北軍が勝利したものの
それまでに築いてきた
水運事業のアドバンテージの利を活かし
アメリカの近代化において蒸気船における
物資運送ビジネスの勢いは
留まることがなかった
・
・
・
・
話は戻る__。
ブラウン局長が云ふには
その差出人はかつての敏腕保安官で鳴らした
トーマス・オーウェンと知らされた。
ジェイコブはその名前を聞いて
思い当たる節があった。
もう30年も前の話で
アレクサンドラが溺死体で見つかった時に
執拗にまとわりついてきた
あの時の保安官である。
(今頃になって逮捕状とは?
何があったというのか?)
しかし、内心は穏やかではいられなかった。
ジェイコブ自身には余罪がある。
現在のビジネスを拡大する過程で
邪魔になる者の命を奪うことが
幾度となくある。
その場合はお抱えの用心棒が手を下し
自らが手を下すことはしなかった。
ただ、ひとつの例外として
アレクサンドラの連れ合いの件は
(見境なく自ら手を下してしまった。)
若気の至りであり、痛恨の極みであった。
しかしながら
ジェイコブは強運であった。
アレクサンドラの連れ合いである
ヒューゴが重要参考人として
大方の見解は一致していたためである。
そのヒューゴが行方知れずのため
ジェイコブに容疑が及ぶことはなかった。
19世紀のアメリカには
まだまだ開拓史の気風が残っている。
この元保安官はその職務の名誉にかけて
立ち上がったのであろうか。
(面倒なことになりそうだ。)
ジェイコブは執事を呼び出して
臨戦態勢を申し付けるのであった。
「腕利きの弁護士を用意しろ。
陪審員の調略も抜かりなくな。
それと . . . 用心棒を雇とっておけ。」
・
・
・
・
ディヴィッドソン郡保安局にて
トーマスは裁判所からの任命を正式に受け
陪審員への召喚状を作成し
ジェイコブを追い詰める手筈を
着々と準備していた。
当時、ソフィアからの事情聴取を思い返す。
「姉の無念を晴らして下さいまし。」
淡々と語るソフィアの目に光は宿ることなく
人間が真に哀しみを背負うときはこのような
表情をするものなのであろうか。
彼女のような聡明な女性でさえも
心の中は片翼をもぎとられた鳥のように
もがき苦しんでいるソフィアの表情が
今でも脳裏に焼きついて離れられなかった。
トーマスは召喚状を送達を終えた頃には
すっかり陽が暮れており、帰り支度をしようと
ロッカールームを開けた時である。
なにやら着替えの服が赤く滲んでいる。
取り出してみると血でシャツが真っ赤に染まっていた。
戦慄がはしったその瞬間
何かがドサドサとロッカーから転げ落ちた。
「 ! ! 」
そこにはいくつもの鷹の生首が
転げ落ちていた。
このような手口は裏世界の輩が恫喝する手口の
常套手段であることを知っている。
(すでに局内にもジェイコブの息が掛かってる
手合いの者が居る。)
と、トーマスは悟った。
(こいつァ . . . すでに俺は狙われているな。)
二十四、蛇の目の刺客
「ジェイコブ・ロバーツ氏の逮捕について
連邦法第4条は適用されない。
事由:サザン・ベル溺死事故から30年以上
歳月が経過しており
本件の刑は時効に値する。」
とトーマスの元に電報が届いた。
それどころか
こちらの州保安局の連中も巨大な権力からの
報復を恐れてか捜査の追及が及び腰であった。
事件の鍵を握ると思われる遺留品や
検死鑑定のカルテなどを
上層部から焚書するように命令が下された。
これはトーマスの読み通りであった。
(やはりな。思った通りだ。)
証拠になりうる遺留品やカルテの原本は
今頃はガットリンバーグの墓中へと向かう
少年たちの幌馬車の中だ。
(彼等の無事を祈ることしかできない。)
天の配剤は
それぞれに与えられた能力や資質、機会など
一人ひとりに違った形で現れる。
フェルディナンドとユーレクと
出逢ったその日__
トーマス自身ではどうしても
埋めることが出来なかった心の地図に
その一片を持ち合わせたかのように
一瞬にしてピタリと当て嵌まった。
人生とは不思議なものだ。
追い求めていた答えは色々な所に潜んでおり
だからこそ面白いとも言える。
この歳老いた元保安官は生涯を懸けて
この世の正義というものに対して
自分なりの答えを出そうとしていた。
・
・
・
・
メンフィス郊外 ロバーツ邸にて
ジェイコブは
「当時の犯行を示す証拠は始末出来たのか?」
と念を押す。
ブラウン局長は気まずそうに
「それは . . . 他州の管轄では至らぬことが多く
証拠となる遺留品や検死結果が
忽然と行方知れずとのことです。」
ジェイコブは怪訝けげんそうな顔で
「あの"フライング・ハイ"のことだ。
何か決定的な証拠掴んでいるに違いない。」
とジェイコブは気を揉んでいた。
(ほんの少しの綻びも見せてはならぬ。)
この執念深く用意周到な男には
妥協するところがない。
ブラウン局長は
「その他の気になる点ですが、
たしか報告によると
遺体を発見した二人の少年達は
もう一人のサザン・ベル__
ソフィア・エイプリルレインと縁あって
旧知の仲とのことです。」
とフェルディナンドとユーレクの似顔絵を
ジェイコブに渡して情報を伝えた。
ジェイコブは眉をひそめ
「ソフィアと言ったな?
たしかあのナッシュビルの家系は断絶して
彼女とアレクサンドラの母親は
生まれ故郷に帰っていったはずだ。」
ブラウン局長は
「なんでも少年達は『ヒューゴの遺骨を
アレクサンドラの下に帰してやりたい。』
と申し出たそうです。」
ジェイコブはブラウン局長の報告を
じっと押し黙って聴き入っていた。
(今どき奇特な人間も居るものだな . . . 。)
しかし何故か釈然としない。
年若い少年たちは何故に
ソフィアやアレクサンドラのことを
知り得たのだろうか?
それともこの度の遺体で発見されたヒューゴの
親類なのであろうか?
ジェイコブの中で疑念が渦巻く。
疑念に囚われると人を信じたり許すことが
出来なくなる。
そのような感情の負のスパイラルは
底知れない黒い感情の蠢うごめく蟻地獄へと
引き摺り込まれる焦燥感に苛まれ
やがて絶望へと変わる時__
人間の持つこの世への怨みや憎悪といった
さらなる地獄の闇へと引き摺られてゆく。
このジェイコブという人間の哀れなところは
生涯において身の回りで彼を諌める者が
たれ一人として居なかった点に尽きる。
ジェイコブは執事を呼び出して
「フェルディナンド・ランスキーと
ユーレク・ボリセヴィチ
二人とも年齢は17歳の少年だ。
彼らを探し出し俺のところまで連れてこい。」
と命じるのだった。
・
・
・
・
こういったジェイコブの指示は執事を通じて
裏社会に精通した人物の元に依頼される。
彼らは賞金稼ぎとして生業を立てており
中には凄腕の狙撃手も居た。
南北戦争後のアメリカは
加速する近代化の中にあっても
"己の身の安全は己自身で行なう。"
と言った風潮が根強かった__ 。
(それは現代においても変わりはない。)
この頃のバウンティ・ハンターと呼ばれる
賞金稼ぎはお尋ね者を捕らえようと
時に銃撃戦になることもしばしばあった。
それは表の世界であっても苛烈であるのに
ジェイコブがお抱えの狙撃手の連中たちは
裏社会で高い報酬を得る
プロフェッショナルの殺し屋hit manである。
(17歳の少年たちにこのような輩を
差し向けるとはあまりにも酷なことだな。)
と執事は内心思いながらも
隣州メンフィスの待ち合わせの酒場に向かう。
酒場のカウンターの片隅に佇んでいる
テンガロン・ハットを目深に被った男が居る。
男の名前はアンドリュー・フィッシャー
"蛇の目Double-ring"と云ふ通称で呼ばれている。
ジェイコブが事あるごとに依頼する
ヒットマンの内の一人であった。
執事は
「やぁ、待たせたな。」と静かに声を掛けた。
「また、アンタか . . . 。
んで?どんな用件なんだい?」
とアンディーは応える。
執事は
フェルディナンドとユーレクの似顔絵を見せて
「彼らはガットリンバーグに向かっている。
ご主人様の元へと身柄を引き渡すようにと
仰せつかっているんだ。」
執事は札束をテーブルに置く。
アンディーがテンガロン・ハットで覆い隠し
ハットの隙間から除くようにして
「50か?」と訊いた。
執事はコクリと頷き
「50ドルだ。」
「問題は無かろう。」と握手を交わし
アンディーは食い入るように似顔絵を眺めて
二人の特徴を聴き出すのであった。
・
・
・
・
ノックスビル ダウンタウンにて
アンディーは標的を仕留めるために
ガットリンバーグの山奥の深い村ではなく
その近郊にある大きな街__
ノックスビルで機会を窺っていた。
西へ行くための拠点として栄えた
宿場町でありアパラチア山脈を越えて
開拓者たちが西へと旅立ってゆく。
(東から往来する旅人を注意すれば良い。)
標的を探し出すことに関しては
野性的な嗅覚と合理的な思考を巡らせ
どのようにすれば良いのかを
この男は要領を知っている。
西からノックスビルへ立ち寄る際にカンバーランド通りがあり、
ダウンタウンへ行く道が分岐するため
アンディーはカンバーランド通りの三叉路の南
丘陵地帯の高台から監視を続けていた。
アンディーは西に向かう旅人を眺めている。
幌馬車に夢と希望を詰め込んだ大勢の
旅人たちを見ていると
(所詮は俺には無縁の世界さ。)
アンディーは標的を待っている間
物想いに耽っていた。
・
・
・
・
アンドリュー《アンディー》の生い立ちは
アメリカ中央のミシシッピ川沿いの
メンフィスで生まれた。
彼は先天性のオッドアイ《左右の瞳の色が違う》であった。
物心がついた頃の記憶では
年老いた父ウォルトに育てられ
14歳離れた姉ナタリーが居た。
ナタリーは精神を病んでおり別室に引きこもり
アンディーは幼かったため
姉と話した記憶はほとんど憶えて無かった。
アンディーが記憶にあるのは
まだ3歳で物心がつき始めた頃に
ヨチヨチ歩きで住んでいる家から
遊びに出掛けた時
樹木から何やら釣り下がっている。
(へんなの?へんな木の実だな。)
幼いアンディーが近づいでみると
吊り下がっているのはナタリーであった。
幼いアンディーは
「お姉ちゃん?遊ぼうよ!
ぼくと一緒に遊ぼうよ!」と声を掛ける。
だかナタリーは無言である。
父親が血相を変えて駆け付けてきた時には
ナタリーは動かなかった。
父親は泣き叫びながら
首を吊ったナタリーを介抱し
「あぁ神よ!なんとご無体な . . . 。」
と泣き崩れていた。
「どうしてお姉ちゃん動かないの?」
"死"ということを理解するには
アンディーはまだ幼過ぎたのだった。
その日を境に父のウォルトは
どんどん老け込んでゆき
アンディーが10歳になった頃には
病で臥せてしまい亡くなってしまった。
ウォルトはその今際の際に
「ナタリーがアンディーの本当の母親で
ワシはナタリーの父親__
つまりアンディーはワシの孫なのだ。」
と告白したきりこの世から逝ってしまった。
自分自身のルーツの詳しいことが
何も知らされることのないまゝ
天涯孤独となったアンディーは
少年ながらにして大人の中に混じって
水夫として働くことで自らの生活の糧を
得るしかなかった。
転換期は迎えたのは16歳の時
若くして南軍に属したことによる。
アンディーはとりわけ銃の扱いが際立っており
長距離からの狙撃の才能を買われ重用された。
アンディーの手にかかれば
銃身の先端にある照準の先に
豆粒くらいに見える人が
引鉄を引けば弾け飛ぶように死んでいく。
まるで神に代わって生殺与奪の権利を
与え給わった英雄の如き錯覚に陥るのだった。
アンディーは何かに取り憑かれるように
ひたすら精密機械のような殺戮を繰り返す。
その正確無比な狙撃は
彼の身体的特徴であるオッド・アイから
"蛇の目Double-ringに睨まれたら最後"と畏怖された。
しかしながら南北戦争は北軍の勝利に終わる。
内戦後のアンディーは元の水夫に戻って
黙々と仕事をしていたが以前とは何かが違う。
人を殺めることを経験したアンディーは
自らの持つ才能である狙撃の特異能力が
戦時以外では必要とされず不満を抱えていた。
彼自身のアイデンティティは
普段の生活の中ではその輝かしい才能を
埋没させてしまっていることに満足出来ず
彼自身がおのずと市井の暮らしから
遠ざかり
裏社会での生きる道しか
考えられなくなってしまっていた。
・
・
・
・
アンディーは東から来る幌馬車を見つけた。
肩からぶら下げたカールツァイス製の双眼鏡で
確認する。
さすがに遠目からでは似顔絵との判別は難しく
それでも容貌は若い少年二人であることは
なんとなく分かった。
アンディーは高台から降りて
二人を追うべく尾行を開始した。
ダウンタウンに続く道を行く
フェルディナンドとユーレクの影に寄り添い
遠巻きに刺客アンディーの足音が忍び寄る。
標的の少年二人はゲイ・ストリート目抜き通り
に差し掛かり街並みを物色している。
おそらく馬宿を探しているのであろうか。
アンディーは先回りして
パトリック・サリバン・サルーンの屋根の上で
待ち伏せている。
(間違いない。俺の標的だ。)
銃身の先端が似顔絵の少年に向けられる。
アンディーは何の躊躇ためらいもなく
引鉄を引いた。
その瞬間__
白馬が立て髪を靡なびかせて
アンディーの眼前を疾風の如き速さで
駈け抜ける幻が見えた。
二十五、猫と蹄音の夜
アンディーが引鉄を引いた刹那__
疾風が駈け抜ける。
目にも止まらぬ速さで何かが通り抜けたのは
アンディーには白馬に見えたが
その姿は幻のように消えてしまった。
アンディーにとっては至近距離とも言える
絶好の機会にもかかわらず
初弾を外してしまった。
街は突然の銃声に驚いて
逃げ惑う人々でごった返し
その人混みを縫うように標的が逃げていく。
もう一発は手応えがあった。
標的の少年に命中したようだ。
だが急所に仕留められなかったようだ。
(ちっ!俺としたことが。)
少年は脇腹を抱えながら幌馬車の陰に隠れた。
馬車の架台の向こう側には
ブーツのつま先がが見え隠れしている
二人が隠れている位置を見当して
架台の向こう側にいるであろう標的目がけて
狙撃を繰り返す。
アンディーは少年二人の反撃を警戒しながら
間合いを詰めていく__ 。
(確実に狙いは外していないはずだが?)
どうにも気配がない__ 。
アンディーは二人が隠れている架台に
近づいてみると
そこには彼らの姿はなかった。
アンディーが遠目に見えていたのは
脱ぎ捨てられたブーツのつま先だったのだ。
標的の少年にまんまと一杯喰わされ
煙に巻かれて逃してしまった。
(あの白馬の幻は何だったのだろうか?
あの初発さえ外さなければ
仕留めていたというのに。)
アンディーは脱ぎ捨てられたブーツを見つめ
肩で息をついた。
・
・
・
・
俺たちは慌てふためきながら
幌の架台から荷袋を抱え込んだ。
ユーレクが小声で
「囮を置いて逃げよう。」と云ふ。
発砲音の方向からは幌馬車の架台が死角になり
ブーツを囮にして俺たちはその場から逃げた。
逃げている間に発砲音が遠ざかっていく。
(なんとか逃げきれたか?)
ユーレクは脇腹を打たれていたためか
安堵した瞬間に痛みで座り込んでしまった。
突然のことで混乱していたが
何者かが俺たちを狙っていることは明らかだ。
まだ完全に逃げおおせた訳ではない。
裏路地に行くと
材木が立て掛けてある小屋があり
その陰に身を潜め
ユーレクが負った傷の様子を診る。
ユーレクの脇腹の腰骨の少し上あたりを
弾が貫通して肉が抉えぐられていた。
荷物のほとんどを置き去りにしたために
大した手当てさえ出来ない。
「なあに。たいしたことはないさ。」
とユーレクは強がっていたが
やはり痛いのかしかめっ面をして
「しばらく横にさせてくれ。」
と云った。
ユーレクは脂汗をかいて横臥せになって
動けないでいる。
俺たちは為す術もなく
身を潜めて回復を待つしかなかった。
どれくらいの時間が経っただろう。
俺は時折り材木の隙間から外の様子を窺う。
あたりはもうすっかり日が落ちている。
裏路地にはガス燈が点り
月明かりの下に一匹の野良猫が佇んで
俺たちの様子を窺っている。
「なあ?俺たちなんで狙われてんだろ?」
俺は野良猫に向かって独り言を呟いていた。
猫は首を傾げるようにして
一瞬目をぎゅっと瞑つむって欠伸あくびをする。
その振る舞いが
(そんなことアタイに関係ないさ。)
とでも言いたげに思えた。
俺の独り言への返事をしてくれているような
可笑しみを感じた。
・
・
・
・
アンディーはノックスビルの街中を練り歩き
標的の少年たちを探していた。
狙いを外したことが余程悔しかったのか
まんまと逃げ切られたことに対する
この道のプロとしてのプライドが傷つけられ
躍起になって探している自分を省みる。
(今夜の俺は冷静さを欠いてる。
奴らはそう遠くには行ってないはずだが。)
アンディーが路地裏の通りに入ると
猫が一匹居る。
フェルディナンドとユーレクが隠れている
木材置き場に向かって
「ニャア. . . ニャア . . . 。」と鳴いている。
(誰か居るのか?)
アンディーは銃を抜いて警戒を強める。
夜も更けていることもあり
木材の陰で途方に暮れている少年の姿は
アンディーには見えていない。
・
・
・
・
フェルディナンドの目線に戻る。
(誰かがこの通りに近づいてくる?)
俺は助けを求め声を掛けようとした瞬間__
男の影は銃を抜いて近づいてきた。
(えっ?これってひょっとすると . . .
俺たちを狙っていた奴か?)
月明かりがアンディーの顔を照らす。
俺には暗がりで顔がよく見えなかったが
この男の放つ尋常でない殺気に戦慄が走った。
裏路地の猫はさらに
「ニャア、ニャア」と鳴き止まない。
猫の様子から、男は俺たちに気付いたのか
木材の陰を覗こうと近寄ってくる。
その時__
暗がりから一匹の仔猫が飛び出してきた。
男は咄嗟に発砲する。
"パン"という音が路地に響き渡る。
仔猫が親猫に寄り添う姿を見て
男は
「なんだ?猫か。チェッ. . .
まったく今日はどうかしてるぜ。」
と吐き捨てた。
しばらくすると
何か別の足音__
馬の蹄の足音が近づいてくるのが聞こえる。
(なんだろう?誰か来たのか?)
男は足音に気付いたのか
一瞬、夜空を見上げて
肩で息をついた仕草をした。
「チェッ!」と舌打ちしたかと思うと
俺たちが隠れている場所から離れていった。
・
・
・
・
猫の親子たちは偶然にも
刺客アンディーの手から
フェルディナンドと手負いのユーレクを
守った形になる。
猫の目に映っているのは夜に駆ける馬の姿__
蹄音の主である。
蹄音の主は白い立て髪を揺らして
遠くへと消えてゆく。
猫の親子は神秘なる主の姿を見届けている。
人間たちには__
けして見ることは出来ない。
俺は月明かりに照らされた猫が
遠くを見つめて何を考えているのかは
知る由もない。
今はただ__
ユーレクの回復を待つしか無かった。
二十六、彷徨いの森
木材置き場の陰で朝を迎えた。
ユーレクは驚異的な回復力を見せる。
脇腹を貫通した銃創は膿むことなくすっかりと
新しい皮膚に覆われて傷が治っている。
(たった一晩でこんなにも治るものか?)
これまでにも旅を通して
"人喰いクロウ"の爺さんの深手の傷さえも
ユーレクの手当てですぐに治ったことを
思いだした。
ユーレクが云ふには
「大したこたぁないぜ。」と
笑顔を見せる。
俺は昨夜起こった出来事をユーレクに教えると
「なるほど。それで相手の顔は見えたかい?」
とユーレクは訊ねる。
俺はかぶりを振りながら
「いや。暗がりでみえなかったんだけどさ。
あの時、誰かが馬に乗って来てくれなけりゃ
俺たち危なかったんだぜ。」
「それは命拾いさせてもらったかもな。」
とユーレクは相槌を打ちながら
「奴がもし俺たちを狙っているとしたなら
何故なんだろう?」
俺は
「なんとなくだけど、
ソフィアやアレクサンドラにまつわる事件と
絡んでるから狙われてんだよ。」
ユーレクは
「俺たちが狙いだとしたら . . .
また狙われるのかも知れないな。」
と眉をひそめる。
「あゝユーレク。この様子じゃ
また何処かで待ち伏せしてるぜ?きっと?」
俺たちが成し遂げようとすることは命の危険を晒してまで行なう意味が
果たしてあるのだろうか?
そう考えるのも無理はない。
何の因果にせよ命を狙われたのは
紛れもない事実なのだ。
ユーレクのお腹がグゥーと音を立てる。
「お腹が空いたな。」
ユーレクが顔をほころばせる。
透き通った眼差しの見つめる先は
グレート・スモーキーの山容だ。
ノックスビルから東へと進み
セイモアからセビアービルの村を経て
そこから南へ進むとガットリンバーグの村に
辿り着ける。
「やってやろうじゃないか。」
俺はユーレクの肩を叩いて励ます。
「よし。陽の明るい内は行動を控えよう。」
俺たちは闇夜に紛れて目立たないように
徒歩で少量の荷物を背にして
ガットリンバーグの村を目指すことにした。
・
・
・
・
アンディーは
少年たちを見失ってから
彼らが来るであろうガットリンバーグの村に
先回りしていた。
月明かりが蒼くさめざめと照らしている。
この村はグレート・スモーキー山脈の麓の
風光明媚な片田舎であるが
至るところに墓地が点在しており
夜になり村人が一斉に寝静まると
まるで村全体が深海の底に沈んだかのようで
生気を感じさせないのである。
骨まで凍りつく__
何かしら得たいの知れない静寂が支配する夜
月明かりに照らされた村の通りに
アンディーの足音がコッコッと響き渡る。
アンディーは黒いコートを羽織り
牧師のような佇まいをしていた。
目深に被ったテンガロン・ハットの奥には
オッド・アイの鋭い眼光が光っている。
精密機械の如く無機質な殺戮を生業とする
アンディーという人物は淡々としている。
"死の誘惑"に駆られた人間とは
およそ自身の感情からかけ離れており
この世に未練なども持ち合わせてはいない。
故に他人の命を容赦なく断ち切るのだ。
ガットリンバーグの村に現れたアンディーは
生と死の狭間に徘徊する
大鎌を手にした死神そのものであった。
・
・
・
・
俺とユーレクは
蒼白い月明かりの下
ガットリンバーグの村に辿り着いた。
冬の始まる季節
寒さが身に沁みてくる。
運命に導かれるように
俺たちはこの村の中心部にある
ホワイト・オーク・フラッツ墓地に着いた。
この地に双子姉妹は埋葬されている。
彼女たちが眠っている墓碑銘を探すには
あたりは暗すぎて何も見えない。
「これじゃ何も見えない。
明日、陽が昇ってから探すとしようか?」
と俺は訊ねてみる。
その時__
「バタバタバタッ」と
一斉に鳥たちが飛び立つ羽音が聞こえた。
たれかが近づいてくる。
泊まり木に羽を休めていた鳥たちが勘付く程に
その人影から発せられる殺気が尋常でない。
ユーレクはくちびるに指を当てて
(静かに|《be quiet》!)と目で合図した。
俺たちは墓石に隠れるようにして息を潜める。
(あの時の刺客に違いない。)
遠くから男が何やら話している。
何を云っているかよく聞こえない。
その男は夜目が利くようである。
暗がりに隠れていても
俺たちの居場所が分かる様子で
近づいてくる。
「逃げろ!」
俺とユーレクは散らばるようにして墓碑の間を
駈け抜ける。
男は無言で発砲するが
狙いは的確で墓石を盾にしなければ
確実に仕留められてしまう。
月明かりにはいつしか雲がかかっている。
漆黒の天鵞絨ビロードが空を覆うようで
より一層に闇が強まるように思える。
あの世で静かな眠りについている墓地の中で
皮肉にも俺たちは生きようともがいている。
発砲と共に閃光がはしる。
ユーレクが撃たれた姿が見えた。
「あっ!ユーレクーーッ!」
俺は叫び声を上げるように駆け寄ろうとする。
「こっちに来るなっ!」
とユーレクが怒鳴っている。
その瞬間__
俺の身体の中に熱いものが入ってきた。
(なんだ?この感覚は?
まさか撃たれたのか?俺は!)
鉛の弾が身体を貫通していき
血飛沫が噴き上げるのが見える。
(俺、俺は死ぬのかな . . . ?)
地面が目の前に迫ってくる。
倒れ込んだ眼前に見えたのは
墓碑銘であった。
アレクサンドラとソフィア
ここに眠れし彼女たちは
白く眩ゆい美しく
無垢で貞淑であった。
時あらずして奪われぬ
彼女たちの死は悲しみを知る年頃
いまだに罪を知らなかった
天国で彼女たちは翼をつけ
明けの星よりも明るく輝き
永遠の一日に咲き誇る
(ここにあったのか。
やっと見つけたと言うのに。)
俺は横たわる自分の身体から流れ出る
黒々とした血が地面に広がってゆく様を
見つめながら意識が遠のいていった。
・
・
・
・
どのくらい時間
意識が遠のいていたのだろうか?
夢の世界にいるのか現実の世界に居るのか
よくわからないままであるが、
意識だけがはっきりとしていて
いつの間にか
見慣れない森の中を彷徨っている。
隣には撃たれたはずのユーレクも居た。
「大丈夫か?ユーレク?」
と声をかけると
「あゝ、おかげさまでな。」
といつもの透き通った笑顔を見せる。
俺はユーレクの見せるこの笑顔がたまらなく
好きだった。
森の中は温かい。
何故か心地良い安心感に包まれた気分になる。
ふと森の奥の向こう側に光が見える。
俺とユーレクは顔を見合わせた。
「一体、何の光だろう?」
俺たちは謎の光に吸い寄られるように
正体不明の光が神秘的な瞬きを繰り返すのを
固唾を飲んで見守っていたが
俺とユーレクは示し合わせるように
光の射す方へと森の奥深くへと進んでみる。
森の向こう側は霧がかかったように幻想的な
光に包まれていた。
ユーレクは小声で
「何か居る . . . ⁉︎」
と耳元で囁いた。
遠くに何かのようなシルエットが見える。
俺たちは木陰に隠れてそっと影に近づくと
暗がりに一頭の白馬が姿を現した。
「見ろよ . . . ユーレク . . .。」
「あゝ . . . フェルニー。こいつは驚きだ。」
それはたしかに居た__。
一角獣ユニコーンが俺たちの眼前に現れて
その神秘的な佇まいを露わにしている。
ユニコーンは自らの前肢を高く上げて
その角で突いてみせる。
前肢から流れ出る血__
(まるで水銀のような)
血を一滴二滴と滴らせて
俺たちの口元に含ませるようにする。
やがてユニコーンは無言で
俺たちの下から立ち去っていった。
二十七、墓碑銘
ガットリンバーグの墓地で
アンディーはたしかな手応えを感じていた。
年端もいかない少年二人を標的にすること自体
プロの仕事師であるアンディーにとっては
造作のないことである。
アンディーは斃した少年たちに近づいて
持ち物を物色し始める。
(こいつら . . . 丸腰じゃねえか!)
雇い主からは連れて来いと言われていたが
実際の賞金稼ぎの現場感覚でいうと
"撃ち合い"になることは免れなかった。
彼らの荷物袋の中を物色する。
書類のようだ。
よく見ると保安局の検死結果が書いてある。
(こいつは重要なんだろう。)
アンディーはこのような後始末も
経験からなせる業であり抜かりない。
袋の中には箱がある。
明けてみると古い頭蓋骨だった。
(こいつら、なんだってこんな物を持ち歩いて
いやがるんだ?)
袋の中をさらに調べると何かある。
それは変哲もない石ころだ。
アンディーは手に取って見ても特に何もない。
その時である。
石ころから銀白のしずくのようなものが
少年二人に滴りおちていたが
アンディーにはそのような不思議な現象は
見えることはおろか、感知さえ出来なかった。
一転して
石ころは急激に熱を帯びる。
これはさすがにアンディーにも分かるほどで
持っていた左手の握っていた指が
灼かれたような激烈な痛みが奔る。
「ぎゃあーーーっっ!」
アンディーの断末魔の叫び声が
ガットリンバーグの村中に轟いた。
・
・
・
・
トーマス・オーウェンが
少年二人が身の危険に晒されていることを案じ
地元の保安官達とガットリンバーグに
駆けつけた頃にはすでに陽が昇っており
少年たちが墓地内に倒れていた。
「くそっ!俺としたことが!」
トーマスはすぐさま駆け寄ってみると
フェルディナンドとユーレク少年二人には
着衣には血糊がべっとりと着いており
あたりも血の海になっていたのだが奇跡的に銃創は治りかけており、息をしていた。
「いったい、ここで何があったんだ?」
・
・
・
・
しばらく経って
俺はようやく目を覚ました。
アレクサンドラとソフィアの眠る墓碑の前に
駆けつけた保安官たちの中にトーマスも居る。
ユーレクも一足早く意識を取り戻しており
「フェルニー、無事だったか?」
と覗き込む。
不思議なことに撃たれたはずの俺たちは
未だに生き永らえている。
(ユニコーンの血を飲んだ夢を見た。
あれは幻だったのだろうか?)
トーマスは色々と質問してくるが
気を失っている間のことは
信じてもらえそうになかったので
云わないでおくことにした。
「では、埋葬しようか。」
ユーレクは双子姉妹の墓碑の隣りに
小さな穴を掘り
ヒューゴの遺骨を丹念に埋葬する。
近くの岩を運んで花束で飾り
アメリカ国旗とフランス国旗を
クロスさせて掲揚するように飾りつけた。
ユーレクは岩の中央に窪みを付けて
懐から取り出した
アレキサンドラとヒューゴの指輪を嵌め込む。
墓碑銘を岩に刻み込む。
Je t’aime pour toujours
フランスより新天地を求めたヒューゴ・サン=シモン
この地で安らかに眠る。
天国の地でとこしえの愛に結ばれんことを。
墓碑を作り終えるころには
すっかり陽が暮れていた。
グレート・スモーキー・マウンテンの彼方は
茜空から濃紺の深いグラデーションの空になり
あの時のユニコーンが空を跳ねている。
山々にユニコーンのいななきが響き渡る。
突然、ユーレクが持っている
アレキサンドライトが発光したかと思うと
微かに震えだす。
その微弱な振動は明らかな意志を持って
俺たちに語りかける。
「ありがとう。わたしたちを見つけてくれて。」
「ありがとう__。」
聴いたことのない女性二人の声だった。
それは小鳥のさえずりのように美しく
耳元でささやくように聴こえる。
(アルビノの双子姉妹だろうか?)
ユニコーンは空を跳ね__
やがて、その姿はおぼろげとなり
星々の点滅へと姿を変えていった。
夜空に渦を巻く幽かな光の帯を紡ぎ出し
宇宙の彼方へと向かう光の道を創り出す。
「あなたたちの旅に
神のご加護があらんことを。」
・
・
・
・
《 物語は第二章へとつづく 》
〜°〜°〜°〜°〜°〜°〜°〜°〜°〜°〜°〜
この物語はフィクションです。
作品中に登場する人物名は実在の人物と何ら関係ありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
