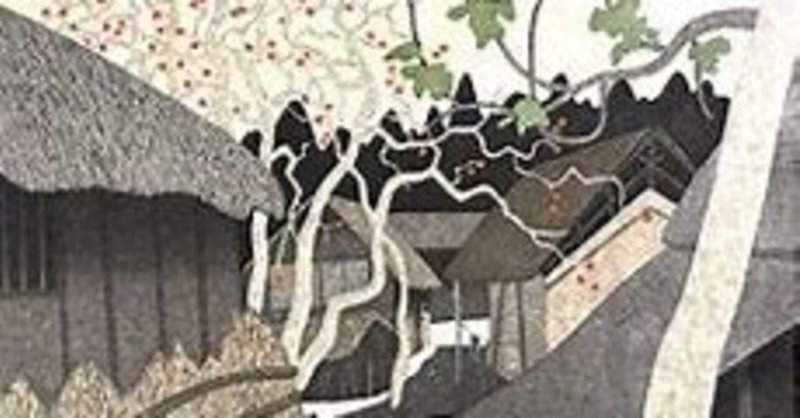
姉が見た航空母艦 帆足孝治

山里子ども風土記──森と清流の遊びと伝説と文化の記録 帆足孝治
翌日、私たちは海地獄、坊主地獄、血の池地獄などを見た後、楽天地とよばれる遊園地の下まで行ったが、ケーブルカーが運休したままだったので遥か高い山の斜面に白い大きな「ラークーテーンーチ」の看板を見上げただけで海岸通りへ戻った。お昼近くなって私たちは、この桟橋から関西汽船の「に志き丸」という汽船に乗って大分に戻ることになった。先生に引率されて高崎山を真近かに望む桟橋に出ると、そこには鮮やかな黄緑色に塗られた大きな汽船が停泊しており、それが私たちの乗る「に志き丸」だった。神戸経由の大阪行きで関西汽船の新鋭船で、私たちに大分まで、ほんのちょっぴりだけ船旅の気分を味わせようという先生たちの優しい心配りだった。
乗船許可が下りると、私たちは先生の制止も聞かず我れ先に夕ラップをかけ登って、あっと言う間に全員後ろの甲板にそれぞれ見晴らしのいい場所を占拠してしまった。先生は生徒たちの間を走り回って「甲板の手摺りに絶対寄り掛かんなよ、海に落ち込んでしもうたら、誰れも助けられんきのう」と言った。
やがてスピーカーから「蛍の光」の曲が流れて船がゆっくり動きだすと、桟橋から見送る人達と乗客との間に色とりどりのテープが投げ交わされた。そばにいた進駐軍の兵隊が桟橋にいる若いパーマネント髪の化粧の濃い女の人を見下ろしながら手を振り、何か英語で言っていた。私たちはほんものの英語を初めて聞いたので大いに驚いた。仲間の誰れかが知ったか振りして「あれがパンパンガールじゃ!」と言ったら、すぐ先生が小さな声で「バカ、そげなこつ言うもんじゃねえ!」とたしなめた。
われらが「に志き丸」は後ろ向きに桟橋をはなれ、しばらくバックで進んだあと、スクリューで海面を大きく泡立てながらゆっくりと向きを変え、舳先を霞がかった大分の方向に向けた。先生が前方はるか向こうの岬の突端にかすかに見える煙突を指差しながら、「あっこに見ゆるんが、日本一高い佐賀ノ関の煙突じゃら」と教えてくれた。
先生の説明によれば、佐賀ノ関銅製錬所の煙突は実際には工場から離れた山の上にあって、工場からそこまで長い大きな煙のトンネルが通じているのだそうだ。毎年一回、そのトンネルと煙突の大掃除が行われるが、日本一の煙突だけに大掃除には大変なお金がかかる。しかし、掃除で出る煤(すす)の中には、その費用を十分賄えるだけの金が混じっているから心配はいらないのだそうだ。
甲板から見下ろす別府湾の海面は青く、私たちは航跡にフワフワ浮かんでくるクラゲというものを初めて見た。「に志き丸」は、そのころ同じく別府航路に就航していた「るり丸」ほどは大きくなかったが、まだ新しい船でスピードも速かったので私たちは大いに満足した。
くらげの浮かぶ航跡のむこうに細長く横たわる国東半島の方を見やると、遠く日出(ひじ)海岸の方角に錆びついた大きな船の残骸らしいものが強い日差しを浴びて横倒しになっているのが見える。そばにいたおじさんに聞いたら、「ありゃアメリカん機雷に当たって沈んでしもうた日本の航空母艦じゃら!」と言った。
以前、まだ日本が戦争に勝ちそうな勢いだった頃、ここを汽車で通ったチエ子姉ちゃんが「沖にいっぱい電気を灯した大きな航空母艦が停泊しているのを見た」と言っていたが、私は、あれがその航空母艦に違いないと思い、今は宇佐に嫁いで行ってしまった姉のことどもを懐かしく思い出していた。
海面を見飽きた私は、皆んなから離れて一人甲板に腰をおろして高いマストを見上げていたが、電信柱を三本も継ぎ足したような高いマストは美しいオレンジ色に塗られており、白い雲が浮かぶ青空に屹立してゆっくりと揺れていた。それを見上げていると自分が船の上にいるのを忘れるようなのどけさだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
