
日本の川下り 3
最近、静岡県春野町に住む友人、竹内敏から美しい竹籠と、その竹籠の制作者梅沢貞夫さんのこれまた神々しいばかりの梅沢さんをとらえたポートレイトが送付されてきた。なんでも梅沢さんは小学六年生のときの転落事故で、右脚を胴体から切断されたらしい。梅沢さんの父親は、座っていても作業ができる竹細工職人の道につかせる。爾来、2019年に八十八歳で没するまで、梅沢さんは春野町の山奥で竹細工職人として生きてきた。独学で編み出していった竹籠は一点一点が芸術の領域に達している。この梅沢さんをもっとよく知ろうと、ネットで検索すると、春野町の広報紙に書かれた記事と、池谷啓さんという方が投稿された記事と、わが竹内が書き込んだ記事があらわれた。たった三点だった。この三点の記事を、「note 」に三日にかけて連続して打ち込んでみた。この三つの記事に飛んできた《スキ》は、 六点、六点、八点だった。竹内は梅沢さんを葬送する辞にこう書いている。
「わが師は、片目と片足を失い、その生涯は波乱万丈であったのは言うまでもない。しかし、梅沢さんはそのことは自分からはいっさい触れずに、愚痴を語ることも全くなかった。風雪と赤貧を越えて辺境を生きる哲学者のように思えた。とても梅沢さんのような生きざまはできないが、私の心の中でいまも梅沢さんは生きている。梅沢さん、あなたに感動している波動はたしかな広がりとなって生きています。ありがとう、合掌」
「note」はこの記事に八点という点数をつけた。それだけてはない。小学六年生のときに片目と片足を失って波乱の人生を生きてきた梅沢さんに「note」は八点と採点したのだ。梅沢貞夫さんの人生はたったの八点でしたと。
![]()
日本の川下り
険しい瀬が連続してやってきた。ばしゃばしゃと水しぶきが前方をさえぎるほどにあがり、カヌーのほとんどを水に沈めて下っていく。怖いと思う間もなくまた大きな瀬があらわれた。まるで屋根からとびおりるように、どどどどどっと瀬の下になだれこんでいく。
もう川は真っ茶色だった。川はごうごうと吠え、波がばしばしとかみそりのような白い刃をたてる。激しくさかまきなだれこんでいく川は、ありとあらゆるものをのみこみ押し流していくパワーそのものだった。父もさすがに危険を感じたのだろう。
「もう少し下ろう。もう少しでトロ場にでるはずだ」
と私たちに叫んだ。そのあたりの川岸は、右も左も切り立った崖なのだ。そこにカヌーを着ける場所がなかった。
そのときだった。翔太のカヌーがひっくりかえったのは。翔太の姿がごうごうとさかまく川に消えた。私たちは叫んだ。翔太は姿をあらわさないのだ。カヌーだけがひっくりかえったまま流れていく。
「翔太!」
母も私も叫んだ。翔太の赤いヘルメットが、信じられないほどのはるか下流であらわれた。父が猛然とパドルを回して、翔太追っていった。
そしてまたそのときだった。私のかたわらにいた母が沈したのだ。赤いライフジャケットをつけた母は、すぐにどす黒い水のなかから姿をあらわした。私が救い出しにいこうとしたとき、前方にごうごうと唸りたてているものすごい瀬があらわれたのだ。私がはじめて経験する、それはもう滝と呼んでいいような瀬だった。どどどどっとうねりながら落下していく水のなかに、私のカヌーものみこまれた。もうなにも見えない。なにもわからない。ただめくら減法にパドリングするだけだった。
私は生きていた。私のカヌーはひっくりかえらなかった。私は激流にさからってテレマークでまわりこんで母を探した。母がその滝のような瀬を木の葉のようにもみくちゃになりながら、どどどどっとすべり落ちてきた。
さかまく水面にぷかりと浮き上がった母は、私のカヌーのうしろにしがみつくと、
「ジェットコースターみたいだったわね、もう一回やってみようか」
こういうときのジョークは顔をひきつらせるだけである。
母をひきつれて重くなったカヌーを激しくスウィーブさせ、岩のあいだに舳先をつっこむと、コックピットから抜け出した。大きな岩の上に立った私たちは、その暴れ川を見てぞっとした。暴力的で圧倒的な流れだった。こんな川をここまで下ってきたのはまったくの奇跡だった。
母のファルトボートが岩の下に巻き込まれていた。餌食にされたようにばりばりと岩の下に飲み込まれていく。神さまが怒っているのだ。いま私たち一家への罰を下しているのだと私は思った。
私のカヌーを岩の上にひきずりあげると、私たちは岩を伝って川を下っていった。私は翔太のことが気がかりだった。私はなんども母にその不安を訴えると、母はお父さんがついているから大丈夫よ、とにかくお父さんはこんな川なんてなんとも思わない達人なんだからと言った。
川は曲線を描いて川幅を広めていた。そこに赤いヘルメットをかぶった翔太が立っていたが、その姿は身も心も激流にうばわれて呆然としているといった様子だった。
カヌーを探しにいっていた父がくやしそうにもどってきた。なんでも父もまた翔太を救いだすときに、ずっと愛用してきたレットマンのカヌーを流されたらしいのだ。どんな川にもたじろがない父もカヌーを奪われた! やっぱり神さまが罰を下したのだと私は思った。
山の中腹に家がぽつりぽつりと取りついていた。私たちはそのなかの一軒をたずねることにした。大岡さんに電話を入れるために。でもこの豪雨ではとてもここまで車を飛ばしてくることはできないだろう。だからそのときは一晩泊めてもらえないだろうかとたのむために。
激しい雨でいまや川となった山道を、私たちはその家めざして登っていった。どっしりとした屋根をのせたどっしりとした建物だった。しかしそこにはもう人は住んでいなかった。家屋のなかのぞくと、家具が散乱し、壁も崩れかけて、もう人がそこから立ち去って、長い年月がたっていることを物語るように荒廃していた。
私たちは土間のような部屋に入りこんで、そこに力なく座り込んだ。希望という希望が一切閉ざされたような虚脱感だった。そんな私たちをあざ笑うように風がひゅうひゅうと吹き込んできて、天井からぽたぽたと雨水がひっきりなしにしたたり落ちてくる。
「ちくしょう! 一度に三隻もカヌーを失うなんて! なんということだ。まったくどうなっているんだ」
父はいらだたしげに言った。そんな父を母がやさしくなだめている。そのとき私はしくしくと泣きだしていた。
「果実、泣かないでちょうだい。果実が泣いたら、みんな悲しくなるわ」
と母が言った。でもそのとき、私のなかから悲しみとも怒りとも嘆きともつかぬものがとめどなくあふれ出てくるのだった。
「私たちに罰が下ったのよ。お父さんにも、お母さんにも、私にも、期太にも。私たちはどうなるわけ? どうしたらいいいわけ? 正直に生きるって、いったいどうやって生きればいいわけ?」
そして翔太も、泣きながら、
「そうだよ。お父さんも、お母さんも勝手なんだよ。自分たちだけで決めてさ。ぼくらの意見はどうなるわけさ。ぼくはお姉ちゃんと別れないからね。大人だけで決めたことなんかに、絶対にしたがわないからね」
そのときの私の一家はきっとどうかしていたのだと思う。母も声をたてて泣きはじめ、父もまた大粒の涙をぽろぽろと流して鳴咽をかみころしているのだった。
その夜、私は寒さと空腹でなかなか眠れなかった。夏とはいえ山のなかはぐんと冷えこむのだ。そしてその日、私たちは昼からなにも食べていなかった。だから私も翔太も、父も母もお腹をくうくうと鳴らせていた。
翌朝、私はぴちぴちぴちゃぴちゃとさわぐ烏の声で目をさました。昨日の嵐が嘘だったようにまばゆいばかりの朝日が差し込んでいる。外にでると父と母が捨てられた家具を椅子にして、コーヒーを飲んでいた。雨戸でつくったテーブルの上には、フランスパンや缶詰やジャムや缶ビールやビスケットがのっているのだ。
「これどうしたの!」
と私は夢からさめたように叫んでいた。
夜明け前に起きた父は、川におりて、昨日失ったカヌーを探しにいったらしい。するとそのカヌー、まるで父を待っていたかのように流木にひっかかっていた。父はそこからいっぱい食糧をかかえて戻ってきたのだった。
私はフランスパンにアスパラガスとセロリとシーチキンをたっぷりとはさんで、マスタードとマヨネーズをぬりつけて、がぶりとかみついた。もうその食べ方といったら飢えた犬のようだったにちがいない。
そこから眺める景色は素晴らしかった。眼下にあの暴れ川がのどかにのんびりと流れている。段々畑が山にのぼっていた。その畑には雑草がうるさく繁っていたが、そんななか太陽をつかみとろうとするかのように、すくっと伸びたヒマワリの群れが、黄金の花をいっぱい咲かせていた。抜けるような青い空をトンビたちがゆっくりと旋回している。もしこの世界に理想の世界があるとしたら、きっとこんな所ではないかと思わせるほど平和で美しい眺めだった。
「あの家にも、人は住んでいないのかな」
翔太が口をもぐもぐさせながらきいた。
「うん、どこも空っぽだったよ。もうこの部落には、人は住んでいないんだ」
「どうしてこんな美しい所を捨ててしまったのかな」
「それはここでは生活できないからよ。食べるだけでは人は生きていけないの。いまの時代って生きていくにはたくさんのお金がかかるんだから」
「ここにあるのは美しい自然だけだ。でもこの美しい自然だって現代人は一週間であきてしまうだろうね」
「そうかな。あんなすごい嵐があるかと思うと、こんな素晴らしい朝があるし。冬になればまた姿をかえるんだし。あきることなんてないと思うけど」
と私は言った。
「そうだな。果実のような自然大好き人間はあきないかもしれないな」
「ぼくもあきないよ。川で毎日遊べるじゃないか」
「そうなの。この子たちはこういう所にむいているのよ」
「日本人は田舎を捨てて都会に出ていく。しかしおれは思うのだけど、こういう辺境の地にしっかりと根をおろして生きていくことが、これからの時代を切りひらいていく最先端の仕事かもしれないな」
「そうね。こんな美しい自然のなかでしっかりと生きていけば、もっとちがったものが生れてくるかもしれないわね。とても厳しいことだけど」
「川にくるたびに思うのは、いかに都会が気違いじみた論理で動いているかだ。成長という名のもとの建設と破壊だ。あくことなき拡張と拡大、攻撃と征服なのだ。富と繁栄で満たされていくようにみえるが、実は人間は少しずつ滅んでいるのかもしれないな」
そして父は夢みる人のように、
「きっと人間はこんなところでも、知恵を出せば生きていけるはずなんだ。これからの時代を切りひらいていけるような仕事だってできるはずだ。こんな所でもう一度人生をやり直していくのも素敵なことだな。なにもかも捨てて」
母も言った。
「いいわね。あなたがやるというならやり直してもいいわよ」
しかし、そのツーリングから二か月後に、父と母は正式に離婚した。結局、あの朝の光りのなかで私たちが話した話は実らなかったのだ。しかしそれはなんだか、私と翔太にあたえられた宿題のように思えた。私と翔太がどう生きていくかということの。
完
![]()
「日本の川下り」は《草の葉ライブラリー》版「クリスマスの贈り物」に編まれている。
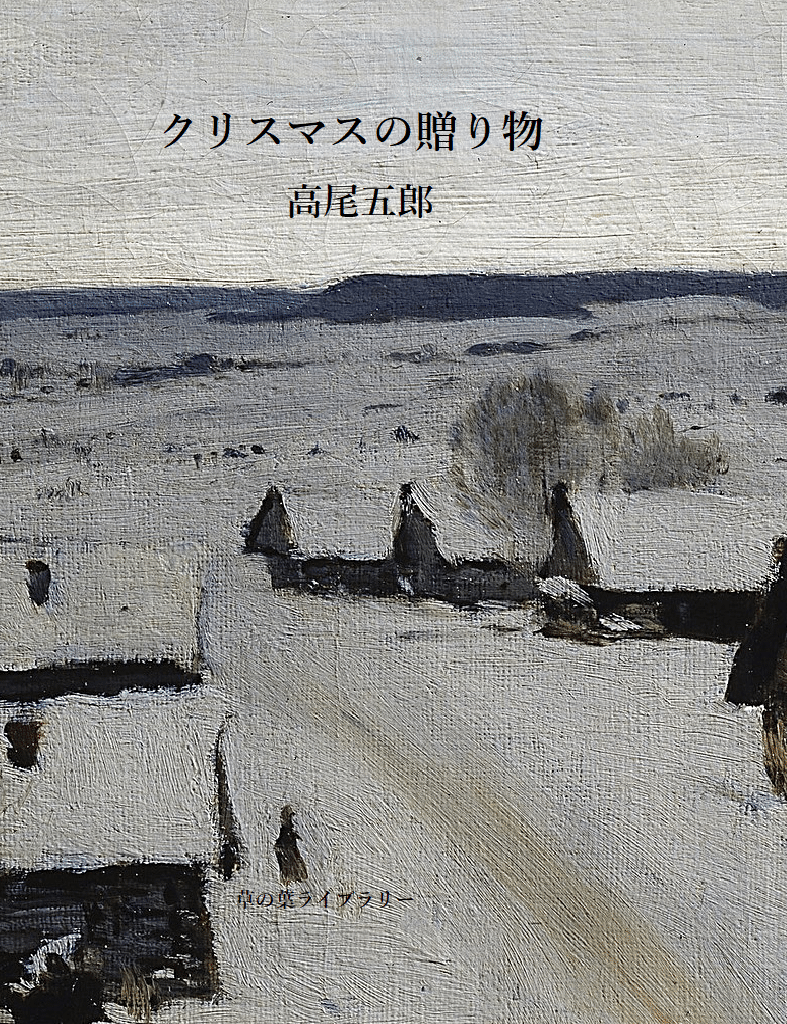

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
