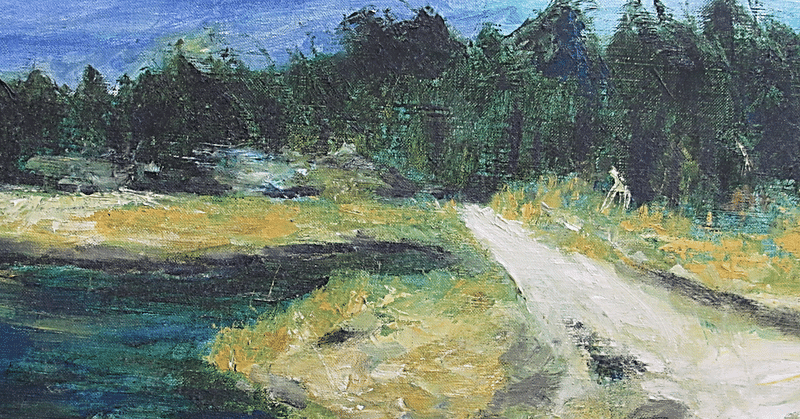
私の中の唐牛健太郎 島成郎

序
一九八四年三月四日、午後八時半過ぎ、沖縄宣野湾の我が家に独りいた私に電話がかかってきた。東京の芹澤誠治が、いつもの底が抜けたような大声とはちがった淡々とした口調で「唐牛が死んだ」ことを伝えた。
すでにその数週間前から、真喜子さんとともに病床につきっきりでいた篠田邦雄らから殆んど毎日、遠く南大東島の巡回診療先まで、危篤状態に陥った唐牛の病状が伝えられていたのだったが、この報せの瞬間に私の時間はとまってしまった。
あわただしく鳴り続いた電話の応対も上の空、やがて夜が明け、一番の飛行機で羽田へ飛び、待っていた佐藤粂吉の案内で築地の癌センター地下の霊安室に辿りつき、既に解剖を終え静かに横たわっていた唐牛にあうまでの十数時間、私は殆んど完全に唐牛と二人だけで過した。
あのブントの時代、初めて相知ってから二十七年、私の中に生き続けてきた唐牛と二人だけの時間は、余りにも生々しく鮮烈なものだっただけに、現実の彼の死顔を見た瞬間迸った感情の爆発の中で、凍りつきカプセルに閉ざされ、私の奥深い所に追いやられてしまった。
そして──その時からもう二年以上の月日が過ぎた。
通夜、葬儀、納骨、一周忌、三回忌といった儀式に否応なくつき合いながら、私は同じような時問をもったに違いない多くの人たちと知りあった。
そしてその一人一人の中の唐牛について聞いたのだが、その多くが私にとって未知のものであったことに驚かされた。
もっといってしまえば、私は唐牛が生きた四十七年の生の実際を殆んど知らなかったとさえいえる。
御両親のこと、函館の少年時代のこと、北大での活動、最初の奥さんの和子さんのこと、ヨット、石狩、与論島時代の話、長かった紋別での漁師の生活、コンピューター・セールス、徳洲会や奄美選挙活動、そして筑後まで一緒だった真喜子さんのことも、さらにこれらの時代を通してつきあった様々な分野にわたる人々のことも、聞く話が一つ一つ耳新しく、しかもそれぞれの思い入れを吐露したもので、私の唐牛の像を遙かに超えたものであった。
この私の中でさらに大きくなっていった男の軌跡を自分なりにたどってみたいという気にもなり、函館や紋別などの地にも行き、彼を愛した人々と会うことによって、唐牛の生活に少しでも触れ、実感しようともした。
しかし、知れば知る程奥行きは深く、行動は八方破れで、しかもその心情は屈折しており、到底、私が確かめうるものではないことをあらためて知らされた。
そんな私が今、唐牛について何を語ることができるのか。
あの死の報せの後の十数時間、すべての現実が止まったまま、私の心のすべてを占めた彼と交わした独白のいくつかを、私の中の唐牛健太郎の虚像を記す以外にはありえない。

1
一九五九年五月の或る日、私はひそかな、しかし固い決意をもって独り東北本線の列車に乗っていた。行先は北海道、札幌。当時では丸一日を要した長い旅であったが、私の頭の中は、一人の男をどう口説き落とすかという思いだけで占められていた。
一人の男──それが唐牛健太郎であった。
その前年の一九五八年十二月十日、私たちは、それまで所属していた日本共産党に叛旗をひるがえし、共産主義者同盟(ブント)を結成した。
一九五〇年共産党に入った私は、以来、青春のエネルギーをこの党のために投入してきたのだが、五五年「六全協」と呼ばれた会議以後、開始された党改革の闘いに不退転の姿勢で立ち向かった。
生田浩二、森田実、星宮煥生、小泉修吉、片山廸夫、佐伯秀光らとともに、戦前からの多くの神話のベールに覆われたこの党の誤りに挑みながら、すでに指導力を失っていた党中央にかわって自力で学生運動の再建と闘いを続けてきた。批判は進めば進む程、党内にとどまることができなかった。学生とはいえ、戦後日本の社会運動の中で一つの政治潮流をつくってきた全学連という組織を担っている以上、闘いは政治的にならざるをえない。しかも党中央によって改革の道がたたれた以上、これと常に対立しながら自立した運動をすすめてきた学生党員たちが、この党と袂別し新たな組織をつくることは必然の勢いであった。
物心つく頃から党とともに過し、この体臭を身につけて育った私は、逡巡と躊躇の末、最後は断崖から飛び降りる気持でブント結成に踏みきったのだった。
長い間の呪縛から解放された私のような経歴をもったやや年長のグループとともに、党の権威に全く捉われず自由に運動に参加していた若い学生達がこの組織に結集した。結成大会に北海道代表として出席した唐牛もその一人だった。
五六年に北大に入学、その一年後には自治会委員長、更に道学連委員長、全学連中央執行委員となっていた唐牛は、この時すでに全学連とブントを支える最も若い中核の一人となっていた。
結成とともに書記長の役を担わなければならなかった私は、当初から多くの難問に直面した。日共に対抗するのみならず、国際共産主義運動を律していたスターリン主義に反対し「世界革命」を謳い、既成のあらゆる組織への反逆を宣言したのだが、その実体は無い無いずくしの学生小集団である。
マルクス主義を掲げながらも、既成マルクス主義に反発する実に多様な心情の集まりだったともいえる。
このような頼りない小組織が徒手空拳でいかにエスタブリッシュメントに立ち向かうのか。そんな思いで香村正雄、古賀康正、樺美智子らの無償で働く人たちの助けをかり、事務所をつくり、雑誌を発行しながら年を越したのだが、休む間もなく一つの決断に迫られたのだった。
一つは当然予想された日共の大々的赤狩りとの闘いであり、二つには結成当時から内蔵していた革共同との競合である。一時革共同との共存、吸収を考えていた私も、この組織の陰湿さと教条主義に愛想をつかし、五九年三月にはこの両者を排してブントによる全学連の全面掌握を考えねばならなくなっていた。
外部からみればたわいない人事争いともいえようが、結成したブントの意図をいかに明瞭に世に示すかに頭を悩ましていた私たちにとっては、依拠すべき唯一の組織といえる全学連を破壊工作から守り、ブント流学生運動を創る上で真剣な課題であったのだ。
共産党的体質を持たない新しい世代による全学連幹部の一新──到達した結論は極めて単純であったが、いざとなるとそう簡単には進まない。当然のことながら焦点はシンボルといえる全学連委員長に誰を立てるかである。
ブントには若い優れた人材が多く集まっていた。清水丈夫、青木昌彦、北小路敏、加藤昇、伊藤嘉六、篠原浩一郎らの面々である。
委員長は中央常駐だから東京のものがあてられるのが順当だろう。東大、早大、京大といった学生運動、ブントの拠点校といわれる所から出すべきだ、等々の議論を経て何人かの候補者があげられたが、すべてそれぞれの理由で本人や組織から否定され最後に登場したのが唐牛健太郎であった。
五五年以降、学生運動と党活動に明け暮れていた私の家には、いつも全学連の学生たちがたむろ寝泊まりしていたが、そんな若者の中で一際印象づけられていたのが唐牛であった。
別に雄弁であったわけでない。殊更親しく個人的につき合った仲でもない。
いつも二コニコと笑って他の連中からみればむしろ控え目でいるのだが、東京の者にはみられない大ざっぱでカラリとした明るいたくましさと、直観的に本質を見抜く詩人の感覚を併せもった風格は、スラッとした長い足とまだ幼なかった紅顔の少年の容姿とも相俟って鮮やかな存在として私の中にあった。
勿論、ブント結成に至る過程で北海道の責任者として活躍していた彼の組織力は抜群であった。だが後年になっても唐牛に様々な場で出逢った人が一目で魅了されることになるのも、彼が若い頃から発散していた人間の匂いともいうべきものによってではなかったか、と思うのである。
そんな唐牛を委員長にという私の提言は、最初は唐突にさえ思われ、素直に受けいれられたわけではなかった。全国闘争の経験がなく未知数である彼を危ぶむ声も多かった。また北海道の組織や本人が強く反対するだろうとの予想もあり、あれやこれやの議論が続いたが、私はこの中で逆に、ブント全学連を象徴する委員長は唐牛以外にはあり得ないと確信するに至り、最後は「島に一任する」との同意を漸くとりつけ北海道に向かったのだった。
札幌でどのような会議と議論があったのかは覚えていない。しかし灰谷慶三らの北海道ブント指導部はすでに労対部長として予定してある唐牛を中央に持っていかれたら困る、島が来たら酒を飲ませて追い返せと予めきめてあったらしく、話はかなり難航したように思う。しかし執拗にねばった揚げ句、最後は本人の意志次第ということに持ちこみ、一対一の膝詰談判ということに相成った。
その後の彼とのつき合いが何時もそうであったように、この時も昼間からビールを飲みながらの話であった。 「東京には偉れえ人がウジャウジャいるじゃねえか、なんで俺みてえな田舎者が委員長にならなければいけねえんだ」と最初はゴネていた唐牛も、「うんというまで俺は帰らないよ」という私に面倒臭くなったのか、最後は「とにかくやってくれ」という私の懇願に「しゃ─ないな、行くことにするよ」ということで決着がついた。この時は負っていた重荷が下りた気になり、すぐ東京へ電話を入れた後、夜中までまた飲み出したのだが、新たな遙かに重い荷物を唐牛のみならず私もずっと背負うことになったという思いには、全く至らなかった。
口説いた私に心配がなかったわけではない。東京に出てくれば当然一人で食っていかなければならないが、ブントや全学連に彼の生活や棲家を保障する力などありやしない。委員長になっても自分の依拠する場を持たないとうるさい連中の多い東京ではとかくやり難い。おおらかな北海道育ちの唐牛がそれまでの生活とは異質の体験をすることは明らかだった。そんな私の心配をよそに「東京の奴は酒をのまねえんじゃないかな?」とて一言いっただけで引き受けた彼の態度には、その後一貫してあった「生活は賭けである」という信条が既にあらわれていた。
賭けはなされた。
その1ヵ月後一九五九年六月、全学連十四回大会でブントは革共同、日共との争いを経て執行部多数を獲得、唐牛健太郎は中央執行委員長に選出される。
この時、唐牛、二十二歳

2
唐牛が全学連委員長となって東京に移り住んだのは、あの安保闘争の最中であった。
生活に馴染む間もなく、闘いの場におかれたが、その場その場をしっかりと生き抜くという彼の流儀は全学連の中でも遺憾なく示され、委員長としての実力を誰もが認めるのにさほどの時間を要しなかった。
七面倒な議論を嫌い行動によって決断する唐牛のスタイルはブント全学連の新しい魅力を創り出し、代々木や革共同を圧倒して大衆的支持を一挙に拡げる発条となったのだ。
こうしてブントは創立一年にして全学連主流派の位置を確保したが、私たちはただ多数派を維持するために組織をつくったのではない。時あたかも日米安保条約改訂が政治日程に上ってきたのに対し、これが戦後政治の一つのキーとなると判断した私たちはこの闘いに組織を賭けることにした。
五九年十一月二十七日、全学連を先頭にした数万の学生・労働者が社共らの指導部をのりこえ、警官隊を突破し国会構内に入るという闘いによって、ブントは公然と社会の前に出ることになり、翌六〇年の六月までの半年間、唐牛を委員長とする日本全学連は闘いの全局面で運動の牽引車たる役割を演ずる。
この嵐の日々、唐牛は何をしていたのか。
すでに四分の一世紀を過ぎた今でも、この時代をふり返ると、私にとってかくも濃密に日々が躍動して過された時はなかったといえよう。
それはただ青春の冒険に充たされたということだけでなく、日本最大の政治闘争の中に身をおき、その大衆的運動とともに浮沈したという経験によるのであろう。
繰り返された一つ一つのデモの相貌とその中での熱っぽい議論、行動を共にした多くの友の顔が私の中で浮かんでくる。
委員長となってから十ヵ月の間に三回も官憲に逮捕されるという激しい状況におかれ、また組織の責任者の役割を負わされた唐牛にとっても生涯忘れ得ぬ試練の日の連続であったろう。
しかし今、私の中の唐牛をブント・安保闘争の脈絡でふり返ってみると、その鮮明な画像は意外とこの闘いの主道とは離れた所で結ばれていることに気付く。
それは、公式の記録からは絶対に窺い知ることのできない独特の行動パターンをもったブントの性格にもよるのだろうが、この時を生きた唐牛の奔放、型破りな行動と屈折極まりない心情に由来する。
私の中の像は、深夜に終わる会議の後、新宿に出て飲み明かし夜が白々と明ける頃別れていくという場面ばかり明るく、公式の会議や集会で喋る唐牛など一つとして輪郭のはっきりしたものはない。はっきりしないのは当然で、重要と目された会議でも何時の間にか姿を消しているのが普通であった。
本郷金助町にあった全学連の事務所でも彼の姿を見ることは余りなかったように思う。始終会ってはいたのだが、お互い私生活には口をいれず、泣きも愚痴もなく陽気に馬鹿話をするのが私たちのやり方だったせいか、唐牛があの日々どんな生活をしていたのか、詳細は今になっても定かでない。
そんな唐牛であったが、私にとっては最も頼りになる友であった。
政治状況が完全に流動化し、通常のありきたりの思考と行動では処しきれない局面に終始立たされ、日々賭けに似た決断が要求されていた私にとって、問わず語らずのうちに通じあう友の存在が最大の力の源泉であった。ブントには数多く優れた同志たちがいたが、私が心情的にも依拠できたものはそう多くはない。その一人が亡き生田浩二であったが、彼とは全く違った意味あいで、いわばいつもピッタリと波長があったのが唐牛であった。
順風にのっている時は余り必要でないのだが、方向定まらぬまま大波にもまれている時にこそ彼の存在は私には欠かせない貴重なものだった。
そのような唐牛の姿が私の中で今に至るも生き生きと浮かび上がってくるのが六〇年四月二十六日未明の場面である。
すでに大詰めに近づいていた安保闘争は、この日に予定されていた国会デモをめぐって激しい議論に包まれていた。相変わらずのスケジュール闘争でお茶を濁そうとする社共ら指導部にたいして、全学連は再度国会へとの方針を出したが、その具体的戦術についてはブントの内部で最後まで一致がみられなかった。しかしこの日の闘い方如何がその後の展開に決定的影響を持つと判断した私は不一致をおして強行突破の方針をきめ、これに賛成するものをひそかに集めて前夜から全都をオルグしてまわっていた。全学連書記局も東大も東大駒場も反対するなかで賛成したのが唐牛だった。彼は現場指揮を志願し、方針は彼に委ねるということで学連を了承させた後、私たちとともに夜を徹して都内各大学のブント細胞や自治会執行部を説き伏せてきた。漸く一段落して新宿の寿司屋に辿りついたのは明け方に近かった。一緒にいたのは、篠原、藤原(慶久)、陶山(健一)、常木守らだったと思う。
当日のデモに備え国会正門前に急ごしらえの装甲車を並べてバリケードをつくっている状況を見てきた私たちは、これを突破するには火を付け車を燃やすか、車によじ上って飛びこむしかないな、ということになり、アジ演説で直接呼びかけ、一人一人飛びこんだらどのくらい学生が続くか、誰がどの順番でやるかなど話しあった後は、今度は相当長く豚箱に入らなければならないだろうから、今日はゆっくり食い飲んでおこうとまた馬鹿話を交わしていた。
「もし百人以上の学生が続いたら何を賭ける、酒と彼女を差し入れろ」などといいながらも唐牛は私の顔をじっと見いり「俺達は今日でパクられて終わりだからいいが、島は後、まだまだ、反対した連中ともつき合わなけりゃいけないし大変だろうな」とつぶやくようにいって杯をまたぐっと飲みほした。
数刻の後「じゃな」と別れていった時には夜は完全に明けていた。
その日の午後、国会前に集まった万余の学生たちを前に「バリケードを突破し国会へ」と叫ぶような演説をした後、装甲車に上り警官隊の中に飛び降りた唐牛は篠原らとともに逮捕され、投獄される。
彼らに続いてバリケードをよじ上っては飛びこんだ学生たちは、私たちがその朝予想した数の十倍を超え、この日のデモの性格を一変させ、五月へと続く闘いの大きなうねりをつくった。
五月、六月と大衆の参加は雪だるまのようにふえ、国会周辺は連日デモによって埋められた。そしてブント・全学連は六月十五日、再度国会へ突入する。樺美智子を失ったこの闘いは岸政権をゆるがせたが、六月十八日、空前の規模の群衆が取りまく中で安保条約は自然承認され、安保闘争は敗北の中に終熄する。しかしこのクライマックスともいえる五月、六月、唐牛はすでにいない。
唐牛にとっての安保闘争は四月二十六日をもって終焉したのだった。
後年語られるような、水際だった演説をし颯爽として全学連デモの先頭に立つ若き獅子、唐牛委員長の姿は、四・二六をもって最後とする。
そして──私の中に現在まで鮮明に残っている唐牛は、同じ六〇・四・二六の日付であっても午後の国会前の英姿ではなく、暁の新宿の飲み屋で私につぶやくような言葉を吐いて別れた後姿である。

3
六〇年十月、六ヵ月の巣鴨生活を終え娑婆へ出てきた唐牛は、引く手あまただったブント諸派の誘いをふりきって最初に私の所にやってきた。
安保終了後のブント分裂の中、手を拱いて全く無為の毎日を送っていた私にとっては、まさに遠来の客であったせいか朝まで飲んで揚げ句の果てはともどもひっくり返って寝てしまった。
唐牛にしてみれば半年の隔絶された独居のうちに、あれよあれよと移り進んでしまった世の中の動きを掴んで現職委員長としての身のふり方を相談する気があったのだろう。
しかし、すでにブント崩壊すべしと判断し、なるようになれと書記長としては無責任極まりない態度でいた私は、「好きなようにすればいいのじゃないか」といった調子で、彼も「じゃ、そうするか」などで終わったように思う。ただ、あの四月以降の闘いとその後のブントの内部闘争の筋道を、私の酔っ払った勢いの片言隻句からピタリと察知しただけでなく、ふて腐れたように事態収拾にも動かなかった私の心内を鋭く感得した唐牛にあらためて深い親近感を抱いたことだけは確かな感覚で残っている。
この日以来始まった唐牛の逡巡と彷徨の歩みは、安保闘争の敗北とブント分裂・崩壊の中で私たち一人一人が味わった苦渋に満ちた模索と著しく異なったものではなかった。
例えばブント分裂諸派の一時の選択において唐牛は、最も近かったといえる清水、青木らの全学連グループと袂を分かち、古賀、常木らの戦旗派に属した。
その後、戦旗派の一部が黒田寛一らに屈伏し、更に清水、北小路らが同じく革共同に移行する流れの中にあって、後年最も唐牛らしからぬといわれた行動──革共同加盟の道をとる。この六一年のブント転向劇の進行にはさすがに私も唖然として、真底ブントは崩壊したと自分の行為とともに、苦く苦く噛みしめていた。
当然のことだが、本質的に相容れぬ革共同との同棲は長くは続かず、やがて政治的生活から離れた唐牛の無頼の日々が続く。
夜になるといずこからともなく集まっては飲み、夜明けまで町を徘徊し、朝になると綣どこかの家でぶったおれるように重なりあって寝てしまう。そんな生活があくことなく繰り返されたが、この頃、最もよく唐牛と一緒にいたのが篠原であり東原吉伸であり、青木であり、そして私であった。
この時代でも私たちは何時も陽気であり、酔えば子供じみた悪ふざけに興じていたが一人一人の胸のうちにはさまざまな思いが渦巻いていたのであろう。
そしてなによりも、熱気に溢れていた学生運動の現場から離れてみた時に、磐石の重みで襲いかかってくるのは食わねばならぬ生活の苦痛である。
私も共産党時代から女房の稼ぎで漸く生計を維持していたのだが、毎日することのなくなった六〇年以降の数年間、十円の電車賃がないために一日痴呆けたように寝て過したこともすくなからずあった。それでもまだ食えるものと酒だけはなんとかいつもあったためか、蛸部屋のような私の家には金のない連中がいつも誰か泊まっていた。
そして仕事をしていた女房の金を虎視眈々と狙っていた筆頭が唐牛であった。ない酒代をどこからとなくせしめたり、ただ酒の場を探してくるのに天与の才を発揮した第一人者でもあった。
しかし、いかに若さに任せて奔放にふるまおうとも、自分の手で食うことをしない生活は所詮書生っぽの馬鹿騒ぎに過ぎない。
今考えれば懐かしい無頼な彷徨の数年の後、一九六三年、唐牛も私もそれぞれ生活の道を歩むことになる。病いに倒れた女房に代わって私は塾をひらくことで急場をしのぎながら、ながらく捨てていた医学の道に再挑戦することを決意、悪戦苦闘の末、六五年、医師の免許を手にした。
唐牛も六〇年以来親しくつき合っていた田中清玄氏の事務所で働くことになる。
二十六歳のことである。

4
ところがこの実社会での再出発という最初のとばくちで、唐牛は生涯ついてまわった「六〇年安保闘争の全学連委員長」という称号の負の力をまず味わわねばならなかった。
唐牛ならずとも、若き日革命を論じ左翼運動に走ったものならば誰でも、社会の報復の厳しさに一度は身を哂さなければならないだろう。
唐牛がエネルギー・コンサルタント企業なる会社でサラリーマンの生活に入ったとき寄せられる非難も本質的にはその次元のものに過ぎなかったといえよう。しかしそこでの登場人物があの田中清玄であり、あの唐牛健太郎であったことから、左翼諸党派やマスコミの悪意ある攻撃を一斉に浴びることになったのである。
この「事件」はその後も繰り返し流布され、「唐牛物語」の一つの色合いにもなり、胸くそ悪い評論や憶測を多くつくりだしてきたので今さら多く述べる気もしないのだが、唐牛と田中氏との交わりに当初から最も近くにおり、あの報道の最中にも彼と共に過すことの多かった私としては、やはり一言だけはいっておかねばならないだろう。
悪煽動の一つ、金のことについていえば、政治組織をつくり闘いをしようとするならば金が要るのは自明の理である。あの安保闘争が私たちの当初の予想を遙かに超えた大闘争になった中で、ブント書記長としての私の仕事の大半は金づくりであったとさえいえる。記録には全く残らぬこの労多き仕事に黙々としてあたった生田、香村、東原、神保誠らの手をかりながら、これまたブント流に大らかに金をつくったが、その中で当時としては大口といえる寄付者の一人に田中清玄氏がいた。しかし大金持とは決していえぬ氏のカンパは、ブントや全学連の全闘争資金からすれば数パーセントに過ぎず、ましてやこれによってブントや全学連が動かされたなどという話は笑止の限りといえよう。
更に田中氏についていうならば、この人もまた世の様々な虚のレッテルを受け続けた人である。ここではただ安保の最中初めで出逢って以来、私にとっても唐牛にとっても生涯の深いつき合いをすることになった人であるとだけいっておこう。その行動のスケールの大きさ、驚くほど異色な交友範囲の広さ、更にいくつの年になってもロマンを追う若さと情熱など、そう簡単にお目にかかれる人物ではない。氏が安保闘争とブントに共感を寄せ、身銭をきって私達を応援したのも、老獪な右翼陰謀家の策略などではさらさらなく、戦前の挫折した左翼指導者の夢が甦り、また氏も求めて止まなかった戦後日本社会批判の新生の芽を本能的に嗅ぎとったからであろう。このような人間を見る目ぐらいは、いかに若かったとはいえ、私や唐牛にしても持ち合わせていた。
またこの田中氏の企業に入ったことをもって右翼への転向とするような事大主義的錯誤の思想とも私たちは無縁であった。したがってあの左翼的デマゴギー自体に痛痒を感じたわけではない。
事実、唐牛はあの時もその後も弁解じみたことは一言も発せず、彼流の週刊誌向けのせりふで流していたのだが、終始一緒にいた私は、あの攻撃の中におかれた唐牛が少なからぬ衝撃を受けていたことも認めないわけにはいかない。
彼が真剣に心を痛めたのは「たかが二十歳の若僧が東京に出てきて、一年そこそこの間、酒を飲み飲みデモをして暴れ、何度か豚箱に入った位のことが何時の間にか「戦後最大の政治闘争の主役全学連委員長」というシンボルとなって一人歩きしてしまっているという事態であり.あの運動と組織の象徴を担わされていることを初めて自覚したことにあった。
また「安保も全学連もブントも、今のあっしにや関わりのないことでござんす」といってしまうには、まだあの体験は余りにも生々しく、そして彼も若かった。
後にも先にも一度たりとも私に見せたことのない苦渋の色を露わにしながらも、ここでも彼は男らしく、優しかった。
報道に狼狽し唐牛の責任にして逃げの一手を計ったかつての盟友をも許容し、また私についても「島まで巻きこまれるとヤバイからな」と一切を自分の所で引き受けて過したのだった。
しかしその中にあっても、妄論飛び交う中でただ一人真正面から向かった吉本隆明の論がでた時には「少しホットしたよ」と弱気の告白を私に吐いたり、函館の母親に「悪評にめげず頑張れ」と電報をうったりしていた苦悩の唐牛を、今まじまじと身近に見つめるのである。
この時知らされた虚像の重荷は、その後彼が拒否し、更に無視し、そして時代を経て風化した時期にはこれを楽しんだ気配もあったものだが、その意志とは離れて終生唐牛にまとわり続けたものであった。
三年余の田中事務所勤務を皮切りに続けられたさまざまな流転の生活も、常に「あの唐牛が」という語り口から免れることができなかったのである。
ともあれこのような苦汁をなめながらも、他人の下で働き給料をもらう生活に入り、ここでも人一倍の仕事をした唐牛であったが、似たような強い個性を持つ田中氏の下では堪えられなかったのであろう。やがてここを出て、堀江謙一らとヨット会社をつくったり、新橋の一杯飲み屋「石狩」を引きうけたりして、その度毎に週刊誌に話題を提供し、「唐牛物語」を自演していく。
意識して過去を切り捨て、ただ医師の道を歩むことにのみ専心していた私は、この時代の唐牛の生活は殆んど知らない。しかし時々会う度に、新しい道を模索しながら生き抜こうとする強い意志と現実の厳しい辛酸を読みとらずにはいられなかった。
そして齢三十をこえた自分の生を見つめて一つの跳躍を考えていたのであろう。一九六九年、彼は私にも一言もなく忽然と東京から姿を消したのだった。
ちょうど時を同じくして、私も遠く沖縄の地に移り、以後十五年この島の医療にあたることになる。間違いなく、一つの大きな転回が唐牛にも私にもおこったのだった。

5
お互い個人的なややこしいことには余り触れない私たちの習わしから、唐牛が全く沈黙のまま去っても、また何年も消息がなくても「あいつも頑張っているんだな」と思っただけで、なにがどう彼の中におこっているのか憶測することもなかった。
辛うじて私のもとにとどいたのは、南の与論島で上方をしていたかと思うと、今度は一転して北の最果てオホーツクの海で漁師をしているというような噂だけであった。
その唐牛が、全く突然、沖縄の我が家に芹澤と二人で下駄履き姿で現れたのは一九七五年の冬のことだった。
私は南島に移り住んでから数年経っていたが、病院や保健所の診療に追われている毎日だったので、「オホーツクの海は冬は凍ってしまって仕事にならねえから出稼ぎの旅をしているんだ」とかなんとかいいながら五、六日も腰を据え昼間から酒を飲んでいる彼らの応待は女房にまかせていたが、夜になると一緒になって始まる酒宴はいつまでも終わらず、駄法螺と与太話の連続で楽しい再会であった。
しかし今、私の脳裡に刻みこまれているのはその会話ではなく、久し振りの再会で示した唐牛の、口に出さなかったありようである。
精神科の医者として飯を食うようになりながらも、私は人の心の奥底にことさら触れたがらない性向をもっている。
或る意味では鈍感であるといえよう。そのせいか当時は何気なく見過していたのだが、ずっと後になって──彼の死後最近になって知った話の脈絡から、あの日の唐牛をひときわ彼らしかったなと偲ぶのである。
六九年東京を去った彼の生き様が一つの転回であるといったが、それが全学連を背負った社会的生活への袂別を意味しただけでなく、若き日よりの伴侶であった津坂和子さんとの別れとともに真喜子さんとの出発でもあったことを、私はうかつにも全く知らなかった。二十代の日々私の家によく現れた唐牛は和子さんを伴ってきたこともあり、私たち夫婦も親しみを抱いていた間柄であった。女である女房が彼女のことを話題にのせたのも自然の成行きであったが、一瞬の沈黙と暗い翳りをちらっと見せた後、唐牛はすぐ話を変えてしまった。そしてその時には一緒になって五、六年も経っているはずの真喜子さんのことなど一言も触れずに、沖縄滞在を終え別れたのだった。
しかも後日きいたところではその前日まで一緒だった真喜子さんを与論島に残しての来沖だったという。
事実、私が真喜子さんを実際に知ったのはその七年後、八二年に徳洲会の活動で沖縄に来た時が初めてであった。
剛毅な半面、極端なほど含羞な彼の性格を示したともいえるが、それだけでなく六九年の遍路が唐牛の深く屈曲した心の旅路と転生であったことを物語るものであったと思えるのである。
元来は無口であった唐牛は、後年特に酒が入ると饒舌なほど多弁になりその語りは人を惓きさせなかったが、自分自身の心の襞は頑ななまでに人に見せることを拒んだ。
そんな寡黙の男──唐牛を私はこよなく愛したが、その姿を彷彿させるものでもあった。
袂別は常に新たな道への出発である。いくばくかの遍歴の後一九七一年、唐牛は紋別に居を定め北海に漁る海の男となったが、遙か遠くにいた私はこの期の彼の生活がいかなるものであったか知る由もない。
しかし、私は一見恰好よいこの転身に、またまたつくられた自然児物語も、羨望の念で唐牛らしい生き方と拍手を送った人たちの憶測をも殆んど信じない。
四十近くなった男が全く見知らぬ土地に住み、体一つで稼がねばならぬ生活がそんなに簡単なことでなく、またそう面白おかしくあった筈がない。
唐牛流にただひたすら漁師になりきろうとしたのであろうが、頑健だった彼の肉体の極限が試されるような日日の繰り返しだったに違いない。
しかしまた、沖縄での私の経験に即して考えてみると、十年近くに及んだ紋別の生活は唐牛健太郎の人生において最も大きな意味あいを持っていたことも確かであろう。
彼の死後その足跡に少しでも触れてみたい思いで零下二〇度という寒さの紋別の地を訪れ、船を下りた時彼が毎夜のように行ったという小さな店で真喜子さんや当時の友人たちと酒をくみ交わしながら吹雪の夜を過した。その人々の姿と雪の中の港街の風景から辛うじて当時の彼の匂いを感じることしかできなかったが、この流氷の地に唐牛が長く住んだ心うちが伝わってくる気がして、一夜のつき合いの彼の友人がずっと以前からの私の友であったように思えてならなかった。

6
長い空白を経て、再びよく会うようになったのは、船を下り、病いに斃れた母親をつきっきりで看病し、その死を葬った後もなおとどまっていた函館時代のことであった。
無聊をかこっていたためであろうか、私の本土への短い旅先で、北海道からあらわれた唐牛に出くわすことが多くなった。
安保以後すでに二十年の歳月が過ぎていた。
しばらく振りだったせいか唐牛は一見驚くほど変わったように私には映った。
短刈ながら薄くなった頭髪、酒焼けしふてぶてしい感さえ受ける顔貌、長い漁師生活で鍛えられたがっしりとした体型などの肉体的変貌に、変転しながら生き抜いた豊富な社会体験からのたくましさがあらわで、二十代の長幼の差が完全に逆転した感さえ受けた。また生活の場をはるかに超えた広さと深さを持つ人々との交わりにも裏打ちされたのであろうか、その語りも絶妙で味わいがあり、何人かの友人たちとの席もいつの間にか唐牛の独壇場になってしまうのにも感嘆した。しかも最果て僻地での長い肉体労働の生活にも拘わらず、社会と文化を見据える鋭い知的感性はいささかも衰えず言動には若さが漲っていた。
しかし、若干の戸惑いの後、一貫して変わらぬ唐牛を見てとりながらも、何か彼にそぐわない不安定さをも感じざるを得なかったことも事実だった。
ある京都の夜でのことだった。
今泉正臣や佐野茂樹らと昼間から飲み続けていた私が、唐牛のお喋りに突如向っ腹を立て、酒をぶっかけ杯を投げつけ怒り出したことがある。酒乱相手では経験豊かな彼だけに、その場を引くことによって喧嘩にもならず、次の朝にはまた泊まり先の今泉の所で一緒に飲み出すといった酔っ払いのとるにたらぬ一幕だったが、今よく考えてみると、この時期唐牛はなにかを求めて一歩踏み出そうとしながら、未だ行方定まらずにいるための苛立ちを、彼自身の言動に垣間見せていたように思う。そして沖縄での精神医療にのみ限定して仕事を続けていた私に対して、ことさら挑発的な毒舌を浴びせた彼に、決断と行動という私の中の唐牛と異質なものを感じさせたことが私の暴発を誘ったのではなかったか、などと思ったりもする。
一九八一年、唐牛は十二年振りに再度の東京出奔を決意する。
唐牛が背広姿にネクタイといういでたちでコンピューター・セールスに汗を流していた東京でのある日、ちょうど上京していた私に呼び出しがかかり真昼間のレストランで酒宴が始まった。一緒だった小泉修吉や片山迪夫と別れた後、私はふと沖縄で知り合った徳田虎雄の事務所が近くの赤坂にあることを思い出し、「面白いやつがいるから一寸会ってみないか」と唐牛を誘って大平元首相の事務所があったというビルの八階に陣取る徳洲会本部を訪れた。すでに相当量の酒が入っている私たちを迎えた徳田もすぐ沖縄の泡盛を出して応じたが、これが唐牛と徳田の最初の出会いだった。
昼間の突然の訪問であり、この時は小一時間の雑談で別れたのだが、わずかのやりとりの中にも両者に閃くものがあったことは確かで、窓から見える国会議事堂を指さし天下を取る話を始めた徳田の大法螺に唐牛がすこぶる生真面目に応酬しているのを私は側で黙ってきいていた。
しかし沖縄に帰りすっかりそんなことを忘れていた一、二カ月後、またまた突然の電話で「徳田と一緒に仕事をやることにしたんだがマスコミがまた騒ぎそうなんでおめえには知らせておくよ」といってきた時には最初はまた与太話かと思った。だが、若干のはにかみをみせながら極めて神妙に話を続けるのに、こりゃ本気だな、とすぐ察知して、彼らしい決断に拍手を送りながらもそれまでに気がついていた徳田虎雄についてのコメントと危惧をのべた。私の話を珍しく素直に「ふんふん」ときいて電話をきった後は例によって音沙汰がなく、その後の話は、この奇妙なコンビを伝える週刊誌の記事で知ったのだった。
二十四時間診療をスローガンに全国に次々と病院チェーンをつくり医療革命を叫ぶ徳田に、最初は拍手を送っていた人々も、やがて彼が在来の保守政治にのめり込むに至って次第に冷ややかな目を向けるようになっていったが、それにもまして「体制に常に挑戦し続けたわが英雄、唐牛健太郎」が「俗物二流政治屋の徳田虎雄」と手を組み、こともあろうにその選挙運動に血道をあげたことに多くの友人たちが首をかしげ、更には死後までこの選択に非難を浴びせるものも少なくなかった。
しかし、唐牛の人生で最後になってしまったこの闘いの時、直接つき合うことの多かった私は、彼のこの行動と心情を殆んど了解することができる。
彼が東京に再度出た理由はさまざまであろうが、俗な言葉でいえば「もう一旗あげて」社会に再挑戦したいという誰しもが襲われる衝動であったことは間違いない。そしてその方向と場を探し求めていたのだが、すでに平和な安定した世の現在の日本では容易にこんな道がみつかるわけがない。
唐突な行動の連続に見えた唐牛は、決して世をすねた彷徨の旅人でもなければ、奇を衒って自己を顕示する芸能文化人でも一発事件屋でもなかった。
また観念の世界に上昇し、そこから社会を討つ思索の人となるには余りにも生臭い生活の人であった。
彼は真剣に四十年の自分の生きた体験を踏んで、日本の社会と政治に挑む現実の行動をまさぐっていた。その道筋の中に医療・福祉・教育といった人間の弱みにつけこんで栄える現代社会の討つべき標的があった。
そして同時に、人と人との関係が稀薄になりながらも高度な技術に依拠して肥大してしまった経済官僚的政治国家ともいうべき日本の構造に、最も人間臭い政治を求めて楔を打ちこみたいという強力な願望があった。
そんなことを唐牛風に構想していた中での徳田との邂逅であり決断であったのだ。
唐牛の交遊関係は知られるように私たちには想像できないほど多様であった。その一方の極に田中清玄や徳田虎雄、田岡一雄らの世を騒がす強烈な個性の持ち主がいた。騒がしつつすでに社会的場を確保した有名人といってもよい。
この関係でも一貫していたのは、彼らの感性を共感した限りにおいて最後までまっとうにっき合い通すということであり、彼らを利用しようという根性は爪の垢ほどもなかった。
徳田虎雄との間もそうであった。
桁はずれのバイタリティに感心しただけでなく、異常なまでに出世・名誉といった世俗に固執し続け、その馬鹿馬鹿しさを知りながら、倦むことなく行動し実践し演出していく徳田にある共感と親愛感をさえ抱いたのだった。
そして共働をきめた限りいささかの手抜きもしなかった。医療の知識を貪慾につめこみ全く馴染まない医者たちとのつき合いも含め、病院づくりにも全力投球をしていた。また徳田が選挙に突入した局面では、最も困難だった喜界島を受け持ち、ここに独り住みつき、島の人々と生活を共にしながら徳田の勝利のために労を嫌わなかった。
極めて短い期間であったのに、各地の徳洲会病院の医師・看護婦・事務員などが唐牛に示した親愛の情と信望のあつさに直接触れて私は舌を巻いたものだった。
むろん激しい気性で波長もちがう二人が長く共存することは当初から考えにくかった。私の提言もいれ、唐牛は徳洲会と徳田を援助しながらも経済的には全く独立し、秋山肇氏の厚意で提供された市ヶ谷のアパートに事務所をひらき「炫燿社」なる看板を掲げたのだが、これも独自の社会政治の行動を構想しようという唐牛の決意を物語るものだった。
唐牛が徳田との活動の中からどのような次の道を拓くであろうか、私が最も期待し見守っていたところであったが、その端緒を見ることもなく終わってしまった。
徳洲会での闘いの日、沖縄中城村での徳田の講演会に、初めて会った真喜子さんともども私も酔っ払って参加したのだが、唐牛がいとも真剣な顔をして地元の青年たちに話をしているのを二十年前と錯綜しながら聴いていた。考えてみればあの全学連時代でも私が唐牛のまともな演説を聴いたことは稀れだったのだ。
やがて選挙戦が熾烈になっていき一九八三年も明けたとき、あの運命の日がやってきた。

7
一九八三年二月二十二日、那覇の小さな酒場で私は唐牛と二人だけで静かに飲んでいた。喜界島で体調に異変を感じ沖縄徳洲会病院に入院中であったが、全検査を終了したといって病院を抜け出し、保健所に居た私や保健婦らと一緒に食事をした後のことであった。
どこで仕入れた知識なのか、自分の症状を分析して「直腸癌か、潰瘍性大腸炎か、内痔かだな」など医者の私を前に診断まで下すのだったが、病気らしい病気をしたことなく、恐らくはじめて病院と医師に全肉体を委ねてやはり内心複雑な思いだったのだろう、いつになく早い時問にきり上げ病院に戻っていった。
その翌朝だった。病院で診察していた私に電話で「やっぱり癌だったな」と自分で告げたのだった。告げられた私の方が狼狽していう言葉も失っているのに「すぐオペをするが、日本で一番の医者にかかりてえからすぐ東京に行く。人工肛門に似合った衣裳のデザインを考えておくからな」と例の調子を崩さず一人で喋って、会う間もなく上京していったのだった。
この日から唐牛健太郎の最後の闘いが始まる。
医者でありながら私は彼の病いとの闘いに何ら手をかすこともできず無力であった。 そんな苛立ちを終始感じながら、癌センターや千葉の病院などに彼を見舞ったが、その闘病振りにはいつも心うたれるものがあった。
自分を冒している病いから日をそらすことなく、恐るべき意志力で立ち向かっていた。一時一時に精一杯の賭けをしているようでもあった。
最初の手術から死に至るまで、小山靖夫先生を初めとする医師団は日本最高の技術をもって治療にあたったのだが、どの医師も看護婦も一人の患者という以上に唐牛を愛し、文字通り一緒になって癌と闘う姿に逆に私たちが励まされる始末であった。
しかしまた私はこのような状態の唐牛に会うのは堪えきれない程辛かった。私の唐牛は強靭でたくましく美しい肉体を持ち、豪酒で笑いながら悪態をついている男でなければならなかった。
たとえ手術とはいえ、彼の身体がメスによって傷つけられるのは許すことができないとさえ思った。ベッドに縛りつけられるように点滴注射をうけ、苦痛に眉をひそめる唐牛はあってはならなかった。
唐牛もまたそのことを知っていた。
自分の心の痛みをみせるのを拒み続けてきた彼は、身体の病いに冒されている自分の姿を他人に曝すことにも極度のはじらいと苦渋を隠さなかった。特に私に対してはそうだったようにも思えた。
手術後のリハビリも終え半年振りに退院してきた折の挨拶状に「酒は飲むべし」と一言だけ書き、人工肛門を抱えながらも豪快にウィスキー一本をあける姿をみ、また真喜子さんや主治医の天願勇先生を従えながらも、沖縄まできて飲みあうようになった時には、ああ唐牛は甦ったなと歓喜したのだが、その直後から癌は急速に全身に転移、容態悪化、再び癌センターに入院するに至った。
年の暮、病院に行った時には、唐牛はすでに死期を予知していたのだろうか。見てはならない姿を見た私は、その場に居たたまれず、同席していた草間孝次氏とともに早々に帰ることを告げたが、唐牛も「もう帰るのか」とやや弱々しくいっただけで引きとめることもしなかった。
これが最後であった。
南島に戻った私の所に、時々刻々容態の変化が報告され、意識あるうちにもう一度会いたい思いに捉われ続けたが、死の病床にある唐牛を見たくないという本能的感情が優位をしめたまま、三月四日を迎えたのだった。
最後の対面で見た唐牛の顔は、私が終生好きだった美しく爽やかな笑顔だった。すでに敢えて覆う必要もなくなった心の奥底の襞も解き放った安堵の相もみせていた。
私はこの最後の一年、それまでの目まぐるしかった動とは対照的な静の場で、唐牛とつき合えたことを幸せだったと思う。
この中で深く知り合うことができた夫人真喜子さんが「この一年ほど楽しかったことはなかった」と死の直後としては不謹慎とも思えることを昂然といっているのをきいて、その心情を痛い程共感した。彼女にとって「健太郎を二十四時間看護し続けた」日々は最も充実した生であったのだろう。
唐牛にしてもそうであったと私は思う。
波瀾に満ちた、しかし短かった生の最後の日々、彼の脳裡に何が浮かんだのか、それは誰も知らない。
しかし、「もう帰るのか」とつぶやいた後に「俺はさきにいくからな、島はまだ大変だな」といおうとして呑みこんでしまった唐牛の言葉が、二十四年前の投獄前のせりふと重なりあって、その後ずっと今に至るまで私の心耳に響いてくるのである。
一握の灰になってしまった唐牛を葬るために、四十九日後、真喜子さんや数人の友人とともに生地函館に赴いた。そして一周忌、三回忌と三度この地を踏んだ。生まれ育った湯ノ川町の湯川寺の広間で昼間から賑やかに酒を飲んだだけのことだが、親族の方々やいつも夜まで騒いだ幼い時からの友人たちの暖かい雰囲気に包まれながら、あの唐牛にとっての故郷はこの地以外にはなかったのだ、との感をしみじみ抱いた。
そして長い旅の後、この地に帰り、ただ一人の児として母と同じ場所に眠ることになった、自然のままの唐牛を、いま一度、はっきりと、見たのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
