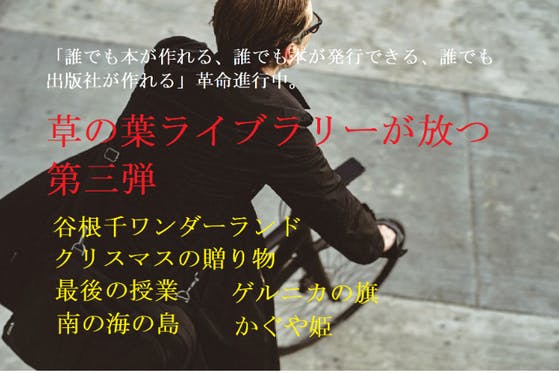南の海の島 3
平島から瀬戸島、千石島、笠戸島と回った南海丸が、樫山の住む姫島を間近にとらえたのは、鹿児島を出港してから二日目の朝十時ごろだった。五月の陽光をうけて白い砂浜がきらきらと輝いていた。緑につつまれた丘陵がゆるい起伏を描いている。おだやかで柔和なたたずまいをした島だった。とうとうきた、これでようやく地獄の苦しみから解放されると思った。しかしそれにしてもなんという遠さなのだろう。まるで地の果てにきたように思えるほどだった。
ポンポンと小気昧よい音をけたてて、一条の白い帯びを引きながら小さなはしけがやってきた。はしけには四、五人の男が乗っていたが、ぎらぎらした陽を浴びた男たちの肌の黒さと、その頭にまいた手拭の白さが鮮やかだった。南海丸の脇腹にその小さな船体を着けたが、そのはしけに飛び移るにはちょっとした勇気と決断力といったものが必要だった。おだやかな海と思ったが、はしけと南海丸は互いに上下に揺れて、大きな落差をつくる。落差だけではない。波のうねりで大きく引き離されたりするのだ。飛び移るタイミングを間違えたらざぶんと海に落下する。その島に上陸するのは、瀬戸島から乗った老人と私だけで、その老人はひらりと舞うように飛び乗ったが、私の跳躍はたぶん無様なものだったにちがいない。
うねる波を切り裂いて、はしけは島を目指した。飛沫がばしゃりばしゃりと飛び散る。私も容赦なく飛沫の洗礼を浴びた。入江を回って小さな湾のなかに入った。岸壁には島の人たち十数人が、接近していくはしけをじいっと見守っていた。はしけからロープが岸壁に投げ上げら、そのロープに引っぱられて、船体が岸壁に横づけされた。老人はまた身軽にひょいと上陸した。私もまた島の人たちの痛いばかりの視線を浴びるなか、岸壁にひらりと軽快に飛び上がったつもりだった。ところが岸壁に足をひっかけてもんどりうって転倒してしまった。おまけに手にしていた紙袋の中身が、ぱっとあたり一帯に飛び散ったから目もあてられない。一人の若い女性が駆け寄ってきてそれをかき集めてくれたが、その女の言い草といったらなかった。
「みっともないわね、都会人って、これだからいやになるのよ」
実際、みっともない上陸第一歩だった。私は照れくささを隠すようにありがとうといった。
「あなた、どこからきたの? 東京?」
「そうなんだ、東京からきたんだ」
「なにしにきたわけ?」
その女の口調といったらとげとげしく挑戦的で、あなたなんかのくるところではないといわんばかりなのだ。ちょっとむっとした私は、
「君には関係ないことさ」
「関係あるのよ、この島では、個人のことは全体のことなの、たった百十七人しか住んでいない島なんだからすべてに繋がっていくの」
「樫山先生に会いにきたんだよ」
「あの人の友達ってわけ?」
「まあ、ね」
「それじゃあ、私が学校まで連れていってあげるわよ」
「それはうれしいな」
「じゃあ、ちょっとそのへんで待ってなさい」
と命令するのだ。
岸壁の奥に木が立っていてその木陰の下に腰を落とした。揺れるはしけやうねる波に目をやるとまた吐きそうになる。やっと地獄の苦しみから解放されたとはいえ、ぎりぎりとねじられるような頭痛はそのままだった。
島の男たちがはしけから荷を下ろしはじめていた。その生意気な女もその作業を手伝っていたが、そのペースといったらだらだらのろのろで、いつ終わるとも知れない作業に、私はバックを枕にして土の上に身を構たえた。木立の下の空気はからっとしていて、海から吹いてくる風が心地よかった。私はいつのまにかまどろんでいた。
「どうしたの、大丈夫?」
女がかがみこんで、私の肩をゆすっていた。
「ああ、船酔いなんだよ」
「だらしないのよね、東京人は」
まったく生意気な女だった。もうほっといてくれといおうとしたら、
「もう少し横になっているといいわ、気分がよくなるまで、待っててあげる」
といって彼女も座りこんだ。形のよい足が、私の前に投げだされて、ちょっと目のやり場に困った。
「ねえ、あなた、煙草あったら、一本くれない」
私はロングピースをさしだすと、
「生意気な煙草すってるのね、この島にこんな煙草、売ってないわよ」
「君はこんなところで、なにをしているんだ」
「こんなところとはご挨拶ね」
「いや、なんだか、まるでこの島のイメージに似合わないからさ」
「なにをしてるって、いろいろしているのよ」
「君だって、みっともない東京人じゃないのか?」
「まあ、ね、私、絵をかいているのよ」
「なるほど、ゴーギャン的心境かな」
「ゴーギャン的心境か、まあ、いろいろあって、むずかしいところなのよ」
彼女の明るい顔が、ちょっと複雑なくもり方をした。
「もう大丈夫だよ」
「そう、じゃあ、いきましょうか」
私たちが歩きはじめると突然、
「私は黒沢倫子、あなたは?」
「ぼくは鈴木一夫」
「ずいぶん平凡な名前ね」
「平凡で悪かったな」
「樫山英雄という名前よりはいいわよ」
「そういえば、あいつの名前は、ずいぶん生意気だよな」
「そうなの、あの英雄主義が、とっても鼻もちならないの」
ガジュマルの木立がさわやかな緑の木陰をつくっている。そのかたわらにはハイビスカスやブーゲンビリアの花が咲いていて、ここはあきらかに南国だということを語っていた。
岸壁から五分も歩かないうちに集落に入った。珊瑚を積み上げ塀が碁盤の目のように築かれている。その塀のなかに床を高くしたこじんまりとした家屋が建っているが、人が住んでいる気配が稀薄だった。隣の家屋もまたその隣の家屋もそうだった。あたりはひっそりとしていて、まるで村全部が眠っているかのような静けさだ。子供たちは学校に、大人たちは農作業か漁にでも出かけているからなのだろうかと思ったが、そうではないらしい。朽ちた家があり、崩れかけた家があり、もう廃屋になってしまった家もあった。
「二軒に一軒は、人が住んでいないみたいだな」
「そうなの、若い人たちは島を出てしまうわけ、ここに残っているのは老人ばかりになっていくのよ」
集落を抜けてだらだら坂を上がっていった。一気に高度を上げると、いま通ってきた村落が一望された。七、八十戸の家屋が樹木のあいだにひっそりと包まれていた。
その集落の前には白い砂浜がやわらかい曲線を描いていた。そして緑にかがやく海。美しい光景だった。私はなんども感嘆の声をあげた。
「美しい景色って、残酷なことなのよ」
と倫子は、私を非難するようにいった。
丘陵にのぼりきると、なだらかな高原といった景観になり、そこに学校があった。グランドがあってその奥に校舎か立っていた。平屋のなんの変哲もない細長い建物だった。その窓ガラスがさんさんと降り注ぐ陽を浴びてきらきらと光っていた。
私たちが校庭に入っていくと、校舎の一番端の教室の窓から、一人の男がじっと私たちをみていた。倫子が彼にむかって手を振ると、その男もちょっと手を振りかけたが、かたわらを歩く私を警戒してか、その手を止めた。また、じいっと私がだれなのかを観察している風だった。
私はサングラスを取り、大声で樫山の名を呼んだ。とうとう私がだれだかわかったのだ。彼はなんと教室の窓から飛び出すと、私にむかって駆けてきた。全速力でつんのめりになりながら走ってきたのだ。私も走りだしていた。
「とうとう、きてしまったよ」
「なぜなんだい? どうしたというんだ? どういうことなんだ?」
「君を驚かそうと思ってね」
「なんという男だ、知らせてくれればいいのに、まったくどういうことなんだ」
驚きと感動でなにを話していいのかわからないといった様子だった。その目には涙さえにじんでいる。私もまた胸が熱くなった。
「ここは世界の果てという感じだな」
「そうだね、日本の中心からみれば、南の端だよ、まったく」
![]()

![]()
「草の葉ライブラリー」は「CAMPFIRE」で六作品をクラウドファンディング中です。「CAMPFIRE」を訪れてみてください。こよなく美しい音楽に疲労した心を癒してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?