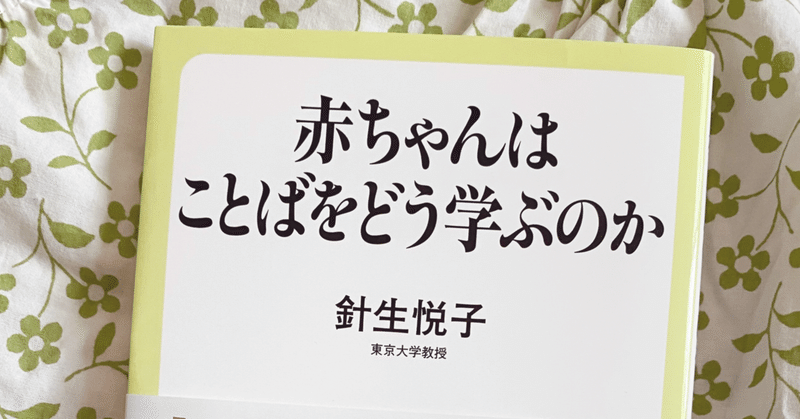
#読書記録 『赤ちゃんはことばをどう学ぶのか』
タイトルの内容が、ただ単純に気になったので
手に取ってみました。
赤ちゃんが言葉を習得するのは容易なことではない
私たちが新たに言語を学ぶときは
「do = 〜する」のように
母語を使って、学ぶことができます。
しかし赤ちゃんは言語そのものを
自分で発見、理解し学んでいかなければならないのです。
私たちが指差しで
「これはりんごだよ。」と“りんご”を教えようとしても
赤ちゃんからすると
「コレハリンゴダヨ」の音にすぎず、
そもそも指差しという行動が
指先の指す方向を示す行動ということも知らず、
“リンゴ”でひとつの言葉となっていることも分かりません。
赤ちゃんがどれだけ高度なことを成し遂げて成長をしているのか、それを知ることで我が子の成長を、より喜び、より讃えることができるように感じます。
指差しの起源
指差しひとつとっても、私たちが知っている目的の指差し行動ができるようになったか、を見る視点が増えるだけで、成長を喜べる機会が増えます。
指差しを覚えた赤ちゃんは、自分では遠くのモノを指したりするのに、他の人が指差しして見せたときにはその指を見ます。
指差しの起源には2つの考え方があり、
ひとつは「リーチング失敗説」
もうひとつは「注意観察説」があります。
「リーチング失敗説」は、目標のものに手が届かないながら、そちらに手を伸ばし続けていたところ、誰かがその目標のモノを取ってくれた、という経験をするなかで、赤ちゃんは指差しの効果を知るようになり、指差ししてモノを要求するようになっていくと考えられています。
しかし、8ヶ月か9ヶ月の赤ちゃんの指差しの始まりとして報告されているのは、相手に何かをしてもらうための指差しではなかったというものが多い。
なぜ他の人に何かをしてもらうための指差しでないことが分かるかと言えば、赤ちゃんは指差しをしているとき、一緒にいる人の顔を見たりしないからです。
もう一方の「注意観察説」は、対象に注意を向けてそれを調べようとする行為に由来します。
私たちはモノを掴もうとするとき、人差し指以外の指も伸ばして手を広げるが、指差しは人差し指一本を伸ばすだけである。私たちがこのように人差し指だけ伸ばした手の形を作るのは、何かに触ってそれを調べてみようとするとき。
赤ちゃんにとって「人差し指を伸ばすことはその対象を調べること」なのだとすれば、他の人の指差しを見た時も「その指が何をしているのか」にこそ注目することになります。
このように子どもの指差しへの反応は、指そのものを見るところから出発し、指そのものを見てしまっても、指差されたモノが近くにあればそれを見ることができ、それがやがて、少し離れたところにあるモノを指差された場合にもそれを見ることができるようになり、1歳半頃になれば、指差れたモノを見つけるためには首をめぐらせて指差されたモノを正しく見つけるようになります。
そしてこの頃までには、子ども自身も、誰かにそのモノを見てもらうために指差しするようになります。
赤ちゃんの「私とあなた」「私とモノ」の世界
指差しを始めたばかりの赤ちゃんにとって、指差しは自分1人の世界の中のもの。赤ちゃんは、誰かがそれを見て反応してくれることをまるで期待していません。
何かを渡されると、それを眺めては口に持っていき、角度を変えてはまた口に持っていき、ということに熱中し、「私とモノ」の世界に没入します。
誰かが働きかけに応えて声を出したり、笑ったりするときも、赤ちゃんにとっては、その相手と赤ちゃん自身しかおらず、そんな「私とあなた」の世界には、一緒に見たり、やりとりして楽しむものはありません。
しかし、9ヶ月10ヶ月頃、やがてその世界に、他の人が入り込んできます。
最初は別々だった「私とモノ」だけの世界と「私とあなた」だけの世界がつながり始めます。
赤ちゃんは、誰か他の人に、
それを見てもらう、それをとってもらう、
そのために指差しをするようになります。
同時に、他の人が、指差しで何を伝えようとしているかも分かるようになってきます。
それから、赤ちゃんは、他の人に向かってものを差し出すようになります。
赤ちゃんは自分こ持つモノと相手を見比べて、自分の差し出すモノに相手が反応することを期待しています。
他に、相手の視線をしっかり追って、相手が見ているモノを確実に見つけることができるようになっていくのもこの時期です。
また、1歳頃から、子どもが初めて見たモノや状況に対してどうふるまったらよいか迷ったときに、一緒にいる人の様子(表情や声など)を見て参考にする社会的参照が見られるようになります。
例えば犬を見て、この動物に近づいても大丈夫かどうか迷うと、子どもは近くにいる人の様子をうかがいます。そして、その人が楽しそうにしていれば、安心してその動物を触りにいくのです。
もっとも、それはあくまで迷ったらときであって、どうしても「触りたい!」と思えば、子どもは誰の顔も見ることなく触りに行ってしまいます。(これは大人も同じです。)音の区切りはなぜできる?
「赤ちゃんと私」の世界に共有するものができたら、
好きな人と美味しいものを食べて「美味しいね」「美味しいね」と言い合うような喜びがあるのかなーとワクワクします。
音の区切りはどう見つける?
赤ちゃんは、周囲の人の話し声(発話)の中から、単語を聴き取る必要があります。
しかし、私たちが話すとき、音は切れ目なくつながってしまっており、どこからどのまでが1つの単語かを示す区切りなどなく、発話の中から単語を聴き取ることは、簡単ではありません。
それがどのような感じであるかは、
知らない言語を誰が流暢に喋るのを聞いたとき、切れ目なく繋がった音の流れの中で、そもそも単語はどこからどこまでなのがさっぱり分からないと感じた経験があれば、その難しさは理解できます。
「マタミルクガホシイノ?」「イッパイミルクノンダネ」「ミルクモウイラナイ?」
大人なら、物理的につながってしまっている音の流れであっても、そのなかに知っている単語をすぐに見つけることができます。
でもこれが赤ちゃんになると、私たちと違って、まだ単語の知識もありません。
音のつながり方のルールを見つける
考えてみれば当たり前なのですが、“ミルク”という単語は、いつも同じ形をしています。
つまり、/ミ/という音のあとには必ず/ル/が続き、そのあとは必ず/ク/です。
しかし、単語の外側では、音のつながり方はそのときによって様々です。
/ミ/の前は、何もないこともあれば、/イ/のこともあり、また/ク/のあとは、/ガ/が来ていることもあれば、/ノ/が来ていることもある、という具合です。
このように、単語はいつも同じ音の形をしていなければなりません。
つまり、単語の内側で音と音のつながる確率は100%となります。
一方、単語と単語の境界に目を向ければ、音の繋がる確率は100%よりずっと低くなるはずで、
こうしたおとのつながりかたを手がかりにすれば、切れ目のない音の流れのなかからでも、単語を見つけ出すことはできるはずです。
赤ちゃんの単語発見を知る研究
まず、8ヶ月の赤ちゃんに、人工的に無意味語をつなげて作った次のような音の流れを聞いてもらいます。
「ツピロゴラブビダクパゴチゴラブパゴチビダクツピロビダクゴラブツピロ」
実はこの流れのなかに、100%の確率で繋がった音のかたまり、つまり単語がいくつか入ってます。
これを1分あたり270文字のスピードで、何の抑揚もない一本調子で読み上げられたものを2分間、赤ちゃんに聞いてもらいました。
そのあとのテストでは、先ほどの音の流れのなかに出てきた“単語”(たとえば/ビダク/)を聞かされたときと、出てこなかった単語(非単語、たとえば/ラピパ/)が聞かされたときで、赤ちゃんが異なる反応を示すかが調べられました。
具体的な反応としては、どちらか一方ばかりを聞きたがる、ということがあるかどうかを見るために、赤ちゃんが音のする方をじっと見つめていた時間(聴取時間)を測定しました。
(もともと人間には、音がすると音源の方を見るという性質がある。)
こうして調べてみると、赤ちゃんは単語より、非単語の方を明らかに長く聞くことがわかりました。
赤ちゃんにとっては、単語より非単語の方が新鮮に感じられたということです。
もう少し赤ちゃんの気持ちに寄り添った言い方をするなら、2分間にわたって聞かされた音の流れのなかから単語を見つけ出すことに成功し、その単語にはもう飽き飽きしていたので、それとは違う“新しい”非単語を聞かされて思わず注目した、という結果です。
しかし、その後の研究で、生後8ヶ月くらいの赤ちゃんでは、同じ単語が、別の人の声で言われたり、別の感情で話されたりすると、同じ単語だと分からなくてなってしまうことが分かりました。
ミルクは/ミ/のあとに/ル/がきて/ク/がくる、
というのは当たり前すぎて気付きませんでしたが、
そこに気付いて研究することに、感動しました。
赤ちゃんは必要でないと学ばない
第二言語のオーディオを聴かせた時と
第二言語を話す人に話しかけられた時とでは
後者が言語獲得に貢献していたことを知り、
赤ちゃんも大人も、リアルなコミュニケーションがあってこその言語なんだなあ、と感じました。
赤ちゃんは例え私たちにその成長が見えなくても、毎日学んで成長している
赤ちゃんが言葉を発するまでも、たくさん聴いて発見して、私たちが成長を発見するまでの間に日々小さくて大きな一歩を歩んでいることを知りました。
この本を読んで
私たちが認識していることが全てじゃない。
赤ちゃんの成長を共に喜ぶために、どんな成長を辿るのかもっと多く知りたい。(知れて良かった。)
と思いました。
(こちらでピックアップしたことは本の内容のほんの一部なので、ぜひ手に取って読んでみてください。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
