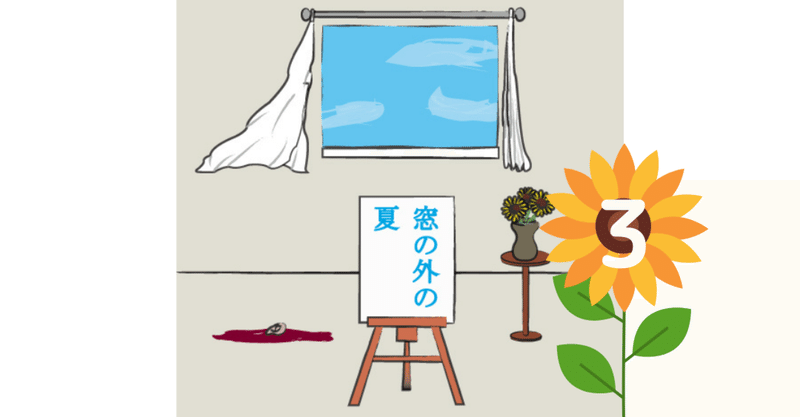
窓の外の夏(3)
フィンセントは病室で目を覚ました。すでに、パリからテオも到着し、わたしたちは代わる代わるフィンセントを看ていた。
「左耳はどこだ」
目覚めたフィンセントは、開口一番そう言った。わたしとテオは顔を見合わせた。ぞわりと寒気がした。自らの左耳の所在をたずねるというのは、奇妙なことこの上ない。
「切り落としたわたしの左耳はどこだ、ポール。あれをウージェニーに送るんだ、そう言っただろう」
覚えていたのか。あの言葉は一時の衝動で、目覚めればすっかり忘れているだろうと根拠もなく考えていた。まるで一文無しになったかのような絶望感が、わたしの全身を満たす。
わたしは観念して、ポケットから小包を取り出した。それをフィンセントに渡す。フィンセントは体を起こし、大事そうに包みを受け取ると、今度はテオに顔を向けた。
「わたしはいつここから出られるんだ」
「医者はそうかからないと」
テオが真面目な口調で答える。テオは嘘がつけない性格だ。フィンセントはうなずいた。
「戻ったらすぐに、ウージェニーに手紙を出す」
まもなく退院すると、フィンセントは宣言通り、ウージェニーに自らの左耳を送った。ウージェニーはさぞ驚き、気味悪がることだろうと思ったが、わたしは彼を思いとどまらせようとはしなかった。フィンセントのことも、ウージェニーのことも、言ってしまえばどうでもいい。わたしは、絵を描くためにここに来た。絵に関係のないことに、わざわざ首を突っ込む理由はない。
フィンセントと言葉を交わすことがいっそう少なくなった。触らぬ神に祟りなし、だ。退院してからというもの、フィンセントは以前にも増して、付き合いにくい男になっていた。会話が成立しない。絵を描くこともなく、時折獣じみた奇声を発しては暴れている。彼の左耳は、彼のなけなしの「正常」を司っていたのかもしれない。フィンセントの世界は彼一人で十分成り立っているようで、他人がそこに参加する余地はなさそうだった。
わたしはというと、ひたすら絵を描いていた。同居人の気が触れようがどうしようが、わたしにできることはそれしかない。わたしの世界は至ってシンプルに構成されている。一方、フィンセントの世界は、あまりに人間的な要素が複雑に絡み合っている。二人が分かり合えるわけもない。互いに、この家には自分しか暮らしていないのだという素振りで、一ヶ月近くを過ごした。我慢の日々だった。
フィンセントが発作を起こしたのは、二月の初めのことだった。わたしは、自分の画材をできるだけ隅のほうに移動させ、部屋を破壊するフィンセントをぼんやりと眺めていた。テオに手紙を書く。
彼を病院に送り届けたら、ここから去ろう、と考えていた。ここにわたしが求めているものはない。タヒチへ渡ろう、と計画もしていた。あの楽園なら、きっとわたしを満たしてくれるに違いない。
フィンセントが、しばらく精神病院で過ごすことが決まったのち、わたしは荷物をまとめ、アルルの「黄色い家」を後にした。フィンセントと寝食を共にした期間は、半年にも満たなかった。濃い時間だった。確かに気の休まることはなかったが、それまでのわたしには考えもつかなかったことを知れた気もする。その思いは、ここタヒチでさらに強くなった。
ここには、誰もいなかった。経済的に支えてくれる友人も、わたしの絵を酷評する失礼な素人も、誰もいなかった。同棲していた女性にも、すぐに逃げられた。
「黄色い家」で、わたしはフィンセントに、「自分のために絵を描いている」と言い切った。その考えに変わりはない。ただ、「自分のために」絵を描くには、「誰か」の存在が必要なのだ。「誰か」の支えがあって、初めてわたしは「自分のために」絵を描ける。そのことに、わたしは、タヒチに来て気づいた。あのフィンセントですらいるべき存在だったのだと、今になって感じる。わたしは、画家としての自分を他人に受け入れてもらいたいとは思わない。だが、傍にいてもらいたい、と強く思う。ただ、そこにいてもらいたい。
ふと目を上げれば、窓の外は夏だった。
わたしは、数年ぶりに向日葵を描いた。生前のフィンセントが必死になって描いていた、向日葵を描いた。後悔をたっぷりと混ぜた絵具で、キャンバスを染めた。フィンセントはわたしに何を訴えかけていたのだろう。わたしはその声に少しでも耳を傾けようとしただろうか。その心に、寄り添おうとしただろうか。
わたしは、泣いていた。
絵筆を持った右手が、どうしても動かない。
いただいたサポートは、なんでもかんでもに使います。使途はnoteで公開します!
