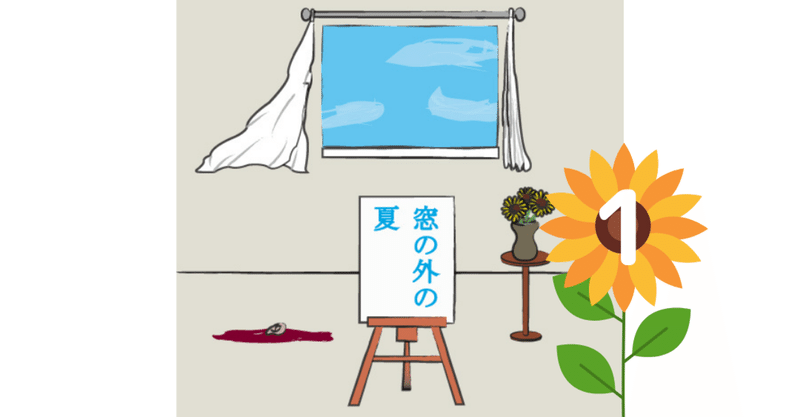
窓の外の夏(1)
わたしがフィンセントと共同生活を始めて二ヶ月近くになる。南仏の太陽が相変わらず暖かく優しくアルルの町を照らしている。そんな太陽の満ち足りた輝きのもとで、わたしたちはこの二ヶ月、小さな「黄色い家」で、ひたすら互いをののしり合い、貧乏を嘆き、そして絵を描いた。
「ポール、君は、何のために絵を描いているんだい?」
ある朝、わたしが壁に向かってキャンバスを置き、ある女の絵の制作をしていると、唐突にフィンセントがそう言った。彼のほうは南向きの窓に向かって、ひまわりを挿した花瓶を置き、制作をしていた。フィンセントが、ちらりとわたしのキャンバスを盗み見る。
「目の前に居もしない女性を、そんな暗がりで、誰にも見えないような場所で描いて、楽しいかい? 君は何のために絵を描いているんだい?」
わたしは絵筆を止めない。下らない質問だ。
「楽しいさ。わたしは、わたし自身のために絵を描いているんだ。誰に見せるのでもない。わたしにしてみれば、そんな騒々しい場所で描く君の神経が知れないね」
フィンセントは、わざとらしく溜息をついた。
「そう言うが、実際にわたしたちの作品を買うのは他人じゃないか。そんな心持ちじゃ、売れるものも売れないだろう。かわいそうに」
「あいにく、売れないことには慣れているんでね」
自嘲しているわけではない。本心だった。
「わたしも同じだ。売れないことには慣れている。慣れきっている。しかし、認められないというのは、いくぶん寂しいものがありはしないかい? わたしが何ヶ月もかけて仕上げた一枚は、誰からも求められていない。だとしたら一体、わたしは何のために描いているのだろう、なんて考えてしまうよ」
「自分のためだ」
それ以外に、何があるというのだろう。馬鹿げている。
「君はどこまでもタフだね。羨ましいよ」
フィンセントが鼻を鳴らした。それで会話は途切れる。いつもそうだ。
わたしに言わせれば、そうやっていつまでも売れることにこだわり続けられるフィンセントのほうが、ずっとタフだ。
フィンセントは変わり者だ。わたしとは合わない。それが、二ヶ月間彼と一つ屋根の下で過ごしてみて、たどり着いた結論だった。彼は、絵画というものは、他人に何らかの感情をもたらすために描くものだと考えているらしい。一枚完成させるごとに買い手があるかどうかを気にして、1人で精神を乱している。絵は、単に自分の心を慰めるためのものであるというのに。
「この間、隣町の婦人に贈った絵が、彼女の家にある鶏小屋の穴をふさぐのに使われていたんだ」
フィンセントが、再び話し出した。わたしは、煩わしいと思いつつ、よかったじゃないか、と相槌を打った。
「よかった、だって!」
いきなりの大声に、わたしは絵筆を取り落としそうになる。もう少し静かにやれないのか、と怒る場面だと思ったが、結局そうはしなかった。無駄だ。テオによると、フィンセントは、幼い頃から激しい気性の持ち主だったらしい。つまり、家族が数十年の時間をかけてすら、その性格を改善できなかったのだ。今さら赤の他人であるわたしがたしなめたところで、何の効果も期待できないだろう。
「よくないさ。いいのもか。わたしはあの絵を、どこかの家の穴に蓋をするために描いたのではない。そうだろう? その役割を果たすべきは、わたしの絵ではない」
わたしには理解できない感情だった。
「その婦人は、君の絵を買ってくれたんだろう。その絵を欲しいと思ったわけだ。幸せなことじゃないか」
「ああ、婦人はわたしの絵を求めてくれた。鶏小屋の穴のためにね! まったく、笑える話だよ」
「分からないよ。一体、何が気に食わないんだい?」
フィンセントは、少しの間考えるように唇を噛み、それから静かに口を開いた。
「この家に移る少し前から、ずっと、向日葵を描いているんだ。嫌いな人間なんてきっといない、皆に愛される向日葵をね。絵は、わたしという人間そのものだ。ひまわりを描けば、わたしという人間ももっと受け入れてもらえるかもしれない」
好きにすればいいさ、とわたしは返した。彼の言うことは理解できたが、共感はできなかった。
「君も描かないかい」
フィンセントが明るい声を出した。わたしは首を横に振る。
「向日葵ならもう描いた。二つね。わたしにはそれで十分だ」
そうか、と疲れたようにフィンセントが呟いた。自分の言葉に賛同してもらえないのはいつものことだ。そんな、諦めにも似た呟きだった。
「でも」
そんなフィンセントを見ていると、居たたまれない気持ちになった。
「例えば、向日葵を描く君の姿をわたしが描く、というのはどうだい? 向日葵はもう十分に描いたが、向日葵を描く画家の絵は経験がない」
フィンセントは、わたしの真意を確かめるように眉をひそめた。それから、その言葉が一時の気の迷いなどではないと分かると、叫ぶように声を上げた。
「わたしの絵なんか描いたって、それを誰が必要とするんだい? こんな気狂いじみた画家の制作風景なんて、誰の興味もひかないだろうに」
わたしはそこで初めて、絵筆を止めた。自称「気狂いじみた画家」を振り返り、彼に言い聞かせるように言葉を発する。
「わたしは、わたしのために描いているんだ。誰の興味をひくためでもない。わたしが描きたいと思ったものを描く。それだけだ」
つかの間に沈黙ののち、フィンセントが肩をすくめた。そのまま自らのキャンバスに向き直る。どうやら、理解することは断念したらしい。
それでいい、とわたしは思った。理解する必要はない。フィンセントがわたしを理解したとき、それはもはやフィンセントではない。批判し、蔑み、背を向ける。それが、わたしたちの正しい関係性なのだ。
いただいたサポートは、なんでもかんでもに使います。使途はnoteで公開します!
