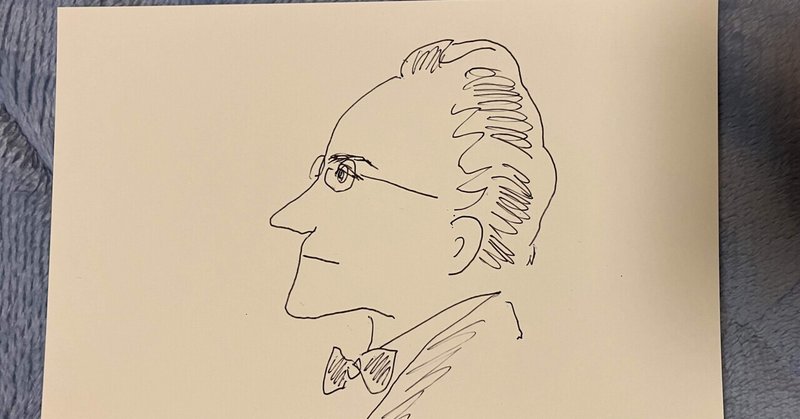
【人物伝】グスタフ・マーラーの素顔[2]〜シェーンベルクとの関係性〜
グスタフ・マーラーはアルノルト・シェーンベルク(1874-1951)と意外にも深い関係を持っていたことはあまり知られていない。
このことを確認するには、石倉小三郎著『音楽文庫 グスターフ・マーラー』(音楽之友社 昭和27年出版 絶版)を参照すると、次のような記述が見られる。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
彼を死の床において苦しめたものに、今一つ別の問題があった。
それは誰が自分なき後シェーンベルクを援(たす)けるだろうかということであった。
当代の若い音楽家ーー彼はマーラーより14歳若かったーーのどんな貧困、どの様な嘲笑にも屈しなかったその意地の強さ、自分が正しいと思ったものに勇敢に邁進する自信の確実さに対して正直なる尊敬をもった。
彼はできる限りの事をしていつもシェーンベルクを援(たす)けた。
その作品の演奏に当たってはわが身の危険を恐れず挺身した。
彼は人間として彼を愛していたのであった。
彼は彼と雑談し、論争することを好んだ。
このいとも不思議な、才気溢れた、魔力をかけられていたような二人が熱心に論争するところには格別の異彩が放たれてあったと云われている。
マーラーはいつも彼の賞讃者の先頭に立った。
全力を盡(つく)してその解釈説明に当たり、出版社等とも熱心に交渉した。
マーラーがシェーンベルクの作品に対して理解をもったのはその初期の作に対してであって、彼の後半期の作の、すべて以前のものを否定する様な音の夢の姿に対しては真の理解をもち得なかったのであるから、その時に至っても、否、死の床に於いてさえ、シェーンベルクの前途を彼が心配していたということは、彼の美しい厚い友情を立証する外の何者でもない。
後期の作に対しては理解をもち得なかったばかりでなく、あの音色の旋律の議論に対しては、彼の音楽家としての想像力は、身の毛がよだつほどな恐ろしさを感じた。
あの警句的簡潔・無音階(アトナリテイト)・リズムなしの印象的技法にはさすがの万能指揮者、どんなむつかしい総譜にも驚いたことのないマーラーが茫然としてたじろいたのであった。
それを目を通して理解すること、読むこと、云いかえれば光の像から音の像を想像することは出来ないとして流石の彼も断念した。
(〜中略〜)
「若し未来の音楽がこの様なものでなければならないのなら、何の為に私は交響曲を書こうぞ」とまで彼は云っている。
若しシェーンベルクの人物とその芸術家らしさに満腔の傾倒をもっていなかったなら、若し、彼が、この若い音楽家が、やり方によっては容易に名声も金をも得られようものを、自分の芸術的信念のために受難の途を敢てふみ行き好んで困苦と誤解の苦難をしょって行った事に対して驚異の念をもたなかったなら、シェーンベルクの作品など激しい罵詈を以て片づけてしまったであろう。
マーラーはこの人の作に対して断定的な事を云うのをさけていた。
否、彼はこの人の作を理解し得ないに拘らず、その正直な烈しい格闘ぶりに対しては最大の尊敬を払うに吝(やぶさ)かならずと、断然明白に宣言している。
(〜中略〜)
その頃シェーンベルクのものを所演すると何か事が起るのを常とした程であったから、マーラーが彼の作を指揮し、その解釈に当って賞讃を表明することは、自分の為には大に不利益であったに拘らず、彼は敢然としてこれに立ち向かったのであった。シェーンベルクの為に盡(つく)すことは、彼にとって真に心からの喜びであったらしい。
ある時マーラーが自作の第六と合せてシェーンベルクのニ短調四重奏を指揮した。
そのあとでマーラーがそれに対して賞讃の意を熱心に表明したとき、ある一人の青年がわざとらしく誇示的にシッシッと音を立てて妨害した。
マーラーは怒って「わしがほめているのに何で君はそんな事をするのか」と云った。
「わたしはあなたの穢(けが)らわしいシンフォニーを妨害したのですよ」
「それは君の顔に書いてあるさ」
もし止める人がいなかったら腕力沙汰にまでなり兼ねないほどの形勢であったという。
マーラーはその時既に帝室歌劇場の支配者として飛ぶ鳥を落とす程の威望を担っていたに拘らず、この様な事が起こったと伝えられている。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
なぜ、そこまでシェーンベルクを寵愛したのかは、本書に結論づけていることはない。
[1](前投稿)における彼の性格、また上記本文からも推測できることだが、二面性の性格による、周囲との衝突も少なくなかったマーラーにとって、偶像崇拝的な人間像の存在が作られていたと見ることができる。
そして、矢おもてに立たされたのがシェーンベルクなのであった。
シェーンベルクの後期の作品には理解を示すことはなかったというが、作品の全体的傾向は置いておくとしても、親心のような友情を注ぎ込む対象はシェーンベルクの人間性によるものであったことは誤りではないようである。
(上述の同著の表現は一部旧字等にふりがなを付して記述しています。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
