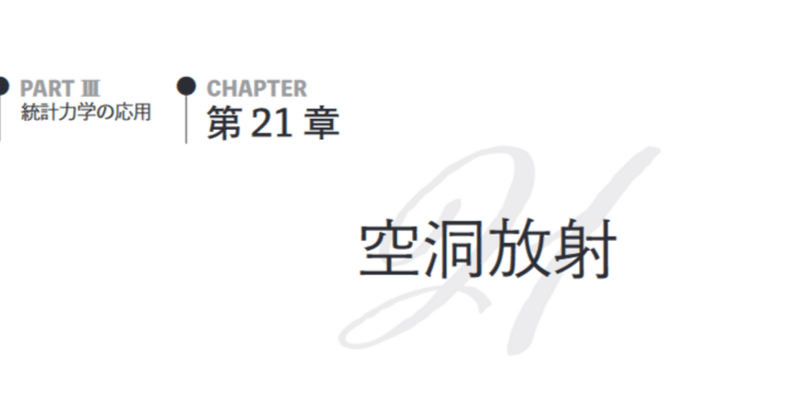
熱力学・統計力学 第21章問題解説
「熱力学・統計力学 熱をめぐる諸相」第21章章末問題の解説。解答例はこちらを参照。
第21章は電磁場、光子気体の統計力学である。20章と同様に、統計力学では必須のテーマである。ただ、統計力学の範疇に収まるものでもないため、書く方としては非常に扱いに困る問題である。
内容的には、三つのポイントがある。
(1) 電磁場のエネルギー密度を扱うこと
通常の熱力学系では熱容量を測定することによって系のエネルギーを捉えているが、電磁場の場合は、放射測定があるため、エネルギーを直接的に扱っている。
(2) Maxwell方程式を用いたエネルギー密度の変形
Maxwell方程式を用いた式変形は、電磁気学でも扱っている計算である。ただし、電磁気学ではエネルギー密度の式を導出することはあっても、それをさらに変形して調和振動子型の表現にまでもっていくことは行わないだろう(わざわざする意味がない)。その点はここであらためて理解してもらいたい。ベクトルがたくさんあるなどして計算はけっこうややこしいが、決して難しいものではないだろう。
(3) 電磁場の量子化によるPlanck分布の導出
もっとも重要なポイントである。電磁場の量子化はやや唐突でとまどうかもしれない。この問題は26章でも議論するので、そこまでいってから考えてもらいたい。多くの統計力学の教科書でそうなっているように、場の量子化の問題はここではあまり深入りしすぎない方がよいと思われる。
分野の狭間にあるような問題、総合的な問題を議論することはとても難しいが、面白くもある。物理をやっている気がすごくする。各法則体系を理解することはあくまでも手段であって目的ではないのだが、深入りすればするほど目的化してしまう。実際のところ、本書の目的は熱力学・統計力学を習得することなので、そういう面があることは否めない。総合的な問題を考えるときは、理解できることとできないことを切り分けて考える必要がある。一部を理解できないからといって全部を投げ出すこともないだろう。まえがきにも書いたように、物理は多方面から並行して理解を深めていくのが望ましい。
[21-1] 誘導放出・自発放射と分布関数
Planck分布は、量子力学や統計力学が確立している現代では、電磁場の量子化など非自明な要素はあるが、比較的簡単な計算で得ることができる。
本文にも書いたように、Planckが1900年に初めてこの分布を得たのは類推による。[21-3]で議論するように、2種類の関数を内掃するものとして提案された。
ここで用いる方法はいずれのものとも異なる。3種類の過程のつりあい条件から分布関数の形が特定される。つりあい条件のみでは係数までは求まらないが、温度無限大で分布関数が無限大になることを課すと$${B_{12}=B_{21}}$$が導かれる。係数$${A}$$はWienの法則([21-3]参照)との整合性より得られる。
本文で行った計算とは異なる議論で得られるが、離散化された準位があることやBoltzmann因子を用いるなど、量子力学や統計力学の知識は必要となる。この計算はEinsteinによる。1916年のことである。ちなみにこの年は一般相対性理論を完成させた年でもある。分布関数に用いられている係数AやBはEinstein係数とよばれている。
Planck分布はBose統計との関係でさらに異なる視点から議論される。26章でも触れるが、そこで重要な役割を担ったのもまたEinsteinである。これは1924、1925年のことなのでまた後の出来事となる。
[21-2] ゲージ場と電磁場のエネルギー
本文の計算をフォローしてほしいので出題した。ほとんど同じような計算を行えば答えを得ることができる。本文(21.3)式のように電場を表すのは、一般性を失わないとはいえ、不自然に見える。この問題を解くと、aがベクトルポテンシャルを表すとわかる。
(a). 電磁気学でよく知られているように、電磁場はスカラー・ベクトルポテンシャルを用いて表すことができるが、スカラー・ベクトルポテンシャルは冗長(非物理的)な自由度をもつ。自由度の消去(ゲージ固定)の仕方はいろいろあるが、ここで用いるのは(21-2.3)、(21-2.4)式の放射ゲージ(radiation gauge)である。真空中で電荷・電流密度が0のときに用いることができる。スカラーポテンシャルが0でベクトルポテンシャルのみとなるので、扱いやすい。放射という名前の通り、まさに本章で扱うような状況を記述するのに便利なゲージである。
(b)(c). 基本的には本文と同じ計算である。こちらの方が効率よくできるかもしれない。
本文の(21.18)、(21.19)式の関数形を導くのはかなりややこしい。境界条件を用いて式を一つ一つ書きながら進めていけばできる計算ではあるが、あまりにも繫雑になるので詳しくは書かなかった(そのため、ここで導出してもらったり、問21.2で詳しく考えてもらったりしている。ちょっとしつこかったかもしれない)。
[21-3] エネルギー密度のふるまい
Planck分布は本文では図示しなかったので、ぜひ考えてもらいたい問題である。
(a). ポイントは、分布関数が$${\omega/T}$$の関数として表されること、その変数について極大値をもつことの二つである。そのような関数であれば何でもWienの変位則を満たしている。
Planck分布の極大値は解析的に求まらないため、極大値の存在を示すには少し工夫が必要となる。
(b). 関数を完全に特定しなくても議論できることはある。実際問題、Planck分布がPlanckによって提案された時点では、量子論が確立しておらず、Planck分布は類推に過ぎなかった。そのため、(a)や(b)の性質などを頼りにしてある程度関数形を限定していくことに意味があった。
研究をしていると、そういう考察が必要になることはよくある。限定された情報からありえる性質を特定していくことは非常に重要である。どんな問題、分野でも役に立つ。
(c). 高温ではBoltzmann因子が全て等しくなってくるので、状態密度が見えるようになる。一方、低温ではBoltzmann因子によって主要項が決まる。統計力学一般に言える性質である。(d)を扱うための準備ともなる。
(d). 低温でのふるまい(A21-3.15)式はWienの法則(放射則)とよばれている。Wienの変位則を満たしている。図に表すと、Planck分布はWienの法則とReyleigh-Jeansの法則を内挿しているとわかる。
付録の最後で述べたように、図をプロットするときのルールは両軸に用いる変数を無次元化することである。ただ、理論的にはそれでよいかもしれないが、両軸は温度に依存する変数となっているため、温度を変えたときのふるまいが読み取りにくいかもしれない。その場合は適当に変数を決めて、異なる温度でいくつかの曲線をプロットした方がよい。例えば以下のようである。

こうすると、温度を大きくするとピークの位置(横軸の値)およびuの大きさ(縦軸の値)がそれぞれ大きくなることがわかる。
グラフプロットのルールは付録やここで力説したが、具体的な値を用いる問題ではそれにしたがわない方がよいこともある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
