
私の自己考察をはじめる
文章の中には、意図の伝わらない自己完結的なものがいくつかある。
厳密に言えば、その書いた人の心のようすや感受性や日頃の視点はわかるが、それら筆者の内部が文章の中に置かれてはいるが、そこから「言葉(=Communicable form?)に変形せしめたもの(=言語化触媒)は一体何なのか」が読み取れないもののことだ。
買い物のメモや旅行記なら「記憶の保存」。手紙なら「コミュニケーションそのもの」。小説なら「物語の具現化」か? いずれにせよ意図を想像できる。
ここに書き散らしたものは支離滅裂で散文とも言いがたい。正直書いている自分でも意図がよく分からない。ただ少なくとも言えるのが、この行為によっていつもいつも自分が救われているような気がするということ。
今こうして綴っているのも、そのために過ぎない。
◼️ 「写真を撮る意味」を考える

手に触れられるアナログでリアルな世界と、コンピュータによるデジタルデータの世界とが当たり前に共存する前線を生きる今この時代。
年代とともにその前線に近づいた世代もいれば、生まれて間もなくからその世界線が当たり前の世代も現れている。
写真においても、アナログとデジタルは不断に混じり合う不連続線として隔世世代の間を周回する。誰もが美しく鮮明な写真を撮れて、誰もが昨今はやりのノスタルジーな写真を生み出せる。そんな時代、何(対象)を撮っても何(機材)で撮っても、写真は詰まるところ同じような一般解に至ってしまうのではないか。美しいか、ノスタルジックか、繊細か、荒っぽさか…。
本当に望んだ絵をつくるのであれば、もはや写真という手法を採る必要もない。BlenderやMidjourney、アップデートを経たPhotoshopなどデジタル一存の制作でイメージに限りなく近い絵を一瞬で生み出すこともできる。
この時に考えなければいけないのが、「なぜ撮るのか」。
つまり写真を撮ることの意味にある。
Intuition is a very important part of my brain, a sort of speak off. I have never really had concepts. It was always following intuition before I really thought.
DARKROOM RUMOR より
写真を考える時の一助として、ここに世紀の写真家ロバート・フランクの言葉を引用してみようと思う。彼の言葉から、コンセプトは直感に追随するものであり不言の意思である感性に重きが置かれていることがわかる。
写真は必ず人類の一瞬を捉えていなければならない。
これはリアリズムです。でもリアリズムだけでは不十分で、そこにはビジョンがあるべきです。この2つが合わさって、ようやく私の写真は完成するのです。
VOGUE JAPAN より
しかしVOGUEの引用から、かならずしも直感的感性のみで写真が完成するわけではないことが分かる。
ビジョン、つまりはその写真を通じた未来の世界またその構想が相備わっていなくてはならず、それなしでは写真は完成に至らない。ビジョンはある種、コンセプトの原形・萌芽ともいえ、写真作品の意を近似値で示す言語それ以前のカタチが、シャッターを押すまさにその瞬間から不言の形で組み込まれていることが分かる。
ロバート・フランクというあまりに偉大な写真家の考え方を取り上げたが、これは直感的感性とコンセプトの位置付けに関するいち意見に過ぎない。
しかし大前提として、「写真を撮ることの意味」に真摯に向き合った彼の結果として写真の根本に上述したような意志が置かれるに至っている。依然、写真を撮る意味は重視されるべきものなのだ。
彼の生きた1924年から2019年のおよそ1世紀に及ぶ時間、世界的注目を浴びるような写真を撮り続けた彼でさえ、その意味を確立し大切にしてきている。いくらこの数十年の間にデジタルの目まぐるしい発達が写真界に影響を及ぼそうと、一人の写真を撮る者として「撮る意味」を考えない理由はどこにもないのだった。
◼️ なぜ私は写真をつくるのか

なぜ写真を撮るのかを、なぜ考えなくてはならないのかを述べたところで、以後では私自身の写真に目を向けて「無意識に私が訴えかけていること」は何なのかを考えていきたい。
どちらかといえばシャッターを切る瞬間はいつも直観的ではあるも、ただそこに直線的な構造が見えなくてはならない。単なる単一の直線構造だけではなく、都市形と自然によって生み出される雑然とした荒々しさも相まった逆説的な単純さが見える。
セルフヌードポートレートの構図自体においても同様のかたちが見えるも、殊にこの主題においてはまた異なる意図がある。
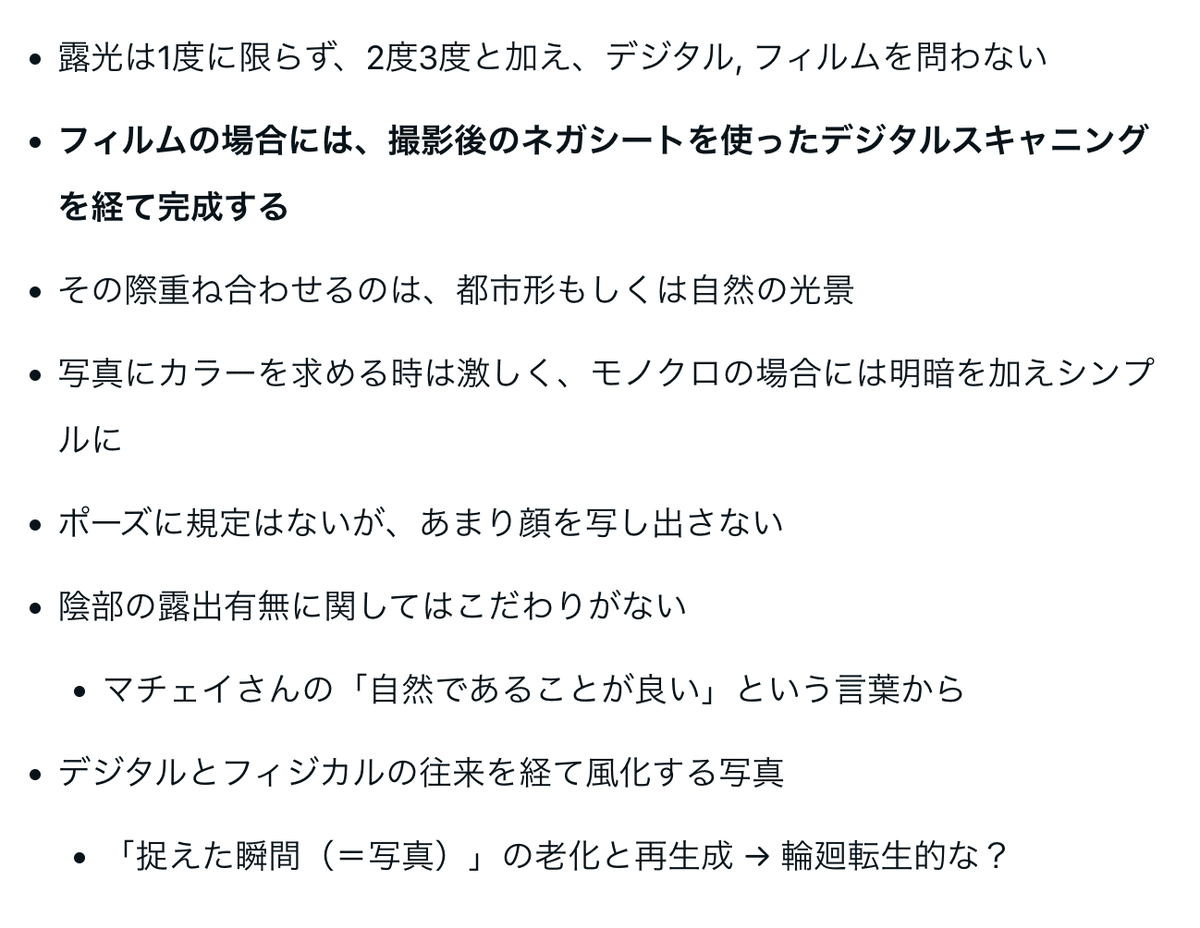
『第n人称のセルフポートレート』という題名での写真群からはじめた作品は、分人としてあらゆる場面に不特定の人称として立ち現れる個のありようが起点となっている。家庭・職場・友人という既存のコミュニティはデジタルソーシャル上にも重複され、またそのプラットフォームの数だけ累乗的に増加する。分人主義やドラマツルギーの考えの中では演じる役割が変動するだけで、全てが同一の個となる。「小説の登場人物がいかに多かろうと、また、それらのキャラクターがいかに違っていようと、それらはすべて作者の分身である」というフロイトの言葉がまさにそれだ。ユングのアニマ・アニムスも統合的自己を考えるあたり同様かもしれない。
紛れもないその事実を、纏うもの全てを取り去って一人一人の同一の個を重ね合わせる形で描写している。
直線的な描写は、正直さ・誠実さを保ち失ってはならないという意志かもしれないがしかし、さまざまに演じられる私という個の中では誠実さや優しさのみで切り抜けられる場面が全てではないことを知っている。
◼️ その思想と行動とはリンクしているか

とある広告写真家とメッセージのやり取りをする中で、最近気付かされたことがある。
端的にいえば、「撮影者と被写体とが歩み寄ること」だった。

君を撮ったやり方で、他のモデルを撮るようなことはしないからね。”
この間のヌード撮影では、完全にこれとは反対のことをしていた。
久方ぶりに、セルフヌードポートレートでなく他者のヌードポートレート撮影を行ったのだ。
確保できる時間が曖昧で、コンセプトも相談することもなくテストシュートのような感覚で撮っていたのも事実だが、そこに歩み寄る姿勢があったかどうかでいえば、わずかほども見られなかった。
”セルフポートレートを撮るのは、誰も本当の私の姿をその通りに見ていないから。”
”セルフポートレートを撮る人は大概がナルシスト。ただそれは肯定的でポジティブな意味合いでのナルシズムに基づく。”
過去にセルフポートレートに関する意見を集めていた時のメモを見返すとこうした言葉を記していたが、いずれからも読み取れるのは、自己を中心とした意志の表明であって、そこに他者が入り込む余地はわずかにもないということ。
セルフポートレートとはそういうもので、誰かに宛てるなど対話を前提としたものではない。いわば独白のようなものだと感じる。
そうであるからこそ、同じヌードであれ、対自 / 対他のヌードとには大きな違いがある。後者の場合。彼が言うようにダンスするかのようにお互いが歩み寄る必要があるのだ。
なぜヌードなのか / なぜ自分ばかり撮るのか / なぜ装飾品やプロップを用いないのか / なぜ画面いっぱいに映り込む構図が多いのか / どのような意図で多重露光写真を撮るのか / なぜ都市形や自然と自身の裸体を重ねるのか …
そして私が撮ったその時のヌードに関していえば、それは完膚なきまでに独りよがりのダンスだった。答えの出ていないこれらの問いには、もしかするとこのダンスを会得することで解が与えられるのかも知れない。
◼️ 自身のことをどれだけ知っているか

真の力の姿は、抵抗と没頭にある。
不断の攻撃に対し聞く耳を持たず語りもせず、獣のごとく相手の虚を狙うこともなく、一挙手、一投足すべてを律令に基づき遂行するもの。
大真面目な顔で冗談を言うこと。早く歩くこと。順序立ててものごとに懸ること。これら全てが逆説的に、自身の真の力の姿に帰属するのではないか。
歩き方や話し振りなど瑣末なことがらを取って見ても、それぞれ人の数だけ種類があることだろうが、それら全てには内在的・顕在的ないし無意識的・自覚的かはさておき何らかの所以があるはずだ。
私の場合には、早く歩くのには心身の健康と時間の節約が念頭にあるからだと思うし、順序立てて物事を行うのはなるべく避けられるミスを遠ざけておきたいからだ。反面、感覚的に行動に移ることも多々あるが、先行きの読めないどうしようもないケースに限る。
『夜間飛行』の中で記されていることは、瑣末なそうしたことがらをはじめ自身の取り組む仕事やプロジェクトなど全てに懸る姿勢として展開され得るだろう。これが写真というプロジェクト、仕事にあっても同様であり、「写真を撮る意味」を考えるにあたってその根本にあるといっても過言ではない。
今まさに「抵抗と没頭」が失われようとしていて、「真の力の姿」が霞がかっている。その霞を振り払いふたたび「抵抗と没頭」を手元に置くための一撃、それこそが自分を知ることだと思う。そこからは、決して逃げてはならない。続けなくてはならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
