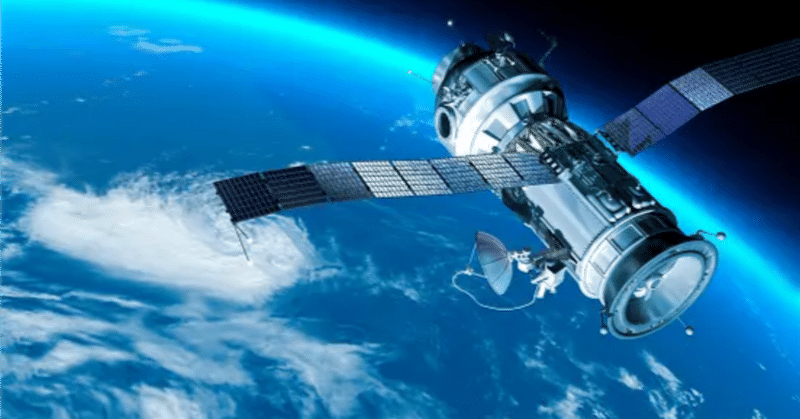
新たな領域のセキュリティ - 宇宙安全保障(前編)
はじめに
近年、政府が宇宙開発に関連してさまざまな動きを見せている。特に、防衛省は、スタートアップを含む民間企業との契約を次々と締結している。これは、政府が宇宙という分野を国防の重要な一領域と捉えていることの顕れだろう。
ところで、「宇宙安全保障」という言葉を聞いたことはあるだろうか。スター・ウォーズシリーズのようないわゆる「宇宙戦争」の世界を思い浮かべるだろうか。結論から述べると、実態はその世界とは少し違う。
そこで、誤解を解く目的も兼ねて、今回は宇宙安全保障をテーマとして取り上げ、そもそも現在宇宙という領域では何が起こっていて何が問題となっているのか、そして宇宙を取り巻く諸課題に対応すべく政府はどのようなことを行なっているのか、ということについて前編と後編に分けて解説していく。
前編となる本記事では、日本政府の宇宙領域に対する現状と課題の認識について解説する。
そもそも宇宙安全保障とは
政府は、この宇宙×安全保障という分野をどのように定義しているのだろうか。政府の意図を知るには、「宇宙安全保障構想」を参照するのが良いだろう。
「宇宙安全保障構想」とは、2023年6月13日、内閣府の宇宙開発戦略本部によって策定された政府文書である。
同文書内では、「宇宙安全保障上の目標」を以下のように定義している。
宇宙安全保障に求められることは、宇宙空間を通じた国家安全保障上の目標への貢献であり、宇宙安全保障の目標は「我が国が、宇宙空間を通じて国の平和と繁栄、国民の安全と安心を増進しつつ、同盟国・同志国等とともに、宇宙空間の安定的利用と宇宙空間への自由なアクセスを維持すること」である。
つまり、日本政府にとっての「宇宙安全保障」とは以下の要素によって構成されているのである:
宇宙空間の国防への活用
宇宙空間の安定的利用の維持
宇宙空間への自由なアクセスの確保
宇宙という領域を取り巻く現状と課題
では、なぜ「宇宙安全保障構想」を策定する必要があったのだろうか。その背景として、①宇宙空間をめぐる競争、②宇宙空間における脅威とリスクの拡大、③民間イノベーションの推進が取り上げられている。
(出典:内閣府「宇宙安全保障構想の概要(案)」)
①宇宙空間をめぐる競争
同文書は「今日、宇宙空間は、外交・防衛・経済・情報、そしてそれらを支える科学技術・イノベーション力といった国力をめぐる地政学的競争の主要な舞台となっている」と評価する。確かに、最近の戦争において、宇宙空間の軍事利用は不可欠な要素となっている。ウクライナ侵攻においてロシアが思惑通りに作戦を遂行できない理由の一つに、人工衛星がもたらす地上監視や通信がウクライナに軍事的優位を与えていることが指摘されているのは有名な話である。
②宇宙空間における脅威とリスクの拡大
同文書は、「宇宙空間における脅威は急速に拡大している」と指摘する。具体的には、「物理的に低軌道の衛星を破壊する直接上昇型衛星攻撃」や「サイバー攻撃などの非物理的な手段によって衛星機能を無力化する能力」などが挙げられている。実際、最近ロシアが核技術を用いた衛星破壊兵器の開発をしているとの報告が米国防総省から発表されたのは記憶に新しい。
また、「宇宙空間においては、各種のリスクも拡大している」とも指摘されている。2011年米国国防総省発表のNational Security Space Strategy(国家宇宙安全保戦略)が記した「space is becoming increasingly congested … competitive(宇宙空間はますます混雑し、競合している)」という一節は、現在の宇宙空間の状況を象徴している。特にスペースデブリ及び衛星を含めた宇宙物体数が急増している。JAXAによる推計では、2021年時点で少なくとも12000個以上の物体が地球の周りを周回しており、また、少なくとも50万個のスペースデブリが軌道上を漂っているとされている。
(出典:JAXAホームページ)
これにより、宇宙物体同士の衝突リスクが増大しているのである。
③民間イノベーションの進展
同文書は「今日、民間部門における宇宙技術の革新が急速に進んでいる」と述べている。以下の映像を観た事はあるだろうか。
https://www.youtube.com/watch?v=z_1VyyiOw1s
これは、イリジウム通信衛星(Iridium-NEXT)を搭載したスペースX社の再利用可能ロケット「ファルコン9」の、ヴァンデンバーグ空軍基地からの打ち上げと太平洋上の無人船への第1段目ロケットの着陸を記録したものだ。従来のロケットは一度打ち上げられると回収される事はなく、いわゆる「使い捨て」の状態だった。しかし、現在のスペースX社の持つ技術を用いると、ロケットを「再利用」することができる。これによって打ち上げコストが驚異的に削減されているのである。あくまで一例に過ぎないが、このことからも、宇宙開発はもはや国家の専売特許ではないどころか、民間部門が技術革新の担い手となっている事が想像できるだろう。
その上で、政府は、「政府の宇宙安全保障上のニーズを民間部門に明確に示すことにより、民間投資が促進され、開発ペースの迅速化や製造コストの低廉化などを通じ、産業基盤・産業競争力が強化され、それが宇宙安全保障の一層の強化の実現に資することが期待される」と述べている。つまり、政府がますます勢いを増す民間部門をサポートないし活用することが求められているのである。
おわりに
政府は宇宙という領域の現状に関して、
・宇宙空間や技術は地政学的競争を構成する要素となっている:
・宇宙空間はますます「混雑・競合」しており、それに伴う宇宙物体同士の衝突リスクが高まっている:
・宇宙開発の担い手はすでに民間部門にシフトしており、政府はそれをサポートないし活用していくことが求められている
との認識を抱いていることがわかった。
次回の記事ではこうした課題意識や現状認識を踏まえ、実際に政府はどのような戦略的アプローチや施策をとっているのかということについて解説していく。
参考資料
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
