
Reviews(Broadway DNA Blog/2024)
What We're Seeing: Kaimaku Pennant Race’s "HAMLET | TOILET" at UTR
Centering on an act of fecal filial piety, Murai’s creation invites a whimsical wiping of the story you thought you knew.
NATALIE RINE
2024/01/19
After an excruciating period of outcry and (thankfully) premature grief over the almost-cancellation following a severance by long-time host The Public Theater, New York’s preeminent forum for international and experimental theater has returned loud and proud.
The Under the Radar Festival, which has always mingled international artists with local ones in pursuit of what the festival’s founder, Mark Russell, refers to as “the global downtown,” has uniquely felt the pressure of the rising costs of cultural exchange, an unfortunate economic reality in an increasingly isolationist geo-political environment worldwide.
Despite these challenges, the show must go on, encouraging New Yorkers to look beyond the American myopia of our artistic-exportation soft power privilege and engage with welcoming artists of global renown in their own languages, on their own terms, in their own shows– like Japanese theater company Kaimaku Pennant Race’s HAMLET | TOILET.
Led by playwright-director auteur Yu Murai, KPR’s genre-bending view has been described as "hyper-nonsensical absurdist philosophical comedy," kneading highly stylized Japanese cultural references into kaleidoscopic, tableau takes on Western masterpieces. The company has made previous NYC appearances with their groundbreaking Romeo & Toilet and 2019’s boxing ring manga-meets-Macbeth Ashita no Ma-Joe: Rocky Macbeth. In a similar dramaturgical vein, HAMLET | TOILET riffs on Shakesepare’s tragedy with a quintessential Japanese idiosyncrasy: the “greatest toilet culture in the world.”
Number two or not number two? That is the question asked in this zany production, posed in a very catchy rap after quite possibly the most iconic opening scene of the Festival: personifying a toilet. The cast of three, adorned in KPR’s signature white bodysuits (purposefully sperm-like, to mimic the familial problematics of almost any Shakespearean protagonist they take on adapting at this point), are arranged to embody a toilet seat, handle, and sitter, taking turns spouting and sputtering “to be or not to be” as if in the throes of anal agony. Their clipped, a capella refrain picks up speed moving from staccato to forceful bellows all punctuated by flatulence, resulting in a universally side-splitting humor as an icebreaker into the world of Murai’s play.
Thus establishing everybody poops as a great equalizer, the play moves to introduce us to the Hamlet-adjacent character, cursed in this iteration to possess the iconic, torturous psychic blockage as newly iconic, torturous bowel blockage. Centering on an act of fecal filial piety, Murai’s version of Hamlet (played with humorous, earnest gusto by Takuro Takasaki) undergoes an anime-adjacent power-up to receive the spirit of his father inside his bowels, accepting his belly pain as his own father’s suffering. Until his father’s business on earth is finished, Hamlet’s “business” won’t be finished either…. It’s almost infuriating how ingenious it all is.
Takasaki is joined by G.K. Masayuki (Ophelia, Claudius, Horatio) and Yuki Matsuo (Patient, Laertes, Marcellus), creating a tornado of frenetic energy to bring the zany premise to life. Rather than a didactic scene-by-scene copy-paste, Murai instead cherry-picks plot-essential scenes to magnify and turn topsy-turvy in a brisk ninety minutes, dialing the energy and circumstances up to a hundred.
Engaging with such a whimsical reworking requires at least some base knowledge of the source material (much to the confusion of the chitchatters sitting behind me). Exemplary highlights of Murai’s convincing concept include Ophelia being flushed down the toilet, a PVC pipe confessional, Hamlet calling out for his mommy to wipe him, and later ending the play defecating in a slain Claudius’ mouth (now that’s king shit). Signature to the play’s absurdist style is Murai’s use of precise, looped repetition, utilizing the comedy rule of threes to run a scene over and over in the same way one ruminates on the same thoughts over and over– especially when sitting alone with one’s bare thoughts on the toilet.
The stage itself is relatively bare, consisting of a suggestive three-stalled frame designed with artistic and economic flexibility in mind. Flanking the stage are monitors for English supertitles, allowing the non-Japanese speaking audience to see a semblance of Murai’s signature copious word play, infusing the Elizabethan essence with modern Japanese nods. With so much repetition involved in playing the same scene over and over again, the eye scansion between action and translation flows minimally once you catch on to the gimmick, creating a seamless, unintrusive bilingual experience.
Besides being an excellent economical choice for international touring due to the small cast and design size, the play was pointed out by the audience Q&A as also being prime for students to engage with, no doubt because of the accessibility of potty humor encouraging a fresh entrypoint to the Bard’s masterpiece. While UTR doesn’t particularly cater to a student demographic, I would be keen to see further international touring of KPR’s work add student and youth performances.
KPR’s HAMLET | TOILET may be centered on man’s most private place, where one is alone with one’s thoughts and pure being, but the experience of the performance brings the audience together in a shared evening of laughter and unmistakably, unapologetically human matter/s. From the sing-song wordplay of the title to the topsy-turvy scenework of the actors, Murai’s creation invites a whimsical wiping of the story you thought you knew.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私たちが見ているもの:UTRでの開幕ペナントレース「HAMLET | TOILET」
うんこ孝行という行為を中心に据えた村井の創作は、あなたが知っていると思っていた物語を気まぐれに拭い去ることを誘う。
ナタリー・ライン
2024/01/19
長年の主催者であったパブリック・シアターが撤退し、中止寸前まで追い込まれたことに対する反発と(ありがたいことに)早すぎる悲しみの耐え難い期間を経て、国際的かつ実験的な演劇のためのニューヨーク屈指のフォーラムが堂々と帰ってきた。
アンダー・ザ・レーダー・フェスティバルは、創設者のマーク・ラッセルが言うところの「グローバル・ダウンタウン」を追求するために、常に国際的なアーティストと地元のアーティストを混ぜてきた。
このような困難にもかかわらず、ショーは続けられなければならない。ニューヨーカーに、芸術輸出のソフトパワーの特権というアメリカの近視眼を越えて、世界的に有名なアーティストを迎え入れることを奨励し、彼らの言語、彼らの条件、彼らのショー-日本の劇団開幕ペナントレースの『HAMLET|TOILET』のように-に参加することを促すのだ。
劇作家・演出家の村井雄が率いるKPRのジャンルを超えた視点は、「超ノンサンクスな不条理哲学コメディ」と評され、高度に様式化された日本文化の引用を万華鏡のように練り上げ、西洋の名作をタブロー化する。このカンパニーは、画期的な『ROMEO and TOILET』や、2019年に上演されたボクシング・リング漫画とマクベスをミックスさせた『Ashita no Ma-Joe: Rocky Macbeth』でニューヨークの舞台に立ったことがある。同じような演劇の流れで、『HAMLET|TOILET』はシェイクスピアの悲劇を、「世界一のトイレ文化」という日本の典型的な特殊性でリフする。
ナンバー2か、ナンバー2ではないか?という問いかけが、この奇妙な作品に投げかけられる。この作品は、演劇祭で最も象徴的なオープニング・シーンである「トイレの擬人化」の後、非常にキャッチーなラップで表現される。3人のキャストは、KPRの特徴である白いボディスーツ(この時点で彼らが翻案するシェイクスピアの主人公のほとんどが抱える家族間の問題を模倣するため、わざと精子のようなものを着ている)に身を包み、便座、取っ手、座る人を具現化するように配置され、肛門の苦しみのどさくさにまぎれて「なるようになるか、ならないようになるか」を交互に口走ったり吐いたりする。彼らの切れ切れのアカペラのリフレインは、スタッカートから力強い咆哮へとスピードを増し、そのすべてが便の音によって中断される。
こうして、誰もがうんちをすることが偉大なイコライザーであることを確立すると、劇はハムレットに隣接する人物の紹介に移る。この人物は、象徴的で拷問のような精神的閉塞感を、新たに象徴的で拷問のような腸閉塞感として持つように呪われている。村井版ハムレット(高崎拓郎がユーモラスかつ真面目に演じる)は、糞尿による親孝行行為を中心に、アニメにちなんだパワーアップを遂げ、父親の霊を腸の中に受け入れ、自分の腹痛を実の父親の苦しみとして受け入れる。父の地上での仕事が終わらない限り、ハムレットの「仕事」も終わらない......。その巧妙さには腹が立つほどだ。
高崎のほか、G.K.Masayuki(オフィーリア、クローディアス、ホレイショー)、松尾裕樹(患者、レアティーズ、マーセラス)が加わり、熱狂的なエネルギーの竜巻を巻き起こして、奇想天外な前提に命を吹き込んでいる。村井は、教訓的なシーンごとのコピーペーストではなく、筋書きに不可欠なシーンを厳選し、エネルギーと状況を100倍に増幅させながら、90分という短い時間の中で大きくひっくり返した。
このような気まぐれな再創造に取り組むには、少なくとも原作についての基本的な知識が必要だ(私の後ろに座っていたおしゃべり好きは大いに困惑していた)。オフィーリアがトイレに流されたり、塩ビパイプの懺悔室が登場したり、ハムレットがママに体を拭いてもらうよう呼びかけたり、劇の最後には殺されたクローディアスの口の中で脱糞したり(これぞキング・ウンコだ)。この芝居の不条理なスタイルに特徴的なのは、村井の正確でループした繰り返しの使い方だ。人が何度も何度も同じ考えを反芻するのと同じように、喜劇の法則である「3」の法則を利用して、シーンを何度も何度も繰り返す。
舞台そのものは比較的素っ気なく、芸術的かつ経済的な柔軟性を念頭にデザインされた、示唆的な3本の柱で構成されている。舞台の両脇には英語字幕用のモニターがあり、日本語を話さない観客にも、村井の特徴である大量の言葉遊びの一端を見せることができる。同じシーンを何度も繰り返し上演することで、アクションと訳詞の間の視線移動が最小限に抑えられ、このギミックを理解すれば、シームレスで邪魔にならないバイリンガル体験ができる。
少人数のキャストとデザインにより、国際ツアーに最適な経済的な選択であることに加え、観客のQ&Aでは、この作品は学生にとっても取り組みやすい作品であることが指摘された。UTRは特に学生層をターゲットにしているわけではないが、KPRの作品の国際ツアーに学生や青少年向けの公演が加わることを切望したい。
KPRの『HAMLET|TOILET』は、人間の最も私的な場所、つまり自分の考えや純粋な存在と一人きりになる場所が舞台の中心かもしれないが、公演の体験は、観客を笑いと紛れもなく人間的な問題の共有の夕べに巻き込む。タイトルの歌のような言葉遊びから、役者たちのてんやわんやのシナリオワークまで、村井の創作は、あなたが知っていると思っていた物語を気まぐれに拭い去るように誘う。





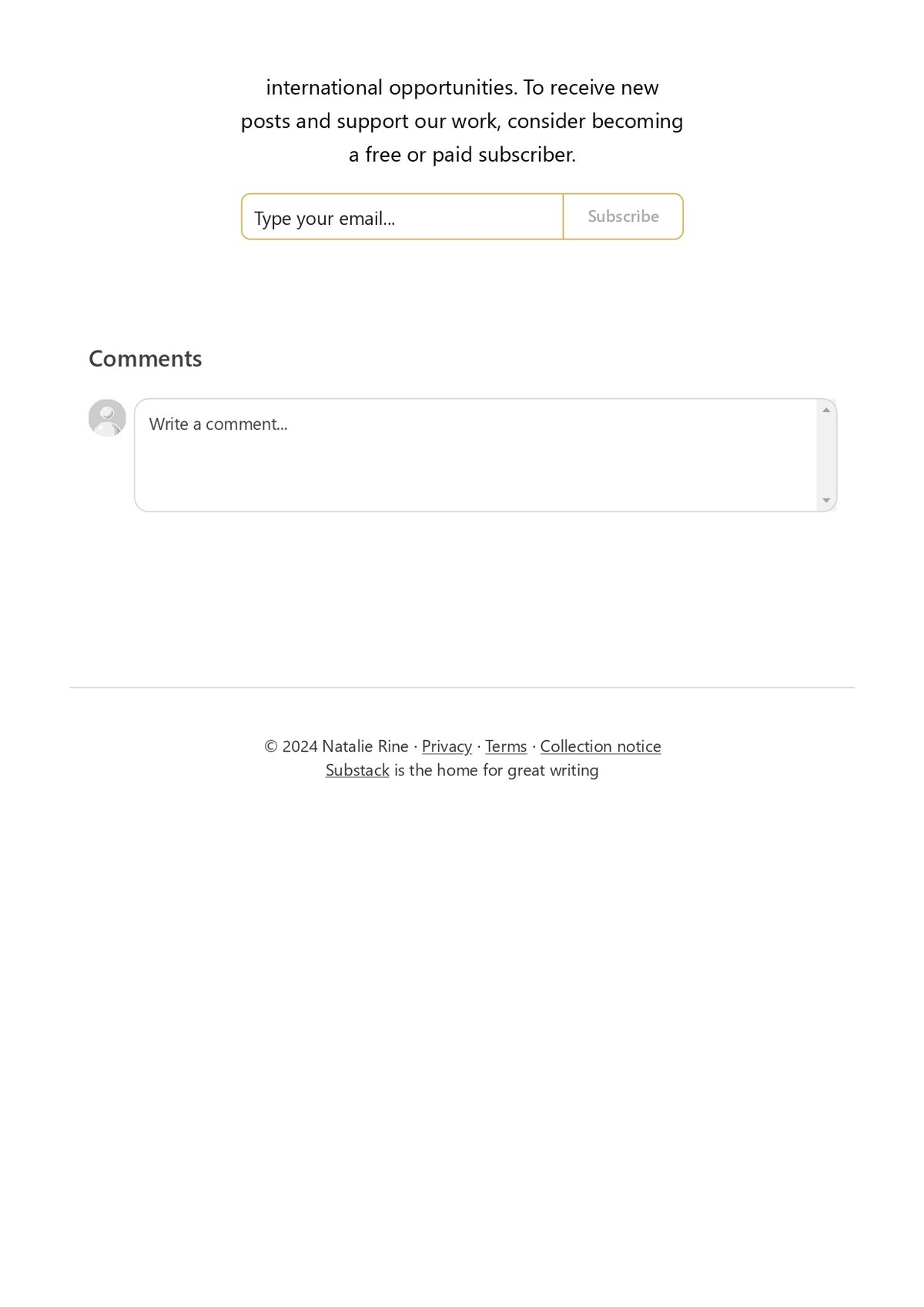
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
