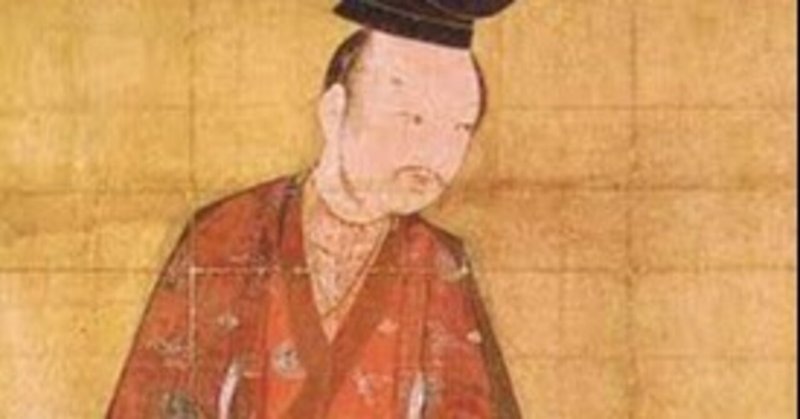
第四章 なぜ源義経は殺されなければならなかったのか!?
・朝廷を無視した主従関係を確立
そして、この頃に戦の天才源義経と再会。
奥州藤原氏のもとで育ち、幾つか軍勢も持たせて貰って兄と合流。
頼朝は、義経を後継者と目して、確かに可愛がっていたらしい。
それと同時に、鎌倉殿と御家人という主従関係の強化に力を注ぐ。
鎌倉武士(坂東武者に更なる追随者を含む)311人を前に、お前たちは俺の直属の部下だよね、御家人だよねって宣言して、朝廷抜きにした新しい組織を作る。
平家が、天皇との婚姻と武力で権力を握っていたのに対し、源頼朝は武力メインでの権力掌握に舵を取る。上皇とのマメなコミュニケーションも疎かにはしないが、あくまでもそれを行うのは自分。
自分を飛ばして上皇の命令に従う奴は、斬る。何故なら、上皇に自分を飛ばして繋がられてしまうと、鎌倉幕府が上皇に骨抜きにされてしまう危険があるから。
『鎌倉殿である俺がルールだ! お前らの土地は俺が守るから、俺に従え』
それを行動でみんなに叩き込んでいく。
・活躍させたいのは鎌倉武士
で、その頃にオフィシャル武士源義仲が、平家討伐で大活躍して京都入りするわけだが、京都の機微を全く分かっていない為、反感買いまくって逆賊認定されてしまう。
後白河法皇は、話が通じない義仲ではなく、頼朝に助けを求め、頼朝は義経を派遣する。
頼朝は、奥州藤原氏に脅威を感じていた為、鎌倉から動くことができず、派遣したのは義経率いる五〜六百騎だったらしい。
そこに、義仲に反感を覚える伊勢や伊賀の勢力が加わる。
だが、それに加えて源範頼を主力として派遣。
何故なら、義経に付いている軍は、鎌倉の軍ではない。
奥州や伊勢や伊賀の軍。
頼朝としては、鎌倉の軍に武功を立てさせたい。
そして、論功行賞で絆を深めたい。
結果、勝利して、活躍した御家人たちにきちんと褒美を与えた為、頼朝は源氏の頭領と目されることとなる。
この『活躍させて褒美を取らせて、絆を深める』のが、頼朝が用いた強力な人心掌握術!
・実は、平家との和睦に日和ったりもした
だが、未だ平氏がいる。
三種の神器も安徳天皇も奪われている。
それでも、ほとんどの朝廷の人も、義経でさえも和平を唱えたらしい。
義経の率いる伊勢や伊賀の軍には、平氏(※平家は伊勢平氏出身)も大勢いて離反の恐れがあったし、頼朝も平家との協調路線も考えていた。
だが、後白河法皇は譲らなかった。
平家二万 vs 源氏二~三千
普通、やめとけって思うよな。
後白河上皇の無茶ぶりはずっと凄いし、それでなんとか生き延びてるのが、天皇の権威に裏打ちされた自信を窺わせる。
一の谷の戦い。
義経が戦争の天才であったこともあるが、後白河法皇が平家に和平の申し出をして騙し討ちをしたことで勝った。
ロマンを潰すようで申し訳ないが、鵯越はなだらかな丘だし、義経たちはその丘を越えてもない。
全て後世の脚色であった。
この後、頼朝は鎌倉武士である土肥實平と梶原景時に平氏討伐を命じる。
義経には京都の守護を任じる。
矢張り、鎌倉武士団であるか、そうでないかが重要。
もしも義経が功績を立てると、朝廷から鎌倉武士団以外が評価されることになってしまう。
頼朝はそれを避けたかった。
だが、鎌倉武士たちは苦戦して決着が付かず、仕方なく頼朝は後白河上皇に義経に追討命令を出して欲しいと願い出る。
ところが、義経軍は、平氏出身も多かった伊勢・伊賀の兵士たちの反乱で動きを止めてしまう。
その為、頼朝は改めて鎌倉から軍隊を派遣することにする。
源範頼、和田義盛、千葉常胤、北条義時、比企能員、三浦義澄といった鎌倉勢オールスター。
滑り出し上々で山口辺りまで進撃できるんだが、飢饉の影響で兵糧に困窮したり、水軍がないことや馬の不足で移動も困難で、士気が撃沈。
範頼は、半分以上が故郷に帰りたいって言ってるって頼朝に訴える。
頼朝は、急がなくていいから、三種の神器と安徳天皇の身柄を持って帰るようにと念押ししている。それと、九州を味方に付けろとも。
その結果、九州と同盟を結ぶことができて、水軍と食料を得て、腰を据えた戦いに臨むことができるようになる。
ちなみに途中で後白河法皇は平家に和睦を申し出たりもしてるんだが、「あんた一ノ谷で騙し討ちしたくせに、どの口がそれを言うか!」って一蹴されてる。この人は、ちゃっかりし過ぎ…。
・義経の独断
だがしかし、タイミングを同じくして、義経が内乱を平定して進軍できるようになる。
ここで頼朝と意思疎通しようとすると、手紙の往復で二〜三ヶ月かかる。
現場は、いつまで兵糧が持つかも分からないし、速攻で決着を付けた方が良いのではないかと、独断で判断してしまったのだろう。
一応、後白河法皇には理由を告げているし、朝廷でも早く平家を倒してくれという声が強かった。
大阪辺りで一ヶ月腰を据えて水軍を集めて組織化し、屋島にこもった平氏討伐に頼朝の許可を得ずに乗り出してしまう。
ここもまたやらかしポイントで、畿内の水軍だから、鎌倉武士団ではない。
義経は軍事の天才だから、屋島に籠もる平家軍にあっという間に勝ってしまう。
その連絡が鎌倉に届くのが、一ヶ月弱後。
頼朝としては、平氏を滅ぼすのは範頼主軸の軍であって欲しいと思っていたので、もやもやを覚えたことだろう。
ここで付け加えると、頼朝は鎌倉武士団に対してきめ細やかに気遣う文を送っている。
源範頼からの義経出っ張りすぎって愚痴をフォローしたり、千葉常胤や北条義時といった主力の武将たちに感謝状を送ったり。
一方、義経軍は、彼のめざましい活躍に惹かれ、更に兵士が集まって軍が膨れていき、余裕で最終決戦に挑めるまでの戦力になる。
義経は連絡での時間ロスを惜しんで、またもや指示を仰がず独断での速攻を選ぶ。
頼朝としては、時間を掛けてもいいから、鎌倉武士団の顔を立てて欲しいし、三種の神器と安徳天皇の身柄も欲しいわけだ。
これが、二人の決裂に繋がっていく。
壇ノ浦の戦い、源氏の舟 八四〇艘、平家の舟 五四〇艘。
源氏勝利、勝因は諸説ある。
源氏が勝つが、頼朝の希望はことごとく裏切られる。
鎌倉武士団は活躍できず、三種の神器も安徳天皇も失ってしまう
この連絡が届くのも一ヶ月後。
その報告を読んで、頼朝は無言だったらしい。
・頼朝が許せなかったポイント。
※安徳天皇と三種の神器を確保しなかった。
※迅速な平家討伐ばかりを優先する後白河法皇に従っているように見える。
※鎌倉武士団に功績を立てさせなかった。
だが、義経も、京都にいる以上、後白河上皇の意思を無視することもできなかったという、やむを得ない事情もある。
実際のところ、義経は、多少時間が掛かろうとも、頼朝と密接に遣り取りをしていれば良かったのだろう。
梶原景時が「義経は自分一人の力で平家を倒せたと傲慢になって、御家人たちが反発している」という報告を頼朝にしている。
頼朝からこれを見ると、義経が傲慢かどうかはさておき、自分の支持基盤である御家人たちから弟が嫌われてしまったうえに、本人にその自覚がないということに、激しい危機感を覚える。
自分より後白河法皇の言うこと聞くし、戦争は強いけど、組織論全然分かってないだろう!って、とても困る。
ここで、頼朝が義経に生温い対応をしてしまうと、過激な武士団である坂東武者たちに、恐らく嫌われる。
「なんだ、結局、俺たちよりも身内が可愛いんだな」って不信と反発が生じて、頑張って築き上げた、御家人の支持が揺らいでしまう。
だから、組織をまとめる為に、仕方なく義経を切り捨てることを選択したのではないかと思われる。
奥州藤原氏のもとで比較的伸び伸びと生きてきた年若い義経と、紆余曲折経たうえで罪人として坂東武者の傍で育った頼朝の、人生経験と学びの差。
・ついに決裂へと
朝廷は、義経は平家討伐の立役者ということで、官位を与え、懐柔しようとした。
これも、朝廷との関係を自分メインで繋ぎたい頼朝としては許せない。
だが、義経としては、頼朝の為に頑張って平家討伐したのに、なんで疑われてるのか、怒られてるのかと解せない。更に、折角仲間にした軍を捨てろ、検非違使の役職も捨てろと言われ、哀しみと憤りしかない。
ここで、源行家叔父さんがやって来て、頼朝への謀反を唆す。
源行家は、頼朝の下には付かずに後白河上皇に付いているので、頼朝の政治的理念からすれば絶対許せんマン。
義経に行家を討伐するように命じるが、義経はついに頼朝よりも行家へと信頼を置いてしまい、対決姿勢へと向かう。
行家と共に挙兵を目論み、後白河法王の頼朝追討の宣旨も脅し取り、当然兵士が集まるだろうと思ったが、僅か二百騎しか集まらなかった。
つまり、これまで義経が軍勢を集めることができたのは、頼朝の権威を背負っていたから。
あと、後白河上皇の宣旨はころころ変わるから、どうせ義経が負けたら取り下げられるやろうって感じで、信用がない。
・源頼朝、出陣からの鎌倉幕府爆誕!
ついに頼朝が出陣する。
恐らく、現時点での日本最高の軍事力。
義経は為す術もなく九州に逃げ延びて行方知れずになる。
入京した頼朝は、無防備となった後白河上皇を脅して、全国の守護・地頭(警察と徴税やる人)の任命権を認めさせる。
これが、鎌倉幕府の誕生。1185年11月29日。
・奥州平泉征伐!
義経のその後は、大河ドラマ通り。
奥州藤原氏の藤原秀衡に庇護され、優れた君主だったから頼朝からの外交圧力も毅然と撥ね除けて貰えるが、程なく秀衡は高齢による病死。
秀衡は、跡継ぎの藤原泰衡に、義経を主君にしろと言い残すくらい、義経を評価していたんだが、跡継ぎとしては到底納得できる筈もなく、不穏に。
頼朝も、軍事的天才義経との直接対決は避けたいので、搦め手を駆使して、藤原泰衡に義経を騙し討ちにさせた。享年31歳。そして、この時点で既に、藤原泰衡討伐の宣旨を朝廷から出させている。
朝廷は、この報を聞いて、藤原泰衡討伐の宣旨を取りやめにするんだが、頼朝は聞かない。
「いや、戻らん。鎌倉に討伐の為の御家人を集めてるんだ。戦争するって決めたからには、やるんだ!」
覚悟したことを中途半端にしたくない武士ルール。
「喧嘩するぞッ!」つったのに、「やっぱやめます」やると面子が潰れる。
あと、マジで奥州藤原氏は脅威だったから、本当に潰したかった。
こうして、頼朝率いる武士団は朝廷の命令を真っ向から無視できる勢力として台頭できる実力を世に示すこととなる。
更に、ひいひい爺さん義家の、坂東武者を率いての東北攻めの再現となる。
「俺たち、以前も同じことやったよね! お前たちの先祖の坂東武者は、俺のひいひい爺さんの義家に率いられて、東北攻めに見事打ち克った。今回もその武功に肖ろうぞ!」
この燃えるドラマが、武士の魂を焚き付ける。
これで集まった武士が28万騎(※『吾妻鏡』の記述。間違いなく誇張。ノリと盛りで書かれてるのが、軍記物の特徴)
何はともあれ、大軍が集まったのは間違いなく、これで、己の影響力を、朝廷にも身内にも外野にも知らしめることができた。
こうして奥州藤原氏の砂金と馬と土地は、参加した武士たちに惜しげもなく恩賞として分け与えられることとなる。今回味方してくれた、かつて敵対していた武士たちにも。
こうして、頼朝のご恩と奉公の概念を、全国の武士たちに知らしめたのであった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
