
第4章第6節 富山日報への移籍
大井冷光の生涯を論じるとき、最も難しいのは明治41年かもしれない。この年の6月下旬ないし7月上旬に、冷光は『高岡新報』から『富山日報』へ移籍したが、それを裏付ける資料は乏しく日記の数行のみである。移籍の理由はいまだ推測の域を出ない。
恩義を裏切る行為?
6月24日「匹田主筆富山日報入社勧告の為来訪、洋服のまゝ葉巻をくわいつゝ語る、入社して予の事務の半分を助けよとなり」
6月25日「晩先生へ行く、社としては君を放し難きも君の栄進を妨ぐるは予個人として忍びずと語らる、途中窪美老人を訪ね相談せしに先生と同意見なり」[1]

※号は雪堂、明治41年当時は41歳
『富山日報』主筆の匹田鋭吉が冷光に会いに来た。そして葉巻をくわえながら移籍を勧めた。冷光が『高岡日報』主筆の井上江花に相談すると、江花は「会社としては辞めてもらっては困るが、個人的には君の将来を考えると止めることはできない」と言った。そして江花の史学の仲間で冷光が先生と尊敬する窪美昌保も同じ意見だった、という内容である。
この時期、新聞記者の移籍や引き抜きはしばしばあった。冷光の場合、大家族を抱えて生活が苦しく、より待遇のいい新聞社に移ったのでないか、という見方がある。しかし本当にそうなのだろうか。

明治41年当時は37歳
※『江花文集』第1巻(1910年)高岡市立図書館蔵
冷光は明治38年からの3年間、井上江花にひとかたならぬ世話になった。育ての親にあたる伯父が相場で失敗して家出したため早稲田進学をあきらめて19歳で一家7人の生活を背負わなければならなくなったとき、就職の世話をしてもらった。江花の書いた記事の切抜きを借り、それをヒントに編纂した日記を批評してもらった。休日のたびに探検団に誘ってもらい、仲間と野外に出る趣味の面白さを教わった。軍隊に入営した1年間は頻繁に文通を交わし愚痴を聞いてもらった。長男の名付け親にもなってもらった。そして軍隊のあとはたまたま空いた高岡新報富山支局の新聞記者に推薦してもらった。冷光の江花に対する恩義は挙げればきりがない。
2人の間にはユーモアという共通項もあった。明治40年3月20日、江花36歳の誕生日に、冷光は翁の面の絵はがきに「若草に加賀万歳を召されける」と祝いの句をしたため、わざわざ紋付羽織を着てお祝いに参上し、江花を驚かせている。[2]冷光と江花は強い師弟関係で結ばれていたはずなのである。
江花から離れて他の新聞社に移るのは、相当の理由がなければ裏切り行為に等しいといってよかろう。匹田の移籍勧告が冷光の心を動かし、江花もそれを認めたのには、待遇問題でない事情があるのではないだろうか。2人の主筆の間に立った冷光は、おそらく心のなかで葛藤し、人生を大きく左右する決断を下したにちがいないのだ。
日付は1年勘違い
本題に入る前に指摘しておかねばならないのは6月24日という日付の問題である。富山日報の匹田が来訪した日だが、江花が編集した冷光の日記では明治40年6月24日となっている。これは誤りである可能性が高い。なぜなら、匹田は明治40年5月21日から7月27日までの68日間、清と韓国に取材旅行に出ていて富山にいなかったからだ。明治40年6月24日は南京にいたのである。
明治40年6月だと冷光はまだ記者半年の駆け出しである。そんな記者を引き抜くために、そもそも他紙の主筆がわざわざ訪ねてきただろうか。明治41年6月24日であれば、記者生活1年半、仕事ぶりの評価も出てきたころだ。そして最初の出版物となる『立山案内』が印刷にかかるときだった。
冷光の日記は、大正11年に『高岡新報』で連載された「冷光余影」に収録されている。井上江花が冷光の死後、文夫人などから集めた日記や書簡を整理して編集したものである。明治40年6月2日以降について、江花は「日記は次第にゾンザイに流れ重要覚え書体となりて終に四十一年六月十五日で尽きている」と注釈を付けている。
15年前の記憶をたどりながら編集したさい、明治40年と41年の取り違えたみられる例はほかにもある。例えば東京の勧業博覧会を取材したときの視察記は9編あり、すべて明治41年とされているが明治40年の誤りだ。入社の辞も明治41年とあるが、明治40年が正しい。この頃は誤植がよくあるので江花のミスと断定できないが、移籍話が交わされた重要な日もまた1年取り違えた可能性が高い。[3]
匹田の移籍勧告は明治41年6月24日として話を進める。
移籍話を読み解く上でポイントは2つである。1つは、匹田鋭吉が「予の事務の半分を助けよ」と言ったのはどういう意味なのか。具体的に何か事務があるのか、それとも匹田の仕事全般なのか。もう1つは、江花が「君の栄進を妨ぐるは予個人として忍びず」といったのが本心だとすれば、栄進とは何かである。この2つのポイントを考える前に、匹田鋭吉と井上江花、2人の主筆の深い因縁について記しておかねばならない。井上江花については先行研究があるが、匹田の富山日報時代については詳しい調査はこれまでない。
読売出身の奮闘主義者
匹田鋭吉は明治元年生まれ、岐阜県郡上八幡の出身である。早稲田大学の前身にあたる東京専門学校の政治経済学科を明治21年7月に卒業し、読売新聞主筆の高田早苗(半峰)の推薦で同社に入社した。最初は英字新聞の翻訳をしたが、政治部に配属され記者としてのキャリアを積んだ。明治27年9月、日清戦争で大本営が広島に移ったことから特派員として派遣された。その後、主筆の下のポストである編集長をつとめたらしい。伊藤博文に単独取材したのも読売記者時代である。明治30年8月、一身上の都合で読売新聞を辞めた。その後、帝国法令研究会を設立し、自ら主幹となった。政治家や役人を会員に募って講義録を頒布していたらしい。[4]
匹田が改進党系の地方紙『富山日報』の主筆に着任したのは明治36年1月1日である。当時35歳。政治記者出身で中央にもつ幅広い人脈や、組織を自分で立ち上げる行動力を買われてのことだろう。明治38年9月、日露講和条約をめぐって不満の声が渦巻いたとき、自らが発起人となって富山市の光厳寺で富山県民大会を開催し、5000人が集まったその場で、内閣の更迭と謝罪を求める決議をまとめている。
匹田はいつも紙面で強い論陣をはり、目新しい企画を積極的に実行した。匹田が富山日報を去るとき、部下たちは「奮闘主義」と評して称えている。
裃を着た道化る性格
一方、井上江花は匹田の4歳年下で石川県出身。ロシア正教会の伝道学校を卒業したのち四国・松山で布教活動をしていたが、病気をきっかけに故郷に戻り、小説を書くようになった。明治33年に『高岡新報』に入社し富山支局記者となってからは社会問題に関心を抱き、明治35年2月に大阪で起きた人頭黒焼き事件が富山に波及したことを取り上げたり、越中米の品質改良キャンペーンを展開したり、明治初期の農民騒動の記録を掘り起こしたり、精力的な取材活動を見せた。
江花は明治40年12月、富山支局詰めのまま主筆に上り詰める。小説から評論まであらゆるタイプの記事を書き、特にユーモアのある文章に定評があった。冷光に言わせると「裃を着ながら道化るといったような性格」だったという。[5]自身は、競合紙『北陸タイムス』のコラムに「猫好きで宴会嫌い」と寄稿している。[6]人望が厚くのちに後輩たちが江花会を組織し、『江花文集』という叢書を出版した。
2人の主筆を比較すると、出身地が隣県で縁のない富山の地にやってきた点は共通するが、匹田は中央紙の政治記者出身の辣腕、江花が学者肌の地方紙記者という対照的な2人である。[7]
移籍騒動後も交友関係
そんな2人の人生が交差したのは明治37年2月のことである。匹田が江花に富山日報への移籍を持ちかけ、江花も合意して移籍が実現したのだ。『富山日報』紙面にはいったん移籍が公表された。ところが驚いた『高岡新報』がすかさず異議を申し立て白紙に戻ってしまう。10日間の移籍騒動だった。県知事の李家隆介が調停に入ったともされている。[8]
『富山日報』は、明治18年創刊の中越新聞の流れを汲む改進党の機関紙である。富山県内では最も古い由緒ある朝刊紙だった。一方の『高岡新報』は県内2番目の都市高岡に本拠を置き、米取引の相場紙から一般紙となった夕刊紙である。紙面はいずれも4ページで、明治末期から大正にかけて、記事の質でもそん色ない水準にあったが、部数や社格あるいは地域への影響力には当然差があったに違いない。
10日間の移籍騒動によって、匹田と江花は仲違いしたわけでなかった。その後も近所同士で互いの家を訪ね、親しい関係が続いた。例えば、明治38年6月4日の日曜日に神通川で舟遊びをし、同月24日には洪水の見舞いに匹田が江花の家を訪ねている。[9]明治40年12月に富山県が組織する『越中史料』編纂委員会ができると、2人とも地元紙の主筆として評議員となっている。
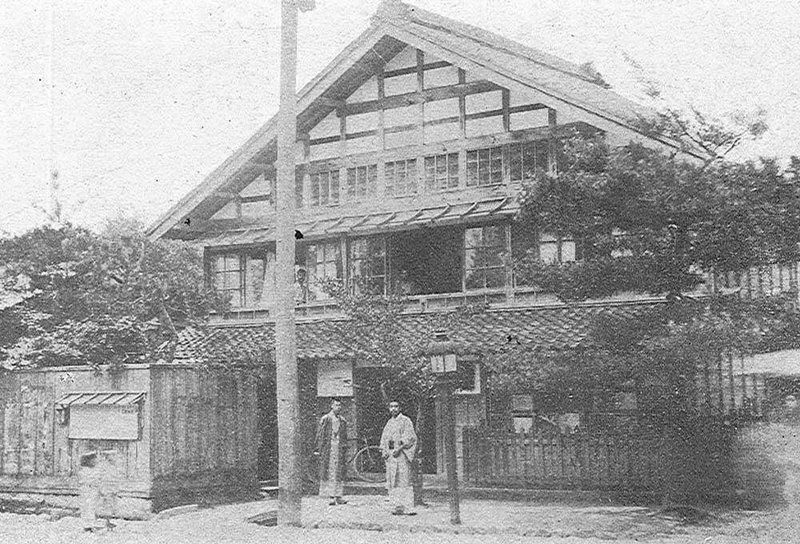
『富山実業案内』明治42年(富山県立図書館蔵)
「生活苦で移籍」は疑問
話を明治41年に戻そう。冷光は5月までに『立山案内』を編集したが、これ以外にどんな仕事をしていたのか。江花が収拾した明治41年作の文章をならべてみると、「田舎駅の五分間」「羽衣新地」「朝の取引所」「オチニ志願」「瀧屋の貸屋」「紡績工女」「二ツの寄席」「禅僧生活」の8編がある。いずれも高岡で書かれたルポである可能性が高い。41年の日記には「五月二十六日より高岡の側面観察をなす」とあり、ルポがこの側面観察にあたるのかもしれない。5月30日土曜日に書かれた江花の日記と照合すると合致する。この日記によれば、冷光が夜高岡から帰宅し、江花もそこにいって照ちゃん(光雄のことか)が饅頭を食べる場面が微笑ましく綴られている。冷光はこのころ高岡本社に勤務していた可能性がある。[10]
そして6月24日。匹田が移籍勧告にやってくる。
移籍理由は生活苦という見方について今一度考えておこう。
明治40年6月1日の日記に、貧乏を嘆くかなり具体的な記述がある。記者生活半年、初の東京出張から帰ってきて半月たつ頃である。長いが全文引用しよう。
6月1日「貧の虜となり一月計り日記さへ手に付かなかったのは男らしくもない、最早や米屋には二十円計り借金がある、明日出来上るセル地夏服は八円二十銭、それでチョッキは未だ誂らへられぬのである、魚屋へは月末迄に三円は有るだらう、清明堂の本屋に四円二十銭、八百屋に二円の見つもり油屋へ二円、それから除隊の際改造して持って来た靴は裏に口が開いたのでズックのを注文したので二円余は取られるアゝこの月末には五拾円以上がなくてはならぬ」[11]
15円の月給に対して50円以上の借金があったことになる。1年後の明治41年6月までに、家計が大きく改善したとみられる事象はない。しかし、冷光が給料の高い会社に移りたいなら、冷光が頼みに行くだけでよいのに、匹田が勧告に来るというのはどういうことだろうか。「葉巻をくわえながら」という表現は、匹田の高飛車な姿勢が想像される。
江花にしてみれば、自身がかつて移籍騒動を経験し、親しい匹田自身から事前協議があったにちがいなく、それなりに考えるところがあっただろう。『高岡新報』の紙面づくりにまい進しているなかで、待遇が不満だという単純な理由で冷光が退社すると言い出したら、江花は納得できたのであろうか。
擬国会とウラジオ旅行隊
匹田の側から移籍話を見てみよう。「入社して予の事務の半分を助けよ」。当時、匹田が抱えていた事務は何か。
匹田は、企画力と行動力に優れた主筆だった。前述したように明治40年に68日間の清韓取材旅行を自ら敢行し、紙面に長く連載した。翌41年4月には「擬国会」という大がかりな事業を展開している。擬国会とは模擬国会のことで、県内の名士142人に大臣役や代議士役を演じてもらい、国会と同様の論戦を行って、議会政治への関心を高めようというものである。[12]
擬国会では、江花が無所属の院内総理、匹田が革新党の院内総理を務めた。議事はあらかじめ、政府不信任案を提出して内閣が総辞職、匹田が新首相に就くことが決まっていたので、茶番劇のようにも見える。しかし、中央政界を取材した経験がある匹田だからこそできた一大事業だった。東京の各新聞は「富山県の大擬国会」「大仕掛の擬国会」と報じたという。注目すべきは、冷光もこの擬国会を見ていたと日記から読み取れることである。首相役に就く辣腕政治家の匹田の姿は、冷光の目に焼きついたことであろう。
擬国会が終わってから、匹田はすぐさまもう一つの大型事業を展開した。「浦塩行旅行隊」というロシア・ウラジオストクへの海外旅行企画である。前年の旅行をヒントに、現地領事が富山県出身であることにも目をつけて立案したらしい。6月1日に社告を打って一般参加者を募集した。企業から協賛も集めて、紙面連載した。匹田によると、新聞社の海外旅行企画としては朝日新聞の世界一周会、北陸新聞(金沢)の韓国旅行などの前例しかないという。冷光の移籍話が持ち上がった6月24日は、まさにこの事業の真っ最中であった。
浦塩行旅行隊は結局90人が参加し、8月3日から9泊10日、敦賀港経由で行われた。旅行隊に加わった富山日報社員は匹田を含め3人で、冷光は参加していない。[13]匹田が冷光に「助けよ」と迫った事務は、浦塩行旅行隊の事務ではなく匹田自身の仕事全般をさすのであろう。
移籍後の連載から推測
冷光が移籍した理由を3つの推測に整理しよう。第一に、高岡新報の勤務地が富山支局から高岡本社となり、自宅からの通勤が遠くなり不都合が生じていたのでないか。第二に、行動派主筆である匹田の人柄や編集方針に引かれたのではないか。第三に、この年の初めに立てた「趣味の向上に尽くす」という目標、そして巌谷小波のようなお伽作家になるという目標を実現するには高岡新報よりも富山日報に移ったほうがよいと考えたのではないか。
富山日報に移籍して冷光がどんな仕事をしたのかをみていこう。富山日報に載った冷光の最初の署名記事は明治41年7月9日から3面で5回連載の「本市の三幼稚園」である。この時すでに幼児教育に強い関心があったものと見られる。署名はないが、7月1日から3面で3回連載の「老妓の観たる歴代の知事」や7月14日から3面で11回連載の「酒席に於ける富山紳士」も冷光の仕事と推測される。
7月23日から3面で6回連載の「六根清浄(立山登山の栞)」があり、立山への強い関心がうかがい知れる。この立山の連載は分量としては少ないが読みごたえがあり、情報を継ぎ接ぎしただけの『立山案内』よりも生き生きとした筆の運びとなっている。また、12月1日からの「思出多き新兵時代の思い出」(7回連載)は得意の兵営物の記事である。
『富山日報』の大井冷光署名記事(明治41年)

冷光が書いたと推定される記事(明治41年)

この明治41年から明治42年にかけての冷光の記事を見ると、趣味に関する記事が多い。冷光は、事件事故や政治経済を追う社会部や政治部の記者でなく、学芸記者を目指していたのではないだろうか。ここで一つの疑問が生じる。学芸記者を目指すなら、政治記者出身の匹田鋭吉より井上江花のもとで記者をしていた方がよかったのではないか。
しかし匹田の意外な一面を知るとこの疑問は打ち消される。
博文館に人脈あった匹田
匹田は明治21年7月、東京専門学校を卒業した直後、わずか1か月ほど博文館につとめたことがあった。学生時代から文芸趣味があり、20歳のとき『金蘭花縁』(共隆社、明治21年3月)という小説集を著した。学資を得るための内職だったという。
明治から大正にかけて出版王国と呼ばれた博文館は、明治20年に創業した。創業直後の博文館に匹田が入ったのは、東京専門学校の同窓生で坪谷善四郎(号は水哉、つぼや・ぜんしろう、すいさい)の引きがあったからだ。匹田は、同じ東京専門学校卒の中山整爾と「日本之女学」を編集したという。[15]
坪谷は、明治24年から明治27年末まで編集局主幹であったから、明治24年に出版された巌谷小波の記念碑的作品「こがね丸」(『少年文学』第1編)の出版にもかかわっていたにちがいない。博文館は明治28年、雑誌『太陽』『少年世界』『文芸倶楽部』を創刊したが、『太陽』主筆は坪谷、『少年世界』は巌谷である。坪谷はのちに博文館の取締役になる。
博文館にかかわった3人

匹田は、富山に来てからも中央とのパイプをしっかり持っていた。明治39年6月6日、富山日報は創刊以来の紙齢が7000号に達し、記念紙面を制作した。1面に寄せられた各界の祝電のなかに、巌谷小波の句「七丈に余りて楠の若葉哉」が出ている。2日後の8日には、坪谷水哉の比較的長い祝文が掲載されている。
匹田との具体的な接点はまだ分からないが、匹田は冷光が憧れる巌谷小波と旧知だったのである。冷光から見れば、匹田は単なる政治部記者でなく中央の出版界に通じしかも文芸趣味も解する人物だった。
翌明治42年、巌谷と久留島が富山に訪れることを地元紙で東京電として最初に報じたのは『富山日報』である。そして巌谷と久留島が富山に訪れたとき歓迎晩餐会であいさつに立ったのが匹田鋭吉である。巌谷と久留島の来県によって、富山という地方都市で、児童文化運動が一気に花開くことになる。富山日報へ移籍した冷光は、その中心に立つのである。[16]
◇
[1]「冷光余影」55『高岡新報』大正11年5月20日。冷光の富山日報移籍の月日を確定できない理由の一つに、図書館に所蔵されている『富山日報』紙面の欠落がある。たまたま、明治41年7月1日付の4ページのうち、1ページ目と2ページ目だけがそっくり欠落している。当時は、移籍時に「入社の辞」を紙面に掲載することがよくあった。もしかしたらこの1面が見付かれば、そこに冷光の「入社の辞」が掲載されている可能性がある。
[2]「冷光余影」2『高岡新報』大正11年1月2日。「冷光余影」49『高岡新報』大正11年5月14日。明治40年3月20日の日記は同じものが2回掲載されている。
[3]40年と41年の取り違い問題で今後検討を要する問題として、江花が編集した冷光の文章の中に「散る散る日記」がある。41年10月11日から21日までの日付があり、19日を除く10日間、高岡でなく富山で書かれたようだ。日記とはあるが私的な日記とは違い、新聞のコラムのような内容である。大村歌子編『天の一方より』(1997年)によると、明治41年10月19日は冷光の第2子である長女静代が亡くなっている。19日の日記がないのはそのためなのだろうか。
[4]「私の在社当時と今日」『読売新聞』大正11年5月23日。『新聞集成大正編年史』大正11年度版中(1984年)。読売新聞社編『読売新聞八十年史』(1955年)。熊崎利夫『匹田鋭吉氏の足跡』1943年。帝国法令研究会は、『朝日新聞』明治30年8月15日2面。明治30年1月10日には、自由党大会を取材した際、議員に殴打され、読売と朝日の記事になるほどの大きな事件となっている。匹田の帝国法令研究会(東京府京橋区弥左衛門町15番地)は明治30年10月『帝國法令研究會雜誌』を創刊、隔週で発行した。明治31年9月に24号が発行され、現在確認されているのは明治32年発行の25号までである。匹田は明治43年2月末に富山日報社を電撃辞任し、いったん九州日報に移籍したあとすぐに富山に戻って、創刊1年半の競合紙『北陸タイムス』の主筆となった。そして1年後、汚職事件で有罪判決を受けて富山を離れた。大正2年には岐阜日日新聞社長となり、さらに2年後、代議士に転身、昭和17年まで7期を務めた。
[5]『江花文集』第2巻p114。冷光が富山日報記者時代に書いた記事。
[6]「好きと嫌ひ」28『北陸タイムス』明治42年5月9日。「宴会は交際の単純な道具で、大嫌いです夫れに侯等の天爵であるから、世人の疑惑を受けたり、碌な事のないものです。逃げる如うに、避ける如うにとして居ます」とある。
[7]
[8]河田稔『ある新聞人の生涯 評伝井上江花』(1985年)p74-76。
[9]井上江花『老梅居日記』大正15年(1926年)11月(『井上江花著作集』第3巻1985年所収)p39-41。
[10]「冷光余影」44・49・54・56・58・60『高岡新報』大正11年4月25日-6月4日。饅頭の話は「崑崙日記」『江花文集』第1巻による。「下関随筆」『江花文集』第5巻によると、大井冷光は高岡市の車屋の隣の家に住んでいたことがあるという。
[11]大村歌子編『天の一方より』(1997年)によれば、明治40年6月1日の日記には続きがあり、清明堂の福田から本の執筆を依頼されたが、江花に相談したら割の合わないからやめたほうがいいと忠告され早速断ったという話につながる。少なくとも明治40年6月の時点では、生活に苦しんではいたが、移籍を考えなければならないほど金に困っていたようでもない。
[12]擬国会は明治41年4月5日と6日の2日間、富山市五番町の光厳寺で開かれた。参加者142人が7つの政党に分かれ、政府与党3党が63人、中立2党が35人、野党2党が44人。服装は羽織袴か洋服、受付で党派別に議員章を付け、傍聴席も設けられた。事前に国務大臣役が割り振られ、院内総理など細かい分担も決められていた。議長選挙、法案提出、首相の施政方針演説など議事進行も国会と同じように行われた。『富山日報』明治41年4月4日、5日、6日、8日などによる。
[13]浦塩行旅行隊については、『富山日報』明治41年6月2日の論壇。8月3日に隊員名簿。
[14]「酉留奈記」3・19『高岡新報』大正10年11月2日。井上江花は「(巌谷小波)の著書の大部分は一通り目を通して居たが、私はお伽ものに深い趣味を有たぬ上に小波さんの作品の愛読者では無かった」と記している。江花は『高岡新報』明治43年1月2日13面に「越中の伝説口碑」を特集し、富山県内30の話をまとめ、連載している。
[15]坪谷善四郎編『博文館五十年史』(1937年)、p25、p30。
[16]匹田鋭吉と大井冷光を結ぶ線は巌谷小波以外にもう一つ考えられるが、さらに検討を要する。それは孤児院である。鈴木明子・勝山敏一『感化院の記憶』(2001年)によると、柴谷龍寛が明治40年2月に設立した深敬保育園と、さらに明治42年4月に設立した富山県感化院代用施設「樹徳学園」を、匹田は紙面で紹介し寄付を募るなど支援していた。同書によると、「匹田はリベラルで独創的な新聞人であった。貧困者たちの生活に目を向け、彼らの救済をさまざまなレポートを通して訴えた。柴谷への支援はその一つであった」という。冷光も孤児であった時期があり、匹田の取り組みに共感したかもしれない。ちなみに明治40年2月15日の冷光の日記に柴谷が高岡新報富山支局を訪ねたと記されている。冷光はまた明治38年9月29日に富山で開かれた岡山孤児院音楽会に出かけ、音楽と活動写真を楽しんだことや、井上江花の家に孤児院の生徒が来ていたことを書き記している。しかし明治41年の時点で、冷光自身は家庭をもち、生活が苦しく、慈善事業に関心をもつ状況にあったかどうかは分からない。その一方で、冷光の友人の島谷直方が樹徳学園の職員であったこととの関連が興味深い。いずれにしても冷光と孤児院の関連は今後の調査研究が待たれる。(2013/03/20 14:30)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
