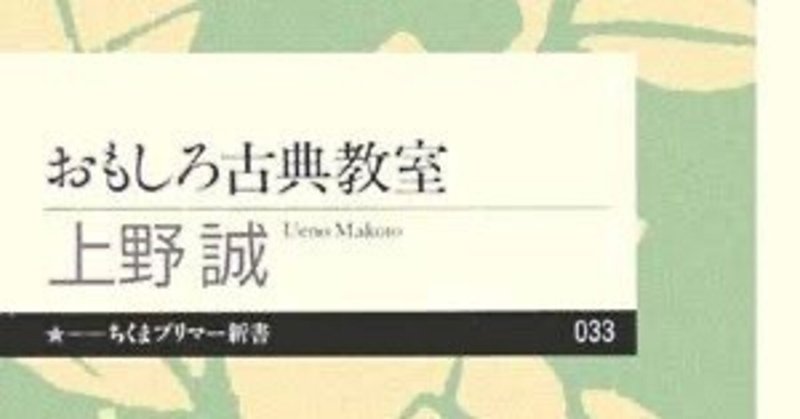
古典の入門3 『おもしろ古典教室』上野誠
古典の入門書を語っている。3回目に取り上げるのは、上野誠『おもしろ古典教室』(ちくまプリマー新書 2006年)だ。1回目は歌人、2回目は小説家による入門書だった。3回目の著者である上野は国文学者だ。いよいよ本格的な入門書に近づいてきた。
とはいえ大所高所からご高説を垂れる形式の本ではない。「あとがき」によれば、上野は月に何度も、時には10回以上、高校生相手に授業や講演を行っているそうだ。それだけ教育の現場に求められている語り手である、ということだろう。高校生相手の語りの名手と言って間違いあるまい。本書はそんな上野の授業や講演をベースとした本だ。きっと読みやすく感じると思う。
さて本書の執筆目的は、上野の言葉を借りれば「古典って案外おもしろいじゃん」と思うようになることだ。その裏にはコラムで触れているような国文学の不人気があるのだろう。問題意識は橋本治とよく似ている。ただし古典そのものに抱腹絶倒して欲しいわけでは無さそうだ。上野は次のように言う。
古典だからすばらしいのではない、その古典を読んでおもしろいとか、たのしいとか思う「今」と「自分」がすばらしいのだ
古典を学ぶ人は、「自分」が「今」読んでいるんだということを強く意識して、読んでほしいのです。そうしないと、古典は過去の人間の残した単なるカスやゴミと同じになります。
少々、ドキリとした。僕は授業では、読み方を示すだけで自分の考えはあまり語らない。楽しそうに読むことは心がけるし、生徒と一緒に読みを構築していくことは実際楽しい。だけど読んだ自分について語るということは避けている。僕はリテラシーを伝える人間であり、生徒がそのリテラシーを用いてできるだけ多くの古典作品に触れられるよう導くのが仕事だ。個々の生徒が触れた作品を面白いと思うかどうかはそれぞれの勝手で、面白いということを押し付けてはならない。そう考えてきた。
だが上野の言葉に触れ、それでは不足なのではないかと考え始めている。読んだ古典と自分の体験や記憶を結びつけ、古典に示された視点からそうした体験や記憶を解釈する。その経験を経ねば古典がカスやゴミになる、と上野は言っている。生徒がそのような読みをするために、まずはやってみせ、そしてさせてみせなければならないのかもしれない。
小林秀雄の『考えるヒント』を思い出した。随筆集だ。電子頭脳(今でいうAIだ)と将棋。大阪行きの急行の食堂車で出会った、大きな人形を連れた老夫婦。満開の桜。出会ったものや触れた人をきっかけに、小林秀雄は考える。考えを言葉にして示す。その言葉が力強く、面白い。
上野の示している「すばらしい」自分とは、こういう小林のようなすばらしさではないか。
何かと出会い、考え、出会った後の自分を言葉にする。その行為は、積み重ねて技術にする価値のあることのように思えてきた。それを担うのはきっと国語という科目だろう。そして古典もまた、考えるヒントにする価値のあるものなのだ。
上野は古典と出会い、どんなことを考えただろうか。それが気になる人は、本書を読んで損はない。きっと上野の中に生きている古典のおもしろさを、少々羨ましく思いながら、感じられるはずだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
