
心臓リハビリテーション効果
2021年7月23日、東京オリンピック開会式。
その日、マウンテンバイクで練習中、長年の身体の訴えを無視した事で、帰宅中に急性心筋梗塞で倒れた。救急車で専門病院へ連れていかれた。
重症だった。集中治療室で2度ほど意識をなくしたが助かった。
医者には、助かったのは奇跡に近いと言われた。
そして、現在、逆説的な話だけど、長年の心臓の訴えを無視して続けた運動のかかげで、心臓機能は健常者並になんとか回復した。
今回はリハビリの効果の話
前回は3ヶ月にわたる心臓リハビリで何をどれくらいやったかを報告したが、今回はその効果、つまり回復に関してまとめてみた。
■治療に関して
急性心筋梗塞を起こす。
右冠動脈、左冠動脈の2本、他にも何カ所か詰まってしまい、カテーテルを3回施術して、ステントを5箇所入れた。
■CPX検査(心肺運動負荷試験)*1
リハビリ開始から1ヶ月経った10月1日に、CPX検査をする。
心エコー*2検査は9月21日実施した。
CPX検査方法
検査は、心電図の電極を胸に貼り、顔にマスクを着けた状態で血圧を測定しながらエルゴメーター(自転車)をこぐ。
心電図や心拍数の変化、不整脈の出現、血圧変動他、連続呼気ガス分析装置によって集積された結果を解析し、運動耐容能および運動処方の作成をする。
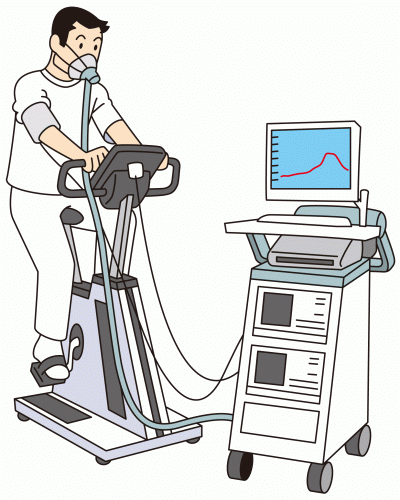
1回目のCPX検査からリハビリを続けて、3ヶ月後、12月27日に2回目のCPX検査をする。
結果比較
■1回目のCPX(心肺運動負荷試験)2021年10月1日

① 狭心症の検出、運動誘発性不整脈の評価
CPXによる狭心症の検出 「なし」
② 運動耐容能の評価
用語説明
1)Peak VO2(最高酸素摂取量):
これ以上もはや運動ができないという強度における酸素摂取量。
2)AT(嫌気性代謝閾値):
有酸素運動が無酸素運動に加わる時点での酸素摂取量(乳酸を蓄積することなくできる運動)
3)Peak VO2/HR(最高酸素脈):
最大負荷時の心拍出量(心ポンプ機能)の指標 最大心拍
4)METs(メッツ ):
運動強度の単位で、安静時を1とした時と比較して何倍のエネルギーを消費するかで活動の強度を示したもの。
--AT値時 心拍数 91回/分 負荷74W
--AT値時酸素摂取量 4.4METs(運動強度)
--AT時酸素摂取量 同年代の健常者の107%
--最高運動負荷 心拍数 138回/分 負荷161W
--最高酸素摂取量 7.7 METs(運動強度)
--最高運動負荷量 同年代の健常者114.6%
--最高酸素摂取量 同年代の健常者の109.0%
評価として、健常者より高い値。
しかし、今回はまだまだ怖くて全力を出していない。
心電図なども問題なく結果は順調だが、
心エコー検査の心臓機能(左室駆出率)*3 39.0%
まだ復活してない。
--------------------------------------
■2回目のCPX(心肺運動負荷試験)2021年12月27日
ここまで毎日自宅でもリハビリを続けている。
(自分の作ったメニューだが、非常に良いいと理学療法士からお墨付きを貰った)

① 狭心症の検出、運動誘発性不整脈の評価
CPXによる狭心症の検出 なし
② 運動耐容能の評価
AT値時 心拍数 115回/分 負荷84W
AT値時酸素摂取量 6.1METs(運動強度)
AT時酸素摂取量 同年代代の健常者の144.2%
最高運動負荷 心拍数 161回/分 負荷171W
最高酸素摂取量 8.8 METs(運動強度)
最高運動負荷量 同年代代の健常者121.7%
最高酸素摂取量 同年代代の健常者の125.0%
心臓に負担をかけないで運動能力を上げるには AT値をあげていくしかない。まさにロングトライアスロンのトレーニング方法だ。これは得意分野だね。
今回は心臓が復活している感触があったので、心拍数を上げてみた。心拍数はかなり上がった。
これはAT値を上げる練習の効果だと思う。
心エコー検査、心電図なども問題なく結果は順調。
心臓機能(左室駆出率) 52.0%
復活している。健常者の値になっていた。
「コレが一番嬉しい、壊死したと思っていた心臓が復活している」
普通は死んだ心筋は戻らないようだが、たまに運動選手なんかは心臓機能が戻るそうだ。
「理由はよく分からないが、まれに復活することがあるそうだ。なにか別の形で心臓の動きを補っているのだろう」
人体の不思議、論文がかけるパターンだとか。医師にそんな説明をされた。
その結果、寿命が戻ったことになるとも言われた。
結果は良かったが、現状は、心臓はサイボーグ、薬も飲んでいる。
今後も気をつけて運動と食事管理をするようにと言われた。
体成分分析に関して
リハビリを開始した9月より、体重は2キロ増えているが、体脂肪率は変化していない。
筋肉量が増えた分の体重増加だ。むくみもない。
ミネラルなどの栄養成分的には全く問題ない。
これは妻の食事のおかげである。何十年と続ける食事の影響は大きい。運動も同じで、若い頃は何とかごまかせるけど、60過ぎると確実にそれまでの食生活と運動不足のつけが回ってきて、その後の人生(健康)に影響する。
人生100年と言っても、前半の生き方(食、運動など)で、後半は左右されると思う。
私自身、40年続けた色々なスポーツの継続で今がある。

体成分履歴 2021.9.3 2021.12.27
体重 kg 57.3 59.2
筋肉量 kg 44.7 46.1
体脂肪率 % 17.5 17.6
---*1
CPX(cardiopulmonart exercise testing)は、心臓に病気のある方でも、心臓に負担をかけすぎずに、安心して長時間運動が続けられる運動の強さ(AT:嫌気性代謝閾値)を調べる検査です。また、心臓リハビリテーション時の運動処方作成や、高血圧・糖尿病などで運動療法が必要な方に用いられます。心不全における心機能分類や、治療効果の判定、運動耐容能測定などにも利用されます。
---*2
心臓超音波検査(心エコー)は心臓を輪切りして心臓の状態を見ることができる検査です。超音波という『音』を使って心臓を検査するので、放射線のように身体に害はなく、今現在の心臓を観察できるとても有用な検査です。
---*3
左室駆出率(LVEF)
心拍ごとに心臓が放出する血液量(駆出量)を拡張期の左心室容量で割って算出される。
左室駆出率は50%以上が正常とされており、その数値を基準にして心疾患患者の状態・予後を把握することができる
LVEF=(拡張末期容積-収縮末期容積)÷拡張末期容積×100
=1回心拍出量÷拡張末期容積×100
METs(メッツ )と運動
運動強度の単位で、安静時を1とした時と比較して何倍のエネルギーを消費するかで活動の強度を示したもの。
登山におけるMETsは、ハイキングが6Mets
一般的な登山が7METS、バリエーション登山が8Metsと言われている。
ヤマレコ公式ブログだと、登山における行動「歩く」「登る」「休む」などを平均するとだいたい5METsあればいいそうだ。
これはクリアーしている。
ロードバイク、マウンテンバイクで普通に走るのには、AT値で120W位欲しい。7.0METsくらいかな。
今後の目標
2021年12月27日→目標値
AT値時 心拍数115回/分 負荷84W→心拍数125回/分 負荷120W
AT値時運動強度 6.1METs→7.0METs
最高運動負荷 心拍数161回/分 負荷171W→心拍数170回/分 負荷200W
最高運動強度 8.8 METs→12.0 METs
心臓に無理はさせられないので、AT値でのMETsを可能な限り上げていくのが目標。
これからは下の表、黄色を基準としてやっていこうと思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
