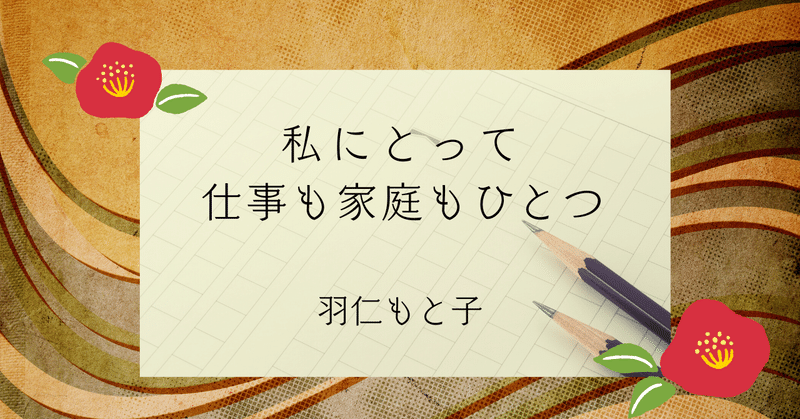
明治女に学ぶ美しい人生のたしなみ*第三回 ひとりでにいま現在(いま)のことがお留守になっている
羽仁もと子
明治6(1873)~昭和32(1957)年。青森県八戸市に生まれる。日本初の女性ジャーナリスト。二番目の夫・吉一と共に明治36年女性雑誌『家庭之友』を創刊、五年後に『婦人之友』と改題し婦人之社を設立。子供向け・年配者向けの雑誌を出版する一方、大正10(1921)年、自由学園を創立し教育に携わる。
私にとって仕事も家庭も一つ
実生活に即した内容の女性生活誌は、私たちの暮らしにすっかり馴染んでいます。しかし明治の頃は、まったく新しい定期刊行物にほかなりませんでした。明治三十六年四月三日に創刊された『婦人の友』(創刊時は『家庭之友』)です。同誌が羽仁夫妻による合作であったという点も注目すべきでしょう。
妻・もと子は執筆を、夫・吉一は経営面を担当しました。まだ仕事を持つ女性に対する風当たりの強い時代に、妻の才能を信じ生かそうとした吉一のあり方を「尻に敷かれている」と見る向きもあるでしょう。けれど私は、むしろ真の男らしささえ感じます。男としての自信がなければできないことだと思うからです。
二人は手を携えながら『家計簿』『子供之友』『明日の友』と創刊、さらには自分達の目指す学校教育実現のため自由学園を創立するまでになります。
一本気な性格のもと子は、時に編集会議の席で吉一の意見を強く斥けるようなこともあったといいます。そんな時は、たいてい吉一が黙ったようです。けれど、後でもと子も反省し、毎回、歩み寄りながら刊行し続けた。夫婦でありながら、同志と呼ぶに相応しい関係だったのでしょう。
私たちの家庭生活は、私たちの仕事の中心点であり、仕事は家庭生活の延長である。二つのものが一つになって分かれ目がない。そこに私たちの事業の特色も家庭の特色もあることを感謝する。ここに来る道筋は険しくても、導かれて私たちの於かれたこの場所こそ、ほんとうに私たちのものであった。
困難が予想されても、なお勇み立っていった
吉一は、もと子にとって二人目の夫です。最初の結婚はわずか半年で離婚となりました。そのことを、もと子は「苦しい事件」としながらも、「色々な困難を予想しながら勇み立った」と回想しています。そして実際、日本で初の女性ジャーナリストの第一歩は、この時に踏み出されたということもできるのです。
「なんとしても書く仕事に就きたい」と考えたもと子は新聞の校正募集に応募するも、女性は募集していないと断られます。それでも二度目の募集に、「女の私が従事してみたい訳」を詳しく書いて履歴書と一緒に提出。すると一日だけ校正を行ってみる機会を与えられたのです。その結果、「男でもこれほど確かな校正ができるものはない」と見事採用となったのでした。
当時、男ばかりの編集局は「動物園」と称されていました。もと子が入っていくと「動物園に女が来た」とはやし立てる声が起こります。もと子はといえば、この境遇が嬉しくて、ひたすら仕事に打ち込むばかり。やがてはやし立てる者はなくなりました。
校正に終始することに飽き足らなかったもと子は、採用されるかどうかはともかく、記事を書いて提出するようになりました。その根気と筆力が認められたのでしょう、ついに専門の記者になることができたのです。
女性ジャーナリスト第一号の誕生でした。

私たちは苦労してはじめて人になり、また人が分かる
開拓者であるもと子には、それ故の苦労もありました。
社会から受けた扱いを約言すると、「侮蔑や反感や一種の虐待は世の中の臆病や負け惜しみや愚痴や無理想から出ており、同情と奨励と助けは世の中の真実と聡明と良心とから出ていた」としています。
しかし、こうした経験こそが、もと子に人間的な深さをもたらすことになりました。
真実とは何か、愛とは、良心とは、勇気とは…。
さまざまな出来事と真摯に向き合い、問いかけては答えを見いだそうと努めることが、彫刻の一彫り一彫りのようにもと子という女性をかたちづくっていったのです。
「涙の多い正直な心で人にもまれると、はじめは味方に対する愛と感謝が深くなり、段々に敵に対しても理解と思いやりが深くなるばかりである。私たちは苦労してはじめて人になり、また人が分かるのである」(同)
過去の自分は客観性を帯び一人の女性として話しかけてくる
晩年、もと子に最後の苦難が訪れました。大戦末期、国家至上主義の只中、キリスト教と自由主義を貫く『婦人之友』に内閣情報局及び陸海軍報道部の圧力にかかったのです。もと子は毎月当局へ出向き、思想が異なっても国を思う真心に変わりないことを主張しました。老体に鞭打ちながらも信念を貫く姿に報道部長はついに心を打たれ、かえってねぎらったほどだったということです。
「私どもは生まれながらの愛国者でした。(中略)私どもはこの国を通し、この国の婦人を通し家庭を通して、ほんとうにこの人の世を愛します」(同)
家庭の主婦として、母として、仕事に携わる女性として、常に読者に寄り添い続けた生涯は、そのものが紛う事なき真実でした。思想や主義など遙かに凌駕し得たでしょう。
道なき道をひたむきに歩き続けたもと子。
その生き方を思うと、静かな勇気が沸き起こってきます。
(初出 月刊『清流』2019年3月号 ※加筆修正2022年8月20日)
※著作権は著者にあります。無断での転載・引用をお控えください
みなさまからいただくサポートは、主に史料や文献の購入、史跡や人物の取材の際に大切に使わせていただき、素晴らしい日本の歴史と伝統の継承に尽力いたします。
