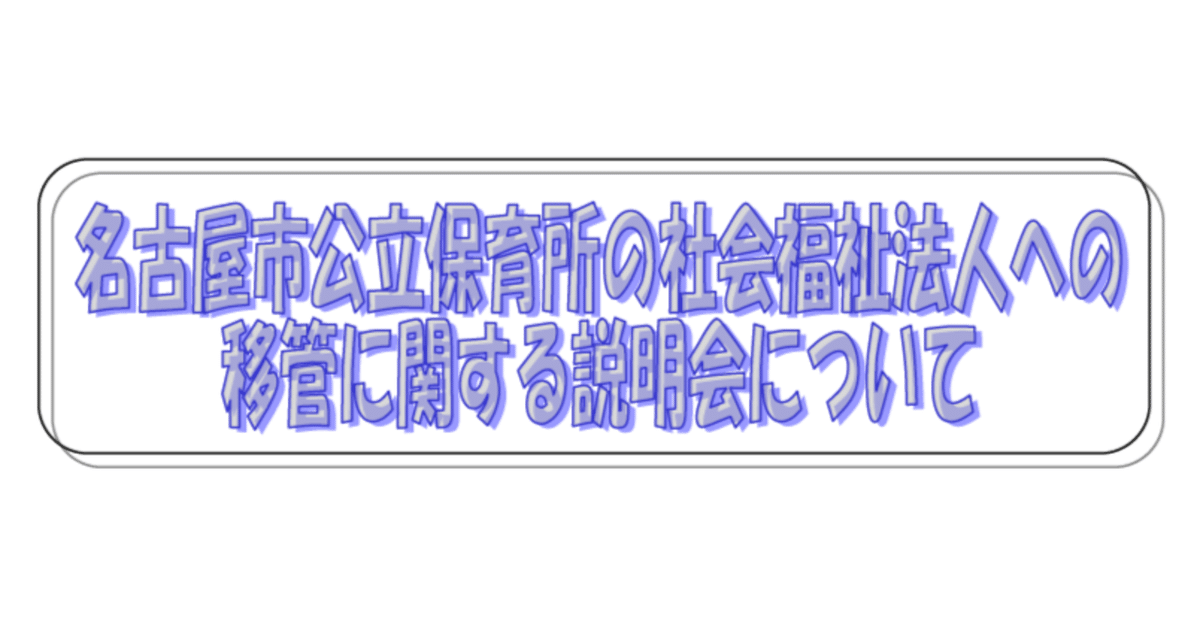
保育施設の第三者評価
公立保育所の民間移管
当法人は、令和3年度に移管先法人として選定をいただき、令和5年度より移管を受けることになりました。
その公募要件には、いまだに疑問を感じています。
公募要件の一つ

「苦情解決の仕組」には違和感を感じません。
現在の公立保育園でも、苦情解決の仕組みは実施されています。
問題は、「第三者評価」です。
それも、「第三者評価」を受けることに疑問を感じているのではありません。他者、第三者から客観的な評価を受けることは重要なことです。
ただ、第三者による評価結果を一つだけ提示されて、その結果を、誰がどのように「評価」するのでしょうか。
評価結果の取扱い
第三者評価は、評価機関が、予め定められた項目、および、評価基準に従って、評価を実施します。
各項目について、A・B・Cの評価結果を判断するのです。
第三者評価を受けるのは、保育内容の向上のためです。
特に最初、3年以内に受ける第三者評価は、公立で継続された、高い保育内容が、民間に移管して、本当に継続されているのかを判断するため、非常に重要な機会になるはずです。
ところが。
名古屋市内の公立保育園は、いまだ1か園も第三者評価を受けていません。
当法人が移管を受ける公立保育園も、第三者評価を受けていません。
過去に評価結果のない保育内容について、私たちが受けた評価結果を提示し、誰が何をどのように評価するのでしょうか。
保育業界における第三者評価に対する空気感
肌感覚として感じるところでは、保育業界での第三者評価は、非常に価値の低いものと受け止めているように感じます。
令和3年12月の新聞記事に、以下のような内容が掲載されていました。
保育所第三者評価6.6%
20年度、12件で実施ゼロ
保育所で質の確保のため実施が努力義務とされている第三者評価を受けたのは、2020年度に全国でわずか6・6%の1570カ所だったことが27日、全国社会福祉協議会(全社協)の集計(暫定値)で分かった。東京都など費用の補助が充実している自治体に集中し、青森、石川、岡山など12県ではゼロだった。
第三者評価を受けるためには、一定のコストがかかります。
コストとは、評価機関に支払う金額だけでなく、職員、保護者の方にお願いするアンケート等の手間も含みます。
第三者評価を受けるためのコストは、費用も時間も含め、保育にかけられるリソースから削り出す必要があります。
その分、本来は価値あるものとし、評価結果を重く受け止め、資質向上に活用しなければなりません。
名古屋市での費用補助は、3年に一度、それも費用の一部のみです。
民間保育所を集めた保育所長等研修会でも施設監査の中でも、第三者評価の受審を強く勧める姿勢は感じられません。
名古屋市の公立保育園は、一ヶ園も受審していないのです。
公立保育園の移管を受けた法人は、貴重な保育のリソースを削り、それだけのコストを払って、第三者評価を受けて、誰にどのようなメリットがあるのか。
私は疑問に感じます。
第三者評価が悪い、と言っているのではありません。
数多くの保育園が第三者評価を受けなければ、保護者は比較検討ができないのではないか、ということです。
少なくとも、公立保育園の民間移管後、3年以内の受審を要件としているのであれば、移管前の評価結果も併せて提示されなければ、保護者にとって、地域の方にとって、評価結果を理解することが困難ではないか、ということです。
皆さんはどのように考えられますか。
マガジンフォローのお願い
社会福祉法人、保育園等に関連する記事をマガジンにまとめています。
興味、関心のある方、是非、マガジンのフォローをよろしくお願いします。
よろしければサポートをお願いします。いただいたサポートは、今後の活動のために有効に活用させていただきます。
