
【スキ考】すきなもの、ひとつ残らず抱きしめて行くの。
「自問自答ファッション通信」あきやあさみさんのこちらのnoteをもとに、これから【なりたい】【似合う】【スキ】を少しずつ考えていきます。
今回は最終回、テーマは【スキ】について。
なぜカタカナなのか。
それは、「好き」は落ち着いていて清らかで秘めたる恋心という感じだけど、「スキ」は熱っぽくて至近距離で囁くような生々しさがあるからです。
つまり、今回湖森はフルスロットルで熱量高めに自分のだいすきなものを語ってゆくぞ、という宣言です。
ちなみに、最初にこの【なりたい】【似合う】【スキ】をそれぞれ思い浮かべたときに、悩んだことがありました。
【なりたい】と【スキ】の違いって?自分の中で境界線ってけっこう曖昧かも…と。
それで、まず手始めに自分にとって一番の【スキ】であることが明白な「読書」を引き合いに出して考えてみました。
私は読書が好き。本を読んでいるときの自分の心の動きを見つめるのが好き。
じゃあ私は「本が好きなワタシ」になりたいか?
それはNO、なぜなら望むまでもなく私はすでにそうなっているから。
つまり、頭の中や心の中で憧れたり興味を持っているだけではなく、「休みのたびに図書館に行って本を読む」「商業ビルに入ったらひとまず本屋に行ってラインナップや店内の雰囲気(その本屋の特色)をチェックする」「たとえ分厚い単行本だろうが、読みたい気分だったらその本を持ち歩いて電車の中で読む」という具体的な行動にうつしているということ。それが「好き」もとい【スキ】なのだと考えます。
さらに言うと、それをやってるときを想像したときにそのビジョンが内側からの風景(自分の目から見た風景/自分の目がカメラになっている)か、外側からの風景(他人の目から見た自分/自分の姿が女優のようにカメラにおさまっているか)、で判断しました。前者が【スキ】で、後者が【なりたい】です。
もっと言うと、誰に強制されたわけでもないのに気づいたら勝手に始めていることが【スキ】だと思います。
うーん、すでにこの記事は大長編になってしまう予感でゾクゾクしてきましたよ…。
※ちなみに今回の【スキ考】ではまったくファッションの話題は出てきません。どうしても「スキ」 なものを考えると、すきなファッションやモデルさんや芸能人というのは思い浮かばなくて(唯一すきな芸能人は阿佐ヶ谷姉妹さんです)。
だからあまり参考にならないかもなので、すみません。
今回の【スキ考】に関しては、自分的にコンセプトやモチーフ関連につながってくるヒントになると思っています。
それでは次に、前回までの【なりたい考+似合う考】を振りかえると、以下の要素と2枚の画像になります。
【なりたい】
どこかに森の深い緑を感じさせる。寓話の世界に入り込んだように幻想的で、かつ体を締めつけないリラックス感あるスタイル。
【似合う】
青い海と空が似合うナチュラルスタイル、カジュアルではなくリッチ感に寄せる。


ここに、最後の仕上げとして【スキ】をプラスしていくため、これから自分のすきなものをすきなだけ語って、整理していきます。
※詳しいやり方は冒頭リンクのあきやさんのnoteをご覧ください。
それでは、今日お話ししたいことの簡単なお品書きを載せます。
どうか湖森のスキを巡る小さな旅に、お付き合いくださいませ…。

それでは小さな旅のはじまり、はじまり。

・
・
・
・
・
・
・
1.「Pure」
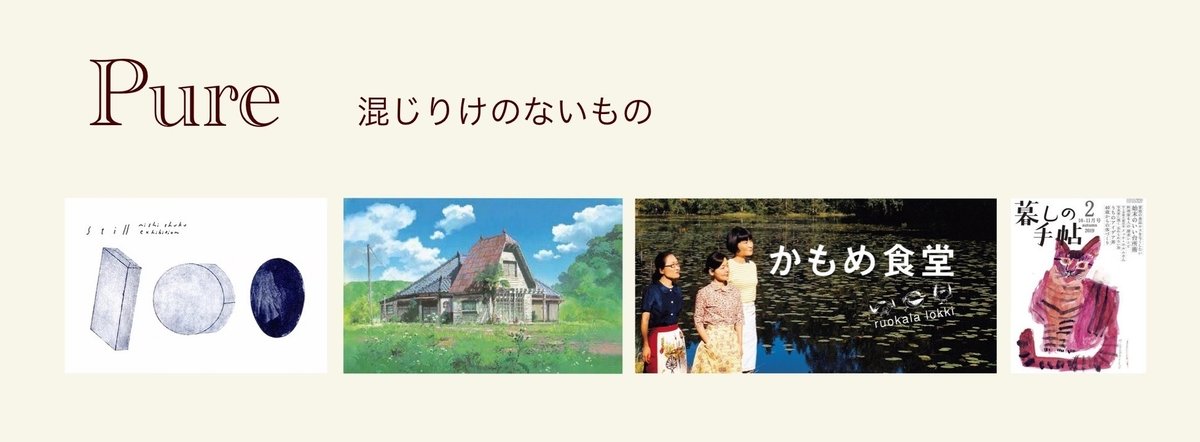
最初のエリアは「Pure -混じりけのないもの- 」です。
作り手の誠実な思いがその作品に素朴な美しさとなって反映されているもの。心が透き通るような軽さと同時に、浮ついたところのない実直で地に足のついた重さもある。
作り手や作品名でいうと(敬称略)、
・西淑(画家、イラストレーター)
・ミロコマチコ(画家、絵本作家)
・トーベ・ヤンソン(画家、児童文学作家、『ムーミン』シリーズの作者)
・宮崎駿(スタジオジブリ監督)
・手嶌葵(歌手)
・kraja(スウェーデンの女性アカペラグループ)
・ダカフェ日記(グラフィックデザイナーの森友治さんがご家族を撮った写真を載せているHP)
・小説『西の魔女が死んだ』(梨木香歩著)
・漫画『くるみ』(深見じゅん作)
・映画『かもめ食堂』
・雑誌『暮しの手帖』
モノやコトでいうと、
・ほうじ茶ラテの味と柔らかい色味
・自家製プレーンクッキー(焦げもご愛嬌)
・レンガ造りの地元の図書館
・文庫本のクリーム色の表紙
・「まどろみ」「木漏れ日」という言葉
似て非なるものとしては、「イノセンス」です。
悪いことを知らない、穢れを知らないイノセントなものには惹かれません。そして、完璧すぎるハッピーエンドにも。
人の弱さも死もいっさい登場しない物語は好みません。
この世にはどうしようもなく哀しくて寂しいものがあるとその人生において身につまされて理解していて、それでもなお背筋を伸ばして「誠実にやっていこうよ」と確かな芯を持って生きている登場人物(または作り手)がスキです。
その声は決して大きくなく、歓心を買える目立つ外見ではなくとも、確かにそこに静かに凛として佇んでいる。
雑踏の中で立ち止まってふと耳を澄ませたときにだけ聴こえる声、私にだけ見える妖精がそこにいる気がするのです。

さあ、それでは景気よくどんどん次のエリアにすすみましょう。
そうだ、お話ししたエリアのことはスタンプを押して記録していきましょう。
なぜなら、湖森は子どもの頃から今に至るまで、イベントのスタンプラリーとレジのバーコードをピッッする機械にはたまらなくエモを感じてしまうから!

スタンプ、ぽんっ!
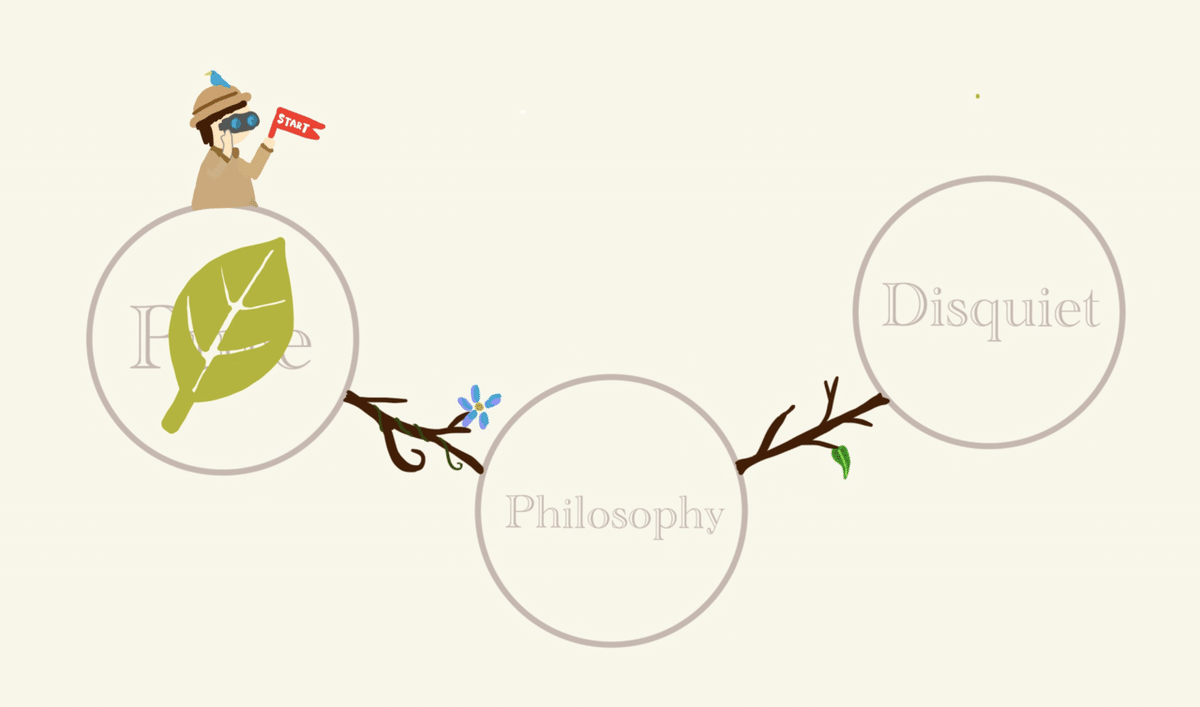
はい、それでは先にゆきましょう。
2.「Philosophy」

次のエリアは「Philosophy -哲学と教養/自分と世界を知る- 」です。
小さな頃は読書といえば小説(フィクション)一筋でしたが、高校生辺りくらいから心理学や哲学についてやさしく書かれた本を読むようになりました。
自己啓発本も嫌いではないのですけど、『嫌われる勇気(古賀史健・岸見一郎共著)』とか『自分の小さな「箱」から脱出する方法(アービンジャー・インスティチュート著)』とか好きなんですけど、失礼ながら起業家に好かれそうな本というか、背後に「成功」「名誉」「人間の価値」みたいなワードが共通言語になってそうな世界が、怖いのです…。(←本自体のことではなく、その本を持て囃している人たちの雰囲気がやや怖いということ。)
そうやって外界に意識が向いているものよりは、内省的な自己理解・自己革新をやさしく柔らかい言葉で説明してくれている本が好きです。
子どもの頃から両親の若干の不仲と姉の病気、中学のとき母を亡くしてからというもの、私の精神はかなり不安定になっていて、いつも自分は青くて暗い丘に建つ小さな山小屋の中に毛布をかぶって丸まっていて、外の強く吹きつける嵐がいずれ過ぎるまではここで耐えしのぶのだ…という風景が心の中にありました。
私はまた、当時母を亡くしてからはとても警戒心みたいなものが強くなっており(なんか野生動物的だナ)、周囲の人のことを誰も信頼しておらず、もともと自己開示が得意ではない(書くことはできるけど喋ることができない)ため、この頃はかなり灰色の時代でした。
私は私自身のカウンセラーになる必要がありました。
だからこそ、心理学の本を読んでセルフケアに励み、恐怖心をなくすためこの世や人間のことを書いた哲学書を読み、大声で叫びたくなるような気持ちを制御することに全神経を注いでました。
そういう理由の始まりであっても、今は純粋に楽しい趣味としてそういったジャンルの本を読んでいます。
ただ、その趣味を大っぴらにすることはできなくて、ごく一部の親しい友人とだけそういう話をするようにしていました。
「哲学」 という響きはなんだかナルシストぽくて、「教養」 という言葉は嫌味っぽくて鼻持ちならない。
だから、こういったものがスキな自分に恥ずかしさ、みたいなものがありました。
そういう気持ちを変えてくれたのが、戸田山和久さんの本『教養の書』(筑摩書房、2020)でした。
文化のもつイヤミで差別的な構造と、文化の多様性と豊かさとは表裏一体である。(略)毒のある土壌に咲いた花のようなものだ。その花にも毒がある。これを知らずに手放しで礼賛するのは能天気だが、その花の美しさに鈍感なのも不幸なことだ。
戸田山和久『教養の書』
キミが大学に行くことの人類にとっての意味は、キミにこうした知的遺産の継承の担い手(リレー走者)になってもらうことだ。このような人々がいないと、人類の幸福な生存は難しくなる。たくさんは無理かもしれないが、一定の人数は絶対に必要だ。キミが学ぶことは人類に必要とされている。
どう、なりたいと思ってくれたかな。なりたいと思ったキミは、それだけですでに「ごく少数の幸福な」若者なのである。
戸田山和久『教養の書』
※太字は筆者による
戸田山さんの本をきっかけに、いまは旧約聖書の勉強をしています。信仰としてではなく、学問としてです。文字から入ると手強そうなので、西洋絵画の宗教画の勉強から入っています。めちゃ楽しい!
今年来年はキリスト教、その次はイスラム教と仏教で三大宗教を学んで、あとはギリシャ神話、北欧神話なども知っていきたいです。
好きなゲームや小説、映画の元ネタにこういったものが潜んでいることがあって、もっとスキなものを深く楽しみたいから勉強することにしました。
戸田山さんはこの本の中で古代ローマの詩人ホラティウスの言葉「Sapere aude」を引用して、英語で言うと「Dare to know.」、日本語だと「勇気をもって賢くあろうぜ」とし、最高にカッコいい標語じゃないかしら?とおっしゃっていて、私もまったく同感なのでこの言葉を座右の銘にしています。
似たような内容で同じく好きなのは、アメリカの神学者ニーバーがつくったとされる「ニーバーの祈り」のこの部分です。
神様、私にお与えください
自分に変えられないものを受け入れる落ち着きを
変えられるものは変えていく勇気を
そして、その二つを見分ける賢さを。
「ニーバーの祈り」
人生の中で困難にぶち当たったとき(わりとしょっちゅう)はこの祈りを思い出します。
私にとっては「困難の中の勇気」というものが大きなキーワードのようです。
さて教養に関して好きな著者は、以下の通り。(敬称略)
・戸田山和久(哲学者)
・梅棹忠夫(人類学者)
・外山滋比古(英文学者)
・黒田龍之助(言語学者)
・アルボムッレ・スマナサーラ(スリランカ上座仏教長老)
・名越康文(精神科医)
以前、あきやさんがtwitterで「人生で嬉しかったこと」のしあわせエピソードを募集されていたときの私のリプもそういえばこうでした。
大学生の頃、あるご年配の教授の講義が面白くていつも講義感想用紙に感じたことや考えたことをビッシリ書いていたら、最終日に「いつも面白い感想をありがとう。あなたのお陰で私は講義をするのがとても楽しかった。」と言われたことです。お互いのリスペクトを交換できたような気持ちになりました。
— 湖森 籠 (@komori__komo) March 6, 2022
やっぱり私は、教養が、学ぶことが大スキで心震えるのだ。
私の原点はやっぱりココにあるんだと思う。
さぁ、次は最後のエリアですね。
そうそう。スタンプも忘れずに。

ぽんっ!

3.「Disquiet」

最後のエリアは「Disquiet -不穏な何か/ざわつく心- 」です。
使われてる画像が全部暗いですね〜。
ホラーというものが全般的にスキで、子どもの頃から祖父のパソコンを借りてはYouTubeで怖い動画を漁ってました。
「Pure」では心穏やかであたたかいもの、「Philosophy」 では理性的で自分の心を制御できるものを求めていると話していたのに、ここでは完全に心をブッ壊しにくるものへの愛を語ります。
それが人間というものの矛盾なのかもしれないし、怖いものを恐れているから怖いものを見たくなる心理なのかもしれませんね。
「人は自分が何から逃げているかわからないときが最も怖い」 という話を聞いたことがあります。
何から自分は逃げているのか、それを見たくなっちゃうんですね。
だから、大雨洪水警報が出ているときに用もないのにわざわざ河川を見に行っちゃう人は実は恐れ知らずのアホなのではなく、ものすごく小心者なのかもしれないですね。
ホラーの中でも何が特に怖いのか、人によって個性はあると思います。
私が怖い(そして大スキ)なのは、「一見かわいらしい世界観なのに実はコワイ」というもの。
以下に挙げるのは必ずしもホラーというジャンルのものではないし、見るからに怖いものもあるのですが、私のスキな作品リストです。
・ゲーム『リトルナイトメア』
・ゲーム『INSIDE』
・アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』
・アニメ『アドベンチャー・タイム』
・映画『シックスセンス』
・映画『シャッターアイランド』
・映画『仄暗い水の底から』
・映画『残穢』
・小説/アニメ『人類は衰退しました』(田中ロミオ著)
・小説『麦の海に沈む果実』(恩田陸著)
・NHKドラマ『六番目の小夜子』(恩田陸原作)
・ドラマ『美しい隣人』
・人形劇『ひょっこりひょうたん島』
・絵本『ミッケ!ゴーストハウス』
・西條八十(詩人)
・北見隆(挿絵家)
キャラクターデザインとかはチマっとしてて愛らしいんですけど、結末や世界観の裏設定が怖いもの。そのギャップがスキです。
ただ、最近では「可愛らしい絵柄なのにグロい」という作品は珍しくなく、それらすべてに魅力を感じるかというとそうではありません。
上記に挙げたものの一部は、子どもの頃に見て幼心に衝撃を受けたものです。
原体験的な恐怖というか、大げさな言い方をすれば「トラウマ」でしょうか。そういうノスタルジックな恐怖がスキなんだと思います。
『ひょっこりひょうたん島』は人形の造形がすでにトラウマチックなのですが、大人になってから「ひょっこりひょうたん島のメイン登場人物は全員1話の時点で死んでいる」という裏設定を知ってからはさらに恐怖(そして愛)が加速しています。
よくある都市伝説ではなく、原作者の方が公表しています。彼らはみんな1話のひょうたん火山の噴火で死んじゃいました。死んでるから食料問題には困らないんですね。
作者は、「ひょっこりひょうたん島の登場人物たちの底抜けの明るさは死後の世界の明るさ、絶望の果ての明るさなのです。」と言っていたそうです。
この「絶望の果ての明るさ」という言葉に、私はすごく勇気づけられています。
すごくタフで、強い発想だと思うんですよね。
哀しいことを哀しいままで終わらせない、諦めの先にある平穏。
ゲーム『リトルナイトメア』についてはスキを超えてもはや愛でして、も〜〜〜世界観がたまらないんですよ!

似た雰囲気だとティム・バートンの『ナイトメア・ビフォア・クリスマス』もありますね。私はナイトメア(悪夢)な世界観がスキなようです。
ただ、やはり素朴でやさしいもの・知的なものを好んでいるのにこういった一種グロテスクな作品構造やキャラクターデザインに惹かれていることにも罪悪感がありまして。
そこを、精神科医の名越康文先生の言葉で救われました。
名越先生ってお顔を見れば「TVで見たことある!」っていう先生かと思うのですが、すごく人間性があたたかくて茶目っ気があって、「人生を楽しもう!」という姿勢が尊敬できる方なんですよね。
料理研究家の土井善晴先生に似てるな〜とも感じます。
他人を「ええやん!偉いやん!それでええんやで。」とやさしく認めてくれる器の広さが似ています。
まさにこの『リトルナイトメア』のゲームを名越先生がプレイ動画を観ながら精神科医として分析・解説していこうという企画の動画内でのお話しです。
詳しくはゲームのネタバレになってしまうので書けませんが、ニュアンスとしては「悲劇的で業の深い、一種グロテスク的なものが昇華されていくさまに触れることでしか、癒やされない心がある。暖められない身体感覚がある。」(めちゃくちゃ意訳してます)ということ。
これがすごく自分の心を言い当てられてるなぁと思いました(動画中では登場キャラクターの心理分析をしたときのご発言です)。
怖い雰囲気の音楽(私はドラマ『六番目の小夜子』のOPのこの曲がダイスキ!)を聴くと不思議と心が凪いだ気持ちになるのは、てっきり厨二病だからかと思ってたんですが、あぁ癒やされてたんだなぁと静かに腑に落ちました。
そして、あと私がとてもスキなのは廃墟!
廃墟はとても美しいですね…。


あそこにいるのは死者(幽霊)ではなく生者の念や記憶がミルフィーユ状に重なってできた層のようなものだと思います。
地元に何件か、廃屋になった木造一軒家があるのですが(たぶん誰も住んでない…と思う…)、通り過ぎるときは横目で見つつその退廃的な美しさにドキドキしています。
廃墟を突き破っていく植物の強さもすきです。
ここのところは、今後自分のコンセプトにもリンクしてくるところなのかもなと予感しています。
終わった場所で新しい命が芽吹いていく、そのコントラストが残酷で美しいなと感じます。
これも言いようによっては「ある種グロテスクなものが昇華されていくさま」とカテゴライズできるのかもしれないですね。
また、あるいは「絶望の果ての(底抜けな)明るさ」とも言えるかもしれません。
…ここが一番熱量強めでしたね。若干息切れ気味です。ふぅ。
まぁひとまずはスタンプを。
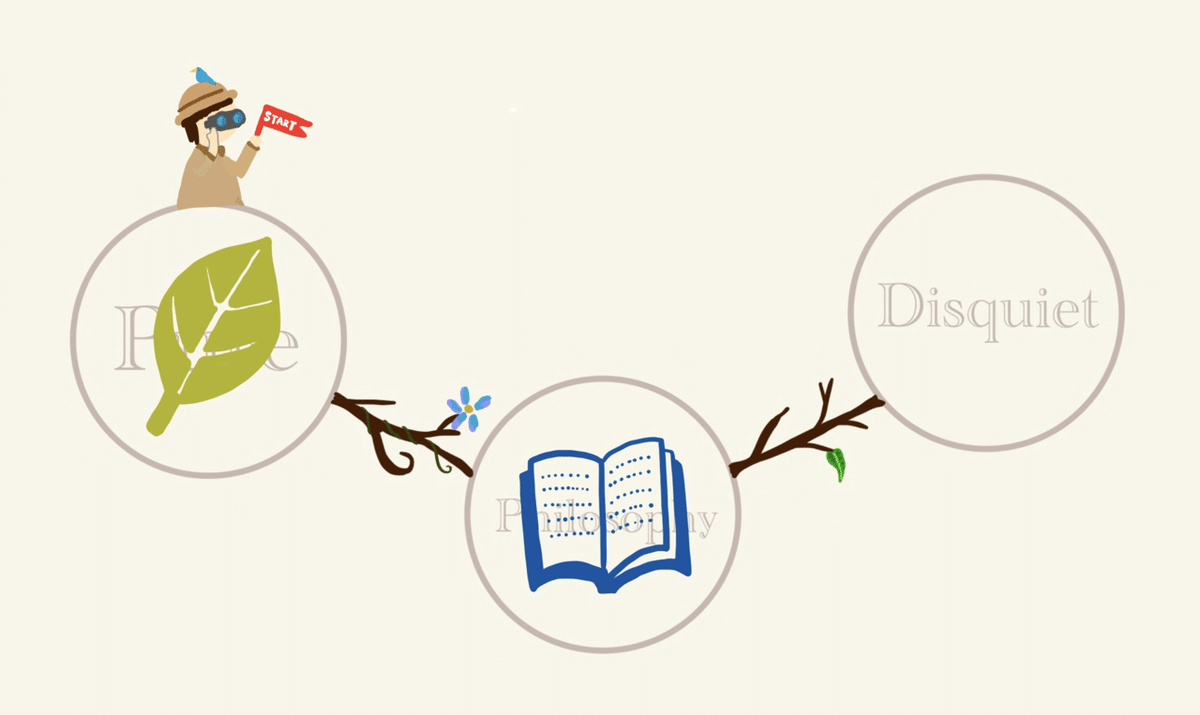
ぽんっ!

ギャッ!怖い!
恨めしそうな目をしてますね〜…。
おや?先に続く道ができました。
どうやら廃線になった線路のようです。
何があるかわかりませんが、この線路を進んでみましょう。
靴紐も心も、いま一度しっかり引きしめて。
・
・
・
・
・
・

おやおや!ここは…?
初めて来るのになんだか懐かしくて不思議と安心する場所です…。
そう、ここは今回の【スキ】を巡る小さな旅の終着地点。
これまでの【なりたい】【似合う】【スキ】のすべてがやさしく溶けあった場所、スウェーデンのどこか深い森の中にある私だけの湖、その湖のほとりに建つ「木漏れ日ツリーハウス」です。
長い旅はひとまずお終い。
もうすっかり夜になってしまいましたね。

「木漏れ日ツリーハウス」は、大きな樹の上にある私の小さなお城。私以外には人の住まない湖畔だから、家にはドアも鍵もありません。
たまに枯れ葉が入り込んだり、野生動物たちがベットで眠っているのはご愛嬌。

テラスでは日除けパラソルの下でのんびりしながら読書をします(私は椅子にキチンと背筋を伸ばして座ったまま本を読むことができないタイプ…)。
夜になったらランタンを置いて、夜風に当たりながら星空を見上げ、デタラメな星座をつくりましょう。お酒が飲めないから、シュワシュワのソーダ水をお供にね。

湖畔には水辺の仲間やヘラジカたちがたくさん生息しています。
ブランコに乗って風を浴びながら、ときには森の中にある図書館に行って、物語の世界に没入しましょう。
人生にはフィクションが必要不可欠だから。

湖と森も好きだけど、本命は森の図書館。もちろん妄想で、ファンタジーだけど。雨とか虫食いとか丸無視で(だって妄想だから)、だから天井なんかない。黄緑色の晴れやかな木々に囲まれて、ただ本棚が立ち並んでいて、いろんなデザインの木製チェアが置いてあって、いろんな本が美しく並べられている。
— 湖森 籠 (@komori__komo) March 20, 2022
そして、大きな樹の根もとにあるこの不思議な扉。

この扉の向こう側はまだ誰も見たことがありません。果たして何が入っているのか、それともどこか別の世界に繋がっているのか。
私の好きな心理学の概念に「ジョハリの窓」というものがあります。
ひとりの人間の内面を4つの窓にわけて考えるこの心理学モデル。
人間が自分というものを認識するときに、実は自己認識できている部分だけでそれが形成されているのではなく、「他人しか知らない私」という面もあったりします。

そして、他人にも自分自身にも認識することのできない面、それを「未知の窓」といいます。
いまだ花開いていない、開発されていない自分の能力や魅力。中身はカオスなのかもしれないし、はたまた空っぽなんてこともあるかもしれない。
それは誰にもわかりません。
しかし、もしかしたら生涯この世の誰一人も解き明かすことのできない謎が自分の中にあると思うと、なんだかワクワクしませんか?
自問自答をし尽くしても、それでも最後まで解き明かされない自分の一面。それは、自分の可能性であり、人生の希望です。
それがあることを知っていて、信じていることで自分という人間をもっと愛せると思うのです。
「おかえりなさい」という言葉にあるように、この場所はゴールではなく、私が思考の小冒険に行ったあとに帰ってきてはひと休みをする、そんな場所です。
この安全地帯でゆっくり休んだら、また小さな冒険に繰り出していきます。なぜならまだコンセプトもモチーフも制服も決まってないからね。
これからもTwitterやnoteで、さまざまなことを自問自答していきます。でも、もし自分の「軸」を見失って迷子になってしまったときは、この湖畔に戻ってきます。この場所は常に私の心の中にあるからです。
ここまで読んでくださって、どうもありがとう。
・
・
・
・
・
おや?
暗闇に乗じて、森の木々の影を縫うように彷徨う「何か」がいます。

フードを深く被ったアレは一体何者でしょうか?
…きっとこの世の者ではありませんね。
どうかヘラジカの住処より奥の森へは足を踏み入れないで。
アレと目があってしまったら、きっと生きて戻ってはこれませんから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
