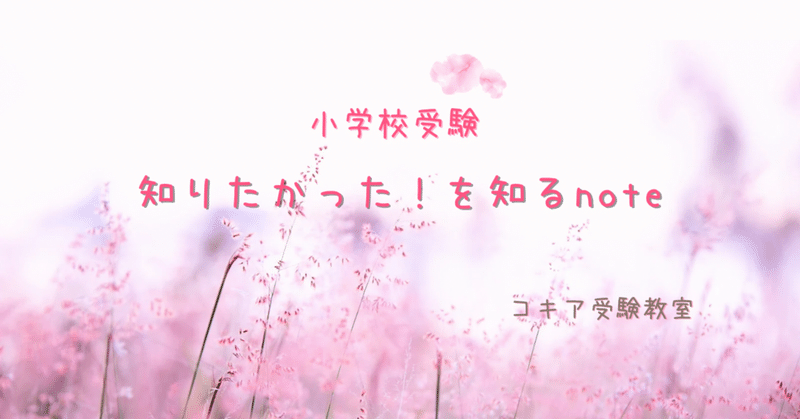
小学校受験 発問の意味が理解できない
こんにちは。コキア受験教室の桜井です。
今日は、発問の理解について少しお話したいなと思います。
模試の講評の中で、大きく落とした問題の原因を伺ってみると、よく「発問の意味が分からなかったみたいで…」という話を聞きます。
(度々あるお話なので、特定の誰かの話ではありません。)
そして、たいていの場合、家で問題を説明してやるとスラスラ解けるようです。だから、親は「解けないわけじゃないのね」と安心しがちです。
でもですね、私としては、発問の意味が分からなかった方が大問題で、単に「その問題が難しくて解けなかった」という方が、ずっと楽観できると実は思っています。
なぜなら、本来解けるはずのものが、というか、親がもうすっかり分かっているものだと思っているものが、問題によってはマルッと解けない可能性があるということですから…どう対策したらいいか迷子になりそうです。
さて、どう対策しましょうか。
対策をするためには、まず原因を探らねばなりませんが、原因として考えられるのは、恐らく経験不足というところに集約されると私は思っています。
同じ問題集しか使ってこなかったり、自塾でしか模試もやっていなかったり。あるいは、単純に取組み数が少ないということが考えられます。
というのは、ある程度の問題数をこなして来た場合、だいたい問題を見た瞬間に「こういう問題かな?」という当たりがつくようになるものだからです。
ですから、この場合、つまり、本来であれば十分に解けるレベルに達しているのに問題を理解できていない場合、通常は「数をこなしましょう」というアドバイスをさせていただいています。
これは、やみくもに量を増やせという話ではなく、同じレベルの類題をやりましょうということです。
例えば、図形分割の基礎が終わったとします。通常は少しレベルアップしたものに手を出したくなるものですが、なるべく同じくらいのレベルのもので別の問題集をやらせるということですね。発問のパターン学習です。
また、コキアでは、こういった「まさか」に備えるため、積極的な外部模試の受験をお勧めしています。
慣れていない問題や環境にも対応できるか確認し、もしできるはずの問題で大きく落としているようであれば、原因を探って対策を考えていきましょうね。
個別相談では模試の講評もさせていただいておりますので、受けっぱなしにしないためにも、是非お申し込みいただければと思います。
そして、こちらは余談ですが、うちの下の子が、この件について面白いことを言っていました。
「問題を先に読まないで、本人に答案を見て問題を予想させれば良いんじゃないの」と。
これを聞いて、私、ちょっとハッとしましたよ。
先ほど、「ある程度の問題数をこなして来た場合、だいたい問題を見た瞬間に当たりがつくようになる」と書きました。
だとすると、確かに回答用紙を見て問題を言わせてみるのも手です。
例えば、回答用紙に同じ大きさのリンゴが8個並んでいる絵があったら…さて、その絵を見て考えうる問題はなんでしょうか。
お子様の作った問題もあり得るなら「なるほどね!確かにあり得る!」として、それで解いてみても良いかも。その上で、「実は、こういう問題でした!」と言って、それも解かせる。
そうすることで、問題はきちんと聞かなければ正しく解けないことも分かりますし、パターン学習を能動的に行うことができることにもなります。表現力という意味でも、とても意味がありそうです。
なかなか面白いアイデアだったので、やってみる価値があるなと思いましたよ!
試行錯誤しながら、苦手克服に向けて一緒に頑張っていきましょうね。
☆学習についてのご相談は、LINEでお気軽にどうぞ(無料です)☆
☆当教室の主催する講座については、アメブロでご確認ください☆
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
