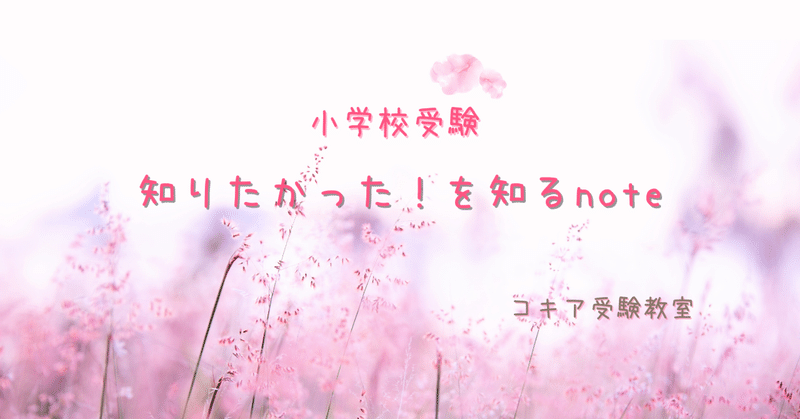
小学校受験 自己肯定感と心のチクチク
こんにちは。コキア受験教室の桜井です。
今日は、先日、コキアで広報をしてくれている鈴木さんとお話していたことを少し書こうかなと思います。
何を話していたかというと、自分の子どもたちの学校生活やなんかの雑談だったのですが、「何かに秀でるって大変だよね」という結論に至った話です。
ある人気校の先生が前に仰っていたことでもあるのですが、小学校受験で人気校に合格して進学する子どもたちというのは、受験日現在において比較的色々なことができてきたお子様が多いわけです。
幼稚園でも、圧倒的に運動ができて、圧倒的に知識があって、圧倒的に理解力もある。
超人気校に進学するということは、「すごいね」と言われ続けてきた子どもが、小学校入学と同時に学内偏差値50になる世界線が待っているということです。
そして、一貫校に行こうものなら、もう堰を切ったように各々が自分の能力を伸ばし続ける。
運動が超人的にできる子、漢字や英語を極めてしまう子、楽器や絵のコンクールで入賞する子、先生にいつも褒められる子、常に友達の輪の中心にいる子、何かの代表に選ばれる子…
みんな、どうやって「人より秀でるもの」を探したのか教えてほしい。なんだか、周囲はみんな何かに長けている気がするのに、自分の子には取り立てて「誰よりもできる」がない気がする。
これは、なにも小学校だけではなく、中高大…そして就職先でも、友人間でも、ママ友間でも、起こりうることです。
さて、皆さん。ここで素直にブラックな自分を出してみましょう。
お友達の成功って素直に祝えますか?祝えますよね。
では、自分が満たされていない時も祝えますか?心から?
我が子を差し置いていつも選ばれる誰かに、「なんであの子ばっかり」という気持ちを抱かず祝福ってできますか。それまで、我が子は常に「選ばれる側」だったのに。
私は、世の中で一番怖いものは「人の嫉妬」だと思っています。(ですから、合格報告は最新の注意を払いましょうね。)
まぁ、さすがに我が子の学校でのことで嫉妬というほど強い気持ちになるわけではないのですが、「そうかぁ、あの子はすごいな」とか「うちの子が秀でているところってどこだろう」とか…
小さな羨望とともに、小さな劣等感。
そういう小さなジャブを毎日受けます。親も子も。
東大出身で、今やある業界のトップにいらっしゃる方がいます。私の元上司です。その人は、元々東大の理系に現役で入学されたんですけど「理系ではトップになれない」と18で悟り、東大の文系に文転されて今の地位に至ります。(身バレするとご迷惑なので、はっきり言えずすみません。)
私から見たら、東大の理系ってだけでトップオブトップです。田舎では神童と言われていたそうですよ。本当にいるんですね、神童って呼ばれる人間…。
でも、その方でさえ、もっと上がいるということを知ったと。
結局、そういうことかなって思います。きっと、あなたが羨望の気持ちで見ていた人にも、劣等感を感じるポイントはある。
これからの人生で、皆さんのお子様もこういう小さなジャブを日々受けることになります。
希望した会社に入れなかった、親友が先に結婚した、同期が先に出世した…そんな「選ばれなかった側」になることは当然誰しもがあり得る。
そんなときに、
・自分の力のなさを嘆いて「どうせ自分なんか」と不貞腐れるのか
・相手に「ずるい」という感情を抱いて嫌悪感を抱くのか
・「よし、自分も!」と自分を奮い立たせてそこに続くのか
・「だったら、自分は他で力を尽くす!」と新たな道を探すのか…
その先の人生って、それで結構違ってくると思いませんか。
よく志望動機で「切磋琢磨してほしい」という言葉を使うのですが、切磋琢磨には、こうした小さな心のチクチクが伴うものなのかなって思います。
親も、心の持ち方を試されますよ。
全てにおいて優秀だと思っていた我が子が、「世間的にはそうでもない」と認めるのは親として勇気が必要です。
それでも、きっと我が子の伸ばすべき「個性」というものは存在していて、それはもしかしたら小さく目立たないものかもしれないけれど、親だけは誰よりも早くそれに気づいてあげたいですね。
そして、皆ができることに「何故あなたはできないの!」と責めることなく、他の誰かが選ばれたことになるべく心から賛辞を示す余裕を持ちたいものです。
それが、きっと我が子の「自己肯定感」に繋がるのではないかな、と。
生まれる前には「元気に生まれてくれさえすれば」と願い、生まれた瞬間には「笑顔で過ごしてくれさえすれば」と願ったはずなのに…親というものはついつい欲が出てしまいますね。日々勉強と反省。
まずは、我が子の心の健康を育んでいかねば。
☆学習についてのご相談は、LINEでお気軽にどうぞ(無料です)☆
☆当教室の主催する講座については、アメブロでご確認ください☆
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
