
山梨インカレ~Inter College 2021~
はじめに
1年ぶりのインカレ、山梨インカレの幕が昨日降り、圧倒的非日常から日常に戻った私です。少し落ち着いてきたので山梨インカレについてのこと、また4月からのチームづくりについても語らせていただきます。
インカレを語る上でそれ以前の話はなくてはならないものです。

今年のインカレ、中央大学がまさに圧倒的な実力を示し優勝しました。
我々筑波大学は
1回戦vs岐阜聖徳大学27-19○
2回戦vs愛知大学34-21○
3回戦vs明治大学28-20○
準決勝vs中央大学25-35●

準決勝で今シーズン2敗している中央大学に敗れて3位という結果で大会を終えることになりました。
今年は去年に引き続きコロナの影響で上半期にゲームらしいゲームがほとんどできませんでした、春リーグは1試合のみ、夏に東海大学とのフレンドリーマッチを経験できましたが、その後キープレーヤーの一人であり、藤代紫水の愛すべき後輩である榎本悠雅がハンガリーへと旅立ち、実践的な場でチームをトレーニングできたのは8月の後半に入ってからでした。
それでも私たちは秋リーグを9試合全て戦い抜く中でチームの方向性を見定め、その精度を高めることができました。そんなことすら満足に叶わなかった西のチームは本当に大変だったと思います。
それぞれの地域で異なる条件(ゲームの量やトレーニングの量の差)での大会になってしまっては、インカレ自体の価値だって下がってしまうだろう、そう思っていたのですが、大阪体育大学が決勝まで進んでくれたことでその考えは杞憂であると証明してくれました。苦しいゲームを何度もものにする勝負強さには本当に胸を打たれ、コーチとしてどのようにチームを作っているのかとても興味が湧きました。
しかしながらゲーム数が少ないことは明らかで、インカレを通して急成長をするチームが我々含め多く見られるのは「同じような力の相手と激闘を60分間繰り広げる」からです。
ゲームをしてみて初めてわかることは本当に多くあり、成功したことはもちろん、失敗だって大きな糧になります。
今季我々は春リーグからインカレを含む公式戦は18ゲームです。インカレ前までだと14。最低でも25は欲しいと感じました。25ゲームがチームがいろんな遠回りをしながら着実と力をつけ、成熟していくまでの最低ゲーム数だと思います。欲を言えば35ゲーム...これだけあればコアメンバーだけでなく16人全員をゲームに自信を持って送り出せる選手に育てる自信が生まれるゲーム数です。
ゲームでの経験が大事なのは選手だけではありません、コーチだって同じです。18ゲーム戦って、周囲の力を借りながらなんとか戦ってきた私ですが、ヘッドコーチとして責任を全うすることが何よりの経験になりました。

『藤本先生じゃなくて浩壽がAつけてるんだ(ゲーム中の役員番号)』
何度も声をかけられました、なぜなら一般的にはあまりない?ことだからです。ではなぜ自分がその役割を?という話を次にしていきます。
突如訪れた"機会"
前任の福田コーチ(現アランマーレヘッドコーチ)がチームを離れることが決まったのが4月3日、練習試合の2日目でした。あとに控える春リーグの開幕戦は17日、私がこの試合で指揮を取ることが決まりました。
福田コーチは私の大先輩、つくば市出身で学園HCから手代木中学校のいわゆる地元の同郷です。高い観察力と選手の気持ちに寄り添いながら積極的なゲーム運びが出来る素敵すぎる人です。

徳田新之介さんたちがプレーしていた2017年度まではゲームの指揮を取るのはローランドでした。2018年度にローランドが法政大学に移ってからは藤本先生が指揮をっていましたが、2019年から福田コーチが本格的にヘッドコーチに。
藤本先生曰く、自分では考えつかなかったり、踏み切れない思い切った采配ができるから。一歩下がったところからチーム全体を見ている方が性に合っている。と。
こんなことを言っては野暮ですが。やはり、私たち若い人間に経験を積ませることを考えてくださっているのだと思います。
そんな右も左も分からない状態からこのチームのコーチングをスタートしました。
それ以前、デンマークから帰って1年間はコーチアシスタントとしてチームに携わり自分なりにトレーニングを組みながら、どうしたら強いチームにすることができるのか考えていましたので、いろんなインスピレーションは既に湧いていました。
しかし、思うこととやってみるとは全くの別物。次章ではそんな内容にフォーカスしていきたいと思います。
井の中の蛙の腹の中のミミズ
”井の中の蛙大海を知らず”
中国から伝来したと言われるこの言葉をご存知でしょうか。
「井戸の中にいる蛙はずっと狭い世界しか見たことがなく海を見たことがないため、視野が狭くありきたりの知識しかない」
浅いなお前、そんな時に使われるネガティブフレーズです。
私はまさに井の中の蛙どころか、蛙の腹の中にいるミミズだったとこのシーズンを通して感じました。
筑波大学を井戸の中と表現してしまうことは少々どころか大分言葉に語弊があります(断言)が、私の存在自体それほど小さく、また非力なものでした。
これまで私は自分が経験したことを使えばチームが強くなると思っていました、しかしその過程には選手たちとのコミュニケーションがあったり、チーム運営があったり、コンディショニングがあったり、強くなっていくために必要な条件を揃えるために多くの人が関わっていることを見えていたはずなのに感じられていませんでした。
海で悠々と泳いでいると思っていたミミズ(そんなミミズはいねえ)は井戸の中どころか蛙の腹さえも出ることができていませんでした。そんな私を井戸の水の中まで助け出してくれたのがスタッフ陣であったり選手たちでした。
”井の中の蛙大海を知らず”
この言葉は日本に伝来してから続きが作られたそうです。
"井の中の蛙大海を知らず,されど空の深さ(青さ)を知る"
たとえ狭い世界だったとしても突き詰めて取り組めば深いところまで知ることができる。そんな意味があるそうです。
この数ヶ月筑波のハンドボールにのめり込み、チームに出来ることを全てやったつもりでした。しかし、振り返ってみればもっと出来ることがあったと思ってしまいます。それがこのチーム、ハンドボールの深さであり、突き詰めたからこそ得られた、また見ることができた「青さ」であると感じます。
だからこそ、もっと広い世界でいろんな花やどでかい木を見てみたい。
今はそんな気分です。

勝ってから言いたいことがたくさんあった
2019年に筑波大学がインカレで優勝したとき、私はデンマークに留学しており、優勝の瞬間に彼らと一緒にいることができませんでした。
優勝した後から良い意味でチームの雰囲気が変わりました。
自信を持って自分たちの活動を広めたいと考えるようになり、SNSについては時代の流れが大きいと思いますが、実際にYouTubeを始めたりTwitterやInstagramを積極的に更新するようになりました。
それまで筑波がやってきた取り組みはとても素晴らしいものだったと自負しています、ただインカレで結果を出せていなかったせいか、選手の中にも後ろめたさのようなものがあったかもしれません、これは私の勝手な感想です。
私たちには理念があります、筑波のハンドボールを、取り組みを世の中に発信していく、それによってハンドボール界そのものをより良くしていこうという考えです。それらを根底に、目指すべき目標をリーグ優勝、またインカレ優勝に設定しています。

私たちが皆さんに理念を共感してもらうためには勝つことが必須、勝てないチームのいうことなんて当てにならない、というのがひどい言い方をしたときの一般的な見解でしょう。
そして2019年、筑波は悲願の優勝を果たします。
つまり、私はチーム筑波の中で唯一、優勝を知らない人間でした。
勝ちたかった。
本当に素晴らしい取り組みをしていると思います。それはよく色んな人から言ってもらえることです。
だからこそ、負けたとしても発信し続けます。また勝つまで発信すれば、負けさえもプロセスの一部としてチームのさらなる進化に貢献することができるでしょう。
この学生界のどこに試合前のミーティングに監督の言葉が「頑張ろう!」のみで成立してしまうチームがあるでしょうか、それは選手一人ひとりがハンドボール観をしっかり持っており、私たち学生コーチ陣がチームの先頭に立って引っ張っているからです。監督である藤本先生は裏でしっかりとチームをコントロールしながら、私たちコーチ陣、また選手が自分たちの力で立って歩けるようにしてくれているのです。私たち自身が自分の力で歩き出したと思い込むほどに。
このチームを一枚の「絵」だとしましょう。「絵」を描いているのは間違いなく私たち学生です。ただ、パレットやら画用紙やら絵を描くアトリエから全てを準備し、私たちにギリギリ気付かせないように絶妙な色をパレットに配合し、絵を描かせた上で「この絵を描いたのは君たちだ、素晴らしい」と言い放ってしまう。
これが藤本先生です。
Road to Intercollege
インカレで印象に残ったゲームの一つ、3回戦の明治大学戦について。
明治大学とは秋リーグの前に行ったインカレシード決定戦、秋リーグと2戦しておりどちらも筑波が勝利していました。能力のある選手たちを抱えていましたがどことなく噛み合わない印象でした。しかし、インカレでは全く印象の違うチームになっていました。

攻撃が整理され、ゴールキーパー高橋選手を中心としたディフェンス、守れればウィングが奥に素早く位置を取り、可児選手が力強く相手コーチを脅かす、そんな明治に前半こそ安全圏でリードを保っていたものの後半15分ごろ、2点差まで詰め寄られます。
しかし筑波は守りでは矢野とGK鈴木(たけ)を中心に、硬い守りを維持。特に後半のたけのセービングは50%、それだけでゲームを勝たせてしまうほどの数字です。攻撃ではエースの藤川が躍動、手詰まりだった攻撃に光がさします。

このゲームはインカレで初めて藤川をフルで起用しました。抜く時間帯がありませんでしたね。
このチームが始まって以来、コアなメンバーの精度が高いことはわかっていました。しかし、戦わなければいけないリーグは長い。7人だけで戦い続けられる状態ではありませんでした。
そこでバックアップメンバーの制度をどれだけ高められるかがこのチームの1番の課題でもありました。そのため、秋リーグの前に行われたインカレシード決定戦では立ち上がりからメンバーを大きく変え、多くの選手が実践の場で経験を積むことができるようにチームづくりを進めてきました。


もちろんすんなりとうまくいくことはありませんでした、コアなメンバーが下がるとチームの勢いは衰え、チーム全体にストレスフルな時間が続きます。
それもそのはず、コアメンバーはバックアップメンバーに対して精度を要求し続ける、バックアップメンバーは経験が乏しい中で切迫した状況に放り込まれパフォーマンスがうまく発揮できない。仲違いのような状態になりました。
私は秋リーグ中、口酸っぱく言い続けていたことがあります。
「この筑波大にはAチームもBチームも存在しない、もしAやBを作るなら違うディビジョンで試合ができるはず、そうしていないのは全員でチーム筑波だから」
綺麗事に聞こえますか?逆です。厳しいんです。
たとえ実力的に劣っていたとしても、ゲームに出て活躍することを目指し続けなければこのチームに在籍する資格がないということですから。
このことは1年生でチームに入部する前に藤本先生から話があります。
「やるかやらないかは選べる」と。
その下地があったからこそ、私は選手を大胆に起用できるのです。
そうして秋リーグでは苦しい時間帯であっても選手を回し、ゲームが成立するように持っていったつもりです、選手たちにはストレスをかけたかもしれませんが、全てはインカレで5試合全て戦い抜くため。
明治戦で藤川がフル出場できたのはそれまでの2試合でかなり休むことができていたからです、そこで彼の代わりに出場した2年生の関や、3年生の山田は来年も楽しみな選手たちに成長してくれるでしょう。


戦う戦士たち、支える戦士たち
それでもインカレ中はサポートに徹してくれた選手たちがいます。
メンバーの20人に入ることが叶わなかった選手たちはコート外でチームにどんな貢献ができるのか考え抜いてくれました。
毎年恒例なのが「モチベーションビデオ班」です。


今年は2年生の林が2年前のインカレで応援隊長だった現4年の町田からその役職を譲り受け、ビデオ作成を中心になって進めてくれました。
毎朝彼の顔がげっそりしていきご飯も食べられなくなって(もともと?)、話を聞くと数時間しか睡眠を取ることができなかったそうです。
今年から入部してくれた外部の広報スタッフたちの奮闘もあり、今大会の広報またモチベは本当に素晴らしかったと思います。
一つひとつが選手たちの力になり、筑波を応援してくれる周囲の方達まで巻き込むムーブメントを作ってくれました。とても簡単なことではありません、そこにはキャプテンの朝野も関わっていて彼のバイタリティには尊敬の念を抱きます。
そんなサポート班も一人のチーム筑波で戦う戦士たちです。
彼らが1年後、2年後にゲームに出て活躍する選手になれば、彼ら自身が語れる人間になれるでしょうし、これからも筑波大のハンドボール部は素晴らしいチームであり続けられることでしょう。
キャプテンが去ったあと
準決勝の中央大学戦、前半20分過ぎ不慮のアクシデントとはいえ、朝野が失格判定を受けてコートを去ることになります。今までチームの精神的な支柱であった彼がもうコートに居られない、その現実を私たちコーチ陣含めて受け入れきれていませんでした。
直後に離されかけ、タイムアウトを取り、なんとか食らいつきましたが前半終了して4点差。ハーフタイムにも重い空気が流れていました。
私自身、どんな声かけ、またゲームの方向性を示そうか悩んでいましたが、矢野の言葉がチームの雰囲気を一変させました。
「こんな暗かったら勝たれへんわ笑もっと明るくいこ」
その言葉にチームが同調し、一つになった感じがして、本当に驚かされたというか、その場で泣きそうになりました。
ハーフタイム明け、観客席にいる朝野に向かって全員で拳を突き上げた頃には4点差なんて本当にちっぽけなものだと思えるようになったほどです。

後半10分過ぎ、1点差まで詰め寄る場面、ゲームを見てもらったらわかると思いますが全員大笑いしながら戦っています。あの時間、私は「がんばれ!」しか言えませんでした。



ここで勝ち越せることが出来れば筑波のただのハッピーストーリーですが、現実はリアルです。中央大学の完成度はそのさらに上をいきました。
皆さん、中央大学の強さは圧倒的な個人の力だと思っていると思います。私もつい先日までそう思っていました。
しかし、準決勝を戦ってそれだけではないと確信しました。
個人だけのチームなら私のゲームプランで必ず勝つことができました。
その想定を上回ったチーム戦術、戦略を司っていたのが監督である実方さん、またセンターバックの中村選手です。
このチームに負けてしまうのなら、胸を張っていられる。そんなコーチ失格なことを考えてしまうほど、良いチームでした。
リベンジの機会がもうないことが最も残念なことです。
さいごに
インカレで勝って行くたびに成長する選手たちを見ました。ゲームをすることが最も必要なトレーニングなのです。その経験をコアなメンバーだけでなく、もっと多くの選手たちに経験させてあげられないことが残念でなりません。
戦うチャンスさえあれば、もっと成長できる。
リーグ戦だって9試合だけじゃコアメンバーだけで戦えてしまう。
3ヶ月で18試合だったなら?2週間に3回のゲームをすることができます。
多くのゲームをするためならば、私たちは会場設営だって片付けだって、やります。松やにを使ってゲームができるなら、全員で松やに掃除をします。
リーグや大会の運営が大変なのはよく話を聞くので。。今現在尽力されている方々のことを悪く言いたいのではありません、ただ、ハンドボーラーたちの、日本のハンドボールの未来のためにもっと変えていけることはあるはずです。
無知で何者でもない人間だからこそ言い放つことができる戯言です。
どうか聞き流してください。
改めて、コロナ禍の中で開催に踏み切って下さった山梨研ハンドボール協会の方々、ありがとうございました。久しぶりのインカレはやはり素晴らしい舞台でした。

これからも学生ハンドボール界に限らず、ハンドボール界全体が盛り上がって行くよう力を合わせて頑張っていきましょう!!!!!!
さて、今日はこの辺りにします。
ご意見ご感想お待ちしております、ぜひ一緒にお話ししましょう。
本日もお疲れ様でした!
筑波大男子ハンドボール部 ヘッドコーチ 森永 浩壽



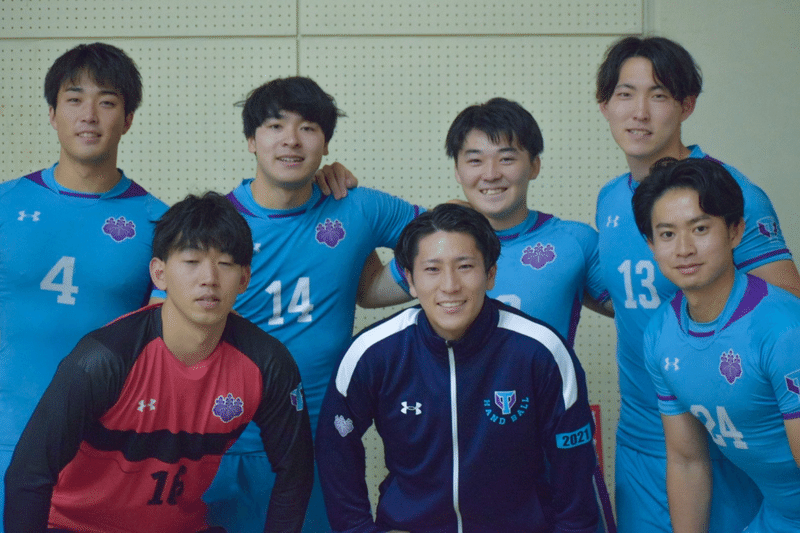
2022年の今、フルタイムで働きながら日本リーグ参入を目指すハンドボールチーム"富山ドリームス"の選手として活動しています。ここでのサポートは自身の競技力の向上(主に食費です...)と、富山県内の地域との交流に使わせていただきます。
