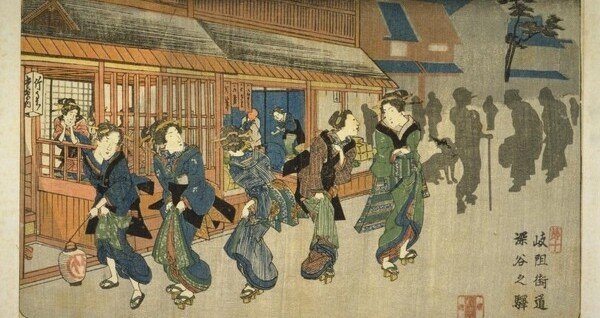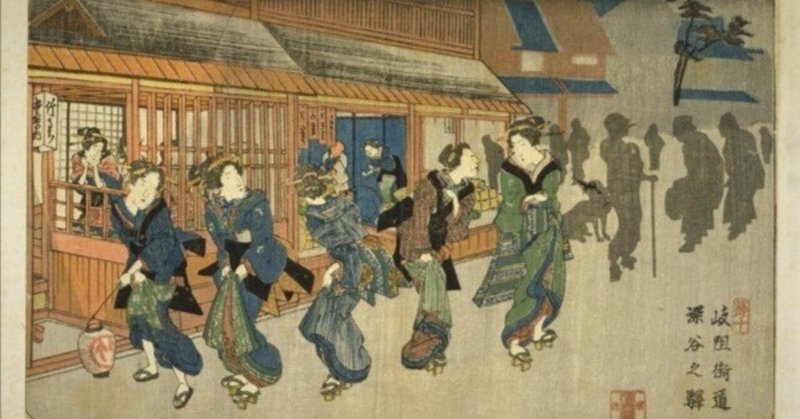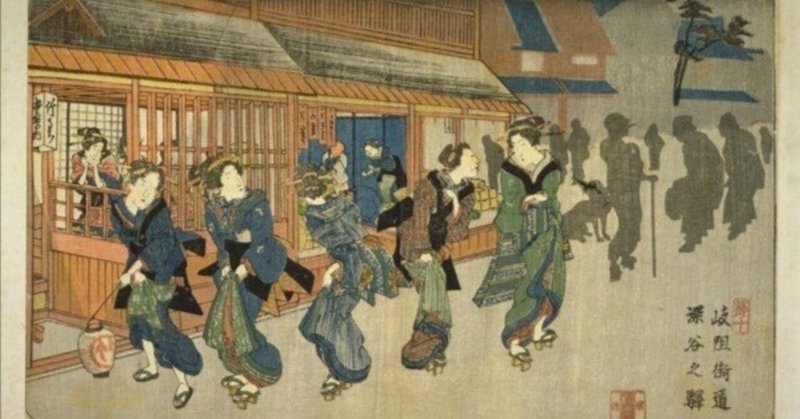2022年4月の記事一覧

生活者のための日本語教育と日本語支援のあり方について ④: 実用的な日本語と自己表現の日本語という2本柱によるカリキュラムの標準化
1.人と交わってお互いのことを話して人生を分かち合う日本語=自己表現の日本語の提案 生活上の諸活動を営む上で必要な日本語、仕事を遂行するために必要な日本語などを実用的な日本語と呼ぶことにしましょう。文化庁がこれまで進め、今後も進めようとしているカリキュラムの標準化では、端的に、実用的な日本語のみが注目されています。この4回シリーズで主張してきたことは、生活者のための日本語教育/日本語支援として、実用的な日本語だけでよいのか、ということです。 「人が生きることを営むというの
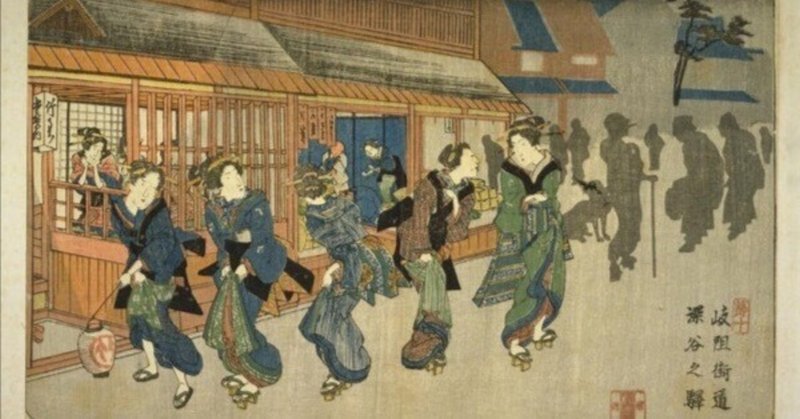
生活者のための日本語教育と日本語支援のあり方について ③: 人間というこの何ともことばに依拠した存在 ─ そして、日本語教育のカリキュラムの標準化の問題
1.昆虫や動物の個-性 人間の個-性ということを考えてみたいと思います。「個性」とするとすでに人間だけの話になってしまいますので、「個-性」としています。「その個体としての特別な性質」という意味です。まずは、昆虫や動物の個-性から。 昆虫や動物に個-性はあるでしょうか。例えば、セミのことを考えてみましょう。クマゼミというのをご存じでしょうか。夏に早朝から「シャンシャン」と鳴く何ともうるさいセミです。 虫好きの人でない限り、「すべてのクマゼミは、同じ大きさ、胴体と羽根の