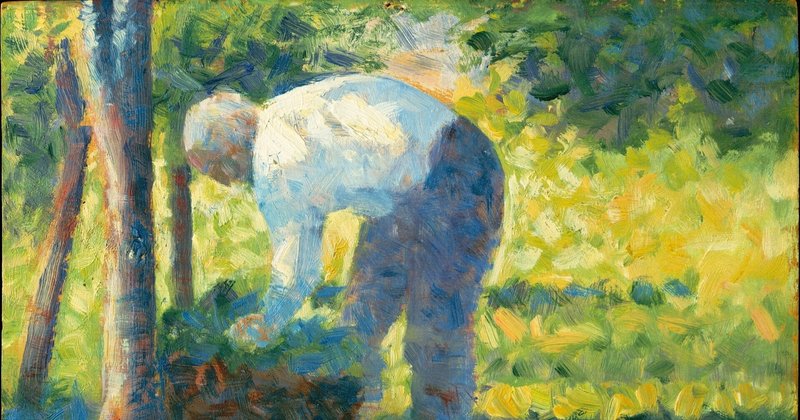
(146) おとなの研究コースをふりかえって
2021年7月22日(木)
今シーズンの「おとなの研究コース」が終了しました。このコースでは、参加者とファシリテーターとで月1回Zoomミーティングを開いていました。昨日はその最終回でした。普段は、コース内容についての質疑応答や研究についての相談などを受け付けています。しかし、今回は最終回ということで、これまでのふりかえりが中心的な話題になりました。
「おとなの研究コース」は2021年で5年目に入りました。ここまで運営をしてきて、難しかったのは、なんといってもドロップ率が高かったことです。全部で3シーズンで完結するところ、1シーズン終えるごとに、参加者は半分に減っていくという数値は改善されませんでした。たとえば、シーズン1で12人参加者がいたとすれば、次のシーズン2に進むのは、その半分の6人となり、さらに次のシーズン3に進むのは、その半分の3人になり、最終的に完遂するのは1人か2人という人数になってしまいました。
内容的に言えば、大学3・4年次のゼミの内容に相当しますので、2年間で90分x60回の分量となります。ですから、無理ゲーといえば無理ゲーなのです。逆にいえば、それでも10人に1人くらいは最後まで到達しているという実績に注目した方がいいのかもしれません。
大人向けのコースが成功する条件
ここまでやってみて、こうした大人向けのコースが成功するためには次のような条件を満たしていることが必要なのかなと考えるに至りました。
(1) 一緒に進んでいく仲間がいること
自分と同時期にスタートを切る仲間がいることは重要なことです。研究するということは、かなり孤独な道のりです。そこで、研究テーマは違っていても、同じステップを踏んで研究を進めていく仲間がいることは心の支えになります。できれば、仲間同士で相談ができる関係を作れるとさらにいいです。ファシリテーターに聞く前に仲間同士で相談しあって解決できると進みが早いからです。
しかし、こういった関係を作れるケースはあまりないようです。オンラインで進むコースであるというところも仲間づくりには不利に働いていると思います。対面で、一緒に研究会に出たり、そのあと食事を共にしたりするという機会があるといいと思います。
(2) ファシリテーターのフィードバックがあること
2週間に一回、課題を提出してもらいながらコースを進めています。提出された課題については、ファシリテーターから詳細なフィードバックがつけられます。このフィードバックによって着実にコースを進めることができます。これはうまくできていたと思います。
(3) よく考えられた無理のないプログラムであること
しかし、問題は課題が提出されない場合です。課題が提出されなければ、ファシリテーターはなすすべがありません。課題が提出されないということは、結果的にはプログラムに無理があったのかなあと今は考えています。
先に書いたように、大学3・4年次のゼミの内容に相当するものを1シーズン3ヶ月の3シーズンでやり遂げようというプログラムに無理があったように考えています。しかし、究極的には大学のゼミ相当の内容をプログラム化しようとしたこと自体に無理があったのではないかと思います。
コースの内容とゴールそのものを考え直さなければいけないなと今は考えています。そこで前回書いた「(145) おとなの研究とアクションリサーチ」の記事につながるというわけです。
そういうわけで「おとなの研究コース」は2021年度末(2022年3月)をもって終了します。ここまでお付き合いいただいた参加者の皆さんとファシリテーターの皆さんには、心から感謝したいと思います。少し考える時間をいただいてからまたチャレンジをしていきたいです。
ここから先は
ご愛読ありがとうございます。もしお気に召しましたらマガジン「ちはるのファーストコンタクト」をご購読ください(月500円)。また、メンバーシップではマガジン購読に加え、掲示板に短い記事を投稿していますのでお得です(月300円)。記事は一週間は全文無料公開しています。
