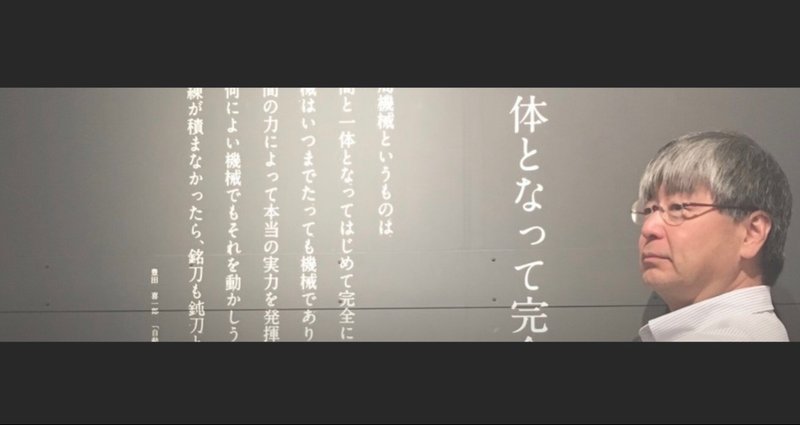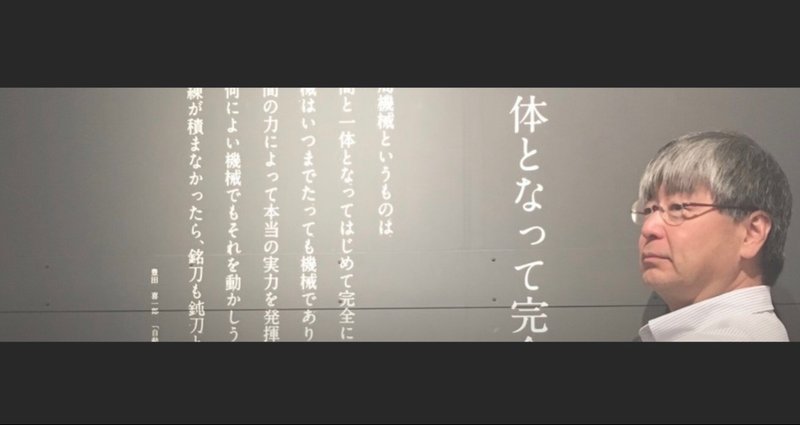一対一の議論ができるのはオンライン開催ならではのメリット
2021年10月18日(月)
日本教育工学会2021年度秋季全国大会が、10月16日(土)〜17日(日)オンラインで開催されました。私は以下のタイトルで発表しました。
向後 千春(2021)授業ビデオにおけるマップ提示と学生参加の効果:パイロットスタディ 日本教育工学会2021年秋季全国大会講演論文集, Pp.107-108
〈あらまし〉大学院修士課程のフルオンデマンド授業において、スライドの代わりにマップを 提示しながらレクチャーをした。また、履修者の一部がZoomに